【元型】【疫病の怪物】


『魔人ドラキュラ』(1931年放映)を観ました。…いや、ドラキュラ役のベラ・ルゴシ、ものすごい眼光ですね!(↑画像左)伯爵の最初の登場のこの時点で、完全にこの人の映画になっている。あと、廃墟の古城と、なんか…伯爵の召使いか?妻か?が三人いるんですけど、この人達の雰囲気も良い。ホラー映画の走りと言われている作品ですが、これは日本の「怪談」に近い“美しい怖さ”を出しています。
ちょっとこれは名画ですねえ………」伯爵、かなりあっけなくヘルシング教授に杭を打たれて死んでしまうんですけどね(汗)
さて、元型(アーキタイプ)としての『吸血鬼』の話です。(`・ω・´)さて、ここ最近、僕がこのブログの中で吸血鬼(とゾンビ)を“疫病に対する恐怖の元型”じゃないか?という仮説に基づいて取り扱い、その吸血鬼もの(あるいはゾンビもの)が流行る…という事にはどういう意味があるのか?と言ったような事を考えてきました。
こう言った解釈を大いに淀ませるというか、吸血鬼というジャンルに別の概念を持ち込んで来たのがブラム・ストーカーの『ドラキュラ』(1897年刊行)であり、その実写映画『魔人ドラキュラ』という事になると思います。ちょっとウィキペディアから、ドラキュラという怪物のスタイルが生まれるまでの部分を引用してみます。
………ちょっと、ティン!ときたので軽く調べてみると、ロンドンの“切り裂きジャック事件”が1888年。…『ドラキュラ』の9年前ですね。また、1893年あたりでは、コナン・ドイルのシャーロック・ホームズが『最後の事件』において宿敵・モリアーティ教授と対決したりしています。……ん。いや、だから何という事もなく、特に繋げた事を言うつもりもありませんが。(´・ω・`)
要するにドラキュラってダークヒーローだと思うんですよね。神話や伝説、あるいは近世の物語からもダークヒーローっぽい者はいくつも窺えるので、あんまり迂闊な事も言えないんですが、それでも1920年代の舞台劇、それから1931年の『魔人ドラキュラ』は近代のダークヒーローの走りの一人であったとは言えると思います。
同時代的に『フランケンシュタイン』や『狼男』も居るワケですけど、あくまでモンスター的な彼らに対して、人間としての振る舞いを無くさないドラキュラの存在はかなり抜けていたと思えます。小さいながらも何か“突破”があったかなと。
とまれ、ドラキュラというダークヒーローの出現は、それまでの吸血鬼のイメージを一新してしまった。一連の記事から僕はずっと、元型、元型、疫病という怪物の元型、と繰り返し言ってきているわけですが、このエポックにより“吸血鬼”という怪物の意味そのものが変わってしまった可能性は大きい。そして、もう一度、本来の疫病の怪物が再臨してくるのは“ゾンビ”の出現を待つ必要があった…と、現状、そういう流れをイメージしています。
また、この一連の話しのきっかけ、最近、吸血鬼もの(とゾンビもの)が妙に流行っているよね?という現象についても、幾分か、いや、相当な割合で、このダークヒーロー性を追った作品群がある事は間違いない所です。
元型(アーキタイプ)というのは、ここでは集団の無意識の心理に触発するもの、あるいは集団の無意識を象徴的に具現化したもの、として取り扱っているのですが、それは今回の『ドラキュラ』のように、一人の才能の出現だけで大きく書き換えられる可能性を持っている物でもあるという事が示されたわけです。
これが何百年もかけて複数の作り手の手によって醸成される伝承や、おとぎ話ならともかく、近代の物語はそういう扱いを受ける可能性は相当低く、そうそう単純化して語れたものではないかなと思います。…まあ、それすらも集団の無意識の影響下にある!という胡散臭い話を拡散する事もできるのですが……まあ、そういう話はちょっと置いておくとして。
それでも元型の話は、確定的に語れるものでは無い事を踏まえた上であれば、方向的には様々な場面で解釈し、考察のツールとして、その意義を持つものだと考えています。色んな要素が絡みあって、なかなか難しいのですが、しばらくはこの“疫病の怪物”の考察を続けて行こうと思います。


『魔人ドラキュラ』(1931年放映)を観ました。…いや、ドラキュラ役のベラ・ルゴシ、ものすごい眼光ですね!(↑画像左)伯爵の最初の登場のこの時点で、完全にこの人の映画になっている。あと、廃墟の古城と、なんか…伯爵の召使いか?妻か?が三人いるんですけど、この人達の雰囲気も良い。ホラー映画の走りと言われている作品ですが、これは日本の「怪談」に近い“美しい怖さ”を出しています。
ちょっとこれは名画ですねえ………」伯爵、かなりあっけなくヘルシング教授に杭を打たれて死んでしまうんですけどね(汗)
さて、元型(アーキタイプ)としての『吸血鬼』の話です。(`・ω・´)さて、ここ最近、僕がこのブログの中で吸血鬼(とゾンビ)を“疫病に対する恐怖の元型”じゃないか?という仮説に基づいて取り扱い、その吸血鬼もの(あるいはゾンビもの)が流行る…という事にはどういう意味があるのか?と言ったような事を考えてきました。
【アーキタイプ】『吸血鬼ノスフェラトゥ』(1978年)疫病の怪物~我がたましいのホラー映画
【アーキタイプ】『屍鬼』~疫病の怪物
こう言った解釈を大いに淀ませるというか、吸血鬼というジャンルに別の概念を持ち込んで来たのがブラム・ストーカーの『ドラキュラ』(1897年刊行)であり、その実写映画『魔人ドラキュラ』という事になると思います。ちょっとウィキペディアから、ドラキュラという怪物のスタイルが生まれるまでの部分を引用してみます。
・ドラキュラとはあくまでもブラム・ストーカーの同名小説の登場人物の名前であるが、この小説本が余りにも有名になったため、現在では「ドラキュラ」と言えば吸血鬼の意味として使われることが多い。
・1920年代に、原作者未亡人、フローレンス・ストーカーから正式に版権を取得した舞台劇が上演される。
原作の中でのドラキュラはおよそ人前に出られるような容姿ではなかった。当時の舞台劇の主流は「室内劇」であり、舞台台本も原作を大幅に改編せざるを得ず、原作における冒頭のドラキュラ城のシークエンスをはじめとして、原作の見せ場がことごとくカットされた。舞台はセワード博士の病院と、カーファックス修道院の納骨堂の2場で進行する。
このため、ドラキュラ伯爵は、人の家に招かれ、人間と対話をする礼儀作法を備えざるを得なくなり、黒の夜会服を着こなす「貴公子然としたイメージ」が確立された。
ちなみに、マントの着用もこの舞台が初めてである。演出上、一瞬にしてドラキュラが消滅するイリュージョンがあり、そのために、大きなマントと大きな襟が必要だった。ドラキュラのマントの襟が立っているのは、この時の名残である。ちなみにマントの正確な着方は、襟を寝かせるものである。
このスタイルを初めて映像化したのが「魔人ドラキュラ(1931)」である。 本来は、制作サイドで独自のメイクを考案していたが、ドラキュラ役のベラ・ルゴシが、重厚なメイクを固辞し、ハンガリー訛りの英語の台詞をもって、舞台のスタイルを映画に持ち込んだのである。これが現在のドラキュラのイメージとなった。
(Wikipedia『ドラキュラ』より)
………ちょっと、ティン!ときたので軽く調べてみると、ロンドンの“切り裂きジャック事件”が1888年。…『ドラキュラ』の9年前ですね。また、1893年あたりでは、コナン・ドイルのシャーロック・ホームズが『最後の事件』において宿敵・モリアーティ教授と対決したりしています。……ん。いや、だから何という事もなく、特に繋げた事を言うつもりもありませんが。(´・ω・`)
要するにドラキュラってダークヒーローだと思うんですよね。神話や伝説、あるいは近世の物語からもダークヒーローっぽい者はいくつも窺えるので、あんまり迂闊な事も言えないんですが、それでも1920年代の舞台劇、それから1931年の『魔人ドラキュラ』は近代のダークヒーローの走りの一人であったとは言えると思います。
同時代的に『フランケンシュタイン』や『狼男』も居るワケですけど、あくまでモンスター的な彼らに対して、人間としての振る舞いを無くさないドラキュラの存在はかなり抜けていたと思えます。小さいながらも何か“突破”があったかなと。
とまれ、ドラキュラというダークヒーローの出現は、それまでの吸血鬼のイメージを一新してしまった。一連の記事から僕はずっと、元型、元型、疫病という怪物の元型、と繰り返し言ってきているわけですが、このエポックにより“吸血鬼”という怪物の意味そのものが変わってしまった可能性は大きい。そして、もう一度、本来の疫病の怪物が再臨してくるのは“ゾンビ”の出現を待つ必要があった…と、現状、そういう流れをイメージしています。
また、この一連の話しのきっかけ、最近、吸血鬼もの(とゾンビもの)が妙に流行っているよね?という現象についても、幾分か、いや、相当な割合で、このダークヒーロー性を追った作品群がある事は間違いない所です。
元型(アーキタイプ)というのは、ここでは集団の無意識の心理に触発するもの、あるいは集団の無意識を象徴的に具現化したもの、として取り扱っているのですが、それは今回の『ドラキュラ』のように、一人の才能の出現だけで大きく書き換えられる可能性を持っている物でもあるという事が示されたわけです。
これが何百年もかけて複数の作り手の手によって醸成される伝承や、おとぎ話ならともかく、近代の物語はそういう扱いを受ける可能性は相当低く、そうそう単純化して語れたものではないかなと思います。…まあ、それすらも集団の無意識の影響下にある!という胡散臭い話を拡散する事もできるのですが……まあ、そういう話はちょっと置いておくとして。
それでも元型の話は、確定的に語れるものでは無い事を踏まえた上であれば、方向的には様々な場面で解釈し、考察のツールとして、その意義を持つものだと考えています。色んな要素が絡みあって、なかなか難しいのですが、しばらくはこの“疫病の怪物”の考察を続けて行こうと思います。
 | 魔人ドラキュラ [DVD] |
| ブラム・ストーカー | |
| ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン |










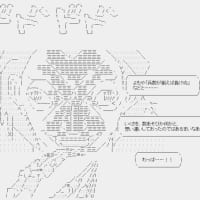
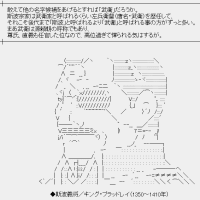
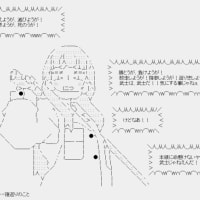
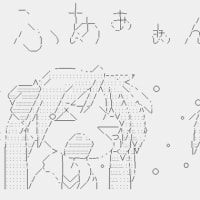

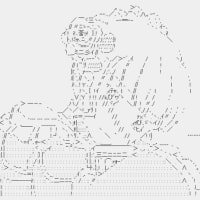

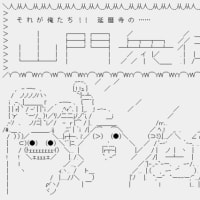
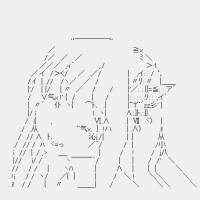
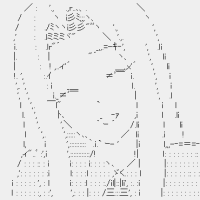
ダークヒーローといえば、ティム・バートンの『バットマン』は、ドラキュラ的なヴィジュアルだとは当時から言われてましたよねー。
ベラ・ルゴシでいえば、ユニバーサルで続編出来なかった『吸血鬼蘇る』がイイですけど、同じスタッフでエジプトに舞台を置き換えて、ほとんど同じことやってる『ミイラ再生』もイイです。
あ、ユニバーサルの『ドラキュラの娘』の監督は、最初のバットマン映画の監督だったりするのでした(汗)
迫力ありますよね