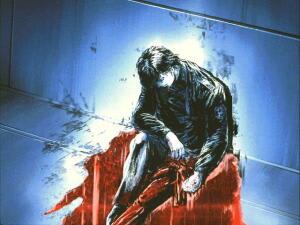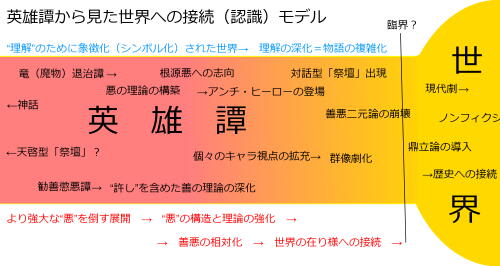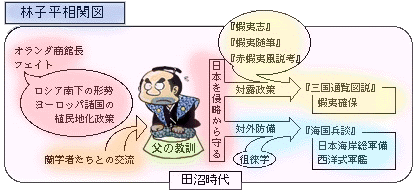【元型】【疫病の怪物】

今期アニメで『屍鬼』(原作・小野不由美)を観ていました。ある隔絶された村に原因不明の死の病が襲いかかる。次々と死んで行く村人たち。しかし、その原因は一向に分からない。しかし、その災厄は村に不似合いな洋館が移築されて来た時期と……いや、ネタバレしないと本題に入れないので言っていまいますが(汗)屍鬼と呼ばれる“吸血鬼”たちが、隔絶された村を一族の根城~安住の地にしようと、浸蝕をはじめる『物語』です。
その物語の顛末や感想は、また別の機会とします。ちょっと、ここで書き留めておきたいのは、ここで登場する吸血鬼“屍鬼”たちの振る舞いは死霊(ゾンビ)的であり、かつ疫病的な存在として描かれていたんですね。僕がこのブログで何度か書き留めている、疫病という恐怖の元型(アーキタイプ)である所の“吸血鬼”の形にかなり近い形で描かれていたと言えます。
吸血鬼という一族を、突き詰めて考えて行くと、未知の領分に置かずに既知となり得るものとして捉えて行こうとすると、かなり必然的にこういう生態になってくるだろうなとは思うんです。


『屍鬼』の中で、屍鬼という存在は、人間の体組織そのものを造り替えてしまう奇病(?)として存在します。襲って血を吸い尽くした者の中で何人かが“起き上がり”、その起き上がった者は同じく吸血鬼として生きる事になる。やはり、この症状は疫病の恐怖と密接に関わっていますよね。
いや、この話自体は、ものの本とか読むと普通にその起源の有力な仮説として書いてある事ですけど、これがブラム・ストーカーの『ドラキュラ』(1897年刊行)という“ダーク・ヒーロー”の登場で、一気に世間のそのイメージは書き換わってしまう。そして、本来的な疫病の恐怖という『元型』は、ゾンビが継承して行っている…とそういう物語を絡めた起源を追っています。(まあ、そのゾンビも本来の意味~おそらくは昏睡者の使役魔術のようなもの~から離れた存在のようですが)
もう一つ。この怪物が持っている最大の特徴の一つである吸血ですが。日本だとあまり聞かない怪物の“症状”と言えると思います。吸血をする怪物がまったくいないわけではないでしょうが、あまりポピュラーではないはずです。(吸血と非常に近しい行為と取れる、屍食する怪物はいますが、これは今回はちょっと置いておきます)
これは、やっぱり吸血鬼という怪物を生んでいる疫病は、もう、ずばり、かつてヨーロッパで猛威を振るったペストそのものと言う事だと思います。一方、日本には明治時代までペストは侵入して来ていない。しかし、長らく天然痘には苦しめられてきた歴史があって。即ち日本には“ペストを具現化”した怪物はいないけど、“天然痘を具現化”した怪物はいるはずじゃないかと思ったり。…ちょっとWikipediaから、ペストの症状と、天然痘の症状を引用します。
…ふむ。吸血という行為にどういう意味があるのかと言えば、身体に直接的な損傷を与えず、しかし、内部からぼろぼろにされて行くという、その死に方の表現なんでしょうね。まあ、実際、ノミの吸血から感染しているようですし、その刺された箇所が腫れていると。うん、完全に吸血鬼だ。(`・ω・´)(←誘導注意)
一方、天然痘はああいう感じ………いや、ここで天然痘の怪物を探り当てようという行為は後回しにして置きたいですが、ぱっと思い立つ事としては、日本だとこういう「よく分からなくって、怖いもの」というのは何でも“鬼(おに)”のカテゴリとして処理している印象があります。返ってヨーロッパだと「よく分からなくって、怖いもの」は“ヴァンパイア(吸血鬼)”の眷族の扱いを受ける印象がある。…こういう混沌とした中から疫病の怪物という視点だけを抽出してその該当を抜き出してくるのはちょっと無理かも…という気もしないでもないですねえ…(汗)
……さて、長々書きましたが、LDが一体何をやっているのか?と言うと(汗)まあ、最近、僕の観える物語界隈でゾンビと吸血鬼が妙に流行っているな?って事があって、その意味を考えたい(想像して愉しみたい)ってだけなんですよね。
この現象を象徴的な何かと捉えるとして、その起源はやはり疫病(ペスト)の恐怖を具現化(元型化)した存在に思えるんだけど(元型の一つとして考えたいという目論見もあります)、現代人のように『物語』を楽しむ余裕があり、かつ、疫病の恐怖を相当に忘れる事ができる先進国の人間に、この元型が残っているとしたら、それはどういう意味があるのか?…てな事を考えたりしています。一定の答えに到達するかどうかは、全く分かりませんが(汗)時々、こうやって書き留めておきます。

今期アニメで『屍鬼』(原作・小野不由美)を観ていました。ある隔絶された村に原因不明の死の病が襲いかかる。次々と死んで行く村人たち。しかし、その原因は一向に分からない。しかし、その災厄は村に不似合いな洋館が移築されて来た時期と……いや、ネタバレしないと本題に入れないので言っていまいますが(汗)屍鬼と呼ばれる“吸血鬼”たちが、隔絶された村を一族の根城~安住の地にしようと、浸蝕をはじめる『物語』です。
その物語の顛末や感想は、また別の機会とします。ちょっと、ここで書き留めておきたいのは、ここで登場する吸血鬼“屍鬼”たちの振る舞いは死霊(ゾンビ)的であり、かつ疫病的な存在として描かれていたんですね。僕がこのブログで何度か書き留めている、疫病という恐怖の元型(アーキタイプ)である所の“吸血鬼”の形にかなり近い形で描かれていたと言えます。
吸血鬼という一族を、突き詰めて考えて行くと、未知の領分に置かずに既知となり得るものとして捉えて行こうとすると、かなり必然的にこういう生態になってくるだろうなとは思うんです。
【『ホワイト・ゾンビ』最初のゾンビ映画~疫病の怪物】
http://blog.goo.ne.jp/ldtsugane/e/84c6a57a82bd47c4876b63a5a82fe6d7
それまで呪術によって使役される人形だったゾンビが、自律性と噛むことによって仲間を増やすという繁殖性……繁殖性というより“疫病性”なんだと思いますが、そういう吸血鬼の特性を持つことで、恐怖映画の一大ジャンルにまで成長しています。
つまりここで言う吸血鬼は疫病~黒死病を持ち込む妖怪としての吸血鬼であり、キャラクター化したドラキュラは、また別の存在という考え方をします。その意味で言えば本来のブードゥー・ゾンビも、魔術師のガジェットとしての存在であって、両者は、今述べている眷属性なるものからは遠い存在でしょう。


『屍鬼』の中で、屍鬼という存在は、人間の体組織そのものを造り替えてしまう奇病(?)として存在します。襲って血を吸い尽くした者の中で何人かが“起き上がり”、その起き上がった者は同じく吸血鬼として生きる事になる。やはり、この症状は疫病の恐怖と密接に関わっていますよね。
いや、この話自体は、ものの本とか読むと普通にその起源の有力な仮説として書いてある事ですけど、これがブラム・ストーカーの『ドラキュラ』(1897年刊行)という“ダーク・ヒーロー”の登場で、一気に世間のそのイメージは書き換わってしまう。そして、本来的な疫病の恐怖という『元型』は、ゾンビが継承して行っている…とそういう物語を絡めた起源を追っています。(まあ、そのゾンビも本来の意味~おそらくは昏睡者の使役魔術のようなもの~から離れた存在のようですが)
もう一つ。この怪物が持っている最大の特徴の一つである吸血ですが。日本だとあまり聞かない怪物の“症状”と言えると思います。吸血をする怪物がまったくいないわけではないでしょうが、あまりポピュラーではないはずです。(吸血と非常に近しい行為と取れる、屍食する怪物はいますが、これは今回はちょっと置いておきます)
これは、やっぱり吸血鬼という怪物を生んでいる疫病は、もう、ずばり、かつてヨーロッパで猛威を振るったペストそのものと言う事だと思います。一方、日本には明治時代までペストは侵入して来ていない。しかし、長らく天然痘には苦しめられてきた歴史があって。即ち日本には“ペストを具現化”した怪物はいないけど、“天然痘を具現化”した怪物はいるはずじゃないかと思ったり。…ちょっとWikipediaから、ペストの症状と、天然痘の症状を引用します。
◆腺ペスト
リンパ腺が冒されるのでこの名がある。ペストの中で最も普通に見られる病型。ペストに感染したネズミから吸血したノミに刺された場合、まず刺された付近のリンパ節が腫れ、ついで腋下や鼠頸部のリンパ節が腫れて痛む。リンパ節はしばしばこぶし大にまで腫れ上がる。ペスト菌が肝臓や脾臓でも繁殖して毒素を生産するので、その毒素によって意識が混濁し心臓が衰弱して、多くは1週間くらいで死亡する。死亡率は50から70パーセントとされる。
◆ペスト敗血症
ペスト菌が血液によって全身にまわり敗血症を起こすと、皮膚のあちこちに出血斑ができて、全身が黒いあざだらけになって死亡する。ペストのことを黒死病と呼ぶのはこのことに由来する。
◆天然痘
発熱後3~4日目に一旦解熱して以降、頭部、顔面を中心に皮膚色と同じまたはやや白色の豆粒状の丘疹が生じ、全身に広がっていく。
7~9日目に再度40℃以上の高熱になる。これは発疹が化膿して膿疱となる事によるが、天然痘による病変は体表面だけでなく、呼吸器・消化器などの内臓にも同じように現われ、それによる肺の損傷に伴って呼吸困難等を併発、重篤な呼吸不全によって、最悪の場合は死に至る。
…ふむ。吸血という行為にどういう意味があるのかと言えば、身体に直接的な損傷を与えず、しかし、内部からぼろぼろにされて行くという、その死に方の表現なんでしょうね。まあ、実際、ノミの吸血から感染しているようですし、その刺された箇所が腫れていると。うん、完全に吸血鬼だ。(`・ω・´)(←誘導注意)
一方、天然痘はああいう感じ………いや、ここで天然痘の怪物を探り当てようという行為は後回しにして置きたいですが、ぱっと思い立つ事としては、日本だとこういう「よく分からなくって、怖いもの」というのは何でも“鬼(おに)”のカテゴリとして処理している印象があります。返ってヨーロッパだと「よく分からなくって、怖いもの」は“ヴァンパイア(吸血鬼)”の眷族の扱いを受ける印象がある。…こういう混沌とした中から疫病の怪物という視点だけを抽出してその該当を抜き出してくるのはちょっと無理かも…という気もしないでもないですねえ…(汗)
……さて、長々書きましたが、LDが一体何をやっているのか?と言うと(汗)まあ、最近、僕の観える物語界隈でゾンビと吸血鬼が妙に流行っているな?って事があって、その意味を考えたい(想像して愉しみたい)ってだけなんですよね。
この現象を象徴的な何かと捉えるとして、その起源はやはり疫病(ペスト)の恐怖を具現化(元型化)した存在に思えるんだけど(元型の一つとして考えたいという目論見もあります)、現代人のように『物語』を楽しむ余裕があり、かつ、疫病の恐怖を相当に忘れる事ができる先進国の人間に、この元型が残っているとしたら、それはどういう意味があるのか?…てな事を考えたりしています。一定の答えに到達するかどうかは、全く分かりませんが(汗)時々、こうやって書き留めておきます。
 | 屍鬼〈1〉 (新潮文庫) |
| 小野 不由美 | |
| 新潮社 |
 | 屍鬼 4(完全生産限定版) [Blu-ray] |
| 越智信次,小野不由美,杉原研二,童夢 | |
| アニプレックス |