1月20日は、京都市北区にある日蓮宗寺院 知足山 常徳寺を訪ねました。時折行く職場の最寄りバス停が「常徳寺前」なので以前から気になっていました。


頂いたご由緒書では、今から約380年前、寛永5年日奥上人を開基として仰ぎ創建されました。その後、江戸時代に本阿弥光悦が鷹峰に芸術村をつくった折に、後藤長兼(1562-1616)が日奥上人の教えにより、鷹峯の東よりの地柴竹の地に常徳寺を、天台宗より改宗したと伝えられています。


寺宝として、後藤長兼像、常盤地蔵、日蓮聖人木造、日奥上人座像があります。
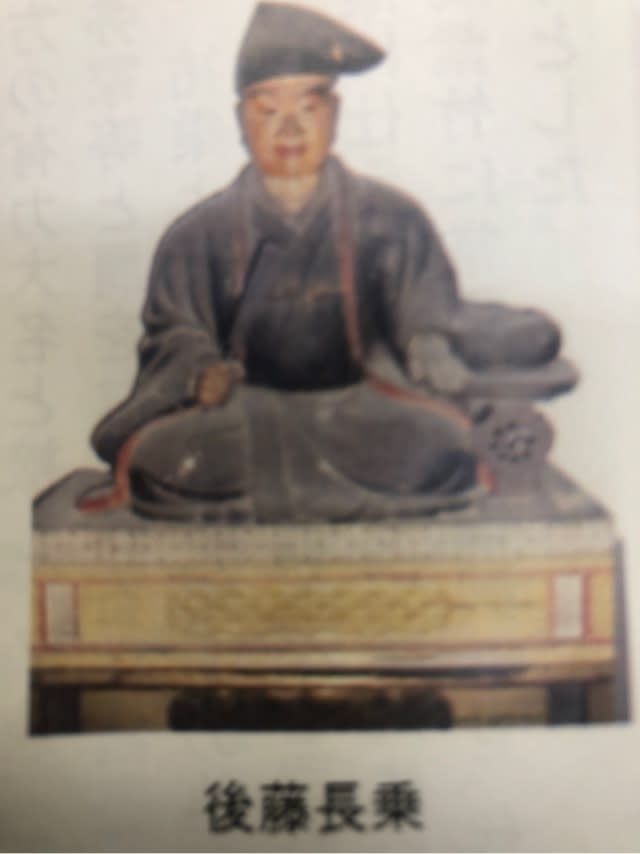
後藤長兼(1562-1616)は常徳寺の檀家で工芸家で秀吉に仕え、大判鋳造を司り、また、秀吉の蔵する軍用分銅を改鋳して判金として片桐且元の元で財務を預かり、秀吉没後は、家康に仕えて後の後藤金座のもとを開きました。

日蓮聖人木像は、大本山妙顕寺二祖大覚大僧正の作と伝わります。
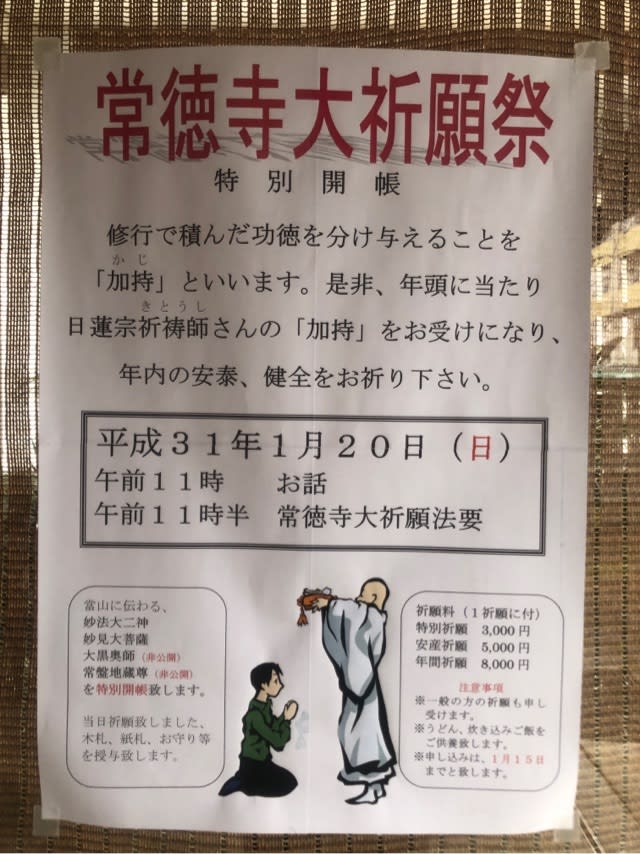
この日は、「常徳寺大祈願祭」が行われ、寺宝も公開されますが10時から仕事のために断念しました。


頂いたご由緒書では、今から約380年前、寛永5年日奥上人を開基として仰ぎ創建されました。その後、江戸時代に本阿弥光悦が鷹峰に芸術村をつくった折に、後藤長兼(1562-1616)が日奥上人の教えにより、鷹峯の東よりの地柴竹の地に常徳寺を、天台宗より改宗したと伝えられています。


寺宝として、後藤長兼像、常盤地蔵、日蓮聖人木造、日奥上人座像があります。
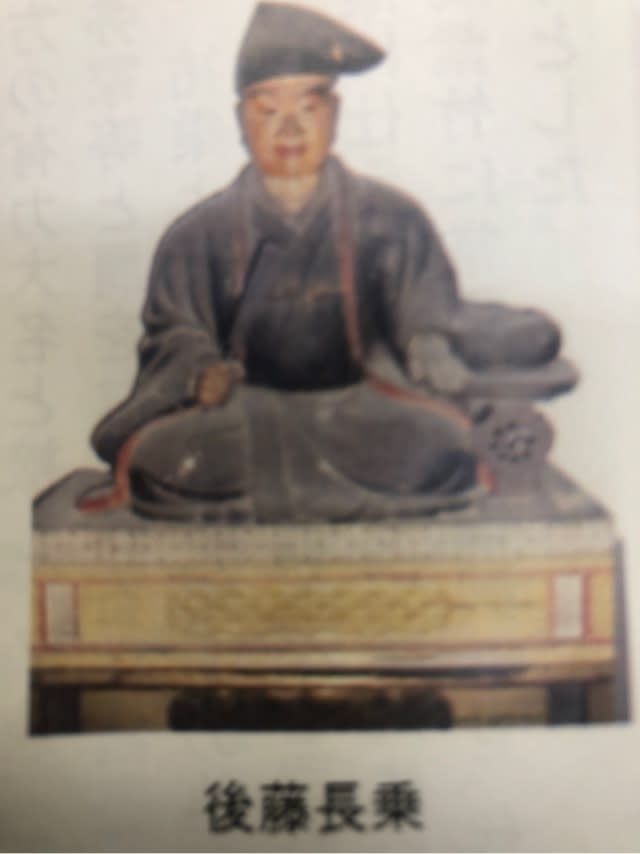
後藤長兼(1562-1616)は常徳寺の檀家で工芸家で秀吉に仕え、大判鋳造を司り、また、秀吉の蔵する軍用分銅を改鋳して判金として片桐且元の元で財務を預かり、秀吉没後は、家康に仕えて後の後藤金座のもとを開きました。

日蓮聖人木像は、大本山妙顕寺二祖大覚大僧正の作と伝わります。
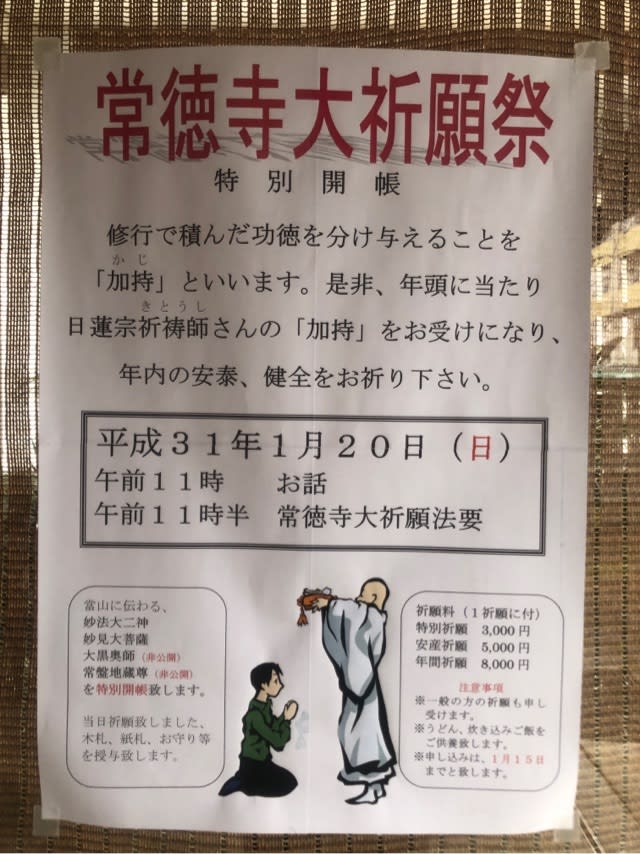
この日は、「常徳寺大祈願祭」が行われ、寺宝も公開されますが10時から仕事のために断念しました。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます