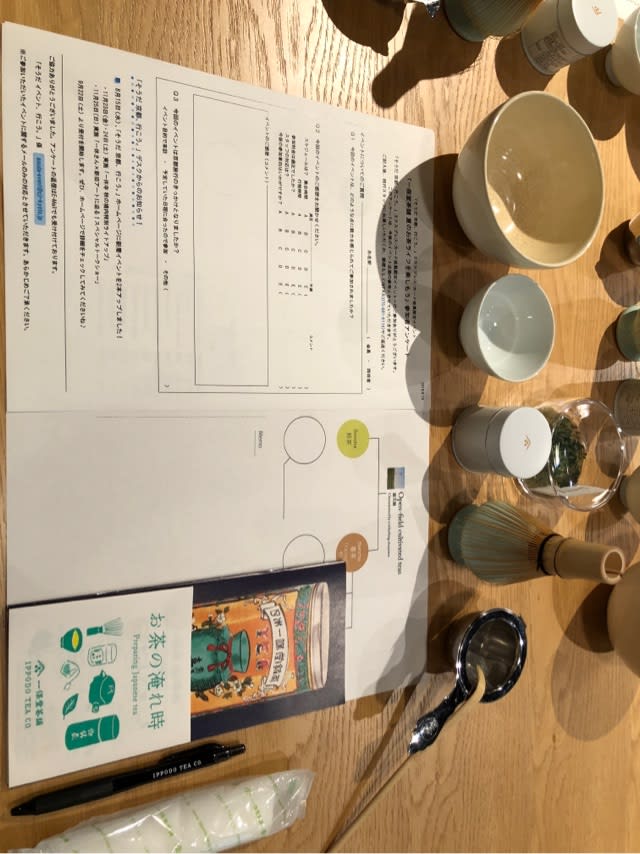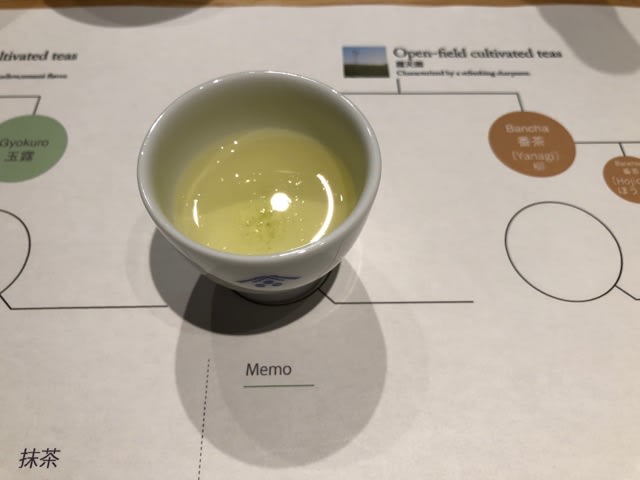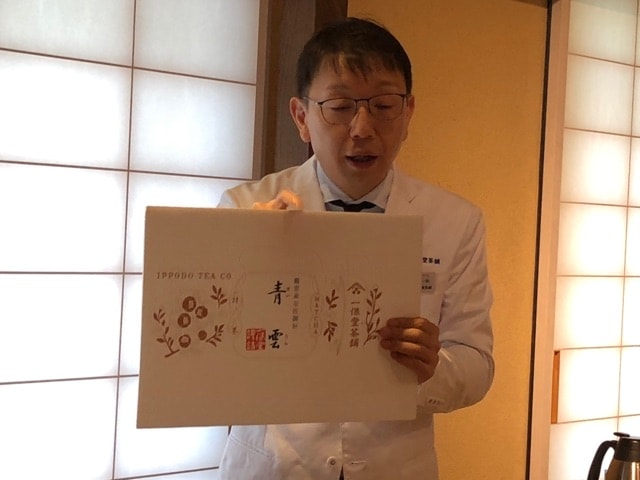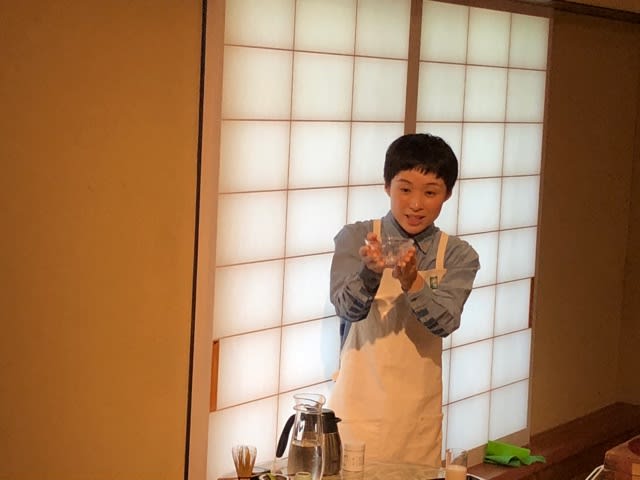今日、8月28日は念願叶ってようやく大山崎にある聴竹居を見学する事が出来ました。
週三日、公開されていますが昨年、国の重要文化財に指定されて以来、大学の建築関係の先生やゼミ学生、団体の見学で大変な事になっているようです。



藤井厚二は、日本の気候・風土に適応した住宅のあり方を実証した環境工学の先駆者です。それまでは環境工学と言う学問分野すらありませんでした。大山崎に12万坪の土地を購入し、実験住宅としての住宅を何棟も建て、5棟目となった聴竹居はその集大成です。彼の実家は広島県の造り酒屋で資金は実家を継いだ兄から出してもらっていたようです。和洋の生活様式の統合と自然環境との調和を目指した近代住宅建築の名作で、高温多湿の日本の夏に適応したさまざまな工夫がなされて昨年、国の重要文化財に指定されました。


内部の写真は出さない約束なのでご御容赦ください。
聴竹居は藤井厚二が東京帝国大学工学大学を卒業後に勤めた竹中工務店が買取り、運営は近隣の住民の方々を中心とする約50名の聴竹居倶楽部の方々が管理、運営されています。
さて、聴竹居が一躍、有名になったのは4年前の天皇皇后両陛下の訪問があってからです。皇后陛下がNHKの「美の壺」をご覧になって強く希望されれ、京都で国際会議が開かれ際に曼殊院とここ聴竹居を訪問されたようです。
天皇家もかかあ天下なんですねー!
同時に重要文化財に指定された宇治にある松殿山荘の参観も11月に予約が取れ、また楽しみが増えました。

週三日、公開されていますが昨年、国の重要文化財に指定されて以来、大学の建築関係の先生やゼミ学生、団体の見学で大変な事になっているようです。



藤井厚二は、日本の気候・風土に適応した住宅のあり方を実証した環境工学の先駆者です。それまでは環境工学と言う学問分野すらありませんでした。大山崎に12万坪の土地を購入し、実験住宅としての住宅を何棟も建て、5棟目となった聴竹居はその集大成です。彼の実家は広島県の造り酒屋で資金は実家を継いだ兄から出してもらっていたようです。和洋の生活様式の統合と自然環境との調和を目指した近代住宅建築の名作で、高温多湿の日本の夏に適応したさまざまな工夫がなされて昨年、国の重要文化財に指定されました。


内部の写真は出さない約束なのでご御容赦ください。
聴竹居は藤井厚二が東京帝国大学工学大学を卒業後に勤めた竹中工務店が買取り、運営は近隣の住民の方々を中心とする約50名の聴竹居倶楽部の方々が管理、運営されています。
さて、聴竹居が一躍、有名になったのは4年前の天皇皇后両陛下の訪問があってからです。皇后陛下がNHKの「美の壺」をご覧になって強く希望されれ、京都で国際会議が開かれ際に曼殊院とここ聴竹居を訪問されたようです。
天皇家もかかあ天下なんですねー!
同時に重要文化財に指定された宇治にある松殿山荘の参観も11月に予約が取れ、また楽しみが増えました。