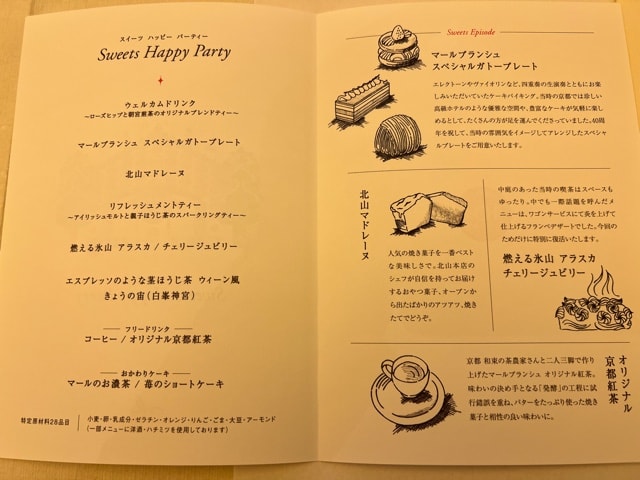10月25日は京都北山にあるマールブランシュ北山本店の「スィーツハッピーパーティー」に参加しました。
この日はマールブランシュがこの地に誕生して40周年の記念日にあたりジョイフルバトン会員の応募者の中から抽選で今回のパーティーに参加できます。
運良く当選しました。(1年分の運を使い果たした感じです、、、)
店内奥にあるサロン・カフェを貸し切っての開催です。
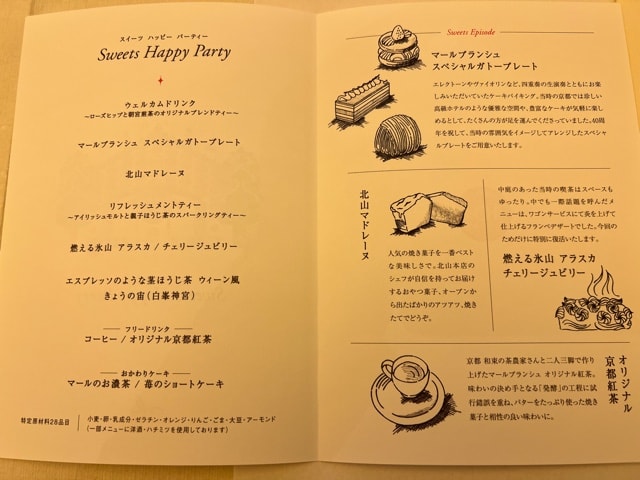
① ウェルカムドリンク
ローズヒップと朝宮煎茶のオリジナルブレンドティー
ウェルカムドリンクに相応しい綺麗な色と切れ味のいいお茶です。
② 京都紅茶
京都・和束町産のお茶を使ったマールブランシュオリジナルの紅茶です。
外国産に比べ味はまろやかでシャープな味が特徴的です。
最初は何も入れずにストレートで頂きました。
半分ほど頂き、レモンのスライスを入れて頂きました。
ストレートの方が紅茶の味や風味がダイレクトに伝わってます。
断然、ストレートがおすすめです。
③ マールブランシュ スペシャルガトープレート
創業当時、実施されていたケーキバイキングを再現したような小さめなケーキがワンプレートに詰め込まれています。
今では本店でも販売されていない"野菜のキッシュ"なども入っていて味は美味しいのは無論ですが、見た目にも"わくわく感"がたまりません。
④ 北山マドレーヌ
⑤ 北山本店だけの限定品
焼きたてを出して頂きあつあつを頂きました。
焼きたてなのでほかほかなのは勿論ですが外側は砂糖が固まり、ややハードですが中はしっとり、、、このハーモニーがたまらなく美味しいです。
店頭のカウンターでも販売されていて、焼き上がりの時間が表示されています。
(1日3回 9時、13時、15時)
⑥ リフレッシュメントティー
アイリッシュモルトと親子ほうじ茶のスパークリングティー
こちらもパーティーだけのオリジナルです。
甘いスィーツをたくさん頂き、お口直しには最適なスパークリングティーです。
ほうじ茶の香が残りリフレッシュ出来ます。
⑦ おかわりケーキ

マールのお濃茶ケーキと苺のショートケーキ
店内でも販売されているマールブランシュの定番ケーキの小型版です。
安定の美味しさです。
2セットもおかわりしていまいました。
⑦ 燃える氷山アラスカ/チェリージュビリー
マールブランシュ北山本店専売のリアル"ショータイム"です。
アラスカの氷山に見立てたホールケーキにラム酒をかけ火をつけて表面に焦げ目をつけます。
最初はそのままで、残り半分は添えられているチョコレートソースをかけて頂きます。
少し香ばしいケーキから味変、、、濃厚チョコレートがより高級感を演出しています。
⑧ チェリージュビリー
ショータイム第二弾です。
ジュビリーはフランス語ですが50周年記念祭とか金婚式を意味します。
キルシュワッサーとダークチェリーをとをひと煮立ちさせて作ります。
そこにマールブランシュだけのレシピでしょうか?バターを溶かして入れとろみがつくまで煮詰めます。
チェリーソースが甘くて濃厚なのでバニラアイスと非常によく合い美味しかったの一言では表現できないですね。
⑨ エスプレッソのような茎ほうじ茶 ウィーン風
小さなカップの中には濃いさたっぷりなほうじ茶が、、、
"エスプレッソのような"とあるように泡に包まれています。
しかし、いいタイミングで飲物が出て来ます。
⑩ きょうの宙(白峯神宮)
マールブランシュのチョコレート専門店「加加阿(カカオ)395」のチョコレートです。
チョコレートの表面には蹴鞠の絵がデザインされています。
白峯神宮は蹴鞠の宗家・飛鳥井家の跡地に明治天皇の勅により創建された神社で、御祭神は無念の情を抱き讃岐の国で崩御された崇徳上皇です。
今はサッカーやバレーボールを始め、球技全般の聖地になっています。
大坪支配人はじめマールブランシュ北山本店のスタッフの皆さま、ホント楽しく、わくわく感に満ちあふれた"お誕生日"パーティーでした。
ありがとうございました。皆さまに感謝申し上げます。