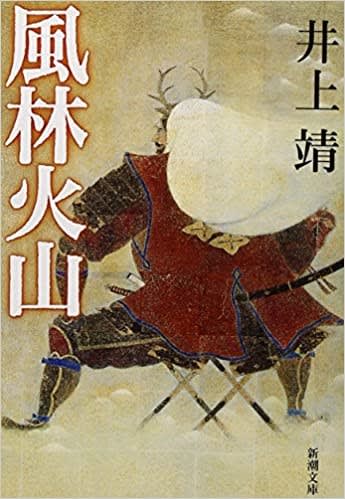2011年に読んで以来の再読。前回。
しょっぱなに登場するのは青木大膳だ。今川義元のお膝元の駿府で浪人をしている。それに対して山本勘助も浪人ではあるが今川家の家老である庵原忠胤の庇護を受けており多少ゆとりがある。庵原と縁戚関係にあるとも言われているが定かではない。大河ドラマでは内野聖陽が演じていたが、ここでは、「身長は五尺に充たず、色は黒く、眼はすがめで、しかも跛である。右の掌の中指を一本失っている。年齢は既に五十歳に近い」みんな怖がって近づこうとしない。
勘助は青木に提案する。板垣信方を襲え、それを勘助が助ける。それで恩を売れれば武田家に仕官が叶うだろう。そしてそのあと勘助が青木を引き抜いてやろうというのだ。
武田信玄は父である信虎を追放したが、その信虎は今は今川に身を寄せている。板垣はご機嫌うかがいに信虎を訪ねていた。その帰り道、例の作戦を実行する。ところが勘助は芝居をするどころか本当に大膳を切り捨てた。行流の使い手と噂されているが 、勝手に噂されているだけで全く剣の技術は持ち合わせていないが、ここぞというときには不思議と力を出す。
そしてなんと1年半後になって板垣から武田家士官の話が来る。庵原に相談するが渋い顔をされる。では、両方から給金をもらうことにすると答える。庵原家から武田家へ派遣されるようなものだ。
武田晴信(後の信玄)をはじめ、家臣たちの前に引き合わせられる。軍師の仕事がしたいと大胆にも希望するが、当然誰からも信用されていない。しかし、板垣と信玄だけはなぜか勘助のことを信用する。信玄はいきなり当初の予定した給金を倍にしたり、自分の名の一文字を与えたり、自分が13歳の時に勘助と出会い、諸国を回るよう指示していた(と、これは嘘だろう)など、いきなり厚遇する。板垣と両宿将老臣とされる甘利は信用していない。勘助を試すため剣の勝負をするよう命じる。剣の技術はない勘助はひたすら断り続ける。剣の勝負などしたくないし、諸国を回っていたというのも勝手に噂されているだけで事実無根なのだ。肯定しないが否定もしないところがしたたかだ。ただ他国からの旅行者の話などはよく聞き、それを実際訪れたかのごとく頭にイメージする才能に優れている。剣術も恐らく頭でイメージした通り扱うことができるのだろう。
まるで闇討ちのように甘利の部下から勝負を挑まれる。はじめ断っていたが、スイッチが入ると回りの声も聞こえず異常な集中力で相手を切り捨てた。甘利は勘助が妖怪のように見え、板垣は合戦以外で殺傷することはよくないとたしなめるだけだった。帰り道板垣から足軽大将として25人預けられる。その説明を受けながら、頭は城をとる話で一杯で全く聞いていない。武田晴信という若い大将とともに城をとっていくのが楽しいものに思えたのだった。この時点で勘助と晴信の尋常ではない信頼関係が出来上がっている。ここまでは勘助の仕官するまでの話。ここからいよいよ軍師としての活躍となる。
天文十三年二月、諏訪の豪族諏訪頼重を撃つため信濃の御射山に陣した。いよいよ攻め入ろうとした前日の評定で、家臣たち、とくに板垣の意見に反して、諏訪頼重を討つのではなく和議を結ぶべきと発言する。その理由を皆の前で説く。晴信は実は諏訪とは親戚関係にあるので気が進まなかったのだった。それを勘助は一人察し、晴信の代わりにそう意見したのだった。自分の思いを代弁してくれた晴信は攻めるのはやめようと決め、皆も同意する。そして早速勘助は使者として諏訪頼重の元に向かう。当の頼重は攻められる道理もないプレッシャーから固まっていたが、和議の申し入れによって安心する。勘助が気陣する際、14歳になる姫とともに見送られた。その姫の勘助を見る目は冷たいのが印象的だった。その後旧交を回復するため晴信の元を訪れた。立て続けに3度晴信の元を訪れ、諏訪に帰った後、晴信は頼重の印象を皆に聞く。皆、頼重に対してはいい印象を持っていた。勘助も意見を求められるが、「皆の前でいうことは憚られる」と言う。晴信は勘助を庭に連れ出し二人きりになる。そこで勘助はなんと、以前とは全く反対に、斬ってしまうのがよろしいという。実はこれも晴信が心に思っていたことを察知し、勘助が代弁したのだった。そして次に頼重が古府(甲府)を訪れたとき、中間頭荻原弥右衛門尉によって討たれた。頼重を討った理由は、頼重のたびたびの訪問に対する礼として、一度は晴信の方から諏訪を訪れる必要があろう、そのとき晴信は暗殺されるに違いないからだということだった。その後、武田軍は諏訪を攻める。圧倒的に武田が勝つ。勘助が城に入ると、一人の娘と侍女が二人いた。娘はかつて冷たい目で勘助を睨みつけた頼重の姫であった。侍女から自害するよう説得され、それを見届けようとしているところだった。ただ姫自身は死にたい気持ちなど全くなかった。何と言われようと、城や諏訪の湖がどうなっていくか見届けたい、と。勘助は思うところがあったのだろう。侍女を含め三人を古府に連れて帰る。晴信に引き合わせた後諏訪に返され、諏訪神社に預けられた。やがて勘助の元に板垣がやってきて、晴信が姫、由布姫を側室に迎えたいと望んでいることを告げられる。ついては晴信がその発言に全幅の信頼を置く勘助に、諫めるよう説得してほしというのだ。しかし勘助は晴信がそうしたいというならそうさせて差し上げればいいと答える。板垣には恩がある勘助だが、そんなことは気にしない心意気、いや、より晴信に対する尊敬が大きいのだろう。と、物語はこうであるが、実際は、晴信の父信虎の時代に諏訪家と融和関係にあり、信虎の三女、つまり晴信の妹、禰々御料人を頼重に嫁がせた。美貌の持ち主であったが、16歳の若さで他界する。二人の間には寅王という息子がいた。側室の小見(麻績)氏との間に生まれたのが由布姫である。由布姫は作者の創作で、実際は名称不明。諏訪御寮人と呼ばれる。信玄と由布姫の間に生まれたのがかの武田勝頼だ。物語では頼重と晴信は一旦和睦したとなっているが、実際は攻められた後甲府に連行され、東光寺に幽閉されたのち自刃している。物語では勘助の軍師としての才能と、晴信との主従関係を印象付けるために、そういう展開にしたのだろう。
由布姫は古府に移され板垣の屋敷に預けられる。勘助は晴信との子をつくることを説得するが由布姫は納得しない。父の仇との子をつくることは屈辱だった。勘助は武田と諏訪の血が流れる子はきっと聡明にちがいない。その子をいかようにでも育てることができる、と説得する。勘助は晴信の正室の三条氏も二人の男児も好きではない。兄の義信は暗く器が小さい。弟の竜宝は生まれながらの盲目。その三条氏が由布姫を訪ねてくる。三条氏は明らかに由布姫に嫉妬していて、会うと、父親討った人に囲われたくて、はるばるやってくるとは、国は亡びたくないもの、と嫌味を言う。それだけを言い捨て、去る三条氏。去ったあと由布姫は決然たる表情で、国は亡びたくないもの。武田の家へ諏訪の血を入れてみようと勘助に告げる。
天文十五年三月。戸石城の村上義清と対陣した。はじめは劣勢で、甘利備前守と横田備中守が討たれる。破れかぶれになった晴信は無茶な戦をしようとしたが勘助が50騎ほど借りて敵を撹乱する作戦をとった。その隙をついて武田軍は攻勢に転じることができた。この功により勘助は加増と部下も増えた。その後由布姫は男児を産む。唐突に出てきたので、何歳で産んだのか、いつ妊娠したのかはよく分からない。この頃になると由布姫は勘助にかなりの信頼をおいている。勘助から、生きろと言われたから生き、晴信の側室になれと言うから側室になり、子を産めと言われたから子を産んだと。勘助も同様となっている。
由布姫の子は四郎と名付けられた。なぜ3番目の稚児(わこ)なのに三郎ではないのか。四郎が妾の子だからだ。北条か上杉あたりから養子を迎える際に先方の気持ちを慮り三郎の名を空けておくのがいいとのこと。
想定外に上杉憲政が武田を攻めてくる。苦戦を強いられることが予想されるため、板垣信方を先鋒に出陣させるよう晴信に諮る。そして大勝利を得る。
その戦のあと由布姫は勝頼とともに諏訪へ帰郷する。勘助が同行する。諏訪の血が流れる勝頼と由布姫を諏訪に行かせることで地元の人の気持ちを落ち着かせる。由布姫は晴信から引き離され、諏訪に追い出されるのではないかと心配する。観音院に滞在するため高取城を出た由布姫と勝頼。観音院で先に待っていた勘助が籠を覗くと、由布姫ではなく、侍女が剣で喉をついて倒れていた。
由布姫は晴信に会うために脱走したのだろう。勘助は失踪したことを誰にも知らせず、自分一人で解決しようと決意する。由布姫に寄り添い相談に乗ってやれるのは自分しかいないと考えていた。一人雪の中を由布姫捜索に出る。翌日に小さいお堂で由布姫を見つける。逃げ出した真相は確かに晴信に会いに行くためだったが、仇である晴信の首を取るためであった。そう思ってた逃げ出したわけだが、今は逆で晴信がいとおしい気持ちである。だが、それが日ごと交互に追って来るにちがいないというのである。2つの気持ちが同時にあるという心境を勘助には理解できなかったが。古府にいれば、三条氏や武田の家臣からの嫉妬を受けるだろうし、姫がいつまた晴信を殺したいという気持ちが湧くかわからない。まずは諏訪にとどまることを説得する。晴信が諏訪を頻繁に訪れるように、諏訪の村上義清との戦い、さらには越後の長尾影虎との戦いを計画しようと、そのために戦の戦略にまで組み込んでしまうのだった。勘助の由布姫に対する、恋心も多少あると思われるが、そんなものをはるかに越えた尊敬のような感情、あるいは生き甲斐と呼ぶべき感情。
事実信州での戦が増え、晴信は由布姫と会う機会が多くなった。そして上田原の戦い。村上義清の渾身の戦い。武田軍は勝ち義清は逃げたが、もう攻めてくることはないだろう。ただこの戦で板垣信方は戦死する。しかし史実は異なっているようで、上田原の戦いでは村上義清が勝利し、板垣の他、甘利が討ち死にしている。因みに板垣信方のあとを息子の信憲が継ぐが、行状悪く、追放ののち誅殺された。一時断絶するが信方の娘婿、於曾信安が板垣家を再興する。信憲の子孫には板垣退助がいる。板垣退助の先祖は板垣信方となる。因みに板垣退助は乾退助ろ称していたが、信方の没後320年に岩倉具定の助言により板垣の姓に復した。
晴信は秘密に油川の息女を呼ぶ。隠れて輿に乗っていたその集団を見つけた勘助は、晴信が由布姫を見限り、新しい側妾を迎えるつもりではないかと懸念し、油川の息女の命をたたねばならぬという位の決意をする。そこまで由布姫と勝頼を崇拝している。
油川の息女のことを晴信に聞くと、全く知らないという。一度は安心するが、晴信が古府へ使いを二人送るのを怪しんだ勘助が、使者の持つ文を確認したところ一通は油井の息女への文であった。晴信に騙された勘助。長尾影虎との戦を終え古府に帰る晴信より先に古府へ帰り、油井の息女の命を奪おうとする。急いで古府に向かう勘助だったが、晴信も二人の侍だけつけて三人で古府に向かう一団を追い越す。そこまでして会おうとする晴信の執念。一足先に古府についた勘助は油井の息女と会う。抜き打ちで斬ってしまおうとしたが、油井の息女には既に二人の姫と、腹に子を宿していた。そして息女の天真爛漫さに、命を奪う気持ちが無くなった。逆に雄琴姫と三人の子たちを命をかけて守るとまで決意する。油井の息女の名前は雄琴姫という。諏訪に帰りながら勝頼と、雄琴姫の三人の子たちのために城を四つは取らなければならないなと想像する。諏訪に帰ると由布姫にかまをかけられ、雄琴姫のことをばらしてしまう。そして、雄琴姫と会うよう段取りするよう命じられる。晴信は雄琴姫のことは由布姫には話していない。由布姫は勝頼を武田の跡取りにすることに執着しているので、雄琴姫に男児が産まれることを快く思わない。因みに雄琴姫というのは井上靖の創作で、実際は油井夫人と呼ばれる。四人子ができ、仁科盛信、葛山信貞、松姫、菊姫(小説では春姫、夏姫)という。この菊姫はのちに上杉景勝の正室となる。武田と上杉というライバル同士が縁を結ぶのだ。由布姫は、雄琴姫と共に尼になると脅す。そうなると晴信は体面が悪いだろうから晴信自身が出家するようにと勘助は促す。当松庵に相談し、桃首座に出家を進めてもらうことになる。そして晴信は出家し、徳栄軒信玄機山と号する。同時に、原美濃、勘助、小幡山城、長坂佐衛門尉も出家する。勘助は道鬼と号する。諏訪に帰り由布姫と会うと、尼になる話は嘘だと言う。桃の木を見るため二人で歩き、由布姫は細くなった腕を見せ、自分は長く生きていたくないともらす。晴信に嫉妬心を抱く一方、実際会うとご機嫌を取ってしまう。そんな生き方が嫌になったのだ。
由布姫、信玄、勘助が珍しく三人で飲む。信玄は次の一手を決めあぐねていた。それを由布姫に決めさせる。由布姫は木曾を攻めるがよいと答え、それに従おうとする。信玄が古府に帰ったあと、由布姫は心のうちを明かす。自分は勝頼がかわいい。正室の子たちが不利な立場になれば、すかさず勝頼を担ぎ上げたい。なんとなれば正室の子たちを殺めたいくらいだ。信玄はその気持ちを察しているようだ。ただ、由布姫の命もあまり長くないというのを感付いていて、由布姫がそれを実行することはないだろうとたかをくくっているのだ。
北条、今川、武田の三者でそれぞれの娘を輿入れさせ、結束を固める。木曾義昌を屈服させ、あとは上杉景虎を討つばかりとなる。病のためみるみる痩せていく由布姫。ある日戦に向かう勘助を由布姫が呼び戻す。勘助62歳、由布姫25歳、勝頼は10歳の時である。由布姫は勘助に特に用があるわけではなく、ただ顔が見たかっただけといい、由布姫に酌をしてもらい他愛もない会話をする。そんな静謐なひととき。上杉の偵察隊が信濃に現れたため、その様子を見に行く勘助たち。対戦するつもりはなかったが、しつこく追いかけてくる上杉隊。その時前方から武田の者が一騎駆けてきて、勘助に、昨日、由布姫が亡くなったことを伝える。動転する勘助。回りが見えなくなってしまう。無我夢中で追手をかわしながら、遂には馬も潰してしまい、夢遊病のように諏訪へ歩いて帰ってくる。由布姫をなくした喪失感が激しい。もう残りの人生は戦をすることしか考えないと思うと同時に、由布姫に向けていた気持ちを勝頼に向けることがもはや生き甲斐となった。
武田軍は周囲を攻め勝ち戦を続ける。その間上杉からも牽制されている。将軍義輝(現在放送中の大河「麒麟がくる」で向井理が演じている)から、上杉と武田の双方に小競り合いを諌めるよう文が送られてくる。しかしどちらも無視している。将軍は全国の大名を統率する立場である。しかし誰も将軍の言うことを聞かず、お飾り状態となっている。ということが感じられる。
謙信は将軍に会うため越後を空けている。その隙に越後を襲うべきだと思われるが、まだその時期ではないと勘助は考える。勘助は信玄にお願いをする。城を一つ建てたい。上杉攻めの拠点にする意味があるが、もう一つ、これは勝ち戦になるので、この戦を勝頼の初陣にすべく、勝頼が進発するための城としたいのだった。因みに大河ドラマ「風林火山」42話「軍師と軍神」では、突然春日山城を去り高野山へ行った(とされる)上杉謙信と由布姫を亡くし失意にある山本勘助がそこでニアミスするシーンがあるが、小説にはない。
高坂昌信に先発させ川中島一帯に点在する上杉勢を一掃させる。高坂は武勇はあるが、自分の考えは持たないため(そのように見られているため)信玄や家臣たちから見下されている。しかし勘助はそんな高坂に、気を遣わなく、好感を持っている。陣中見舞いし二人で酒を交わす。すると何の考えも持たないと思っていた高坂が、自分と全く同じく、城を建て、そこに勝頼を入れたいと考えていることを知る。ただし意図するところは全く逆で、高坂は信玄を始め、義信や身内のものはすべて討たれるに違いない。そして最後を守るのが勝頼をだと考えているのだった。そして高坂は勘助と信玄の戦がこれまで作戦でもって勝利してきたこと、そしてこれからの謙信との戦いは、作戦ではなく力と力の勝負になるだろうと見抜いている。朴訥としてそういう高坂であるが、勘助と信玄がそれまで行ってきた戦のやり方を否定するものであるが、勘助はかえって頼もしく思うような気分になる。その後も高坂と酒を酌み交わしたいと思わせられるのだった。勘助は既に67歳。
城ができる。海津城と名づける。高坂が城代を務める。高坂、勘助、信玄が城に集まる。川中島を見渡せる城からの眺めを見て三者三様の思い。高坂は敗戦の絵、勘助はそれでも勝利に持っていく絵、信玄はここから眺める美しい月の絵。
謙信との決戦が迫り、出陣する勘助。このときの気持ちが感慨深い(287p)天文八年にこの土地を踏んで二十数年、今回生きてこの土地を踏むことはないだろうと思う。敗ける気はさらさらない。なのに再びここへは戻らない気がする。永劫生き続けそうな気すらするが、人間には死期というものがある。自分には今回の戦いが死期の気がする。寿命を断ちに合戦が自分にやって来つつある。
決戦の前に勘助は由布姫の墓を詣でる。自分の命は姫が死んだときに終わっている。など墓前に語りかける。すると何か由布姫が悲しんでいるような気持ちがした。その時麓を勝頼の部隊が通過する。追いかけ、それまで今回を勝頼の初陣にしようとしていた勘助であったが、由布姫が悲しんでいる気がして、勝頼に1年待てという。信玄には自分が何とでも言い訳する。高島城に勝頼を入城させ、城を守るようお願いし、別れを告げる。つまり最後の別れか?出がけに雄琴姫に呼び止められ、勘助はさらに勝頼を守るよう頼む。雄琴姫の息子、信盛も十二歳になり、勝頼の力になれるだろうと言われると安心して出陣する。最終決戦に向かうこのひとときの静かな高揚感がしみじみ感じられる。
武田軍と上杉軍の決戦。史実的には第五次まであるとされる川中島の戦いのうち、第四次にあたる。両者なかなか先端を切り出せず膠着状態。上杉軍は妻女山に陣どる。勘助は武田軍を2つに分け、先陣として1万5千を妻女山に向かわせ山上から上杉軍を襲う。そして追いたてられた上杉軍を川中島で待ち伏せて、挟み撃ちにしようという作戦を立てる。夜のうち霧が立ち込んでいた。明け方にそれが晴れると妻女山に陣を構えていると思っていた上杉軍が川中島の正面に現れた。先陣と違いこちらは少ない兵数であり、上杉軍の圧倒的な兵数に大苦戦する。武田信繁が討たれ、諸角豊後守も討たれる。先発隊はどうしたわけか、まだ帰って来ない。勘助は突撃隊を編成し自ら出陣する。もう四方から切られボロボロだ。そんな時遂に先発隊が戻ってきた。朦朧としながらこれで武田の勝利を確信する。槍で刺されもう何も見えなくなる。勘助の一生の中で一番静かな時間が来た。という一文が感慨深い。板垣信方、由布姫が思い出される。そして敵兵に首をとられようとするとき、勘助はその若い兵士に討たれることに、なぜか満足な気持ちなのだった。
山本勘助の、武田信玄、由布姫、武田勝頼に対する感情。家族でないくせにそれ以上の感情にも見える。これが主従関係における忠誠心とういうのだろうか。何の血縁関係もない赤の他人である武田信玄に対して、この主君には命を捨ててもいい、何を言っても正しいと思える。由布姫に対しては恋愛感情はないし、主君の正妻ではなく側妾だ。その姫に尽くそうとする。そして武田勝頼に対しても、息子ではないが、(勘助に息子があったとして)息子以上に思う気持ちがある。現在のわれわれは勝頼が武田の後継者になったのは知っているが、勘助が生きている時代には後継など考えも及ばないくらいの立場だったはず。それが分かっての上での作者の創作であるのはわかるが、勘助の熱情が伝わってくる。これは戦国時代ではあり得る感情だったのかと思う。そうだったのだと作者は伝えたいのだろうか。そうすると私は作者の伝えたい気持ちを受け取ることができたのだと、うれしい気持ちだ。
クライマックスかつ決戦となると、アドレナリン全開でマッチョな人々が、士気を高めながら相手の首を取ることしか考えていない。負けて自分が討たれると考えること自体が負け犬だ。そんな場面が普通だが、そうではない。この合戦で自分は死ぬかもしれないと漠然と思う。でも死ぬことが悔しいとか嫌なわけではない。この戦場で死ぬことが自然だというような感覚。戦国時代の侍たち一人一人がそんな感覚だったのではないかと思える。
20200930読み始め
20201020読了