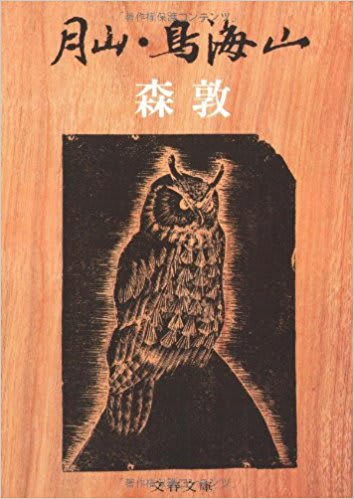本屋で棚を眺めていたら、同じタイトルなのに縦の長さが違う。それはよく知られている森敦の月山だ。何が違うのか手にとって比べると、一方は2017年に出版された新装版だ。表紙を見てみると、イラストが異なる。番号を見ると、旧がも-2-1で、新装版がも-2-2だ。驚いたのは価格だ。旧版が590円で新装版が820円と文庫の割には230円も値上がりしている。こうなると、その価値はどこに表れているのかと気になるが、中身は変わらなさそうだ。では、値上げのための大義名分としては何が考えられるか?表紙イラストの著作権と言うことかもしれない。所詮、値上げのためのこじつけにしかないだろう。読むがわにとって何の関係もないことに230円払って、新装版を買う理由があるのか?と、旧版を買った。しかし、あえて今読む必要があるのかわからない本に590円払って買ってしまうのもどうなのだろうか?
月山は、月山と月沼という2編からなる。
読んでいると、バスが出てきたり、電話が出てきたり、比較的近代的な感じがする。もっと文明の無い時代で、そこからさらに東北の山奥で、一段と素朴な村のようなものを想像していたが、そうではなさそうだ。発表された年を調べると1973年とあるので、自分が生まれた次の年だ。ということは、バスもあるし電話もある。テレビもあるだろうし、当然、電気も通ってるだろう。そう読むとまた違った印象になる。
月山
文で特徴的なのは 、「丸々しており」とか「丸々していて」の意味の文が 「丸々してい、」というもので 、確か、池波正太郎だったかが、そんな文体だった気がする。あまり好きでないのだが。
「わたし」が月山の近くの古い寺にしばらく滞在する日々。この寺にはじさまがいる。住職ではないようだ。ものすごい廃寺のようで、雪で倒壊しそうだし、窓や襖も破れていたり壊れていて、雪にも吹きさらしの状態だ。その2階に障子紙を繋げて作った蚊帳のようなもので寒さをしのぐ。特に寒くて困っているという様子はない。この寺には乞食や押し売りなども立ち寄ることがあるが、一晩だけ泊まってまたどこかへ去っていく。そして二度とは訪ねてこないようだが、「わたし」は数日滞在する。一冬過ごしそうな勢いだ。
村の会合があり、各人が家で作ったイトコ煮というものを持ちより宴会をする。それが甘酸っぱく、「わたし」には口に合わないようだ。甘酸っぱい煮物と言うのがちょっと怪しげだ。酒を密造していたり(それが「わたし」を通じて世間にばれないよう後ろめたさもあってか、親切に接してくれるようでもある)。その宴会での話で、寺の本尊のミイラの話が出てくる。昔、家事で燃えてしまったらしいが、後年、道で行き倒れになった乞食のワタを抜き出して、ミイラにして新たな本尊とした。という話があったり、宴会にいた一人の女が「わたし」の蚊帳がまるで繭の中にいるようだということに興味を持ち、いつの間にか二階に上がって眠っていた。ところが、下でじさまと話をしている間に女は帰ってしまっていた。後にはセロファン性の菊と酒の入った狸徳利だけが残されていた。もしかしてあの女はセロファンの菊が女の姿に変えたのではなかったのかと思う「わたし」。
ここまでで、怪談のようにも思えるこの小説だが、主人公は全く恐れる様子はなく、平然としている。語りが、ですます調なのも一因だろう。
月山は死の山で、後の鳥海山は生の山とのことだ。死の山という事で、さびれた暗い話を連想したが、妙な明るさがある。それは、この月山が、冬になり雪深くなり
世の中と隔絶されることにより、かえってのなかの結び付きが濃くなる季節であって、春が来て暖かくなると人々は夢から覚めたようにそらぞらしくなる。また存在すら薄くなっていく。実際、話の中では、人々はどこかへ消えてしまったかのように書かれている。冬の間あれだけ濃密であった人間関係が、春の訪れとともにそっけなく淡白(疎遠)になっている。冬の隔離された季節にこそ、人々が寄り集まって、土着的に過ごす。それが生々しく、比較的都会で育った自分からすると「生に満ちている」と感じる。死とは逆の生命感だ。この村人たちの土着的な生活が有る意味死者の饗宴と、とらえられなくもな
い。
月沼
月山のリミックス版と言う感じで始まる。月山の説明が再度繰り返される。今回は別の老人との会話だが、月山のときの幻想的な描写ではなく、どちらかと言うと対話形式なので、紀行文とかレポートのような雰囲気。それでいて、対話相手のじさまも実在しているのか、幻をみてるかのような存在だ。
鳥海山
5つの小説からなる。
「初真桑」はエッセイのような雰囲気だ。主人公の自分目線の語りとなり、月山の主人公と同一かどうかはわからない。生と死の境について、多くの人は生が終わると死が始まると錯覚しているが、生が終わるとともに死も終わる。つまり無と言うことか。井上靖の「本覚坊遺文」では、無では無くならない、死では無くなる。と言う文があったのを思い出した。
「鴎」が一番文学作品らしい。主人公夫妻のところにS君と言う友人が訪ねてくる話。鳥海山が見えたり見えなかったり、飛島が見えたり見えなかったり、東北の気候が、そんな曖昧なものにさせてしまうのだが、それが幻想的だ。
「光陰」「かての花」「天上の眺め」と続く。前の話で私たちが知った事を、次の話で主人公が既知の事として話される。そうして段々鳥海山(山形)から離れていく。最後の「天上の眺め」は遠く朝鮮に飛ぶ。奈良辺りのダム建設現場が舞台なのだが、そこで関わることになった朝鮮人労働者。接しているうちに戦時中に朝鮮で過ごしたときの事を思い出す。朝鮮凧の思い出だ。異国の話ではあるが、ノスタルジックで懐かしい話だった。
月山は今でもこんな風景なのだろうか?経験をしたこともないくせにノスタルジックな思いに駆られる。雪に囲まれた冬山の小屋で、テレビもインターネットもない環境、そこで何週間かこもってみたくなった。
新装版
月山
20180114読み始め
20180121読了