これはラノベか?酒見賢一初読み。
第壱部
孔明は算命の術にも通じているのだが、その占いによって劉景升は再来年あたりに死ぬと予想している。仲間に、では自分の死年がわかるのかと言う問いに、わかる。知っていて怖くないのか?人間は誰であれ必ず死ぬ。重要なのは死ぬときに悔いがないかということ。と答える。納得。
「孔明、五禽の戯れに醜女を獲る」の章は、長々と孔明が嫁を貰う話が続く。本当かどうか知らないが嫁は黄承彦の娘で、言わば行き遅れた想像絶する醜女ということらしい。本編にもほとんど登場しないのか名前も不明で、ただ、黄氏としか書けない。これが相思相愛となりめでたく章を終える。
三国志の本編は読んだことがないが、この砕けた感じの、そして本編のあまり触れられていない部分を作者の創作で埋める感じの作によって次、三国志本編を読むのに役立つかもしれない。いきなり本編読むのでなくこの作品をきっかけにしたことはいいことかもしれない。
劉備のもと徐庶が軍師となり、呂兄弟を討ち取ったり、曹仁が仕掛けてき八門金鎖の陣を破り大勝する。この戦闘シーンはなかなか読みごたえがある。
劉備が三顧の礼でもって諸葛孔明を迎えるシーン。ここに作者は特に力を入れていることがわかる。ページ数も多いし、かなり細かく心理描写されている。恐らく本家はさらりと流しているのだろう(勝手な予想)。あのミュージカルは何だったのだろう。冗長に感じたが本家も七言絶句なんかが出てくるのだろうか?第壱部では戦闘シーンや知略を駆使するシーンはほとんどない。曹仁が徐庶の策に敗れる場面があるくらいだ。弐部以降が楽しみだ。
第弐部
遂に劉備のもとに仕官する孔明であるが、全然軍師的な動きはなく、単調な、周辺の話ばかり。とは言え作者なりの意図があるのだとは思う。
博望坡を炎上させるというタイトルなので、いよいよ孔明活躍かと思いきや、あっさり作り話だったと片付けられこちらは不完全燃焼。
恐らく本家三国志の行間を想像して書いているのだろう。本家ではさらりと流しているエピソードをこそそこだけで1つの章を形成しているのだ。反対に本家で本筋とされている、つまり見せ場がさらりと流されているのかもしれない。となると、他の三国志をみてからこちらを読む方がいいとも言える。劉琦が孔明に対して、蔡瑁から命を狙われていると助けを求められるところまで来たが、まだ派手な展開は訪れない。
このおふざけ感は本家もそうなのだろうか?それを現代風にアレンジするとこんな感じになるのだろうか。ここへ来て若干食傷気味になってきた。クドい。田中芳樹の創竜伝もそうだった。中国文学に強い作家というのはそんな傾向にあるのだろうか?いやいやそういう偏見を作らないように気を付けて読もう。
続いて新野炎上の話。これまた新野に攻め込んできた曹操軍50万のうち10万を焼き殺した。と三国志演義の中身が書かれるが、実はこれは創作だったというオチ。しかも劉表もいつのまにか死んでいる。しかし、ここまですかされて読者に見放されなかったものだ。まさか孔明の何の活躍もなく三国志は作り話でした。で、全5巻完結するつもり?
心配したが、劉表死後、サイボウの策略で次男が後を継がされ、曹操が攻めてきた途端、降伏するという場面で、少し孔明の活躍が見られたようで、ちょっと安心した。
司馬遼太郎に似ているか。登場人物ごとのバックグラウンドを語り、ストーリーより出来事の背景に重きを置く。さすがに司馬遼太郎におふざけはないが。
呉の場面になると(誰かの感想にもあったが)「ワシも○○じゃけん」などと、広島の呉市とかけて、そして仁義なき戦いともかけて、広島弁かつヤクザっぽい雰囲気を出している。なかなか本格的な広島弁ではないだろうか。
長坂坡に戦いに入るといよいよ各キャラクターが活躍し出す。優柔不断すぎる劉備、それを踏まえた上で策略を立てる孔明。一番まともで日本の武士を彷彿とさせる趙雲。ただの殺戮マシーン、張飛。見所満載だ。個人的には趙雲の活躍が良かった。
P466糜芳が顔面に数本の矢を立てたまま、ふらふらと駆けつけてきた場面のツッコミに笑ってしまう。もう死んでいてもおかしくはないのだが、本家にそう書いてあるらしい。
この第弐部は2007年に単行本が刊行され、文庫版は2011年なので文庫化まで4年くらいかかるということだが、最終巻の第五部はつい先頃2017年に刊行されたばかりだ。文庫化が4年後となるので2021年、もう少しじっくり読まないと。
第参部
この第参部を読んでいる間に、映画「レッドクリフ」を観た。映画と合わせて読むと相乗効果で面白い。小説では周瑜と孔明は仲が悪い。といっても一方的に周瑜が何の根拠もなく感覚的に「いつか孔明を抹殺してやる」と燃えているだけだが。映画では互いに信頼しあっている。
半分まで読んできて、三国志の見せ場は赤壁の戦いと聞いているが、孔明は関わっていないからすっ飛ばす、などと言っている。また流されてしまうのか?
呉軍は矢の不足のため周瑜から10万本を調達するよう孔明は求められる。映画、レッドクリフでもこの場面があり、周瑜と孔明はいい関係で描かれていたが、ここでは孔明を殺したい周瑜が無理難題を押し付け失敗したら処刑してしまおうという企みから出てきたものだ。映画ではある程度見せ場としてあったが、ここではあっさりとしている。孔明平然としてやったりといったところだ。
今ごろ気づいたが、これは三国志ではない、諸葛孔明伝なのだ。だから、孔明の関わらないことは飛ばそうとするのだ。
赤壁の戦い。何だかんだで飛ばされることはなく安心した。ただ映画ほど長くはなくあっさりとしていた。水軍を放火され、曹操はいち早く逃走した。それを予測して劉備軍は先回りしながら曹操を討とうと言う作戦だが、余裕を見せて今回は曹操をわざと見逃す。赤壁の戦いは周瑜の活躍の話であって劉備軍はあまり活躍していないと言う話をうまく解釈した。関羽は曹操に義理があり、どうしても討てないしがらみがあり、逃がしてしまう。関羽には大きな失敗だが、これも孔明は想定内だ。
余談だが途中浮気をして北方謙三の楠木正成を読んでいたが、これが自分に合わない。チャンドラーもそうだったがハードボイルドが合わないのではないだろうか?文章は単純で会話文が多く読みやすいはずなのだが、全然入って来ない。苦痛過ぎた。それから戻ってこの諸葛孔明は何と読みやすいのか。
赤壁後は孫権と周瑜に任せ、自分達は南州を攻め落とそうとする。各州を各将軍が攻めていくが、南州側は特にやる気はなく、簡単に手に入れてしまう。ここでも趙雲の知略と義が光る。また五虎大将の1人に数えられるという黄忠が仲間になる。
そのうち劉備暗殺を企む周瑜が孫権の妹と縁談と称して罠にはめようと画策する。ここでレッドクリフに出てきた、じゃじゃ馬で男勝りの孫権の妹が登場する。この時まだ17で50近い劉備とかなりの年の差だ。そしてやはり名がなく孫氏と称する。結論からいうと、孫氏が一方的に劉備を気に入り、縁談自体がうまくいったため暗殺どころではなくなった。そして荊州を孫権から借り受ける形で治めることとなった。周瑜は先頃の武州の戦の折り、矢を受け療養中であった。
自分の命は長くないと悟った周瑜は最後に孔明に一泡ふかせようと作戦を練る。赤壁の戦いで弱ったであろう曹操に追い討ちをかける振りをして、劉備と孔明を撃ち取ってしまおうと言うのだ。ところが孔明によって完全に読まれていたため、作戦は失敗する。(史実と辻褄を合わせるためか?)孔明は周瑜を慮り、この事件は一切なかったことにしようと提案する。そのため、戦死者もほぼ出ないように配慮していた。孔明に完敗した周瑜は晴れやかな気持ちで息を引き取る。周瑜の死は呉の人々を大いに悲しませた。第三部では赤壁の戦いより、この周瑜が孔明にこてんぱんにやられ、最後は病に倒れる、という話が見せ場だ。どうあがいても勝てない周瑜。どうしてそこまで孔明に嫉妬するのか、それが歯痒い周瑜。また、全く弱味がなく余裕の孔明にも歯痒い。そんな二人の戦いであるが、最後はやはり感動する。
第四部
ゆっくり読まなければ、と思っていたが遂に2020年8月に第伍部が発売されることが決まった。予想より1年早かったが、そろそろ第四部を読み始めることにしよう。
張松と龐統という人物が中心になる。張松は竹中半兵衛のような人物か。自身野望を持っており、曹操の元に遣わされ、横柄な態度で曹操を試す。小さい男だと見切った張松は去る。龐統は孔明と親友だ。事務仕事に飽きた龐統は仕官先を探す。魯粛の推薦で孫権に面会するが、龐統の不遜な態度に孫権は納得できずこれを拒む。どうしても登用させたい魯粛は劉備の所へ行ってみればどうかと推薦状を書く。劉備の元に行った龐統だが、やはり不遜な態度。それでも劉備はお試しにと辺境の耒陽県の県令とし、様子を見た。しかし1ヶ月丸々仕事をせず、酒ばかり飲んでいた。それを見とがめた劉備は張飛に様子を見てくるよう命じる。場合によっては殺してしまえと。行ったところ1ヶ月仕事を放置したのは、この程度は半日でできるからだといい、実際に半日で完了させてしまう。それに感服した張飛はもっと大きな仕事をさせるべきだと劉備に進言する。
魯粛や呂蒙など呉の人物だが初めは広島県呉市にかけて広島弁だったが、ここへ来て広島というよりは九州辺りの方言になって違和感がある。
曹操対関中十部の決戦がある。関中十部の1人で馬超、十ある部族の1つ。これがなかなか戦上手というか、武力に優れている。曹操は馬超の事を気に入り、部下にしたいと考えるが、まずは関中十部を圧倒的戦略で制圧する。馬超は逃亡する。
曹操は高慢ということで諦め、荊州をふらついていた張松。そこへ劉備主従がオールスターキャストで出迎え歓待する。劉備はこの頃まだ国を持たず、呉の1つの県を預かっているにすぎない。蜀を狙うための一環で張松を落とそうとする。案の定張松は劉備を信頼し、劉璋を売ろうという話を明かす。劉備はその場では謙遜し、張松を国へ返す。
同族を倒して国を奪っても、国の民が従わないのではないかと心配する劉備だが、愚かな王に治められるより、良き王に治められる方が民は喜ぶと龐統に説得される。いよいよ心を決めて蜀に向かう。軍師は龐統だけ兵も三万だけで、孔明、関羽、張飛、趙雲は荊州に残り孫権に備える。
劉備は内心蜀を奪うつもりで益州に向かった。同胞の劉璋に歓迎される。龐統は歓迎会の最中にいきなり切り捨ててしまう作戦を主張したが、劉備は慌てず、まずは人民の心をつかむことが先だと、宴会に浸る。ここで著者の気になるコメントが色々入る。三国志を読んだ人なら常識的なのだろうが、これが初読みの者からすると気になるものだ。まず、蜀を一気に奪おうと考えている劉備だと思っていたが、実際にそれを成し遂げたのは2年半後だったとか、孫権は劉備は益州を奪うための助っ人と考えていたし、妹は劉備に嫁いでいる。それなのに出し抜いて劉備自身が蜀を奪って王になろうとしていることに怒り、妹・孫氏と劉備の実子の阿斗を母が危篤と騙して呉に帰らせようとした。劉備不在中の阿斗の監視役である趙雲はそれを察知し阿斗を奪い返した。どうやら孫氏(小僑)はそのまま劉備と離婚したようだし、阿斗(後の劉禅)は長坂坡に続き、はからずも趙雲に2度も救われたとある。劉禅はあまり好ましくない人物になったのだろう、それを子供の時に趙雲によって命を2度まで救われた。と言うような匂わせがある。
龐統を軍師とし蜀へ向かう劉備だったが、乗っ取りがばれて蜀から追われる。しかも挟み撃ちにされピンチを迎える。1年半耐えた。龐統は打開策がないか地形を探っていたが、ついに突破口を見いだしたが、帰りに伏兵によって討たれる。龐統の面目を潰さないよう密かに孔明に使者を送っていた劉備。しかし間に合わなかったのだ。その後関羽を荊州に残し、孔明は張飛、趙雲達と共に劉備に加勢に来る。それでも苦戦するが、やがて蜀を落とす。素晴らしいのは武力でだけで落としたわけでなく、どちらかというと調略で手に入れたということだ。
曹操は漢中を攻める。張魯が主であるが負ける。通常なら処刑されてもいいはずだが、善人ということで早々に認められ、取り立てられることになった。曹操のいない好きに合肥を攻めた。1万の呉兵に対して曹操側は張遼が守る7千に過ぎない。余裕で勝利かと思いきや苦戦し、退却する。しかしそれを追いかけて張遼が攻めてくる。孫権は危機を迎える。呉の甘寧と、甘寧に親を殺され仲間ながら敵愾心を持つ淩統は、対立していたが、孫権を逃がせるために命を懸けているうちに仲良くなる。この場面は感動する。
曹操は魏の王となる。後継者を曹丕にするか曹植にするかで迷う。その間にも孫権を攻め遂に臣下に取り込む。その頃魯粛が46歳で死ぬ。最大の軍師だったがそれが影響したのか。
多くの英雄が死んでゆく。
荊州を守り、かなり自意識過剰になり増長していく関羽。独自に周辺を攻め国をとっていくのだが、孫権は曹操と結託し関羽を討とうと画策する。三竦み状態が大枠だが、周辺から崩されていくようだ。関羽の最後は寂しい。手兵がどんどん討たれ最後はあっけない。曹操は病に倒れる。曹操は死んでも華美な埋葬をするなとした。しかし盗掘を懸念し、偽の墓を72ヶ所作ったという。張飛も部下に厳しくしすぎ、部下から殺されてしまう。あっけないそして意外な最後だ。関羽、張飛と仲間を失った劉備は呉を仇とし、戦略でなく個人的感情で攻めようとする。孔明は軍師として参加せずそのため、まずい戦いをしてしまう。そして劉備も呉に大敗を期す。
そして白帝城に逃げ籠る。その際孔明が配置した岩で敵を撹乱する。あの奇門遁甲が登場する。敗戦のショックでめっきり気力をなくす劉備で、病がちになる。孔明に遺言を残すが、後継者であり息子の劉禅に才を見ればこれを助け、才がなければ孔明自身が皇帝となれというものだった。
三国志前半の主要人物がほとんどいなくなってしまう寂しい展開。孔明が主役なのだからこれでいいのだろう。
第伍部
いきなり今までのダイジェスト。これをラーメン屋で例えるため余計わからなくなる。
孔明は北伐の前に南方平定する必要があった。5巻に入って孔明の初戦。雍闓、高定、朱褒を互いに疑心暗鬼に陥らせて倒す。これこそが調略だ。あと孟獲が残っているが、南蛮王と呼ばれ、全くの独立部族なのため通常の戦略では落とせない。
孟獲は三國志のはいしょうしの注によると、七擒七縦(しちきんしちしょう)といって、七回負かして捕らえ、七回放っている。そんな学習能力がないのか、執念深いのか、また孔明の寛容さなのか、策略なのか。つまり孔明は孟獲を討とうとするのではなく、服従させ、反乱を起こさせないようにするというのが第一と考えているのだ。
3回まで捕らえ逃がした。この策略は読んでいて楽しく飽きない。しかしこの後もこんな感じで繰り返し話は進むのか。
従者の馬玄にいう「馬玄よ、考えるな。感じるのだ」と孔明はリーのようなことを言った。これはかなりマニアなギャグだ。知ってるからいいものの。リーがブルース・リーのことで、しかも「燃えよドラゴン」のなかのセリフなのだから。
何と4度目もあった。そしてまたもや逃がす。その時、次に負けたら孔明に降参すると言った。そのあと孟獲は禿龍洞に逃げる。孔明が禿龍洞に辿り着くには2つの道しかない。東北の道は通りやすいが、西北の道は険しく、さらに四つの毒泉と道中瘴気に満ちている。東北を塞ぐことで、孔明が攻めてこれないようにした。孔明は偵察兵を向けたが、やはり泉の水を飲んで毒にやられてしまった。伏波将軍の像がある廟に住む老人から万安渓に隠者がいることを教えられる。その隠者は植物の研究家で泉の毒を解毒したり、瘴気を消す薬草を育てている。孔明はその隠者に助けを求めると、快く助けてくれた。名前を聞くと孟節、つまり孟獲の兄だという。なぜ弟の孟獲を攻めるという助けをしてくれるのか尋ねると、弟とは性格は逆で、その横暴さを諭したが聞き入れないので、孔明に、捕らえてよく言い含めて欲しいという。禿龍洞の前まで無事に到着し布陣する孔明。孟獲は仲間の楊鋒に助勢を求め3万の兵がやってくる。安心していたら、既に孔明によって調略されており、楊鋒は孟獲を裏切りこれを捕らえ、孔明の前に引き出す。孟獲は孔明が直接攻めたわけではないから卑怯だといって納得しない。そして5度目も逃がす。
自分の本拠地、銀坑洞で戦うことを決意。さらに木鹿王という法術を使う猛将を呼ぶ。木鹿王は自分は白い象に乗り、虎、豹、狼、毒蛇、蠍などの猛獣を指揮する。諸葛孔明は黄夫人と製作したロボットを使い対抗する。
現在のハノイあたり。孟獲の遠縁、烏戈国の兀突骨(ごつとつこつ)率いる藤甲軍。藤で作った鎧が鋼鉄よりも固く、刀や槍を通さない。まさに無敵の兵。孔明は油につけて固めたその鎧の弱点をつき、火攻めをする。その阿鼻叫喚の場面が凄まじい。孔明はさすがに残酷なことをしたと後悔する。しかしこの7度目の勝利により孟獲を懐柔することができた。南方を征服するのでなく、自治区として認めたのだ。これにより後顧の憂いなく北に出兵することができる。この戦の間、孔明はよく眠ることが多くなった。何か体調不良が心配されるようだ。
魏は曹丕が40歳、在位7年で病死する。後継は曹叡。なかなかの人物。この隙に孫権は魏を襲う。江夏を攻めるが敗北。再度江夏の襄陽を攻めるがまたもや敗北する。孔明は北伐のための準備をすすめる。出征前に出師の表という中国史上、稀代の名文を書く。劉禅に対して気合いを入れ直す内容らしい。
まず、魏の夏侯楙を倒そうとする。そのため元々劉備の元にいたが、関羽が討たれたとき魏に寝返った孟達を再び蜀に寝返らせる作戦。このため綿密に準備していたが、魏の司馬懿によって妨げられ、孔明の第一歩は失敗する。太守の夏侯楙(かこうぼう)は韓徳に蜀を撃つよう指令を出す。孔明はこれを趙雲に対応させる。しかし調子に乗りすぎた趙雲は敵陣に深く入り込んでしまい絶体絶命のピンチ。せめて夏侯楙の首を土産に死を覚悟した。その時蜀の兵が助勢する。張苞(張飛の息子)と関興(関羽の息子)だった。これにより蜀は韓徳を討ち果たし、夏侯楙は南安城に退却し籠城する。これを攻略するため孔明は周辺の安定城と天水城に調略を仕掛ける。この策が良くできている。武力でなく謀略で落とすのだ。
天水城においては大した人物はいない。だが姜維伯約という青年武将は光るものがある。現に蜀軍の攻めを読んでいた。そこで倒すことより取り込むことを考える。
結果としては姜維を蜀に率いれることに成功した。そこからはトントン拍子城を調略で落とし、ほぼ戦することなしに、南安、安定、天水を治めた。孔明は姜維のことを自分の後継と大いに買っている。一方魏延と孔明は噛み合わない場面が多い。
魏の曹真との戦。王朗という老兵が孔明に大義名分を発するが孔明にはこたえない。逆に孔明に一喝され、落馬して呆気なく死ぬ。罵り殺されたという。魏は夜襲で倒そうと計画したが、孔明に読まれておりさらに裏をかかれ兵の大半を失う。曹真は西羌に兵を借りることにした。迎え撃つ孔明は八陣図を使い翻弄する。孔明は勝つ。西羌の頭の雅丹は捕らえられたが孔明は、蜀に恨みがあって攻めたのではなく、魏にそそのかされただけだから罪はないと言って逃がす。これで西羌とのいさかいはなくなるだろう。
次に魏の曹延は司馬懿に作戦を立てさせた。街亭が要の戦場になると読んだ。一方孔明も街亭が要になると踏んだ。そこの司令官を誰にするか。馬謖を抜擢する。39歳の馬謖にとってははじめての活躍の場である。
馬謖には王平が従う。街亭についた馬謖は城を守るという孔明の作戦を無視し、功を焦り魏軍を倒そうと、独自の判断で崖の上に陣を敷く。王平は再三諫めるが聞かず、わずかの兵を分けてもらい王平は城を守る。馬謖は張コウによって水路を絶たれ、結果として敗北する。帰陣した馬謖は、規律を乱した罪で孔明に処刑された。馬謖は孔明の愛弟子である、そして後継者ともなりうる才能を持っていたが、規律を重んじ泣く泣く馬謖を処刑に処したのだった。そしてこの敗北が元で今回の北伐は断念せざるを得ず、撤退することとなった。孔明が帰宅すると黄氏が男児を出産していた。名前は瞻(せん)
魏の曹休に対しては、呉の周魴が魏に寝返ると見せかけ手紙を7通くらい送る。
郝昭の守る陳倉城は、蜀軍が圧倒的に数が優位であり、孔明の特殊兵器もそろっているのに落とすのに苦戦する。これまで孔明は様々な奇策でもって戦いを勝ってきたが、全く冴えがない。
趙雲が死す。戦で死んだわけではない。享年は72歳というから、結構な年齢だったのだ。
魏が南伐といって蜀に攻めてくるが、40日にわたる大雨のため撤退していく。
第四次北伐は孔明と司馬懿の直接対決となる。司馬懿は持久戦に持ち込み蜀の糧食が尽きるのを待つと言う消極策をとる。孔明は絶対勝つと言う強い意思のもと知略を尽くす。戦術的には八陣図を駆使し勝利する。その際魏の重鎮である張郃が討たれる。このままの勢いで魏軍を壊滅させることができたが、糧食輸送の重要な役割を任じられていた李平(李厳から改名している)が孔明への嫌がらせのため、輸送を止めていたため、撤退を余儀なくされた。この李平の行いが読んでいるだけで腹が立つ。孔明も当然怒るわけだが、理責めで李平を追及する。観念した李平は白状し謝罪するが、法を順守する孔明は処刑を命ずる。ところであったが、劉邦の信頼していた人物であるので、命は助けられた。
このあと、呉の孫権の話が挟まれ、諸葛孔明は曹操との対比として描かれたのが三国志という作者の考えが続く。作者は孔明に「この巨大な国は放っておくと必ず分裂する」と言わしめしている。この国ということで中国を示しているが、実は世界中そう言えるのfではないかと感じる。エントロピーの世界だ。
そして3年後の第五次北伐にはいる。それは諦観の風が見えるという。
孔明がなぜこのタイミングで出兵するのか?誰しもそう思った。星占いでも今ではないと出ている。星占いに精通している孔明自身が分かっているはず。
漢中に到着した孔明は関羽の息子の関興の訃報を知る。心臓病。張飛のの息子張苞に次いでの訃報に孔明は落胆する。
孔明の作戦は司馬懿によって打ち砕かれる。敗北したが死を決した孔明は引くわけにはいかなかった。
次に司馬懿は祁山に攻めたがこれは孔明の罠で、多数の地雷で攻められた。火攻めに会い、いよいよ司馬懿親子は死を覚悟する。ところが大雨が降り火を消した。
司馬懿つまり魏の作戦は堅守すること。食料の調達が毎回困難な蜀は長期戦では不利なので、持久戦とする。戦うことが本分の両軍の兵士たちは、戦のないことにいら立ってくる。魏が攻めてきてこれを撃退すること作戦である蜀は、魏を幾度も挑発するが全く攻め寄せることはない。こうして数か月たつ。孔明の健康状態はどんどん悪くなる。明日をも知れぬ状態で孔明は多くの書き物をしたためる。劉禅やその家臣たち、家族などにむけて。延命の儀式も行ったが、それはかなわなかった。赤い流星が3度落ちる、そのうち2回は地上からまた空に帰るという奇妙な現象。3度目は帰ることがなかった。その時孔明は息を引き取った。54歳のこと。
孔明最後の策は、孔明は生きていると思わせること。埋葬せず生きているように見せかけたり、木像を陣頭に出現させたり。それで、司馬懿の魏軍は撤退していった。「死せる孔明、生ける仲達を走らす」という言葉が残る。ただ作者は孔明と司馬懿は。戦をしても双方メリットがないから互いに撤退しようと合意していたのではないかと推理する。
その後は魏延が事実はわからないが謀反の罪で討たれる。孔明に嫌われていたため不遇な死。対立していた楊儀も後に劉禅の怒りを買って庶人に落とされる。孔明は自分の後継者を考えていたがそれも潰える。孔明の死後蜀は魏に滅ぼされる。呉の孫権は耄碌して晩節を汚し、後継者の代でやはり滅ぼされる。魏においてはやがて司馬懿の孫の司馬炎が晋朝を興す。統一が成ったわけだが、間もなく、分裂国家の五胡十六国時代となる。その後も中国は統一と分裂を繰り返す歴史なのだ。ただ孔明は統一を目指すというより三国に分裂させておいて、互いに緊張させることである種の安定をもたらそうとしていたように見える。
天才的な軍師であってもやはりいつかは衰えるか死を迎える。病に冒されてからの孔明は精彩を欠くようにも見えて淋しい。しかし全盛期の活躍は素晴らしい。特に、八陣図という武器はあったが、戦上手というより、駆け引きに長じていたというべきか。
第壱部
20171005読み始め
20171011読了
第弐部
20171011読み始め
20171015読了
第参部
20171017読み始め
20180107読了
第四部
20200729読み始め
20200815読了
第伍部
20200927読み始め
20201022読了










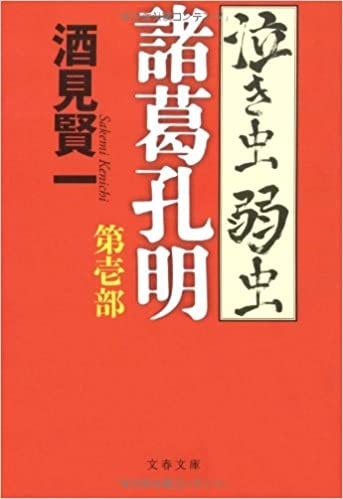
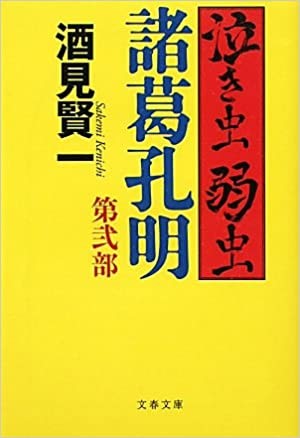
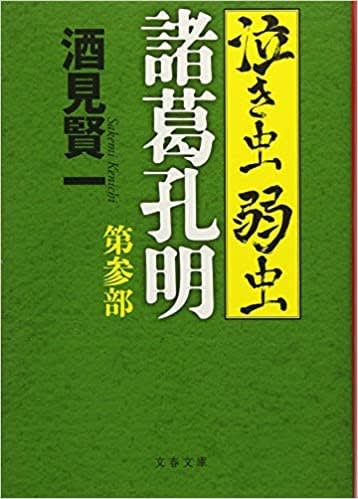
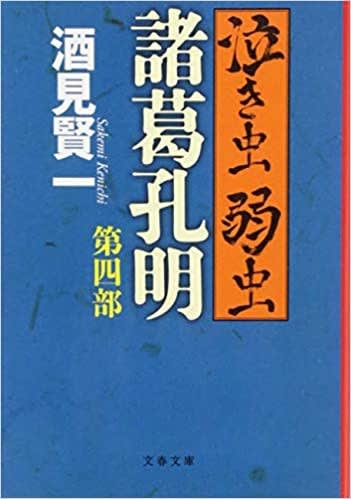











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます