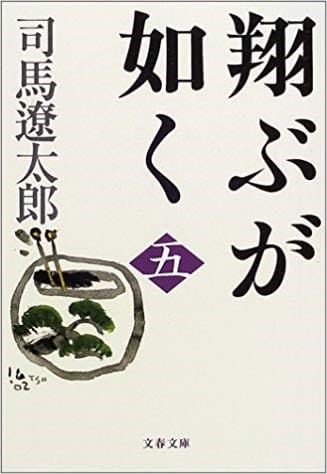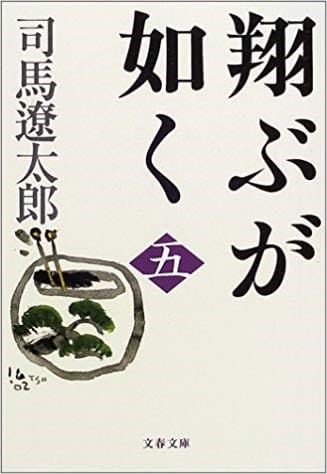





第1巻
p96
明治政府は軍隊を持たなかった。明治4年廃藩置県を断行するに当たり諸方に乱が起こるのを予想し東京に軍を置く必要に迫られた。が、他藩は信用できないということで、いわば身内、つまり薩長土から藩兵を集めた。そのトップは薩摩出身の桐野利秋。これが近衛兵、日本陸軍となっていく。
一方、同じく薩摩出身の川路利良の方は、やはり薩摩藩の郷士で構成した、近衛兵から外れている残りから2千人に加え、あと千人を他藩から選抜し東京における治安兵力を従える。これが後の警察の原型となる。
どちらも西郷隆盛が設計した。
p102
明治の大官は旧幕府の時のように、草履とりを従え身の回りの世話をさせていたのを皮肉り、「明治維新は革命ではなく単に権力交代である」といったものだそうだ。
中村楼での話。薩摩人が荒々しいのがよく分かる。そんな中、西郷隆盛は酒に強くないため早々と出来上がってしまう。川路利良は薩摩人でありながら、職務を優先し不参加。一方、桐野利秋は参加してはいるがその場の騒動の真っ只中、平然と一人で酒を飲む。騒ぎを止めるでもなく、また絡まれることもなく。対照的な3人の様子が描かれる。それにしてもこの桐野という男は全くめんどくさそうな奴だ。気に入らなければ、無表情に一刀の元に切り捨てる。表情からは前触れを読み取れない。さて、こいつは自分に好意的なのかそれとも敵愾心を持っているのか?話をしながら自分はいつでも刀を抜く用意をしていなければならない。これでは落ち着いて対話もできない。そうかと思うと、突然風呂にでも入るかと打ち解けてくる。全く面倒だ。
西郷は革命を起こした張本人である。幕府を倒した。しかし、それによって敗れた武士たちはどうなるのか心配した。倒幕とはそれが結果なのだが、その結果に対して同情した。そのあわれな武士を元気付けるのは征韓論だった。行き場所をなくした武士の不満のはけ口を外国に向け、侵略することでごまかそうと言う考えにすぎないのではないか。西郷自身は(ここではすぐに死にたがるというメランコリー症状的に描かれている)韓国へ行き韓国における開国を迫ろうとした多分自分はそこで殺されるだろう。そうして死ぬことで韓国や日本の未来の碑になることが自分の役目だと思い込むようになった。
内容とは別だが。司馬遼太郎のすごいところは、山田風太郎と違い、小説にどんでん返しのようなものはないということだ。淡々と歴史の事実を語る。はっきり言って「日本史」というくらい。ただ、そこに登場人物の意識が加わる。もちろん未来の我々にとっては過去の人物が何を考えていたかはわからないし、その当時何を考えたかも想像できない。しかし、絶妙のエッセンスで歴史上の人物はこの時こう考えたであろうということを推理して小説に盛り込む。このバランスによって、あたかも歴史はこのように作られたと思ってしまう。山田風太郎は、それを最終的にはまことしやかなエンターテイメントに完成させる。司馬遼太郎はあったかも知れない事実を語る。どちらもすごいことだ。
この「翔ぶが如く」と、前に読んだ「関ヶ原」と共通するのは、章ごとに歴史の人物の人物像を描くことだ。小説全体として調和を維持しつつ、各章で、主人公となるべき人物を立て、その人物自信、その周辺を語る。時にはどこまで脱線するのか?さらにその脱線からさらに脱線するということも発生する。あたかもピンチョンの小説のように(と、言え、まだ完読したことのない自分が勝手に想像するのだが)。感覚としては歴史的事実80%、脚色20%といったところか。ただこのバランスが天才的だ。読み物として面白いし、歴史的事実を知るという意味でも正確だ。
p346フーシェについて。川路はフーシェを尊敬していたが、実はフーシェは悪党であった。それは後の世にわかることで、フーシェは悪党で、川路はそこまでの悪党ではなかった。
第2巻
西郷隆盛をそうせしめたのは、少年時代平凡であったのを「己を愛すなかれ」という自己教育の会得だった。自虐的ともとらえられないが、そうすることで世の中がよく見えるようになった。弟の従道や従弟の大山巌も感化された。大山巌は懐の大きい人物であったが、従兄の西郷従道には及ばない。その従道であっても西郷隆盛には全く及ばないというからいかに隆盛が大きい人物であったかということがわかる。
2巻で意外だったのは、西郷はその大きさゆえに、反乱を起こし新しく幕府を作るのではないかと怪しまれてたという。これは知らなかった話だ。
廃藩置県が必要という話が上がり始めたとき。藩は絶対に廃するべきだと、長州人3人が密議をした。大きな変革だと思うのだが。これに従わぬものは誅殺するなどと戦争が始まりかねないことを言っている。
廃藩置県の協議は長州の木戸孝允、井上毅、薩摩の西郷隆盛、大久保利通で行われた。藩主は一斉に廃止される。つまり身分を取られてしまうということで従わない者もいるだろう。そうなれば討伐すると物々しい。長州に関しては藩主は従う派であったが、薩摩は絶対反対派だった。島津久光がそうだ。そのため西郷は島津から恨まれ続ける。
伊藤博文が尊敬する人物四賢、木戸孝允、大久保利通、三条実美、岩倉具視で西郷隆盛は入っておらず、眼中にはなかった。また伊藤博文、井上馨、大隈重信は仲が良く、若手の急先鋒と言ったところか。この3名が征韓論を潰す役を担う。
明治政府は法制をフランス、ドイツに学び、陸軍はフランス→ドイツ、医学はドイツ、海軍はイギリス。イギリスに学んだのは他には造幣局で、大阪にあった旧幕府の後破損奉行所のあとに作られた。淀川に面する。
朝鮮には武備というものは無きに等しい。武力を持てば中国から警戒され、中国から武力が送り込まれる可能性がある。だから敢えて持たず、有事の際には中国に守ってもらうという体制だったようだ。まさに現代における日本のようなものだ。まさか日本はそう考えてこのようなのだろうか?一体何年前の思考なのだろうか。
「千絵」の章。千絵は極めて幼少の頃から不遇な人生を歩む。さらに不幸なことに
その兄は戦死したという。その兄を殺害したのは桐野だという。何の因果か、千絵と桐野は再会する。桐野は別に敢えて千絵の兄、芦名新之助を不可抗力とは言え殺害することになった。などと、敢えて公言せずとも、そっとしておけばいいのに、ついつい言ってしまうのだ。桐野と言えば1巻で無表情な冷酷な志士のようであったが、ここでは人間味のある人物となる。
西郷は倒幕の頃には様々な権謀を巡らせたが、維新後はそれを捨ててしまった。
三条と岩倉は征韓論を封じ込めようと画策する。板垣に相談すると、西郷を廟議に欠席させてはどうかと提案する。征韓論は結局は西郷が自分自身の死に場所を求めての、いわば個人的な思いだけのものだ。西郷一人が死ねばそれでいいわけだが、天皇の勅使として遣韓してる以上、西郷が殺されれば兵を派遣せざるを得ない。しかしその兵は日本にはまだ数といい能力といい十分ではなく、確実に負けてしまうだろう。それは避けたい。そもそも征韓論は、欧米各国が日本に開国を迫ったように、日本が朝鮮に開国を迫り、提携していこうという考えだが、朝鮮は頭が固く、日本に対しては高圧的であるため、ほぼ確実に遣韓大使は殺されるだろう。そこに西郷はちょうど死に場所を見つけたのだった。
最後、征韓論をどうするか廟議が開かれるのだが、西郷には欠席するよう進められ、無口な大久保がいよいよ腰をあげる。どんな展開になるのか?
第3巻
廟議の朝、西郷は三条に押しかけ、問い詰める。木戸は西郷対大久保の謂わば薩摩内の争いに巻き込まれないよう、わざと欠席する。そして西郷は三条と共に結局昼から参加する。
そこから反征韓論の大久保と征韓論の西郷が争う。大久保は現実的で、現代に当てはめても妥当と思われる理屈だ。つまり、今、日本には物資も金もない。そうやって弱いところに、攻められたら占領されるしかない。そうなれば日本はおしまいだ。それに対して、西郷は、いささか観念的で、韓国に派遣され殺されてもいい、そうすると、日本としては戦争始めざるを得ない。その際 、韓国には対抗できるかもしれない、しかしその隙を狙って清国が攻めてくるかもしれない、さらにはロシアが攻めてくるかもしれない。そうなると今の国力では日本は玉砕されるだろう。しかしそれでいいのだ。そこから強靭な侍の心を持った日本人が再び生まれてくるのだ。つまり軟弱な西洋的感覚の日本人が生き続けても何の意味もないと。
西郷は負けると思われたが、西郷派の暴発による政府の壊滅を恐れ、三条と岩倉によって西郷の意見が採用された。その代わり朝鮮、清、露に対抗できるよう陸海軍を増強することで責任をとろうと考えた。大久保も諦め、身を引いた。
ところがまた反転。あとは天皇に上奏するだけで、西郷も三条をせっつくのだが、三条も岩倉も仮病を使って動こうとしない。しまいには岩倉は財政難を理由に一蹴するのだった。
黒田清隆は薩摩人である。初め大久保の片腕として西郷を失脚させる。しかし西郷の死後、妻の惨殺事件というスキャンダルにより大久保の暗殺にまで発展した。事件の真相は不明だが、酒乱であったことは間違いない。そんな黒田も何と総理大臣にもなってしまうのだからすごいものだ。
西郷が小梅村に引き下がった。黒田が訪問したが何も出来ず帰って来て、その後、弟の従道が訪問する過程での話。左宗棠、さそうとう(ツォ・ツァン・タン)の話だ。アヘン戦争で清国はダメージを被ったのでは?という質問に、日本こそもっと甚大な被害を被っているのでは?つまり西郷を失ったことだという。その頃清国はロシアの脅威にさらされていた。西郷の征韓論は、朝鮮を制圧することではなく、維新後行き場所をなくした武士達が何十万人もいる。朝鮮への派兵は、ロシアからの脅威にさらされている清国へ助っ人を出す、ただその足掛かりだけである。つまりは、対ロシアの日清韓の同盟を意味していたのだという。左とは密約があったという。これがうまくいっていたら日清戦争はなく、日露戦争も様相が変わっていたという。
「陸軍卿」の章の主人公は山県有朋だ。参議になりたいという欲望を持って画策する泥臭い人間として描かれている。陸軍卿であったが参議になりたい。伊藤博文とは同格なのに、伊藤だけが参議になっているのが許せない。それを隠しつつ木戸に遠回しに打診するが軍と政治は切り離されなければならないという木戸の思想により一蹴される。そこで陸軍の職を辞すると申し出たが、向いてる向いていないの話ではなく、与えられた役割を精一杯果たすことが肝要となだめられた。そんな山県有朋もゆくゆくは総理大臣になるのだ。
明治6年から7年にかけて、維新から数年しか経っていないのに早くも新政府は瓦解するのではないかという不安定な情勢だ。また警視庁が創設されるが、どちらかというと秘密警察的な色合いであったり、反政府思想家に対抗する武力集団的な組織だったようだ。社会主義国家のようであり、独裁国家のようで、明治創立記の混迷感が見えて興味深い。また時間の流れが速い。あらゆること、変革が矢継ぎ早に起こる時期だったようだ。
第4巻
各章は長いのだが、3巻の最終章「混沌」だけは短い。明治創世記の不安定さとこれから安定へ向かっていく狭間で、不安定さが増していくのではないかという予感を感じさせる。
本巻序盤は江藤新平が下野し、佐賀の乱を起こす。勢いだけで何の考えもない。結局大久保の罠にはまった形だが、乱は失敗に終わる。江藤は逃げ、西郷を誘い逆転を図る。ところが西郷は期が熟していないと無下に断る。確かに西郷にとっては江藤に対して何の友情もない。自分はもう少し様子を見て、機会を伺おうとしているところに、勝手に乱を起こして敗れたから助けてくれと言われても困るというのが心情だ。しかし、ここで江藤を見捨てたなら、江藤は捕まり処罰される。見殺しにしなければならないという決断をしなければならない。それもまた苦しい。
結局江藤は捕まり東京ではなく地方で裁判(と呼べるのか?)で打ち首を宣告される。しかも前時代的な梟首だ。命じたのは大久保であり、見せしめにするための行動であった。これは衝撃だ。当時の人々、特に反政府思想家でこれから反乱を起こそうと画策していた人たちにとっても相当な衝撃であったようだ。
「私学校」の章。近代的な学校ではなく、武士の精神を忘れないようにするための学校。反政府分子の暴発を抑えつつ、その日のために覇気を保つためのものだ。江藤は早計であったが、薩摩もやはりいつかは、と考えてい
る。この章のなかで井上安武という人物が出てくる。森有礼の兄に当たるのだが、政府への提言を全く聞き入れてもらえず、最後、命と引き換えに意見書を出す。その中には現在でも通じることがある。「政令は朝に出て夕べにかわる。これは本気度が足りないからだ」「人を採用するのに人徳のあるものでなくずる賢い姑息な者のほうを選ぶ」「人事に関して基準がなく、大抵は好き嫌いで決めている」など(意訳)。
中盤から何やらキーマンになりそうな2人の人物が登場する。村田新八と高橋信吉という従兄弟同士の薩摩人だ。どちらも切れ者のようだ。村田は大久保が好きだが西郷に恩もあり薩摩に帰りたい。高橋も大久保派だが村田を尊敬しているだけに、村田が薩摩に帰れば高橋もついてくるだろう。一旦薩摩に帰れば、薩摩志士達が2人を帰さないであろう。いずれ乱が起きたときそれに巻き込んでしまうのを村田は気にしている。そして村田は高橋を残して自分だけが薩摩に帰ることを決めた。その別れの朝が何とも切ない。司馬遼太郎の作品世界で指折りの情緒的場面だ。
その頃の薩摩志士たちは大久保憎しという気持ちだけで盛り上がっているが、倒した後何がしたいのか?それ以前にその計画案も持っていなかった。これは幕末における尊皇攘夷と同じ状態だ。その点村田新八には「西郷を日本国の首相にする」という簡明な意志があった。
にわかに征台論が湧いてくる。琉球の船が遭難し台湾に流されそこで救助を求めるが反対に59名が惨殺される。一度は台湾に出兵しようという話が持ち上がるが、西郷の征韓論は敗れた時期で、征台論もたち消えになった。ところが、全国にくすぶる士族たちの欲求不満を解消する手だてとして、先の事件を盾に台湾に出兵し、惨殺した台湾の族をこらしめよう、それで士族たちの空気抜きをしようと企んだのである。それを発案したのが、あれほど征韓論に反対した西郷従道であり、大久保利通だ。こんなところが矛盾極まりなく、よくこの短期間で全く正反対のことを平然と決めてしまう。江藤新平の極刑は何だったのか?
三条により征台はストップがかかり、大隈が既に出兵の準備を進める西郷従道に伝えに来た。しかし従道はもう止まらない。既成事実を作ってしまおうと無視して兵を出した。しかしこの船旅が過酷で兵士の大半がマラリアによって死んでしまう。台湾上陸後は、こちらは容易く生蕃(せいばん)を抑えることができた。驚くのは台湾の庇護国の清との交渉で、日本の出征費を全額清に要求したことである。まるで無法者だ。清は米国にそそのかされたのではないか?と軽くあしらう。
第5巻
征台問題の解決のため派遣されたのは、当時20代の柳原前光で、老熟を重んじる清国はかなり軽んじた扱いをしたようだ。柳原は公卿出身で、公卿側からも人材を抜擢したいと考える岩倉具視の推しで登用された。さてまず上海に行って潘霨に会ったわけだが完全に軽くあしらわれ、勝手に台湾に行き西郷従道に会い、西洋にそそのかされだけなので無条件で撤退したいと言ってるぞと騙され、従道は骨抜きにされる。柳原は次に李鴻章にあったが、こちらも、君と私では格が違うのだ、君ごときに会うほどはないとあしらわれる。これはいかにも中国らしい。
山県有朋は征台に反対であったが、参議になれないのを拗ねているだけだろうと考えた大久保は山縣を参議にした。しかし論調は変わらなかった。山縣が考えるに挙兵しても、旧藩の士達が従うことはないだろうということだ。そこで大久保は皇帝陛下がいるではないかと答え、納得させる。そしてこれが天皇制の原型となる考えであったのだ。
自分が清国にいかねばならないと考えた大久保は、清に渡ったとき李鴻章を完全に無視した。通例なら北京の本体に面会する前に儀礼的であっても、実質の有力者である天津の李鴻章に会うのだ。どの国もそうしている。その意図したところは不明であるが、先だって李鴻章が柳原を軽くあしらったことを根に持って意固地になったのではないかと考えられる。外交上は、腹に一物持っていても、顔では笑顔で会うべきだったとされるが、これにはなかなかスカッとした。
恭親王が主席となる清と交渉するのだが、初日は酒宴が用意されていた。しかし、今までのようにのらりくらりとかわされて、清国側に丸め込まれるのを懸念した大久保はいきなり質問を投げ掛けた。交渉は数日後に開始で、まずは人を知ろうという清国側は意表を突かれた格好になる。この交渉の場面は手に汗握る。小説はこうでなければ。先ほど読んだ北方謙三の楠木正成などは、こう生きるべしと生きざまをダラダラ書いているだけで全く話の筋がない(ボロクソ、、)
交渉は第7回まで続く。大久保の駆け引き上手に興奮する。とは言え、初め優位に進めた大久保であるが、清国はのらりくらりとかわし、一旦は決裂し至りそうになる。そこで、帰国か、となった後も粘り、次は解決法だけ考えようという方針に転換する。これも初め優位に進んだが、お互い国家の対面、というよりは自国内での政権の維持のために引き下がれず、今度は完全に決裂してしまった。途中イギリスの仲介が入ったが、イギリスの思惑は、台湾から撤退してむしろ朝鮮を侵略してはどうか?(その方がイギリスの思惑に合致するという裏があったようだ)とそそのかす。どの国も悪辣だ。
最終的にはウェードが間を取り持ち、言わば双方の妥協的解決となる。清国は日本の要求する額とまではいかないが賠償金と言うのか見舞金を支払う。これで日本は負けていないと国民に言えるし、清国も見舞金ということで自国民に面目がたつ。この出兵による軍事的損害は少なかったが、マラリア感染という被害の方が大きかったようだ。後半に入ってから、マラリアに感染して瀕死の状態で台湾から帰ってきた熊本の宮崎八郎が中心の話となる。宮崎八郎は歴史的にもそこまで有名ではないが、薩長派閥に入りきれなかった熊本の不運を踏まえつつ、ルソーに心酔し独自の植木学校を設立する。これも現在ではあまり知られることはない。ルソー繋がりで中江兆民が出てきたり、宮崎の年の離れた弟で、こちらの方が知名度が高い宮崎滔天も出てくる。
P282の文がいい。西洋の議院を日本でも始めたいが、西洋の議院は一朝一夕に出来たものではないので、日本が簡単に模倣できるわけがない。という批判に対して、「学問、技芸、機会も同じではないか。もし我々が蒸気機械を用いるのに蒸気の理を発明してからでないとだめだという議論と同じである」
第6巻
なぜか戻ってきている木戸孝允が議会を開いているところから始まる。県令が集まって会議をしている訳だが、意外にも大山はやる気無さそうで歯痒い。とは言え当時は誰もがそのくらいの気構えだったようだ。熊本・白川県令の安岡は民主主義に比較的支持していたが、宮崎から強く討論される。安岡は宮崎の熱心さはわかるし民主主義を目指すことには同情的だが、それは建前で、単に政府を転覆させたいだけなのではないかと見抜く。
島津久光が主役になる章。実際は取り立てて何かに優れる個性ではなかった(司馬は久光をあまり良く描いていない)が、敵に回すと不平薩摩士族が一斉蜂起し、政府転覆を図るのではないかと案じ、左大臣と言う地位に抜擢する。その実、飾りだけで、何の権威も与えられなかった。そもそも久光は民主主義派ではなく、武家社会を維持したい派なのだから、今の政府とは相容れない。政府はただ薩摩の反乱を恐れて、そのためだけに久光を重職に就けた。久光はそれを察知し閣議を始めの1回だけ出席し、体調不良を理由に欠席し続けた。そのうち大久保を断罪し、天皇に大久保を辞めさせるよう直訴までする。とは言え先の理由から、政府は久光に強い態度には出られない。最終的には自ら職を辞すのだが、政治的欲望は収まらず、薩摩に帰り、大久保や三条・岩倉を追い落とすために、今度は西郷を見方につけようと、下野した西郷に使いを出す。節操がない。久光は内田正風を使いに出すが、結局西郷は応じることなく断った。
西郷の言語的特徴は、その論旨や考えを明確に述べることで、言葉を濁さないことだ。この点で政治家と言うより革命家であると言う。
久光の招聘を辞す書面を持って内田の屋敷に行く西郷だが、内田の母は西郷にえも言えぬ魅力を感じたそうだ。そこで内田は自分にはなぜか感じることができないが、西郷には何か人を引き付けるものがあって、その宝物のようなものを惜しくも自分は見落としているのではないかと一旦は思う。しかしそれは念仏信者が阿弥陀如来をありがたく思うようなもので、信者でない自分がありがたく思わなくても、それに何の事はない。というあたりがいい文章だ。ついつい後悔してしまいがちなとき、吹っ切ることができそうだ。
前原一誠と言うのが出てくる。西郷の小さい版で、タイプが似ていて、また前原が山口に帰ると、前原を祭り上げ反乱分子が蜂起すると言う危険性がある。と言う点でも似ている。維新の十傑に数えられる人物だ。しかし司馬は前原は軽く扱っている。あまり政治全体をみることができないということのようだ。前原は、先頃江藤新平が佐賀の乱を起こしたように、萩の乱を引き起こす。しかしそれは政府からそそのかされたものらしい。萩の不平士族と薩摩が組んでしまい反乱を起こされてしまうと抑えきれないだろう。そこで早目に萩で単独で蜂起させ、即時鎮圧してしまう策なのだ。佐賀では大久保利通が仕組んだが、佐賀では木戸孝允と川路利良が仕組んだ。ドロドロした時代だ。
前原一誠が不穏だ。前原は長州出身で木戸孝允もそうだ。長州の事は長州で解決させたいと言う木戸。これに対して薩摩の大久保や川路は遠慮してしまう。大久保らが関与してしまうと、対抗心を持つ木戸が怒り出すかもしれないからだ。そういった意味でも薩摩はこの時代にあって異色である。
前原が乱を起こす前に神風連の乱が起こる。熊本で起きた事件だが、不平士族の反乱というよりは宗教的思想によって反乱を起こす。神道を重んじそのため太政官に反感を持っている。熊本鎮台を襲撃するのだが鉄砲などは破棄すべき外来の利器であるので、日本古来の刀、槍、薙刀で襲撃する。深夜に決行したため、意表を突かれた鎮台側は大量の死者を出した。完全崩壊から形勢逆転したのは当時24歳の児玉源太郎によるところが大きい。兵を立て直し鉄砲を活用し今度は神風連を壊滅状態にする。この神風連の乱の被害の凄まじさは維新以来最大ではないかと思われる。
このたびの熊本鎮台の脆さが西南戦争における、西郷軍が熊本を拠点にすべきという誤解の元となったのではないかと作者は推測する。
第7巻
前原一誠が萩で反乱を起こす。それ以外にも各地で反乱が起きる。隙あらば政府転覆を謀る、そんな不安定な情勢だったようだ。徳川幕府への不満から維新が起き、明治政府が誕生するわけだが、その明治政府に反抗する勢力がまた生まれる。太政官をやめて国へ帰った有力者はそこで反乱の頭に立てられる傾向にあり、大久保や伊藤博文らは東京に残るよう説得を続ける。それとは別に川路により密偵に動きを探らせ、反乱を未然に防止している。小さい反乱はこれによってほぼ初期の段階で鎮圧させられた。
薩摩は維新後も異質の政治を行っていた。近代的な政治を行う他県と異なり、独自で旧態依然とした政治を続けていたのは前の巻から度々示されてきた。鹿児島県だけが特別視されるのはおかしいと大久保は木戸に責められる。つまり、薩長が中心に維新を起こしたのに、薩が全然変わっていない。大久保は木戸に責められ焦る。鹿児島を何とか抑えねば、木戸つまり長州にしめしがつかない。実は大久保には他人には言えないが、島津久光や西郷に対するしがらみがある。何しろ鹿児島の政治の大部分は旧薩摩の人間が就いているからだ。そこで木戸の圧力に対する次善作として長州出身の川口を鹿児島に派遣する。
「内務卿の靴音」の章では、鹿児島にそろそろ不穏な動きが見え始める。大久保は様々な人物を鹿児島に送り、鎮静化させようとしたり、状況を探らせようとする。大久保はこの件に関しては同じ鹿児島出身である自分にとって、内輪だけの問題としたかった。自分だけで抑え込んでしまいたかった。そのため他藩出身の、伊藤博文や大隈重信には一切相談しなかった。章の終わり頃には事実かはわからないが、大久保、川路による西郷暗殺の指令が出たような動きがみられる。西郷一人がいなくなれば鹿児島の不穏な空気は収まるだろうということらしい。
政府の諜報員の中原尚雄と、それを逆利用した私学校側の言わば逆スパイである谷口登太。この対話が西南戦争の発端となったようだ。谷口によると中原が、西郷さえ暗殺してしまえば抑え込むことができると言ったという。しかし中原は西郷を説得し西郷が受け入れなければ刺し違えても自分としては本望だと言ったという。どちらが正しいか後年調査されたが水掛け論と言うことになり、谷口は言説を曲げてしまった。それは政府に懐柔させられたとも、脅迫されたとも言われる。しかし、その谷口はその後長く生きた。ただ形見狭い生活だったようだ。
p217からの「西郷下山」の章。島津斉彬の遺志を継いだのは西郷だ。そしてその西郷を尊敬するのが桐野だ。島津斉彬は産業革命とも言える、産業発展を進めたのに対し、次の久光はそれを止めた。そして斉彬のこの点だけは西郷は異なり、西郷は農業系だったようだ。むしろ大久保の方が産業発展系であり、国家規模で産業の近代化を進めた。そんなところが歯痒い。
これまでの内乱のように発端は他愛もないきっかけだ、何か行動しなければ、という空気が高まり、始めてしまう。そして、蜂起しても戦略や勝算があるわけでもなく何となく行動してみるという雰囲気だ。結局そうやって制圧されてしまうのだが、果たして西南戦争も同様の展開をするのだろうか。実際そうだった。西郷が中心人物であるが、西郷自身ただ死に場所を探しているだけで、むしろ楽観的だ。桐野、篠原も推進派だがこれも楽観的で、始めたら何とかなるだろうという気運だ。比較的冷静だったのが大山だったろう。
第8巻
桐野から始まる。人斬り半次郎と呼ばれた桐野だ(同じ時代の人斬り以蔵と重ねると感慨深い)が、鹿児島に帰ってからは農民として地味な生き方をしている。遡ると桐野は下級武士だったため、昔は、上級武士からひどい仕打ちを受けていた。しかし桐野はそれを甘んじていた。反抗する考えも及ばなかったのだろう。
西郷はここへ来ても静かだ。祭り上げられている感じ。その理由は。西郷は黒目が大きくその目を直視するのが困難で、一度見てしまえば、やられてしまう。なにかその目に魔術的なものがあるということだ。
鹿児島の士族の従軍について動機はなにかと推測するが、残された文献からは、参加しないのは臆病であったり、刺客問題に触れ義心をもって従軍するという意志がみて取れるようだが。しかし、それはまれなケースであって、西郷への刺客問題がなく、政治的思想を掲げて兵を徴集した場合そんな言葉が残ってはいないだろうとのこと。
勝海舟は大久保を政治家として買ってはいたが、長州を嫌っていたため、長州を使う大久保を好んでいなかった、逆にそれに対抗して西郷が郷党組織を率いて武力で破ろうとしていることに好感を持っていた。勝は旧幕府に属していたため、幕府よりの考えをしている。徳川幕府が誕生した当時、薩摩はむしろ反幕府勢力であったが、(ここでも司馬遼太郎による徳川の政治的いやらしさが滲むのだが)、征伐するよりは、懐柔した方がいいだろうという思惑で、その後200年間腫れ物に触るように接してきた。それが平和と安定をもたらしてきたのだが、新政府はそれを無視し薩摩を軽視したのがよくないと考えている。そして勝の結論は大久保と黒田が辞職すればよいと簡潔でキレがよい。
この時代もそうだが、現代においても、重要な書簡、今で言えば電子メールだろうが、極秘の重要なものをなぜ保管しているのか?現代においては大体、不正や汚職の証拠として表に出てくることが多い。捨ててしまえばいいものをなぜ残しておくのか?と不思議に思うほどバカみたいなものもあるくらいだ。明治時代やそれ以前の書簡というのは歴史の転換とも言える重大時の資料として興味深いものだが、現代人もそう言う、後世に自分の功績を残したいという欲を抱いて文書を残そうとするのだろうか。
薩摩の蜂起に対して大久保や岩倉、三条は西郷とは無関係と思いたかった。大山は渋谷を政府に遣い、西郷は無関係と嘘をついた。つまり、西郷を守った。それに対して川路は西郷は参加していると確信しており、直前に情報通信社の海老原穆を捕らえている。山縣は西郷に恩があるものの鹿児島に乗り込んで一気に鎮圧しようと考える。西南戦争の発起時期においてそれぞれの思惑が絡み合う。この辺りが見せ場だ。
後の日露戦争で有名な乃木希典であるが、薩軍鎮圧の頃にも登場してくる。ただまだ若いため未熟な面が多い。政府軍の軍旗を奪われてしまう。これが政府にとっては不名誉なことで、どういった経緯で薩魔の手にわたったか歴史から事実が消されてしまっている。これを推理するミステリーのような展開。
乃木と吉松秀枝の関係。吉松の方が年齢も経験も上だ。しかし吉松が薩長閥でないため、乃木の下に付かされた。クライマックス、援軍を望む伝令を乃木に再三送る吉松だが、乃木に軽蔑的に拒否される場面。辱しめを受ける形となった吉松だが、やり返す。そしてその怒りの勢いで憤死する。これは感慨深い。
司馬遼太郎はしばしば、その時代時代の主要な人物の行動の愚劣さを皮肉る。城塞では大阪方のあらゆる首脳部を批判する。ここでは乃木希典なのだろう。とは言え、歴史の中では乃木将軍と言えば神格化されている。それを否定することで、後に(つまり現代2018年あたりの)批評家から司馬遼太郎は批判されているような気がする。
168と284は同じ内容となる。
薩摩の蜂起は7巻では何となく、の雰囲気で始まったように思われたが、実は軍議の前に話はすでに出来ていて。軍議自体はその確認だけであったことがわかる。とは言え、戦いぶりは出たとこ勝負な空気がある。薩摩人の気風からして、出会った敵をその度に斬っていくだけ。という戦いぶりでその計画性のなさが際立つ。
熊本における戸長征伐。府県庁ー区長ー戸長ー用掛という系があり、中でも戸長は政府から推薦されるくせに給料制でその給料は民からの徴収で賄っている。主に金の徴収を仕事とする戸長は民から盗人呼ばわりされ憎まれ役だ。薩摩蜂起に乗じて戸長征伐が起きる。
第9巻。
薩摩はつまり西郷は勅命を根拠に徳川慶喜を武力によって倒そうとしていた。しかしその寸前大政奉還をしてしまったため泡を食ってしまった。その大政奉還を陰で進めたのが坂本龍馬。すなわち土佐藩であり、家老である後藤象二郎だった(と誤解?した)。ある時京都の薩摩藩邸に訪ねてきた後藤象二郎が、そこを辞去する際、西郷が薩摩藩の藩章の入った提灯を持たせたという。大政奉還の顛末に対して西郷を崇拝し、また土佐を恨む桐野利秋が後藤象二郎を切り捨てようと構えていたところ、その提灯を目の前にかざし押さえつけたという。どこかで聞いたエピソードだが、ここで繋がった気がする。
陸奥宗光が登場する。これまで名前は出てきていたが目立たない。ここでは初っぱなに登場し、反西郷であったような感じ。むしろ西郷の反政府や征韓に反抗しそれを妨げようと画策していたようなので驚く。
西郷はあまり文書を残さなかった。極端に少なかったため、西郷に関わる人達の行動や文書から逆に西郷の人物像を想像するほか無い。つまりそれがこの小説における西郷自身の影の薄さだ。これには得心だ。篠原国幹は口数が少なく実直であり、陽性の桐野とは対照的だ。しかし西郷はそんな篠原を桐野より信頼していたようだ。篠原が政府軍の少将江田の兵によって一発で射殺されたとき西郷は大いに嘆いたということだ。
西南戦争の直前、大久保始め政府の中心人物は京都に集まっていた。岩倉だけが東京に居残った。しかし悪人然としている岩倉が周りに相談できる相手がいないとかなり小心者だったと、作者はかなり小物扱いしている。がら空きになった東京に一人残った隙に反乱軍が勢いづいて攻めてきて、自分の首がはねられてしまうのではないかとビクビクしていたようだ。そのため、岩倉は頻繁に電報をやり取りしていた。電報が普及し始めたのはこの時期からのようだ。ここにいながら離れた場所の様子を手に取るように把握することができると褒める一方、内容が断片的すぎて全体像が一向に掴めないと嘆く岩倉だった。
警視隊という即席の(薩摩討伐のための)軍隊。川路の冷徹までの欧州の警察崇拝。そこから生まれたものだ。それは皮肉にも戊辰戦争で敵であった会津から抜擢した。佐川官兵衛というのが政府の信頼厚く、また住民からの信頼も厚い。面白いのはこの時代にあって人望厚い人物だったという。それは西郷もそうなのだ。
山県有朋は嫌な奴に描かれている。細かいしうるさい。しかし過去に汚職事件を起こしてさえいるこの人物が内閣総理大臣になれたところがすごい。桐野もあまり戦略的な人物ではなく、リーダーとして引っ張る力というのか人望(だけは?)があるようだ。
警視庁抜刀隊というのが組織された。曾て苦しい立場だった会津人を中心に結成された。その従軍記者が犬養毅だ。
p160。薩摩兵は、上代の隼人が翔ぶがごとく襲い、翔ぶがごとく退いたという集団の本性そのままをいまにひきついでるかのようである。つまり、薩摩兵は肝心の鹿児島を置き去りにして進撃しているということだが、ここで初めてタイトルの翔ぶが如くが出てくる。
久光の元に勅使が遣わされた。久光も薩摩蜂起に関わっているのではないかとの疑いだ。しかしそれは心外であり、今となっては憎い大久保の差し金に違いない。礼を尽くし慇懃な対応ながら威厳を発揮する久光がいい。一昔前の考えの持ち主であるが堂々としている。そして県令の大山綱良だが、いわば疑いを一心に受けて(実際は政府から騙され)捕縛されることになり、最期は刑死だった。これも悲しい。
黒田清隆は政府軍として参戦したが、のんびりしていてなかなか立とうとしない。兵隊が足りないと山県に補充を要請するが断られる。多分それは想定済みであったようで。その代わりに京都にいる大久保に補充を要請した。それには、わざと時間稼ぎをしたのではないかという様子が見てとれるとのことだ。つまり、同じ薩摩人であり多少の恩のある西郷をその間に逃がそうとしたのではないか?そう思われる節があるらしい。寛容な人物だったようだ。総理大臣であり、反面、酒乱で妻を斬殺したといわれる変な一面があった黒田であるが。
戦いが激化するに連れ、薩摩の悲壮さがありありとしてくる。司馬遼太郎の個性だろうか。散り際の描写の潔さというのだろうか。それを描かせると随一だ。永山弥一郎の最期は、百姓家を最期の場所にしようと住人の老婆から当時の百円という屋敷一軒新築できるほどの大金を払って買い取った。そこに火を放ち自刃して果てたというから、豪快というのか、最期を最も美的に迎えたわけだ。ただ殉死するように税所左一郎という部下がその家の傍らで自刃したというので、立派な人間は最期をそれなりに迎えることができるが、そうでなければ、地味にならざるを得ないところが寂しい。
はじめから西郷はあまり登場せず、しかもセリフも何もなく謎の人物的に話が進んできたが、「熊本を去る」と次の「過ぎゆく春」でその人物像がクリアになる。と言っても極端に自分の文章や周りの伝が少ないため推測にしかならないのだが、司馬遼太郎の西郷に対するイメージがよくわかる。西南戦争で立ち上がったものの、何だか騙された感を感じていた。大久保がこぼしたように、切羽詰まると投げ出して身を隠してしまう弱さ。それでいて、既にこれまでの紛争で多くの薩摩兵が死んだ、その者たちに対する申し訳なさと、まだ生き残っている兵士に対する義理から、最後の一人になるまで見届け、その上で自刃しようと考えたりする。
第10巻。
劣勢になってからの薩軍の傍若無人ぶりが甚だしい。食料を奪う、金を奪う、人も兵隊として奪う。その端では西郷は再び隠居生活のように農家を宿所とし、そこの木になっている柿を薩軍の一人が知らず、食料の足しと盗んだ。それを見とがめた西郷がその兵士をたしなめつつ、農家には柿の代金として金を渡すという律儀さ。そう言ったローカルの小さいことはあるが 、薩軍が宮崎に退却してから
宮崎県庁を乗っ取り、軍政を敷き、鉄砲の玉を鍋ややかんから鋳直しつつ、民衆を騙して徴収しつつ、紙幣をつくって軍費を作っていたらしい。それは僅か数ヵ月の話だ。その期間でそこまで仕立てるのはある意味すごい。
西郷軍はボロボロで宮崎をグルグル移動している。西郷は鳥羽伏見の戦いの時からそうで、援軍の要請が来るたび「みな死せ」と叱咤したという。全員戦死の気迫でやれば何とかなると言うのが西郷の戦争哲学だったらしい。意外だと思ったが、やがてはそんなものかと納得もした。直前にリチャード・フラナガンの「奥のほそ道」を読んでおり、そこで感染症の蔓延する劣悪な環境で鉄道建設を強要され、病に倒れていく捕虜達。そんな捕虜達に日本軍は気合いが足りない、気合いをいれれば病を克服できると叱咤し続けた。という場面に理不尽さを感じたものだが、日本人は古来そういう考えであることを再認識した。
俵野で薩軍は窮した。西郷はここで解散を決めた。死ぬものは死に、降伏するものは降伏する。そして陸軍大将の軍服を焼いた。飼っていた犬2匹を放つ。また大河ドラマ「西郷どん」であった場面、負傷していた息子菊次郎を看護していた熊吉に政府軍に降伏するよう指示した。弟の従道が政府軍にいるから悪いようにはしないだろうと。大河ドラマではあっさりとした場面だったが、この長い小説を読んできたこの場面は、いよいよクライマックスに近づくという感慨が押し寄せる。
死ぬものは死ぬ、降伏するものは降伏すると発した後、西郷や桐野は可愛岳を脱出する。その直前の軍議に野村忍介は呼ばれず、脱出に際してさえ、知らない間に脱出されていた。桐野から疎われていた。薩軍にあって最も戦略を考える野村に対して、行き当たりばったりな桐野は疎ましいものを持っていたようだ。さらにそういったある種の潔さに美を見出だす薩摩の気風であるため、どうやら西郷も野村のことはあまり好いていなかったようだ。人情味のある西郷と思っていたが、意外と考えのない、逆に言えば侍らしい考えの持ち主であることがわかる。どうも司馬遼太郎はそんな西郷の侍の美学のようなものには釈然としない考えなのかもしれない。西郷だけでない、他の戦国時代から昭和の戦争に至るまで一貫してそういった感情が窺えるようだ。
豊前の増田宋太郎が戦死した場面が印象深い。生前増田が野村忍介に話した、その地方に伝わることわざ。志がいつか成就することを例えて草を結ぶというらしい、しかしこの現状は風を結ぶようなものだと。それがこの章のタイトルとなっている。
城山の決戦。7万対3百。なんという壮絶さ。
西郷を守る兵の中に小倉壮九郎という者がいた。その実弟が東郷平八郎という。その時海軍を学ぶためイギリスに留学していたが、晩年、その時日本にいたらどちらについたか聞かれ、躊躇なく西郷についたと言ったそうだ。
最後は40数人しか残っていなかった。腹を切るのではなく侍らしく敵に向かいそこでたおれることが本懐と考えた。9月24日午前4時に最終決戦が始まり、午前7時に西郷は2発銃弾を受ける。そこでかねて打ち合わせていた通り、別府晋介により介錯させた。桐野は額に銃弾を受けてたおれる。別府と辺見は互いに刺し違えて果てる。壮絶。
当時のそういう考え方だったのだろうが、敵の遺体に対する仕打ちがひどい。敵なのだから憎しみを込めてそのような仕打ちをされて当然だという考えがあったのだろう。
最後の章は大久保の暗殺の場面となる。石川県の不平士族がやり場のない苛立ちを太政官に向けて発したことだ。大久保をはじめ、(すでに死去していたが木戸)、岩倉、伊藤、黒田、大隈、川路などの名前が挙げられていた。ただ、卑怯な真似はしたくないということで、あらかじめ命を狙うことを予告していた。そうではあるが大久保はその考えから、警備など付けず無防備に行動していた。そんな中、紀尾井坂で暗殺に合うというわけだ。殺害された時、持ち物の中に西郷からの手紙2通が入っていたという。何を考えて持っていたのか?作者は、大久保は西郷と仲をたがえたわけではなく、一度もケンカしたことがないという大久保が、西郷の評伝を重野安繹に書かせようとしていた。その資料にと持っていたと推測している。だが、なんだか自分の運命を予感していたのか、親友の西郷の手紙を持っていたことに感動する。
その後の川路も悲痛だ。西郷が死に、大久保が死んだ、それというのも自分の責任ではないか?と思い悩むようになり、日に日にやつれた。そんな時再度警察を学ぶということで留学することになった。それに向かう船で体調を崩し、帰国して間もなく死去したという。一説には毒を盛られたのではないかとのことだ。明治維新の主役たちが次々に世を去っていった。
第1巻
20170110読み始め
20170123読了
第2巻
20170602読み始め
20170815読了
第3巻
20170821読み始め
20170929読了
第4巻
20170929読み始め
20171005読了
第5巻
20171121読み始め
20171219読了
第6巻
20180109読み始め
20180225読了
第7巻
20180315読み始め
20180531読了
第8巻
20180710読み始め
20180909読了
第9巻
20181025読み始め
20181207読了
第10巻
20181223読み始め
20190212読了