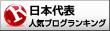6月20日(金)夜にNHK総合「チコちゃんに叱られる」で「サッカー日本代表のユニフォームはなぜ青い」がテーマになりました。わかっていながら見逃し、21日(土)朝の再放送も見逃しましたが、NHK+で配信されましたので見ました。
その理由を説明する専門家として登場したのは後藤健生さんでした。
日本の代表チーム(この時はまだ選抜代表ではなく、国内予選の優勝チームだったため東京高等師範(現・筑波大))が初めて国際試合を行なった時はエビ茶のユニフォーム(東京高等師範のユニフォーム)だったそうです。
サッカー日本代表が初めて選抜形式をとった1930年、当時、国内最強チームと言われていた東京帝国大(現・東大)メンバーに何人か全国から追加する形の代表を結成、ユニフォームは東京帝国大の青いユニフォームを使用、胸に日の丸(当時は旭日旗タイプ)を付けて大会に臨んだところ、見事優勝、1936年には初めての五輪出場となったベルリン五輪に参加、強豪スウェーデンを破り初出場にしてベスト8進出を果たしました。
そのため青いユニフォームはゲンがいいということになり定着、白を基調とした時期もあったものの、襟や袖などを青色にして引き継がれました。
1988年に、突如、赤の日本代表ユニフォームが登場、しかしW杯アジア予選を一次予選で敗退するなど日本代表は低迷、ファンからも不評だったことから1992年オフトジャパン時に再び青に戻したところ、その年のアジアカップに初優勝するなどゲンのいい色ということで、その後は「サムライブルー」と呼ばれる青を基調としたユニフォームのモデルチェンジを繰り返し現在に至っています。
しかし後藤健生さんは、現在の色がネイビーブルー(濃紺)寄りに変化していることにちょっと不満があるとのことで、イタリアのアズーリ(青を意味するアズーロの複数形)、フランスのレ・ブルー(青の複数形)のような決まった青ではないことから、もっと明るいブルーを使って決まった色にして欲しいという希望をもっているようです。
確かに、模様の部分をモデルチェンジするのはいいとしても、色は固定、明るい空色系にするか濃い目の色にするかは協会の考え方でいいと思いますが、大事なのは、世界のどの国も使用していない色を決めて、それを「サムライブルー」と呼ぶ時期に来ていると思います。
これまでのユニフォームはスポーツメーカーの提案主導で作られてきたのでしょうけれど、モデルチェンジしていい部分をきちんと限定して、固定色が引き継がれるような強豪国らしいものにしていきたいと感じました。
その理由を説明する専門家として登場したのは後藤健生さんでした。
日本の代表チーム(この時はまだ選抜代表ではなく、国内予選の優勝チームだったため東京高等師範(現・筑波大))が初めて国際試合を行なった時はエビ茶のユニフォーム(東京高等師範のユニフォーム)だったそうです。
サッカー日本代表が初めて選抜形式をとった1930年、当時、国内最強チームと言われていた東京帝国大(現・東大)メンバーに何人か全国から追加する形の代表を結成、ユニフォームは東京帝国大の青いユニフォームを使用、胸に日の丸(当時は旭日旗タイプ)を付けて大会に臨んだところ、見事優勝、1936年には初めての五輪出場となったベルリン五輪に参加、強豪スウェーデンを破り初出場にしてベスト8進出を果たしました。
そのため青いユニフォームはゲンがいいということになり定着、白を基調とした時期もあったものの、襟や袖などを青色にして引き継がれました。
1988年に、突如、赤の日本代表ユニフォームが登場、しかしW杯アジア予選を一次予選で敗退するなど日本代表は低迷、ファンからも不評だったことから1992年オフトジャパン時に再び青に戻したところ、その年のアジアカップに初優勝するなどゲンのいい色ということで、その後は「サムライブルー」と呼ばれる青を基調としたユニフォームのモデルチェンジを繰り返し現在に至っています。
しかし後藤健生さんは、現在の色がネイビーブルー(濃紺)寄りに変化していることにちょっと不満があるとのことで、イタリアのアズーリ(青を意味するアズーロの複数形)、フランスのレ・ブルー(青の複数形)のような決まった青ではないことから、もっと明るいブルーを使って決まった色にして欲しいという希望をもっているようです。
確かに、模様の部分をモデルチェンジするのはいいとしても、色は固定、明るい空色系にするか濃い目の色にするかは協会の考え方でいいと思いますが、大事なのは、世界のどの国も使用していない色を決めて、それを「サムライブルー」と呼ぶ時期に来ていると思います。
これまでのユニフォームはスポーツメーカーの提案主導で作られてきたのでしょうけれど、モデルチェンジしていい部分をきちんと限定して、固定色が引き継がれるような強豪国らしいものにしていきたいと感じました。