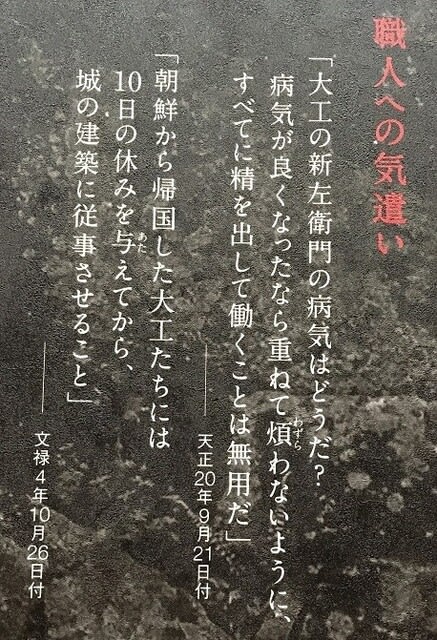「仕組みを作っても根付かない。時間の経過とともに、いつの間にか機能しなくなっている」
仕組みを作ってもそれがなかなか継続しないというのは、多くの組織に共通する悩みではないかと思います。職場で問題が生じた際に、解決策の一つとして挙げられることが多いのが「仕組みにする」であり、仕組みを万能薬のようにとらえている人も少なくないように感じます。
では、そもそも「仕組み」とは何なのでしょうか?辞書によると、「物事の組み立て、事をうまく運ぶために工夫された計画」とあります。つまり、組織において「仕組みにする」とは、たとえば異動や退職によって人が変わることがあっても、きちんと回るシステムを構築するといったことなのではないでしょうか。しかしこの「仕組み」、作ること自体も簡単ではありませんが、さらに大変なのは継続的に回し続け、きちんと組織に根付かせることです。
これに関して実際に仕組みを作り、それを徹底することにより驚異的な数字を出している会社があります。それは株式会社キーエンス(以下(株)キーエンス)で、時価総額14兆4,482億、平均年収 2183万円、売上高営業利益率55.4%、自己資本比率93.5%とのことです。(西岡杏(2022)「キーエンス解剖 最強企業のメカニズム」日経BP)
(株)キーエンスの仕組みは様々あるようですが、私が最も驚いたのは営業の仕組みです。その一部を紹介すると、毎夕先輩と後輩でペアを組み、顧客役と営業役に分かれて1000本ノックのようなロールプレイングを繰り返したり、5件以上のアポがないと外出が許されなかったり、さらに顧客との商談後には5分以内に外報と呼ばれる報告書を記入したりするのです。本書によると、こういった仕組みは営業のみならず、例えば代理店を通さない「直接販売にする」、「当日出荷にする」体制など、「付加価値を最大化する」という目標に向けた同社の仕組みはあらゆるところにあるそうです。
本書では、多くの企業では仕組みを構築したとしても維持継続が難しく、時間の経過とともに仕組みが壊れてしまうのに、(株)キーエンスがこれだけの仕組みを維持継続できるのはなぜなのかについても紹介されています。それによると、これらの仕組みをやりきる人材を育てる取組みや、そのベースにある風土、さらにはその源流をなす創業者の基本的な経営観や仕事観にも焦点が当てられています。ポイントは仕組みを表面的に真似するのではなく、そこに込められた「哲学」も真似するということだとされています。
しかし、入社してすぐにその哲学が浸透するわけではないことから、(株)キーエンスでは個人ではなくチームとしてより良い結果を残すことを目指して、部下の育成にも余念がないようです。こうした育成を通して社員に哲学がしっかり浸透し、それが組織の風土になっているのだと思います。このように(株)キーエンスでは個々の社員が自らやる気になるような内発的動機付けをしっかりと行い、同時に営業利益の一定割合を賞与として社員に還元するなど、外発的動機付けも徹底して行っているのだそうです。
どの組織もが(株)キーエンスのようになるのは簡単なことではないでしょうが、50年という社歴としてはそれほど長くはない時間の中で「哲学」をしっかり根付かせた(株)キーエンス。書籍を通して一部しか垣間見れていませんが、今後もますます目が離せない存在ではないかと感じています。