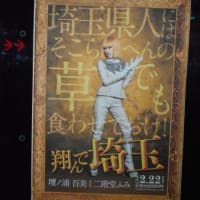文化庁は17年4月27日、地域の有形、無形の文化財をテーマでまとめる「日本遺産」に「足袋蔵のまち行田」など23道府県の17件を新たに認定した。
15年から毎年認定しており、今回の第3弾で計54件となった。初年度は19件、16年度は19件を認定、行田市では当初から申請していた。県内、関東での認定は初めて。オリンピックが開かれる20年までに全都道府県に少なくとも1件、100件を認定する予定。
今回認定された中には、北海道から福井の7道県にまたがる「北前船寄港地・船主集落」、三重、滋賀両県の「忍びの里 伊賀、甲賀」、国内最北の「サムライゆかりのシルク」(山形)、景勝地と食、温泉が楽しめる「やばけい遊覧」(大分)などが含まれている。
行田市では江戸時代中期から足袋を生産してきた。
1890(明治23)年頃からミシンを導入、製品を保管する倉庫として昭和30年代前半まで足袋蔵が立ち続けた。
足袋蔵は、商品や原料を扱いやすいように、壁面に多くの柱を建てて中央の柱を少なくし、床を高くして床下の通気性を高めるなど、内部の造りに特徴がある。当初は土蔵だったが、土蔵の小屋組みは、石蔵、鉄骨煉瓦造り、鉄筋コンクリート、モルタル、木造、戦後は石蔵と多様化していった。
行田には現在、多種多様な足袋蔵が約80棟現存している。
市内には、足袋製造関連事業者が約20社ある。4社が13工程ある足袋の全工程を市内の自社工場で生産、出荷している。出荷額や出荷額は減っても現在も「日本一の生産地」であることに変わりはない。
その一つのユニフォームと足袋の製造販売会社「イザミコーポレーション」は1907(明治40)年創業。現在も年間20万足を製造している。
行田市は、市や商工会議所、自治会連合会などで構成する「行田市日本遺産推進協議会」(仮称)を立ち上げ、情報発信、人材育成などに取り組む。
一方、従来の足袋業界には属していない同市の衣料品販売会社「武蔵野ユニフォーム」では、5年前からスーツやジーンズのスニーカーやサンダルにも合うような水玉や花柄のカラフルなデザインの足袋を開発した。(写真は同社のホームページから)
「SAMURAI TABI」と命名して、仏パリを皮切りに海外進出に踏み切ったところ好評で、アジアやヨーロッパ、米国などでも営業を始める予定だという。
タイミング良く、10月には行田の老舗足袋業者の奮闘ぶりを描いた池井戸潤氏の小説「陸王」もTBSでテレビドラマ化される。
「日本遺産」への指定が「行田の足袋」復活のきっかけになるかどうか。