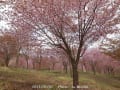今日は午前中の早い時間から裏磐梯(北塩原村)の「桜峠」に行って来ました。
桜峠の桜は2001年の敬宮愛子内親王殿下御生誕を記念して、翌年2001本のオオヤマザクラをオーナー制により植樹したのが始まりです。
この桜は毎年GWに見頃を迎え整然と並んだ桜が絶景で、今では知る人ぞ知るお花見スポットになっています。
満開になったのは5日だったということでしたが、昨日一日吹き荒れていた強風のせいで広範囲にわたり花びらが散っておりすでに葉桜になってしまった木も多く見受けられました。
お天気の方は晴れたり曇ったりであまりぱっとしない上に、黄砂の影響なのか遠くの風景が霞んで見えていました。
青空の下峠一面がピンク色に染まった風景を想像し期待していただけにとても残念な気持ちでいっぱいでした。
お花見が済んだ後は隣接する日帰り温泉施設「ラビスパ裏磐梯」でひと風呂浴びました。
乳白色の湯は肌を優しく包み込みながらじわっと温め、疲れを癒してくれました。
レストラン「SAKURA」が臨時休業(?)していたので、昼食は休憩室内の食堂で「磐梯 山塩チャーシューメン」を食べました。
美味しかったのですが、なんか物足りなかったです('ω')、、、
本当はレストランで評判の二段重ねの「ラビスパ弁当」を食べたかったので。。。
今日のお花見は多分今シーズン最後になると思います。
猪苗代町で一番最後に訪れた桜の名所は「土津神社(はにつじんじゃ)」でした。
ここは紅葉の名所としても知られています。
土津神社は会津藩主松平氏の祖保科正之(ほしなまさゆき)公を祀った神社で、会津藩主松平家の墓所があります。
正之公は自ら猪苗代の地を訪れ没後ここに祀るよう伝え、遺言どおり1675(延宝3)年に創建されました。
徳川二代将軍秀忠の子として生まれた正之公は、やがて初代会津藩主となり数々の功績を挙げました。
また神道を学び「土津」の称号を受けたのでその名を付けたといわれています。
土津神社には正之公の出身地である信州高遠町から寄贈されたタカトウコヒガンザクラの他にソメイヨシノ・カスミザクラなど合わせて数十本が植樹されています。
全体としては今が丁度いい見頃じゃないかなと思われました。
観音寺川の次に向かった先は「亀ヶ城公園」でした。
亀ヶ城公園は中世この地を支配した猪苗代経連(いなわしろつねつら)が建久2年(1191年)本格的な築城法によって築いた日本最古の平山城の城跡である「猪苗代城址」とその周辺を整備した公園です。
猪苗代城址には「鶴峰城址」が隣接しています。
鶴峰城址は文献から猪苗代氏代々の隠居城と伝えられていますが、当初は猪苗代城の分郭として機能していたものと考えられています。
その後近世初頭に猪苗代城址が大改修を受けたのに対して、鶴峰城址には手が加えられなかったため柵列や石積虎口など戦国末期の古い段階の遺構が残されています。
「亀ヶ城」の雅称を持つ猪苗代城址は桜の名所として親しまれています。
猪苗代城址が桜の名所となった由来としては、明治38年(1905年)小林助治・才治父子二代を中心とした町内の有志が私財を投じて桜やツツジを植栽し東屋や観月橋を設け公園として整備したことに始まりました。
亀ヶ城公園の桜の開花状況は全体として八分咲き位といったところでした。
飯盛山の急な坂と石部桜への長い道をひたすら歩き地獄の気分を味わった後で、何なら極楽の気分も味わってみようじゃないかと向かった先は・・・
この日最後のお花見場所である河東町の「やすらぎの郷 会津村(宗教法人 法國寺会津別院)」は49号線沿いにあり、丁度会津若松市の玄関口に当たります。
シンボルの「会津慈母観音像」は御身丈57mで、胎内には1万体の12支御守り本尊が祀られています。
展望窓からは磐梯山・飯豊連峰・会津盆地をパノラマのごとく望むことが出来るのです。
広大な庭園(6万坪)には四季折々に美しい花々が咲き乱れます。
桜はソメイヨシノやしだれ桜など全部で200本ほど植えられているとのことです。
見頃はもうちょっと先のようでした。
全体の三分の二ほど見て回ったところで、残念ながらデジカメの電池が切れてしまいました。
日曜日(23日)のお花見の話の続きです。
鶴ヶ城を後にし次に向かった先は「飯盛山(いいもりやま)」でした。
ここは桜の名所にしては桜の木がわずかしかないですが、白虎隊ゆかりの地として観光地的には多くの見所がある場所じゃないかなと思います。
ここを最初に訪れたのは小学校高学年の遠足の時だったと記憶しています。
小学生ならいざ知らず、前期高齢者(現在66歳)になった今では飯盛山の参道の上り下りは結構きつかったです(>_<)
そのきつさを引きずりながら向かった先は会津五桜のひとつに数えられている「石部桜(いしべざくら)」でした。
古い話で恐縮ですが、NHK大河ドラマ『八重の桜』の冒頭のシーンに登場していた有名な桜です。
その名木は見渡す限りに広大な田畑のど真ん中にぽつんと立っています。
専用駐車場からその場所までは1㎞以上も歩かなければなりません。
飯盛山の石段でダメージを受けた足で・・・
まるで地獄の様だ~~~!!!(@_@)
押切川公園周辺をひと回りした後は、徒歩で「しだれ桜散歩道(日中線記念自転車歩行者道)」の起点場所まで移動しました。
ここは今や会津を代表する人気お花見スポットのひとつです。
廃線となった日中線跡地の一部を遊歩道とし、全長3kmにわたって約1000本のしだれ桜が植樹されています。
ここのしだれ桜の開花は例年ソメイヨシノよりやや遅目です。
この日の開花状況は場所によってかなりのバラつきが見られました。
起点部分では結構咲いていましたが、一番の見所では片側がまだ少ししか咲いていないような状態でした。
全体としては見頃はまだまだこれからといった感じでした。
出来れば来週半ばにもう一度観に訪れたいです。
夕方早めに仕事を終わらして明るい内に行くのは可能ですから。
あくまでもお天気次第ですけどね。
さてと・・・今日もお天気が良さそうなので、朝食を食べてから会津若松市内へお花見に出かけようかなと思っています。