(トマールのキリスト教修道院の城壁)
トマールは、大西洋側から内陸部に入った小さな町だ。この町を有名にしているのは、町を見下ろす丘に建つ「トマールのキリスト教修道院」である。世界遺産。
12世紀、まだ、リスボンがイスラム勢の手中にあったころ、イスラム勢力と激しく戦っていたポルトガルの初代の王・アフォンソ1世は、サンタレンの戦いの勝利に貢献したテンプル騎士団に領地を与えた。
テンプル騎士団は、そこに要塞兼ねた修道院「キリスト教修道院」を建て、以後、ここを本拠としてイスラム勢と戦った。
14世紀、テンプル騎士団は、当時のフランス王の陰険な謀略によって、本部のあったフランスをはじめ、各国の支部組織が弾圧・粛清され、壊滅する。しかし、ポルトガルでは、数年後にキリスト騎士団が創設されて、テンプル騎士団ポルトガル支部の莫大な財産を受け継がせた。
エンリケ航海王子は、サグレスに航海学校を開設した4年後の1420年に、キリスト騎士団の団長に任命され、生涯、その地位にあった。ゆえに、彼はサグレスにいないときには、このトマールのキリスト教修道院を住まいとした。
実は、世界で初めて大航海時代を切り開いたエンリケ航海王子の大事業の財源は、貧しいポルトガル王室の金庫から出たものではない。キリスト教騎士団がテンプル騎士団から受け継いだ莫大な財産から出ていたのである。
つまり、ポルトガルの大航海時代は、エンリケ王子という人を得て、キリスト教騎士団の事業として展開されていったのである。
…… では、そもそも「騎士団」とは何か、と、改めて調べ、調べているうちに、聖ヨハネ騎士団が活躍する塩野七生の『ロードス島攻防記』のことを思い出し、ページをめくっていたらついつい面白くなって再読。あげくの果てに、ロードス島に行ってみたくなって、あれこれと調べているうちに、すっかりブログの方がお留守になってしまった。この2週間ほど、心が、ポルトガルから、東地中海のロードス島へと、ふわふわ漂っていた。
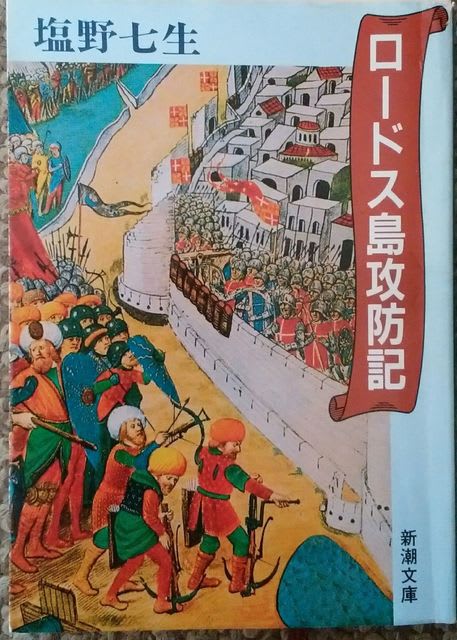
改めて、気を引き締めて、執筆を再開します 。
。
まだ、サグレス岬にいます。
★ ★ ★
10月1日 
「明日は早いから」と遠慮していたのに、サグレスの小さなホテルは朝食を用意してくれていた。朝食はいつもちゃんと食べる習慣だから、ありがたかった。
6時40分、スーツケースを持ってホテルの外に出て、昨日のネットタクシーを待つ。
まだ夜は明けていない。海の音はここまで聞こえてこないが、近くに大西洋の気配を感じる。
ずいぶん長く思えたが、5分遅れで、マダムの運転する迎えのベンツがやって来た。ラゴス発の列車に乗り遅れたら、今日の予定が根本的にくるってしまうので、心配した。何しろ、大陸の果てからもう一方の果てへ、たまたまネットでつながっただけの関係だから。
車の中で、窓の外が明るくなっていった。
★
< 「市民」として >
7時48分始発の鈍行列車が入ってきた。
リスボンまでは昨日の逆コースで、Tunesまで各駅停車で行き、そこから特急に乗り替える。
プラットホームには、地元の通勤客と思われる人たちに混じって、海外旅行用の大きなスーツケースを持った旅行者たちもいる。
私の前を、ヨーロッパのどこかの国から旅してきたのだろう、女子大生と思われる二十歳ぐらいの二人づれの女性が、大きなスーツケースを持ち上げて、列車に乗った。後に続いて、列車のステップに足をかけたとき、驚いたことに、先に上がった女性の一人が、自分のスーツケースを友人に預け、列車の床にズボンの膝をついて、私のスーツケースを上から引っ張り上げようとしてくれたのだ。
とても綺麗なお嬢さんだった。「ありがとう。大丈夫です」と言って、自分で持って上がった。
少しばかりのショックと感動があった。
ヨーロッパの駅のプラットホームは、かなり低い。線路の面から30~50センチぐらいしかないだろう。だから、ホームから線路に「落ちる」というような不安感は全くない。線路に降りるのは簡単だ (降りてはいけないが)。
その分、入ってきた列車のデッキは高い。海外旅行用の大きなスーツケースを持って、狭く高いステップを上がるのは、結構大変なのである。それも、年齢とともに。
それにしても、自分がこういうお嬢さんにいたわられるようになったということが、ちょっとショックだった。
だが、それにもまして、ヨーロッパの若者の、こういう何気ないふるまい方に、感心した。
日本人の民度は高い。人に迷惑をかけない。人の心を慮ることができる。
だが、日本人は、見ず知らずの他者に対して、このように躊躇なく、かつ、当たり前のことのように、さっと手を差し伸べることはしない。
身内(家族や学校や会社や会社の顧客)の「外」の人間に対しては、概して冷淡である。
日本流でいえば、私は、このお嬢さんたちの「外」の人間である。にもかかわらず、ヨーロッパの、これは何だろう??
騎士道精神の伝統 …… ではないだろう。騎士道精神なら、お姫様は、「してもらう」人だ。実際、このときの彼女は、旅行用のラフな姿に「身をやつして」いたが、お姫様のドレスも十分に似合う西洋の美女だった。
多分、ヨーロッパに今も生きる市民精神の伝統ではないか、と思う。「良き家庭」に育った子女は、パブリックな場でそのようにふるまえるようしつけられている。
実際、ヨーロッパを旅していると、今回のような列車の乗降りでも、或いは、駅の高い階段でも、大きな旅行用スーツケースを持って苦労している中高年の女性がいたら、付近の男性がひょいと手を伸ばして、階段の上まで持って上がってくれる。そういう光景は、よく見かける。
パリの大きな道路を渡ろうとして信号待ちしていたら、前に、かなり高齢のよぼよぼのおばあちゃんがいた。ヨーロッパの横断歩道の青信号が赤になるのは早い。心配していたら、青信号になった途端、横にいた若い女性がおばあちゃんの手を取って、大勢の人波に抜かれながら、信号が赤になっても、おばあちゃんのペースで堂々と歩きぬいた。そして、横断歩道を渡り終えると、当たり前のことをしただけ、というふうに、おばあちゃんに小さく手を挙げて、別の方向へ別れて行ってしまった。
街角で『地球の歩き方』の中の小さなマップを開いて思案していると、「何かお手伝いしましょうか?」と声をかけてくれる。振り向くと、買い物籠付きの自転車に乗った品の良いマダムが、自転車を止めて微笑んでいる。
こういう「市民精神」について、以前にも、当ブログで触れた。私がヨーロッパの旅をしているのは、(及ばずながらではあるが)、「ヨーロッパとは何か」ということを知りたいためであり、それが大問だとすれば、小問の一つが「市民とは何か」「市民精神とは」ということである。
以前、当ブログに書いたことではあるが、もう一度、部分的に再掲する。
★
 「西欧旅行…フランス・ゴシックの旅」の10「大聖堂はローマ文明の上に、自由は市民精神の上に」から
「西欧旅行…フランス・ゴシックの旅」の10「大聖堂はローマ文明の上に、自由は市民精神の上に」から
フランスの大統領が「実質的な妻」と別れて、別の女性と同居した、などということが報道されても、ふつうのフランス人やパリっ子は、知らん顔だ。 各自の家の中は各自の勝手。人のプライバシーに立ち入ることは、ゲスのすること。 大統領の評価は、政治家として有能かどうかで決まる。
こういう点において、フランス人は、見事な「個人主義」である。
だが、フランスの個人主義は、「人に迷惑をかけなければ、何をしても勝手でしょう」 と、ただ自己中心的に生きることではない。
杖をついた危なかしい足取りのおばあさんが、長い横断歩道を渡ろうとしている。 すると、横を歩いていた若い女性が、すぐにおばあさんの腕をとって、信号が赤になっても、おばあさんのペースでゆっくりと歩き、渡りきる。 おばあさんがお礼を言い、女性はにこっと笑って歩いて行く。 (フランスの横断歩道の信号はすぐに赤になるが、車は歩行者がいる限り発進しない)。
街角で、東洋人の旅行者がガイドブックを広げて首をひねっている。 買い物かごを乗せた自転車のマダムがピュッと横に自転車を止めて、「何かお手伝いしましょうか?」 。
こうした光景は、地方の中都市だけでなく、大都会パリでも見る光景であり、 日本の社会で暮らしている者にとっては、新鮮に映る。
日本では、誰もがもう少し自分の殻にこもって、「個人主義」で生きているように見える。
フランスでは、各自の家の中は各自の自由、しかし、一歩家を出たら共同体の一員としての市民の自覚……、そういう精神が、まだ生きているように思う。
つまり、市民精神の基盤の上に、自由や個人主義は成り立つ。 今もそういうDNAが残っているのが、フランスであり、そして西洋なのだと思う。
以下、木村尚三郎 『パリ』 (文芸春秋社) から
「ノートル・ダム大聖堂はパリのなかでも最も高い建物であり、……それより高い建物は認められなかった…。パリの建物が6階ないし7階にそろえられているのも、このためである」。
「ちなみに、パリ市内の建築・居住規制は、日本の都市などとは比べものにならないくらいに厳しい。一戸建て住宅は存在せず、大統領・首相以下、誰もがマンション暮しである 」。
「パリが美しいと感じられるのは、建物による均整美だけではない。 洗濯物がベランダなどにまったく見えないからである。…… ベランダに洗濯物や絨毯を干したりすれば、美観を損ねるとして罰せられる」。
「たとえ自分が所有する立木一本と言えども、市の許可なく勝手に切ることはできない。これも、中世以来の決まりである 」。
「それは、パリに生まれ育った人たちにとってだけではなく、世界の誰にも美しいとされる普遍性が追求されているからである。そこに、世界都市パリの面目がある 」。
「市民共同体の一員として、自ら積極的に公益を実現しつつ生きる、これなくして都市に生きる資格のないことを、パリは教えている 」。
そして、辻邦生 『 言葉が輝くとき 』 (文藝春秋) から
「そのとき、メトロがぱっとセーヌ川の上に出て、窓からパリの街が見えた。夕日のもとですごく美しかった。私はただたんに、美しいなという感嘆よりも、そこに、その風景を美しくしている意志があるなと感じた。ただ漠然と美しいのではなく、美しくあらしめよう、きちんとした街にしようという激しい秩序への意図があり、さらにそれを実現する営みがある、これがつまりヨーロッパなのだと思った。ここから、私とヨーロッパとの最初の出会いが始まったと思います」

(セーヌ川のサン・ルイ島付近)
★
 「西欧旅行 … フランス・ロマネスクの旅」の5「日本のロマンティシズムと永世中立国スイスのリアリズム」から。
「西欧旅行 … フランス・ロマネスクの旅」の5「日本のロマンティシズムと永世中立国スイスのリアリズム」から。
旅行に出る前、にわか勉強で読んだ本の中に、犬養道子『ヨーロッパの心』 (岩波新書)があった。そのなかのスイスの章には、このようなことが書かれていた。
「九州ほどの山岳国。……22の万年雪の大きな峠、31の小さな峠。無数の非情な谷。… 見た目は緑で美しいが、実は何も産しない痩地草原地帯 (アルプ) にばらまかれた3072の共同体 (ドイツ語圏でゲマインデ、フランス語圏でコンミューン)。例えば、我が家から2キロ先のジュネーブ(市)は、38のコンミューンから成っている。一応、ジュネーブ圏内コンミューンゆえ、住人はジュネーブ人と呼ばれるが…… 」。
「ジュネーブ市民」という市民はいない。いるのは38の各コンミューンに所属する市民。
「万年雪の峠」や「非情な谷」に閉ざされて生きてきたスイスでは、「共同体」を作って助け合い、自己完結的に生きていかなければ生きられなかった。各家庭の中は各自の勝手(個人主義)。しかし、一歩家を出れば、そこには共同体があり、生きるために各自がその一員として責任を果たし、助け合う。
こうして、「スイス人」の自主自立の精神、市民精神が育った。
※ 菅直人の言う西欧型「市民」── 政党や労働組合などの組織に属さず、個人として、反体制、反権力で行動する人、という「市民」イメージとは、かなりかけ離れている。
★
 「西欧旅行…アドリア海紀行」の1「ヴェネツィアの海へ」から。
「西欧旅行…アドリア海紀行」の1「ヴェネツィアの海へ」から。
その昔、10世紀の終わりごろから16、17世紀まで、アドリア海は「ヴェネツィアの海」であった。ヴェネツィアの商船や軍船が行き交ったアドリア海を自分の目で見たかったということである。海は海だが、そこには目に見えぬ物語がある。
なぜヴェネツィアにこだわるのかと言えば、西欧史の中で、ヴェネツィアの歴史がいちばん好きだからである。
イギリスやフランスやオーストリアなどのような王・貴族と農民という一方的な支配・被支配の関係によって成り立つ封建国家でもなく、フィレンツェのように一見、民主的に見えるが、市民同士の利己がぶつかり合い、絶えず政変・クーデターが起きる内紛の都市国家でもなく、ヴェネツィア800年の歴史には、市民精神(共同体精神)と、時代をタフに乗り切るリアリズム精神が貫ぬいているように思える。
(再掲は以上)
★
市民精神は、共同体の延長としての祖国への愛につながっていく。
ヴェネツィアは都市国家だった。人口20万人足らずの、領土というほどの領土を持たない小国が、通商国家として、大国の横暴に抗して生きていくためにとった政策は、一言で言えば、徹底した「チーム・ヴェネツィア」作戦だった。市民のロイヤリティの高さが、800年の歴史を支えたと言える。
3000の自立心の高い共同体から成るスイスは、永世中立国を宣言した。だが、それは美しいだけの宣言ではない。同時に、国民皆兵制度に立ち、精度の高い防衛能力を保持し、侵略国に対しては国土を焦土と化しても戦うこと、仮に侵略国によって全土を制圧されても、亡命政府を樹立し、絶対に降伏することはない、という宣言もしたのである。それは、現在の国民のことだけを考えてのことではない(「敵が攻めてきたら … 、ぼくは逃げる」)。これまでスイスをつくりあげてきた祖先たちに報い、これからこの国を引き継ぐ子や孫のことを考えての宣言であった。
★
閑話 

先日、NHK・BSで放映されたドキュメンタリー「激動の世界をゆく/バルト三国 ── ロシアとヨーロッパのはざま/小国のアイデンティティ」を見た。
ベルリンの壁が崩壊したとき、弱小国のバルト3国は、数百万の人々が手と手をつなぎ、ソ連に向けて「人間の鎖」を作って、静かに独立を訴えた。その人間の列は、バルト3国の大地を貫く1本の線となって、延々と延び、今、その映像を見ても、感動する。
だが、バルト3国の人々は、今、不安に駆られ、緊張を強いられている。ウクライナ問題のさ中、ロシアは電光石火のごとく、クリミアを併合した。大国ロシアに隣接する小国のバルト3国の立ち位置は、クリミアと同じなのだ。ひとひねりでつぶされてしまう。
また、国を失うかもしれない、という恐怖感を、どれだけの日本人が共感的に理解できるだろう。
弱小国バルト3国の軍事力は弱い。
NATO軍はいる。NATO軍の存在がロシアに対する抑止力になっている。だが、NATO軍といっても、ヨーロッパの各国からの寄せ集めの軍隊で、数か月赴任したら交代する軍隊である。
さらに、人々を不安に陥れているのはトランプ大統領の登場である。NATO軍の中心であるアメリカは、アメリカ・ファーストの立場からプーチンと取引し、我々を見捨てるかもしれない。
最近、志願兵制を始めた。銀行を辞めて志願したある若者は言う。「自分たちが本気で自分の国を守ろうとしなかったら、どうして外国の軍隊が命を懸けて、この国を守ってくれるだろう??」。
敗戦直後、大陸にいた何十万という日本人がシベリアに抑留され、凍りつく寒さと飢えの中、強制労働をさせられて、多くの人々が望郷の思いを抱きながら、死んでいっだ。同じことがバルト3国でもあった。反ソ連の活動をした人の家族が、家族ぐるみでシベリアに連れて行かれ、強制労働をさせられ、倒れ、凍土に葬られた。
ある老夫婦は、そのようにして50年間をシベリアで生き、ソ連が崩壊してバルト3国が独立したとき、やっと引き上げてくることができた。
老いた夫はNHKのニュースキャスターに向かって言った。「どうか、記録してほしい。私の父は、ラトビアの土と枯れ葉の下に葬ってほしい、と言って、彼の地で死んだ」。
また、老いた妻は、ニュースキャスターが、「最後の質問ですが、ラトビアの若い人たちに何か言いたいことがありますか?? 」と聞いたとき、ひとこと、「ラトビアを、愛してほしい」と答えた。
「自分たちが本気で自分の国を守ろうとしなかったら」
「ラトビアの土と枯れ葉の下に葬ってほしい」
「ラトビアを、愛してほしい」
市民精神 (共同体の精神) とは、そういうことだ。祖国を愛することである。
★ ★ ★
< ただし、いろんな人間がいるのがヨーロッパ >
TUNESで、特急に乗り換えて、リスボンへ向かう。
日本で買った特急のチケットは、22号車の、座席は15番。
「22号車」という車両番号を心配していた。22両も連結しているはずがない。間違えて発行されたのではないか?? 自分の座席は、あるだろうか??
しかし、ホームに入ってきた特急は数車両しか連結していなかったが、「22号車」の表示の車両は、ちゃんとあった
座席番号も、不思議だった。日本では、端から1、2、3 … と座席番号をうっている。ところが、ポルトガルの列車の座席番号はアトランダムなのだ。
席について落ち着いてから、つれづれのままに、何か法則性があるのかと、見える範囲の座席番号を眺めてみたが、アトランダムであることがポルトガル鉄道の規則なのだと、考えるしかなかった。所変われば、である。ちなみに「15番」は一番うしろの座席だった。

( 河口に臨むリスボン )
大都会リスボンに入り、高い所を走る列車から、一瞬、リスボンの町を撮影することができた。大西洋の河口に臨む町であることが、良くわかる写真になった。
リスボン・オリエンテ駅では、トマールへ行く列車の発車時間まで、ちょうど1時間の待ち時間があった。
駅構内で、あまり美味しくないサンドイッチを買って食べ、プラットホームで列車を待った。
ベンチに座りたかったが、どこもふさがっている。
3人掛けのベンチの一つを、若い女性が一人で占領していた。女子大生の一人旅か? 横向きに、ベンチに両足を上げ、膝小僧を抱え込むようにして、ベンチを占領している。
端っこが少し空いていたので、あえてそこに座った。すると、両足を少し引っ込め、1人分だけ空けた。「土足の足をベンチに上げるな!!」 と言いたかったが、やめた。異国で、自らトラブルを起こしてはいけない。
私がヨーロッパを、一人一人が市民精神をもったモラルの高い国々だと、一面的に買いかぶっていると思われたらいけないので、こういうレベルの若者もいることを書いた。
人種、民族が入り混じって自由に移動し、「身分的な格差」もあり、日本より経済的格差が大きく、モラルの格差も大きいのが、ヨーロッパである。
★
リスボンからトマールへ行くには、各駅停車しかない。だが、各駅停車の、ゆっくりとした旅も楽しい。
窓から眺めていると、昨日、首都リスボンから南へ向かいながら眺めた景色と、今日、リスボンから北へ向かう車窓風景とは、同じ国とは思えないほどに違う。リスボンの北は、地味が豊かで、人家も多い。
大西洋に並行して北上していた列車は、やがて東へ進路をとり、いかにも草深い田舎の風景のなかを、所々の駅で停まりながら走った。
そして、午後3時、地方の小さな駅トマールに着いた。
★
小さな町だから、若ければホテルまでスーツケースを押して歩くのだが、そうもいかず、駅前からタクシーに乗った。
ホテルは、レプブリカ広場から延びるメインストリートにあった。
道の正面の丘の上に、キリスト教修道院の城塞のような建物が見えた。

(トマールのメインストリートと丘の上のキリスト教修道院)















































 。
。








 。
。 というような、イカツイ城壁が現れ、城壁に沿って進むと、城門が見えてきた。そうか!! 修道院と言っても、戦う騎士団の修道院は、普通の修道院と違って、城塞そのものなのだ。
というような、イカツイ城壁が現れ、城壁に沿って進むと、城門が見えてきた。そうか!! 修道院と言っても、戦う騎士団の修道院は、普通の修道院と違って、城塞そのものなのだ。

















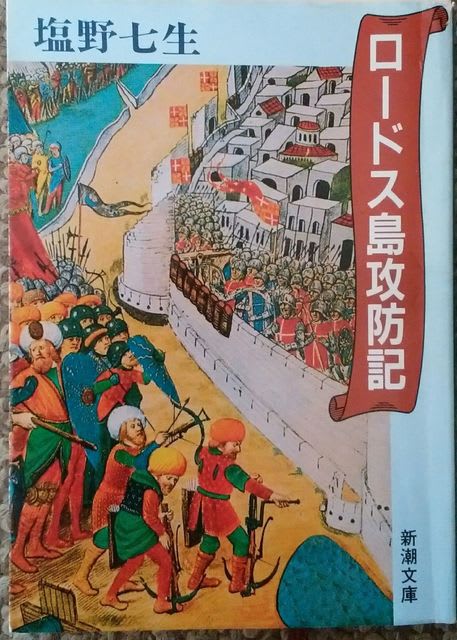
 。
。 「西欧旅行…フランス・ゴシックの旅」の10「大聖堂はローマ文明の上に、自由は市民精神の上に」から
「西欧旅行…フランス・ゴシックの旅」の10「大聖堂はローマ文明の上に、自由は市民精神の上に」から
 「西欧旅行 … フランス・ロマネスクの旅」の5「日本のロマンティシズムと永世中立国スイスのリアリズム」から。
「西欧旅行 … フランス・ロマネスクの旅」の5「日本のロマンティシズムと永世中立国スイスのリアリズム」から。 「西欧旅行…アドリア海紀行」の1「ヴェネツィアの海へ」から。
「西欧旅行…アドリア海紀行」の1「ヴェネツィアの海へ」から。





 。なにしろ、ここの気候は、北アフリカだ。日本を出て5日目。旅の疲れが蓄積している。
。なにしろ、ここの気候は、北アフリカだ。日本を出て5日目。旅の疲れが蓄積している。 が横をゆっくりと走り抜けた。一本道だから、同じ目的地に行くヨーロッパの旅行者だろう。手を挙げたら、停まって乗せてくれるだろうか??
が横をゆっくりと走り抜けた。一本道だから、同じ目的地に行くヨーロッパの旅行者だろう。手を挙げたら、停まって乗せてくれるだろうか?? 













 。
。































 。
。
 と言わんばかりに、瑠璃やメノウやモザイクで飾り立てられている。これぞ、「ザ・イエズス会」である。
と言わんばかりに、瑠璃やメノウやモザイクで飾り立てられている。これぞ、「ザ・イエズス会」である。




 )」…… 確かに、日本も同じです
)」…… 確かに、日本も同じです 。
。 。全然知らない私でも、すぐに読めますよ
。全然知らない私でも、すぐに読めますよ
 謹賀新年。今年もよろしくお願いいたします。
謹賀新年。今年もよろしくお願いいたします。











 みなさん、お元気で、良い新年をお迎えください。
みなさん、お元気で、良い新年をお迎えください。

 や雨の日よりずっと心楽しい。
や雨の日よりずっと心楽しい。
 。
。 と思って見ていたら、カップルが乗車する前に、ドライバー兼ガイドの若者が注意を与えた。それは、車の窓越しに見て、感じでわかった。「他のお客の迷惑になるから、今日一日、集合時間はぜひ守ってほしい」。客に対する礼を失しないように、しかし、笑顔は見せずに、きっぱりと。あの若者、いい感じだ。
と思って見ていたら、カップルが乗車する前に、ドライバー兼ガイドの若者が注意を与えた。それは、車の窓越しに見て、感じでわかった。「他のお客の迷惑になるから、今日一日、集合時間はぜひ守ってほしい」。客に対する礼を失しないように、しかし、笑顔は見せずに、きっぱりと。あの若者、いい感じだ。 )。
)。
 。
。  。
。 。
。





















 たどり着いたら、岬のはずれ
たどり着いたら、岬のはずれ  」 (石原裕次郎「北の旅人」) と口ずさみたくなる、人恋しい淋しさ、哀感が伴う。
」 (石原裕次郎「北の旅人」) と口ずさみたくなる、人恋しい淋しさ、哀感が伴う。










 。
。








 。
。


 や、この旅の最重要目的地の一つロカ岬も、この日のコースに入っている
や、この旅の最重要目的地の一つロカ岬も、この日のコースに入っている  。
。


 」と叫びそうになった。
」と叫びそうになった。 しか、ないんだ」。
しか、ないんだ」。 、水際に公園が広々と広がる地域に入った。駐車場スペースは観光バスや乗用車でいっぱいだ。世界からの観光客が駐車場から群れをなして歩き、あるところでは、長蛇の列ができている。ジェロニモス修道院の華麗な姿も見えた。
、水際に公園が広々と広がる地域に入った。駐車場スペースは観光バスや乗用車でいっぱいだ。世界からの観光客が駐車場から群れをなして歩き、あるところでは、長蛇の列ができている。ジェロニモス修道院の華麗な姿も見えた。
 。アムステルダムで乗り継ぎ、リスボンに現地時間20時05分到着。
。アムステルダムで乗り継ぎ、リスボンに現地時間20時05分到着。  」に参加。リスボンのベレン地区 → シントラ → ロカ岬観光。
」に参加。リスボンのベレン地区 → シントラ → ロカ岬観光。  < 9月29日 (木) > リスボン市街地を観光
< 9月29日 (木) > リスボン市街地を観光 。
。  < 9月30日 (金) >
< 9月30日 (金) >  と鈍行
と鈍行 でラゴスへ。ラゴス駅からタクシー
でラゴスへ。ラゴス駅からタクシー でサグレスへ。サグレス 岬とサン・ヴィセンテ岬観光。
でサグレスへ。サグレス 岬とサン・ヴィセンテ岬観光。  < 10月1日 (土) >
< 10月1日 (土) >  と特急
と特急 < 10月2日(日) >
< 10月2日(日) >  < 10月3日 (月) > ポルト観光
< 10月3日 (月) > ポルト観光 < 10月4日 (火) >
< 10月4日 (火) >  < 10月5日 (水) >
< 10月5日 (水) >  に大きなスーツケース
に大きなスーツケース を持って降り立ち、空港からタクシー
を持って降り立ち、空港からタクシー のフロントに着くのは、できたら避けたい。
のフロントに着くのは、できたら避けたい。
 には乗るな、というのが、リスボン在住の日本人が作成しているブログ、その他からの一致した意見である。
には乗るな、というのが、リスボン在住の日本人が作成しているブログ、その他からの一致した意見である。

 。
。 、疲れていて、すっかり油断した!! 悔しい
、疲れていて、すっかり油断した!! 悔しい

 ので、今後ともよろしくお願いいたします
ので、今後ともよろしくお願いいたします

 。
。







