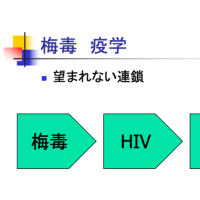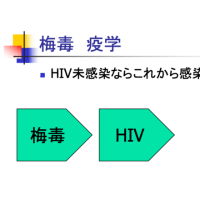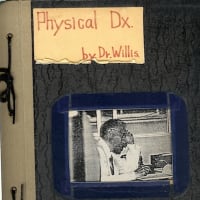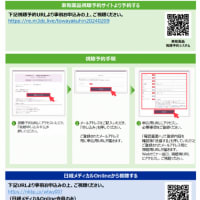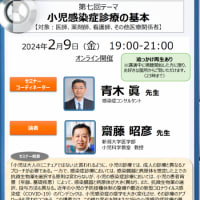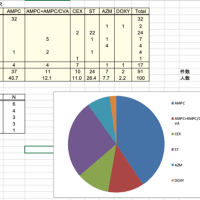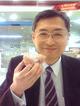編集長のお知り合いには、滅菌・消毒含め、医療の歴史に超詳しい方がいます。
おひとりは、日野原重明先生です。御年100歳、10月4日には101歳です。
もうひとりは、サクラ グローバルホールディングス 会長の松本謙一氏です。
なにせ、病理診断や感染管理で国内外で医療に貢献しているサクラ精機は、1600年代より薬種商「いわしや」として日本橋にて営業です。こちらの社史、本社1階にある昔の医療器具などはマニアには魅力的なものがならんでいます。
松本会長は、手品が上手だったり(^^)大変楽しい方なのですが、空中に浮いている時間のほうが長いのではといわれるほど世界各地をとびまわるビジネスマンで、世界の医療事情にお詳しい一人。(先日のロシアでのAPECの会議では日本人の民間人としてただひとり口演をされた方です)
・・・そう。きっと、皆さんの周囲にも当時を語ることができる人がいます。
例えば・・・コチラの記事を参考にしてください。
「介護から器具の消毒まで…走らないと間に合わない、そんな労働環境でした」
福井県看護連盟
司会:最初に、病院の師長をなさっていましたが、昭和30年前後ぐらいの看護の状況についてお話いただけますか?
ゲスト:(略)消毒はシンメルブッシュが各科にあって、いつも煮沸消毒をして再生し、注射器もガーゼに包んで2本くらいずつ消毒していました。
司会:そんな状態で、感染を起こすということはなかったんですか?
ゲスト:それが不思議となかったんです。何回も消毒しましたので。でも、今思うと、よく事故などが起きなかったな、と思いますね。
(いや、当時は確認する術もアイデアもなかったと思うんですが・・・)
司会:当時のモーニングケアで、衛生材料はどう消毒していたのですか?
ゲスト:それは自分たちで消毒していました。中央材料室なんてありませんでしたし。注射器等はシンメルブッシュで煮沸消毒し、ケッテルなど蒸気滅菌するものは、コッホ消毒器と言われるもので消毒していました。…以前は炭でした。
(・・・知らない言葉もでてくるのであります)
と、ぜひ当時の日誌や、納品書の記録などをもとに、いつ頃、ディスポ製品へのアクセスそのものが可能になったのかを調べてみてください。
昭和33年の様子 京都府立医科大学麻酔科学教室 「京都府立医科大学麻酔科沿革(中央手術部を中心に)1959-1972」
"在来のコッヘル止血鉗子は鉄製ニッケル メッキで、 洗浄して組み合わせた。 それを新しくステンレス製のボックス型鉗子に変更した。 数が多く相当な金額であった。また古い木製の事務机や椅子は廃棄し、カンファレンス テーブルや医員ロッカーなどスチール製に変えた。 点滴台(キャスター付き)やキックバケツなどは、 当時としては贅沢なステンレス製のを新調した。 注射器はガラス製で、 デスポーザブルのものは未だなかった。 注射針は金属製で、皮下,筋注用の1尖と静注用10尖の2種類があった。"
京都府立医科大学中材室の記録。
"採血室の注射器以外は、外来診療科には払い出しをしていないため、現場では、注射器hあ、洗剤とブラシで洗い、濯いだ後シンメルブッシュで煮沸消毒をしていた。病舎でもこのシンメルブッシュは大いに活躍して、まるで材料室の下請けのようだった。外来の注射器が手洗いのあと、カストに詰められ、オートクレーブ消毒ができるようになったのは1974年(昭和49年)頃からであり、注射器のディスポへ切り替えが実施されたのも、同年7月からで、種類は輸血針、静脈針、皮下針、皮内針の四種類で、因に単価は4円50銭であった。"
第308段:「医療廃棄物」(心にうつりゆくそぞろごと)
"私の子供時代の昭和三十年代には父の診察室の隅っこのテーブルの上にある電熱器の上に載せられた煮沸消毒器での消毒でした。(中略)もちろん注射器はガラス製で何度も消毒して使っていましたし、注射針も同様でしたが、注射針の切れ味が悪くなると父や祖父は自分で砥石を使って研ぎ、時にはメスを研いで下さる職人さんが来られると針などもまとめて研いでもらっていたようでした。医療器具の精度や安全性は現在と比べると桁違いに悪かったといわざるをえません。
ある日、小さな診察室には煮沸消毒器ではなく高圧蒸気滅菌器と呼ばれる器械が置かれるようになりました。
「これで、安心して消毒・滅菌が出来るようになった」とうれしそうな顔をして父が話してくれた時の顔は今でも覚えています。当時は煮沸消毒器では完全に病原菌が消毒できないことはわかっていましたが、小さな診療所では消毒する器具の量も少なく大型の高価な機械は買えない時代のようでしたが、やっと小型の器械が発売されて使えるようになったようでした。
今の時代のように、何でも消毒、抗菌グッズが氾濫している状況から考えれば信じられないような医療行為が当たり前でした。予防接種の針は交換しないでアルコールを含ませた綿の上で軽く拭くだけ、同じ注射器、同じ針で次々に予防接種をされた記憶があります。"
三木クリニック
"昔話をすると、院長が医者になった頃は、患者さんは毎朝その日の注射に必要な数のガラスの注射器と太い針を煮沸・消毒して、筆箱のよう形の金属容器に、アルコール綿と一緒に入れて持ち歩かねばならなかったのですから"
糖尿病ネットワーク
"使い捨て注射器が開発される以前は、ガラス製注射器を注射針とともにガーゼに包んで、小鍋で煮沸消毒し、それでインスリンの瓶からインスリンを吸い取り注射していた。ディスポーザブル注射器が開発されてから注射器の消毒がなくなり、インスリン療法はより実施しやすくなった。そして1985年にはノボ社がペン型インスリン注射器ノボペンを発売し、インスリン療法の実施がいつそう容易になった。"
医療機関や介護施設におけるB型肝炎のアウトブレイクは、感染経路がよくわからないものもあるのですが、近年までアウトブレイクの原因にくりかえしなっており、また注意喚起が行われてきたのは、血糖測定に関する器機の共有です。
もっとも、血液がべったりついていたり目に見える血液があれば、そのまま使うことはないのですが、逆にいうと、目に見えないレベルの曝露においてウイルス感染してしまうほどに感染力が強いということです。
Multiple Outbreaks of Hepatitis B Virus Infection Related to Assisted Monitoring of Blood Glucose Among Residents of Assisted Living Facilities ― Virginia, 2009–2011
MMWR May 18, 2012
B型肝炎はじめ、血液由来感染症については、歯科や理容室、鍼灸での感染管理も考える必要があります。
施術者の感染曝露を調べることで、起こりうるリスクの大きさも検討ができます。
もともと歯科や外科系(産婦人科含む)では、医療者での抗体保有率が高いことが知られています。
鍼はどうでしょうか。
「B型肝炎ウイルスは抜鍼後の鍼体に付着する」全日本鍼灸学会雑誌.2002年,第52巻2号,137-140
「東京都鍼灸師会による鍼灸師のB型肝炎ウイルス表面抗原検査について」(1990年)
海外でもアウトブレイク事例は複数報告されています。
A large outbreak of acupuncture-associated hepatitis B.Am J Epidemiol. 1988 Mar;127(3):591-8.
歯科での感染拡大事例の認知もすすみました。
Lethal outbreak of hepatitis B in a dental practice.JAMA. 1986 Jun 20;255(23):3260-4
歯科医院をえらぶときは、当然どのレベルの感染管理をしているのか確認が必要です。
手袋をしない、患者ごとにかえない歯科もあれば、徹底してやっている歯科もあります。
鋭利なものを扱う場として、床屋はどうでしょうか?
今でも、使い捨て剃刀のところもあれば、そのお店の方法で消毒しているところもあります。
一応組合のようなものがあるそうですが(代々木)、それぞれのお店に対する指導権限のようなものはないので、あくまで努力目標であり、どのお店がどのような消毒や滅菌をしているかは不明との回答をいただきました。
----------------------------------------------------------
「理容所及び美容所における衛生管理要領について」(昭和56年6月1日 環指第95号 厚生省通知 一部抜粋)
かみそり(頭髪のカットのみの用途(レーザーカット)に使用するかみそりを除く。以下同じ)及びかみそり以外の器具で、 血液の付着しているもの又はその疑いのあるものの消毒の
手順
(1)消毒する前に家庭用洗剤をつけたスポンジ等を用いて、器具の表面をこすり、十分な流水(10秒間以上、1リットル以上)で洗浄する。
※1.器具は、使用直後に流水で洗浄することが望ましい。この際流水が飛散しないように注意することが必要である。
2.消毒液に浸す前に水気をとること。
(2)消毒は次のいずれかの方法により行う。 (注)消毒薬は医学品を使用すること(以下同じ)。
ア 煮沸消毒器による消毒
沸騰してから2分間以上煮沸すること。
※1.陶磁器、金属及び繊維製の器具の消毒に適するが、くし類等合成樹脂製のものの一部には加熱により変形するものがある。
2.水量を適量に維持する必要がある。
3.さび止めの目的で、亜硝酸ナトリウム等を加えることができる。
イ エタノールによる消毒
76.9v/v%~81.4v/v%エタノール液(消毒用エタノール)の中に10分間以上浸すこと。
※1.消毒液は、蒸発、汚れの程度等により、7日以内に取り替えること。
2.消毒用エタノールを希釈せず使用することが望ましいが、 無水エタノール又はエタノールを使用する場合は、消毒用エタノールと同等の濃度に希釈して使用すること(以下同じ)。
ウ 次亜塩素酸ナトリウムによる消毒
0.1%次亜塩素酸ナトリウム液(有効塩素濃度1,000ppm)中に 10分間浸すこと。
※1.金属器具及び動物性繊維製品は、腐食するので使用する場合は、必要以上に長時間浸さないなど取扱いに注意すること。
2.消毒液は、毎日取り替えること。
3.消毒薬を取り扱う際には、ゴム手袋を着用する等、直接皮膚に触れないようにすること。
4.製剤は保管中に塩素濃度の低下がみられるので、消毒液の有効塩素濃度を確認することが望ましい。
(3)消毒後流水で洗浄し、よくふく。
※1.クリッパーは刃を外して消毒すること。
2.替え刃式カミソリは、ホルダーの刃を挟む内部が汚れやすいので、刃を外してろ紙等を用いて清掃すること。
3.洗浄に使用したスポンジ等は使用後、流水で十分洗浄し、汚れのひどい場合は、エタノール又は次亜塩素酸ナトリウムで消毒すること。
で、厚労省からは平成19年に衛生関連の資料がもう一つ出ています。
平成19年 出張での理容美容
----------------------------------------------------------------
その時代に、現実的にどのような対応が可能だったのかということとあわせて考えることは大切ですね。
集団接種とB型肝炎
おひとりは、日野原重明先生です。御年100歳、10月4日には101歳です。
もうひとりは、サクラ グローバルホールディングス 会長の松本謙一氏です。
なにせ、病理診断や感染管理で国内外で医療に貢献しているサクラ精機は、1600年代より薬種商「いわしや」として日本橋にて営業です。こちらの社史、本社1階にある昔の医療器具などはマニアには魅力的なものがならんでいます。
松本会長は、手品が上手だったり(^^)大変楽しい方なのですが、空中に浮いている時間のほうが長いのではといわれるほど世界各地をとびまわるビジネスマンで、世界の医療事情にお詳しい一人。(先日のロシアでのAPECの会議では日本人の民間人としてただひとり口演をされた方です)
・・・そう。きっと、皆さんの周囲にも当時を語ることができる人がいます。
例えば・・・コチラの記事を参考にしてください。
「介護から器具の消毒まで…走らないと間に合わない、そんな労働環境でした」
福井県看護連盟
司会:最初に、病院の師長をなさっていましたが、昭和30年前後ぐらいの看護の状況についてお話いただけますか?
ゲスト:(略)消毒はシンメルブッシュが各科にあって、いつも煮沸消毒をして再生し、注射器もガーゼに包んで2本くらいずつ消毒していました。
司会:そんな状態で、感染を起こすということはなかったんですか?
ゲスト:それが不思議となかったんです。何回も消毒しましたので。でも、今思うと、よく事故などが起きなかったな、と思いますね。
(いや、当時は確認する術もアイデアもなかったと思うんですが・・・)
司会:当時のモーニングケアで、衛生材料はどう消毒していたのですか?
ゲスト:それは自分たちで消毒していました。中央材料室なんてありませんでしたし。注射器等はシンメルブッシュで煮沸消毒し、ケッテルなど蒸気滅菌するものは、コッホ消毒器と言われるもので消毒していました。…以前は炭でした。
(・・・知らない言葉もでてくるのであります)
と、ぜひ当時の日誌や、納品書の記録などをもとに、いつ頃、ディスポ製品へのアクセスそのものが可能になったのかを調べてみてください。
昭和33年の様子 京都府立医科大学麻酔科学教室 「京都府立医科大学麻酔科沿革(中央手術部を中心に)1959-1972」
"在来のコッヘル止血鉗子は鉄製ニッケル メッキで、 洗浄して組み合わせた。 それを新しくステンレス製のボックス型鉗子に変更した。 数が多く相当な金額であった。また古い木製の事務机や椅子は廃棄し、カンファレンス テーブルや医員ロッカーなどスチール製に変えた。 点滴台(キャスター付き)やキックバケツなどは、 当時としては贅沢なステンレス製のを新調した。 注射器はガラス製で、 デスポーザブルのものは未だなかった。 注射針は金属製で、皮下,筋注用の1尖と静注用10尖の2種類があった。"
京都府立医科大学中材室の記録。
"採血室の注射器以外は、外来診療科には払い出しをしていないため、現場では、注射器hあ、洗剤とブラシで洗い、濯いだ後シンメルブッシュで煮沸消毒をしていた。病舎でもこのシンメルブッシュは大いに活躍して、まるで材料室の下請けのようだった。外来の注射器が手洗いのあと、カストに詰められ、オートクレーブ消毒ができるようになったのは1974年(昭和49年)頃からであり、注射器のディスポへ切り替えが実施されたのも、同年7月からで、種類は輸血針、静脈針、皮下針、皮内針の四種類で、因に単価は4円50銭であった。"
第308段:「医療廃棄物」(心にうつりゆくそぞろごと)
"私の子供時代の昭和三十年代には父の診察室の隅っこのテーブルの上にある電熱器の上に載せられた煮沸消毒器での消毒でした。(中略)もちろん注射器はガラス製で何度も消毒して使っていましたし、注射針も同様でしたが、注射針の切れ味が悪くなると父や祖父は自分で砥石を使って研ぎ、時にはメスを研いで下さる職人さんが来られると針などもまとめて研いでもらっていたようでした。医療器具の精度や安全性は現在と比べると桁違いに悪かったといわざるをえません。
ある日、小さな診察室には煮沸消毒器ではなく高圧蒸気滅菌器と呼ばれる器械が置かれるようになりました。
「これで、安心して消毒・滅菌が出来るようになった」とうれしそうな顔をして父が話してくれた時の顔は今でも覚えています。当時は煮沸消毒器では完全に病原菌が消毒できないことはわかっていましたが、小さな診療所では消毒する器具の量も少なく大型の高価な機械は買えない時代のようでしたが、やっと小型の器械が発売されて使えるようになったようでした。
今の時代のように、何でも消毒、抗菌グッズが氾濫している状況から考えれば信じられないような医療行為が当たり前でした。予防接種の針は交換しないでアルコールを含ませた綿の上で軽く拭くだけ、同じ注射器、同じ針で次々に予防接種をされた記憶があります。"
三木クリニック
"昔話をすると、院長が医者になった頃は、患者さんは毎朝その日の注射に必要な数のガラスの注射器と太い針を煮沸・消毒して、筆箱のよう形の金属容器に、アルコール綿と一緒に入れて持ち歩かねばならなかったのですから"
糖尿病ネットワーク
"使い捨て注射器が開発される以前は、ガラス製注射器を注射針とともにガーゼに包んで、小鍋で煮沸消毒し、それでインスリンの瓶からインスリンを吸い取り注射していた。ディスポーザブル注射器が開発されてから注射器の消毒がなくなり、インスリン療法はより実施しやすくなった。そして1985年にはノボ社がペン型インスリン注射器ノボペンを発売し、インスリン療法の実施がいつそう容易になった。"
医療機関や介護施設におけるB型肝炎のアウトブレイクは、感染経路がよくわからないものもあるのですが、近年までアウトブレイクの原因にくりかえしなっており、また注意喚起が行われてきたのは、血糖測定に関する器機の共有です。
もっとも、血液がべったりついていたり目に見える血液があれば、そのまま使うことはないのですが、逆にいうと、目に見えないレベルの曝露においてウイルス感染してしまうほどに感染力が強いということです。
Multiple Outbreaks of Hepatitis B Virus Infection Related to Assisted Monitoring of Blood Glucose Among Residents of Assisted Living Facilities ― Virginia, 2009–2011
MMWR May 18, 2012
B型肝炎はじめ、血液由来感染症については、歯科や理容室、鍼灸での感染管理も考える必要があります。
施術者の感染曝露を調べることで、起こりうるリスクの大きさも検討ができます。
もともと歯科や外科系(産婦人科含む)では、医療者での抗体保有率が高いことが知られています。
鍼はどうでしょうか。
「B型肝炎ウイルスは抜鍼後の鍼体に付着する」全日本鍼灸学会雑誌.2002年,第52巻2号,137-140
「東京都鍼灸師会による鍼灸師のB型肝炎ウイルス表面抗原検査について」(1990年)
海外でもアウトブレイク事例は複数報告されています。
A large outbreak of acupuncture-associated hepatitis B.Am J Epidemiol. 1988 Mar;127(3):591-8.
歯科での感染拡大事例の認知もすすみました。
Lethal outbreak of hepatitis B in a dental practice.JAMA. 1986 Jun 20;255(23):3260-4
歯科医院をえらぶときは、当然どのレベルの感染管理をしているのか確認が必要です。
手袋をしない、患者ごとにかえない歯科もあれば、徹底してやっている歯科もあります。
鋭利なものを扱う場として、床屋はどうでしょうか?
今でも、使い捨て剃刀のところもあれば、そのお店の方法で消毒しているところもあります。
一応組合のようなものがあるそうですが(代々木)、それぞれのお店に対する指導権限のようなものはないので、あくまで努力目標であり、どのお店がどのような消毒や滅菌をしているかは不明との回答をいただきました。
----------------------------------------------------------
「理容所及び美容所における衛生管理要領について」(昭和56年6月1日 環指第95号 厚生省通知 一部抜粋)
かみそり(頭髪のカットのみの用途(レーザーカット)に使用するかみそりを除く。以下同じ)及びかみそり以外の器具で、 血液の付着しているもの又はその疑いのあるものの消毒の
手順
(1)消毒する前に家庭用洗剤をつけたスポンジ等を用いて、器具の表面をこすり、十分な流水(10秒間以上、1リットル以上)で洗浄する。
※1.器具は、使用直後に流水で洗浄することが望ましい。この際流水が飛散しないように注意することが必要である。
2.消毒液に浸す前に水気をとること。
(2)消毒は次のいずれかの方法により行う。 (注)消毒薬は医学品を使用すること(以下同じ)。
ア 煮沸消毒器による消毒
沸騰してから2分間以上煮沸すること。
※1.陶磁器、金属及び繊維製の器具の消毒に適するが、くし類等合成樹脂製のものの一部には加熱により変形するものがある。
2.水量を適量に維持する必要がある。
3.さび止めの目的で、亜硝酸ナトリウム等を加えることができる。
イ エタノールによる消毒
76.9v/v%~81.4v/v%エタノール液(消毒用エタノール)の中に10分間以上浸すこと。
※1.消毒液は、蒸発、汚れの程度等により、7日以内に取り替えること。
2.消毒用エタノールを希釈せず使用することが望ましいが、 無水エタノール又はエタノールを使用する場合は、消毒用エタノールと同等の濃度に希釈して使用すること(以下同じ)。
ウ 次亜塩素酸ナトリウムによる消毒
0.1%次亜塩素酸ナトリウム液(有効塩素濃度1,000ppm)中に 10分間浸すこと。
※1.金属器具及び動物性繊維製品は、腐食するので使用する場合は、必要以上に長時間浸さないなど取扱いに注意すること。
2.消毒液は、毎日取り替えること。
3.消毒薬を取り扱う際には、ゴム手袋を着用する等、直接皮膚に触れないようにすること。
4.製剤は保管中に塩素濃度の低下がみられるので、消毒液の有効塩素濃度を確認することが望ましい。
(3)消毒後流水で洗浄し、よくふく。
※1.クリッパーは刃を外して消毒すること。
2.替え刃式カミソリは、ホルダーの刃を挟む内部が汚れやすいので、刃を外してろ紙等を用いて清掃すること。
3.洗浄に使用したスポンジ等は使用後、流水で十分洗浄し、汚れのひどい場合は、エタノール又は次亜塩素酸ナトリウムで消毒すること。
で、厚労省からは平成19年に衛生関連の資料がもう一つ出ています。
平成19年 出張での理容美容
----------------------------------------------------------------
その時代に、現実的にどのような対応が可能だったのかということとあわせて考えることは大切ですね。
集団接種とB型肝炎