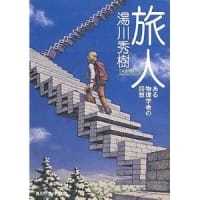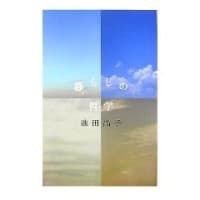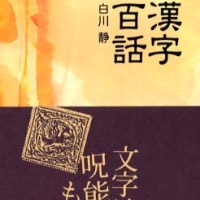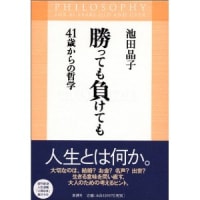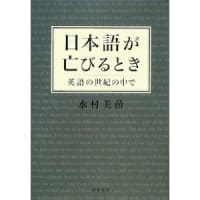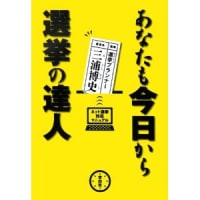平成26年6月23日 MSN産経ニュースより
石原伸晃環境相は6月23日午前、東京電力福島第1原発事故で出た除染廃棄物を保管する中間貯蔵施設の候補地、福島県大熊町の渡辺利綱町長に会い、施設をめぐる交渉について「最後は金目でしょ」と述べた発言を謝罪する。
石原氏は会津若松市内に移転している大熊町の役場を訪問。午後には、同じく候補地である双葉町の伊沢史朗町長に役場移転先のいわき市で、夕方には福島県庁で佐藤雄平知事に会う。石原氏は16日、中間貯蔵施設に関する住民説明会が15日に終了したことなどを、官邸で菅義偉官房長官に報告。その後の記者団の取材に対し「最後は金目」と発言した。
佐藤知事が「住民のふるさとを思う気持ちを踏みにじる」と述べるなど、福島県側から批判が高まり、石原氏は17日の記者会見で陳謝。19日の参院環境委員会で「品位を欠いた発言で誤解を招いた。おわびして撤回する」と述べた。
***************************************************
貨幣とは価値の尺度であること、そして貨幣は価値を媒介する交換手段であることの残酷さについて、いくら机上で理屈を学んだところで、その本当のところはわからないものと思います。「お金に色を付けても色は付かない」という事実について、私が身に染みて理解させられたのは、精神的苦痛の慰謝料の支払いの現場での受け渡しや振り込みの業務に日常的に従事するようになってからのことでした。
「最後は金目である」という論理の破壊力は、お金の獲得を目的にする意思が毛頭なく、その何かを金銭に換算する思考を唾棄すべき時に、否応なく入り込んで来るものと思います。お金を支払う側は、その損失ないし苦痛の負担が制度趣旨である以上、「払えばいいんだろう」という精神の動きを免れません。そして、経済は議論の過程ではなく結果によって動き、世の中のシステムが回り始めます。
貨幣は価値の尺度であるが故に、大金を手にする者に対しては、それがいかなる名目であっても、必ず羨望の視線は向けられるものと思います。「焼け太り」なる概念は、嫉妬心以外の感情が生み出すものではありません。そして、「誠意がない」との直観が「金額が安すぎる」という実利的な形を強いられた瞬間、あらゆる観念はこの色のない構造の中に入れられ、出られなくなるものと思います。
何物かの補填として高い賠償金を得ることは、社会的には「金銭欲が満たされて満足だろう」という判断を向けられざるを得ません。他方で、低い賠償金しか得られないとなれば、人生をお金に換算される惨めさを強いられることになり、いずれにしても損失の修復は不可能です。紛争解決の落としどころが「最後は金目である」ということは、いかなる意味でも正しく、そして残酷なことだと思います。
(続きます。)