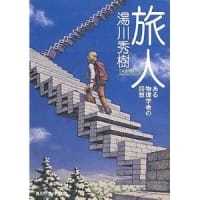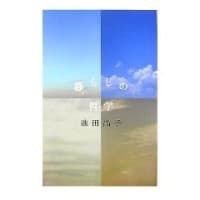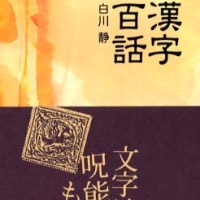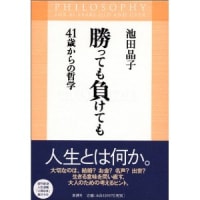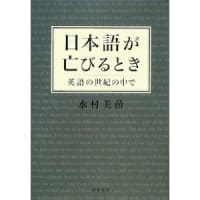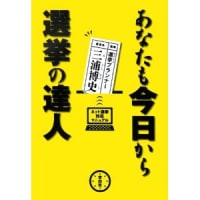犯罪被害者保護を「心のケア」という枠組みで議論するとき、事件そのものに関する論点は微妙にずらされる。被告人の反省や悔悟とは無関係なものとして、国家による金銭的な補償が問題とされることもある。しかし、被害者はとにかく事件そのものの情報が知りたい。そして、裁判に参加したい。これは人間としての当然の要求であるが、法律学はこの要求の意味が理解できない。
被害者がまず何よりも最初に望むことは、被告人が事件について明らかに語ることであり、自分の犯した罪と正面から向き合い、反省して謝罪することである。過去の事件を置き去りにしたまま、将来に向けた心のケアなどと言われても、土台が崩れている所にビルを建てるようなものである。極限まで追い詰められた被害者の声が指し示すものは、人間としての倫理であり、正義である。
哲学はもちろん、この被害者の声を当然のものとして理解する。哲学が扱うテーマは人間の倫理や正義であり、国家による金銭的な補償などは本質的な問題ではないからである。これに対して法律学では、倫理や正義の問題は抽象的すぎて扱えない。哲学から細分化した法律学には、何よりも実用性が求められるからである。
かくして裁判という場は、被告人が自分の犯した罪と向き合う場ではなくなる。被告人は自分の罪を軽くするために否認し、弁解し、あるいは口先だけの謝罪をすることが権利として認められる。これが現在の法律学の到達点であり、現在の裁判が採用しているカテゴリーである。この文脈の中で被害者保護を図ると言っても、被害者が望んでいる最大のものは与えられない。
被告人が自分の犯した罪と向き合うということ、これが人間としての倫理であり、正義である。そうであるならば、現在の裁判は反倫理的であり、反正義的である。社会が本気で被害者保護に取り組むならば、いずれ法律学のパラダイムを脱構築して、哲学のパラダイムからの新たな制度設計が必要となるだろう。
被害者がまず何よりも最初に望むことは、被告人が事件について明らかに語ることであり、自分の犯した罪と正面から向き合い、反省して謝罪することである。過去の事件を置き去りにしたまま、将来に向けた心のケアなどと言われても、土台が崩れている所にビルを建てるようなものである。極限まで追い詰められた被害者の声が指し示すものは、人間としての倫理であり、正義である。
哲学はもちろん、この被害者の声を当然のものとして理解する。哲学が扱うテーマは人間の倫理や正義であり、国家による金銭的な補償などは本質的な問題ではないからである。これに対して法律学では、倫理や正義の問題は抽象的すぎて扱えない。哲学から細分化した法律学には、何よりも実用性が求められるからである。
かくして裁判という場は、被告人が自分の犯した罪と向き合う場ではなくなる。被告人は自分の罪を軽くするために否認し、弁解し、あるいは口先だけの謝罪をすることが権利として認められる。これが現在の法律学の到達点であり、現在の裁判が採用しているカテゴリーである。この文脈の中で被害者保護を図ると言っても、被害者が望んでいる最大のものは与えられない。
被告人が自分の犯した罪と向き合うということ、これが人間としての倫理であり、正義である。そうであるならば、現在の裁判は反倫理的であり、反正義的である。社会が本気で被害者保護に取り組むならば、いずれ法律学のパラダイムを脱構築して、哲学のパラダイムからの新たな制度設計が必要となるだろう。