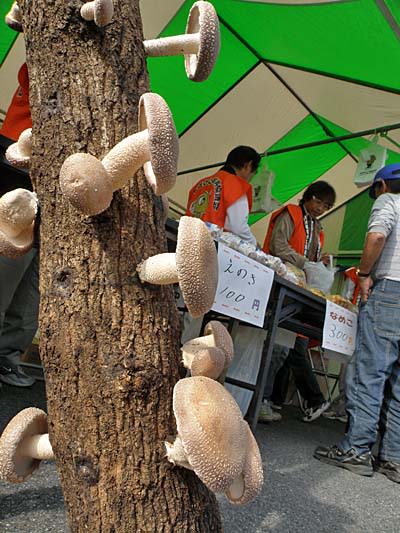いよいよ明日、10月18日から、生物多様性条約第10回締約国会議(cop10)が始まります。
「生物多様性 biodiversity」は、1980年代から使われ始めた新しい言葉で、すべての生物の間に違いがあることと定義し、生態系の多様性、種間(種)の多様性、種内(遺伝子)の多様性という3つのレベルでの多様性があるとしています。
昔の生物の教科書では出てこなかった概念なので、生物体多様性という言葉は聞いたことがあるけど、いまひとつピンとこないなぁ・・・という人も少なくないと思います。
先日、市内の書店に立ち寄った時に、見つけた本を紹介します。
生物多様性 100問 森山正仁 著 福岡伸一 監修 木楽舎

子どもに生物多様性って何?って聞かれたけど上手く答えられなかったよ~ なぜ生物多様性が大切なの? 生物多様性の保全って一般人にも関係あるの? 生物多様性条約って何? COP10って何? 生物多様性基本法って聞いたこともないな~? という人にオススメの一冊。
これらの疑問が100のQ&A形式で、わかりやすく解説されています。
さて、生物多様性条約の目的は
①生物多様性の保全
②生物多様性の構成要素の持続可能な利用
③遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分
であり、明日から始まるCOP10の主な議題は、
①2010年目標の達成状況の検証と新たな目標(ポスト2010年目標)の策定
②遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)に関する国際的な枠組みの策定
です。
生物多様性は人類の存続基盤であり、保全していかなければならないというところは、異議の余地はないと思いますが、現実にはEUなどの先進国と豊富な生物資源を持ち、さらに国土の開発も進めたい発展途上国や新興国との対立は大きく、ポスト2010年目標や生物資源の利用と利益配分に関するルール作りには問題が山積しています。
(アメリカ合衆国は条約の目的の一つ、「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」が、自国のバイオテクノロジー産業に影響を与えるという理由で、未だに条約を批准していません)
昨年開催された気候変動枠組条約第15回締約国会議でも、南北間の対立が表面化しましたが、今回の生物多様性条約締約国会議でも、同様の(否、それ以上か?)の対立が予想されます。
この難しい会議を議長国である日本が、どうにまとめるのか? 世界から注目されています。
でも、COP10に関する国内での関心はいまひとつ盛り上がりに欠けるという印象・・・
「生物多様性100問」を買った書店でも、生物多様性特集コーナーは設けられていませんでした。ちょっとガッカリ・・・。
ところで話は少々変わりますが、現代は生物多様性ばかりではなく、社会、文化の多様性も失われつつありますね。
地域の特産物を使ったB級グルメが流行ったり、地域独特の文化・風習を紹介するTV番組が高い視聴率だったりするのは、文化の多様性喪失を惜しんでいる人が多いためでは?