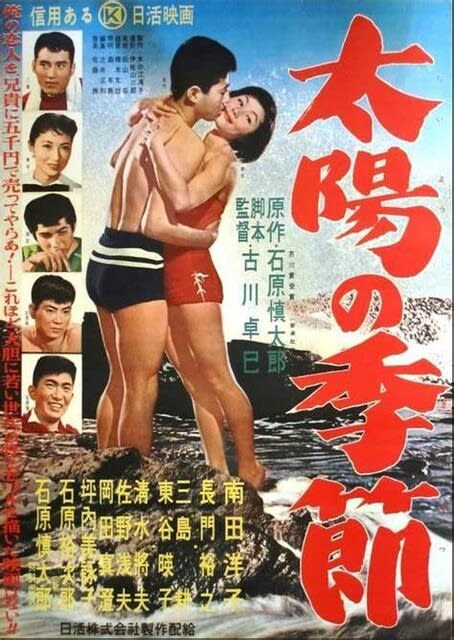真言宗の全面的な協力をえて東映が、1984年に作った空海の伝記映画。当時、さんざ予告編を見たが、はじめて本編を見た。

これは、はじめは空海に勝新太郎がキャステイングされていて、勝新と真言側との会合が開かれた。
その席で、勝は、
「空海は、唐に留学して多数の文献を持ってきたが、中には仏典だけでなく、エロ本もあったはずだ。
だから、俺はマスをかいて、ビンビュン精液を飛ばしてやる・・・」
これに真言側は、度肝を抜かれ、勝新には、ご辞退をいただき、北大路欣也に代わったのだそうだ。
もちろん、北大路は悪くないが、まじめすぎて、破天荒さがないのは、残念なところだ。
幼いころから、優秀さゆえに讃岐から、都(奈良)の大学に来ていた真魚は、本当の学問の意味はなにかと自問し、讃岐に戻ってくる。
それから、全国を修行に自ら彷徨するが、都の桓武天皇が、遣唐使を派遣すると知って、応募する。
その4隻の船の内の1隻には、後にライバルとなる最澄も乗っていた。
最澄も、当時最新の教えだった密教を学びたいとの意思があった。
空海の乗った船には、橘逸勢(石橋蓮司)もいて、彼は出世のために志願したのだが、空海は、本物の密教を学ぶために行ったのだ。
だが、ちっぽけな遣唐使船は、大風に遭って翻弄され、4隻の内、2隻は難破してしまう。
だが、運よく空海の乗った船は、大漂流して南に流されるが、なんとか中国に着く。
そして、、都の長安を目指して行くが、すでに最澄は、長安で密教を学んでいると聞いて、空愕然とするが、空海は、逆に自分こそ、本当の密教を学ぶと決意する。
長安で、彼は、まず梵語を学び、すぐに習得してしまうほど、空海は語学の天才だった。
全体の語りは、空海の叔父の役の森繫久彌のナレーションで進行してゆくので、大変分かりやすくできている。
ついに、密教の祖にじかに合うことができ、本当の教えを受けることができる。
この辺は、アニメなどを使って解説されるが、凡夫の私には、本当には理解できないところだ。
本来は、20年いるべき留学生を、2年で切り上げて空海は、日本に戻る。
西郷輝彦の嵯峨天皇から、そのことを問われるが、空海は、
「密教で、日本を救いたいのだ」と断言し、天皇の信頼を得る。
それは、宗教者というよりも、デマゴーグに近いが、彼が天才であることは間違いない。
そこに最澄の加藤剛が来て、密教の教えを懇願するが、空海は最後までは教えない。
ここは、秀才と天才の対決で、大変に興味深い。
空海は、故郷に戻り、水害を防ぐために、人造湖を作るが、嫌がる農民等を鼓舞し、昼夜兼行で土木工事を完成させてしまう。
まさに天才であり、イタリアのレオナルド・ダ・ビンチみたいな人間だったと言えるだろう。
音楽が、ツトム・ヤマシタで、ここはやはり伊福部先生の重厚さがほしいところだった。
空海の同船には、橘逸勢の石橋蓮司なども乗っていて、か