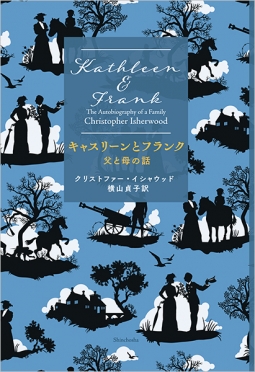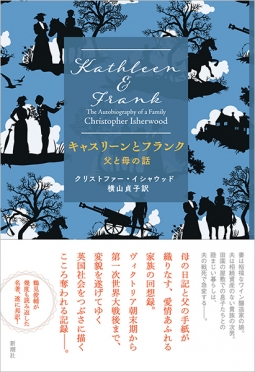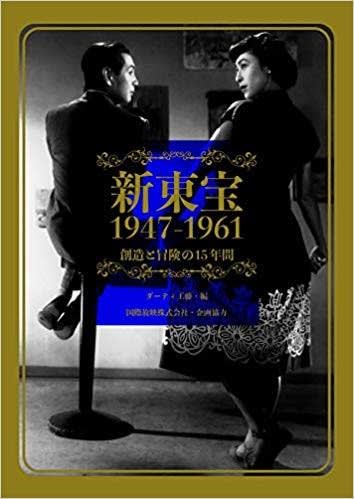先日、中曽根から村上一郎を探していて、彼の妻の伝記が出ていることを知り読んでみる。
そして、彼の話を聞いたことがあることを思いだした。
前に、早稲田で彼の講演を聞いたことがあることを書いたが、その後だと思うが、俳優座劇場で彼の話を聞いている。
それは、三好十郎の劇『その人を知らず』の公演の後に、三好十郎の研究家の川村さんの後に、村上が話したと思う。
かなり大感激した口ぶりで、「そこで見ていて泣いた・・・」というようなことを言っていた。
三好十郎の戯曲は、戦時中に天皇信仰に対してキリスト者として抗して弾圧された人たちを描いたもので、日本では極めて珍しい人たちだったのだ。
日本共産党員をはじめ、多くの左翼が転向し、戦争協力をしていった中で、キリスト教のホーリネス派の人だけがこのように行動したので、三好は驚きをもって彼らを描いている。
そして、この本で知ったのは、村上一郎の父親は、このホーリネス派の牧師だったとのことだ。

村上の妻となる、えみ子は、戦争末期、東京海軍監督官事務所で知り合う。
そこは、海軍への武器をはじめ多くの物資等を配布する事務所で、東京商科大学(一橋大学)の村上と、女子学院出のえみ子は、東監で知り合うことになる。
共に、徴兵逃れ的な意味もあったが、それについて村上一郎は戦後、自分の責任として悩むことになる。
戦時下の恋は、非常に美しいが、それは妻えみ子にとって、戦後のつらい日々の始まりでもあった。
戦後、村上は多くの出版社に勤めるが、長くは続かない。それは村上の直情径行的な性格だが、それは次第に精神的な疾患になっていく。
日本共産党員にもなるが、それは長く続かず、1960年後は、吉本隆明らに近い文化人として活動し、多摩美大での職も得る。
だが、学園紛争で彼の血が騒ぎ、問題を起こして止める。
当時、桑沢デザイン研究所でも教えていたそうだが、当時教わった女性に聞くと相当におかしなものだったらしい。授業中に、いきなり謡をうたい、舞い出したりして、生徒はみなびっくりしたとのこと。
私が、早稲田で彼の講演を聞いたのは、そのころだが、当時もひどい精神状態だったことは初めて知って非常に驚いた。
そして、三島由紀夫の激賞から、彼の自殺事件で、村上一郎は一躍有名文化人になり、それが彼の病をさらに嵩じさせる。
そして、頸動脈を自ら切っての自死。
まことに誠実というか、悲しいことだった。
その後、えみ子は再婚するが、それは必ずしも幸福なものではなかったようだ。
それは、えみ子の村上への愛の大きさを現していると思う。