昨日(14日)の「日本史サスペンス劇場」(日テレ)は「特別企画“東大落城”』と題し、今からちょうど40年前の1969年1月、東大を占拠した全共闘の学生と、機動隊の攻防戦をドラマ化しました。

前年の医学部闘争で医学部の校舎を占拠した学生を排除するため、当時の大河内一男総長が警察力の導入を求めたことから学生の反発を招きました。
これに端を発し、授業料の値上げ反対闘争、70年安保改定反対闘争など、東大紛争は拡大し、学生運動は全国の大学に広がるきっかけになりました。
安田講堂事件とは、東大の全学封鎖にむけて安田講堂や工学部列品館などをを占拠した数百人の学生によるバリケードを解除するために、およそ8000人の機動隊との間で繰り広げられた攻防戦です。
学生は投石、火炎瓶などで抵抗し、機動隊は催涙ガス弾、放水、ヘリからの催涙ガス攻撃など、まるでパレスチナとイスラエルのような規模の違いがありながら、学生たちは二日間占拠し続けました。
「火炎瓶」というのは、ビールビンにガソリンを詰めて、ガーゼなどの吸い込みやすい布で口を塞いだもの。
布に着火して投げると、落下地点で瓶が割れて火が広がります。
ガソリンなので、取扱いに気をつけないと爆発します。
これを機に、学生運動は一層拡大しましたが、70年に安保条約が改定されてからはその多くが挫折。それまで全共闘として連帯を組んでいた各派閥は、中核と革マルの闘争など、いわゆる内ゲバにエネルギーがそそがれ、そして一部は連合赤軍や日本赤軍など極端な活動によって大衆から乖離し、学生運動は急速に衰えて行きました。
番組は、学生運動を否定的には表現していません。
当時の社会背景から、現代への問いかけがなされていたことに好意を感じました。
陣内孝則演じる機動隊の司令官が、東大陥落後、こんな言葉をつぶやきます。
「私は彼らに憎しみも恨みも感じない、それよりも、学生たちをここまで追い詰めたのはいったい何なのかと思う。このこと(失敗)で、未来の学生たちから気力が失われはしないだろうかと、それが心配だ」
警察官がこんな気のきいたことを言うなど信じられませんが、まさに現代は「学生たちから気力が失われ」ています。
派遣切りや高齢者いじめが政府主導で行なわれているような現代は、それに抵抗する勢力が失われたからに他ならないでしょう。
当時現場を指揮した警視庁の佐々淳行が番組の終盤、「若者は怒らなきゃ。40度は困るが38度くらいの熱は出して欲しい」と言った言葉が印象的です。
当時の彼の対応を考えると、「よく言うよ」という感はありますが。
学生運動が大衆運動として発展しなかった最大の理由は、一言でいえば数の問題。彼らに賛同しともに行動する人々が何万何十万といたならば、違った結果になったことは間違いありません。
なぜそれができなかったか。それは学生たちが、自分たちだけのイデオロギーに固執したことです。もっと広範な大衆に受け入れられる柔軟さがあったら、違ったかたちで闘争は拡大したでしょうが。
連帯する以前に突っ走ってしまったことが失敗ですね。
それより重要なのは、活動家たちはあの失敗から何を学んだのか、という疑問が残ります。さらなる発展につなげる活動家が現れなかったことが、今の状況を生んでいるのではないでしょうか。
また、学生運動に否定的な人が少なくありません。それはいわゆる“新左翼”の末期、よど号事件の「赤軍派」や、浅間山荘事件等の「連合赤軍」の暴挙が印象に残っている場合が多いようです。
しかし、本来の全共闘の闘争方針はアピールと学園ロックアウトであって、暴力的な攻撃にはありませんでした。
火炎瓶や投石は、機動隊の放水や催涙弾攻撃に対する抵抗です。したがって、一人でも怪我人が出れば停戦撤退しました。
全共闘と機動隊の対立は、まさにパレスチナとイスラエル。規模が違いすぎる紛争でした。
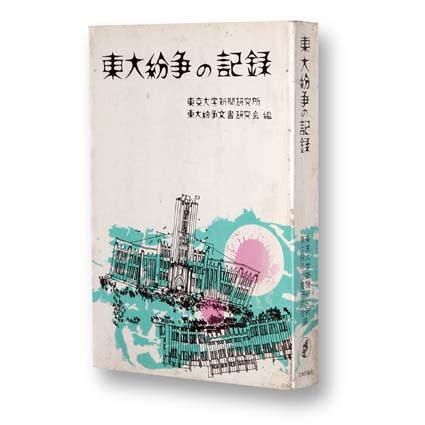
この年、東大紛争を記録した本が2冊出ています。
一冊は安田講堂事件が起きる直前に発行された、東京大学新聞研究所・東大紛争文書研究会編『東大紛争の記録』(日本評論社 1969年1月15日)で、安田講堂事件直前までの記録が掲載されています。

もう一冊は、同年4月10日に発行された東大全学共闘会議編『砦の上にわれらの世界を』(亜紀書房)です。こちらは多くの写真や図版を掲載し、650頁を越える詳細な記録になっています。
この本は当時、日大闘争を記録した『叛逆のバリケード』(三一書房)とともにベストセラーになりました。
ところで、番組の中で「インターナショナル」が何度か学生たちによって歌われます。
「この歌聞くのひさしぶりだなあ」
ぼくが言うと、そばで見ていたカミさんが、
「これ、東大の歌?」
那由と二人でずっこけました。
そういうカミさんですが、「みんな生き生きしてていいなあ、一緒にやりたかった」。
で、「那由(もうすぐ高校生の長女)はどう?」と水を向けると、「たぶんやってる」。
わが家の女性たちは「過激派」です。

「インターナショナル」を久しぶりだと言いましたが、「ソウルフラワー・モノノケサミット」というバンドがロックで演奏していてCDも出ています。
「インターナショナル」は『レヴェラーズ・チンドン』に入っていて、もう1枚の『アジール・チンドン』には「聞け万国の労働者」が入ってます。
【リンク】「昔話ですが…「全共闘」」
◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆
◆出版と原稿作りのお手伝い◆
原稿制作から出版まで、ご相談承ります。
メールでお気軽に galapyio@sepia.ocn.ne.jp まで

前年の医学部闘争で医学部の校舎を占拠した学生を排除するため、当時の大河内一男総長が警察力の導入を求めたことから学生の反発を招きました。
これに端を発し、授業料の値上げ反対闘争、70年安保改定反対闘争など、東大紛争は拡大し、学生運動は全国の大学に広がるきっかけになりました。
安田講堂事件とは、東大の全学封鎖にむけて安田講堂や工学部列品館などをを占拠した数百人の学生によるバリケードを解除するために、およそ8000人の機動隊との間で繰り広げられた攻防戦です。
学生は投石、火炎瓶などで抵抗し、機動隊は催涙ガス弾、放水、ヘリからの催涙ガス攻撃など、まるでパレスチナとイスラエルのような規模の違いがありながら、学生たちは二日間占拠し続けました。
「火炎瓶」というのは、ビールビンにガソリンを詰めて、ガーゼなどの吸い込みやすい布で口を塞いだもの。
布に着火して投げると、落下地点で瓶が割れて火が広がります。
ガソリンなので、取扱いに気をつけないと爆発します。
これを機に、学生運動は一層拡大しましたが、70年に安保条約が改定されてからはその多くが挫折。それまで全共闘として連帯を組んでいた各派閥は、中核と革マルの闘争など、いわゆる内ゲバにエネルギーがそそがれ、そして一部は連合赤軍や日本赤軍など極端な活動によって大衆から乖離し、学生運動は急速に衰えて行きました。
番組は、学生運動を否定的には表現していません。
当時の社会背景から、現代への問いかけがなされていたことに好意を感じました。
陣内孝則演じる機動隊の司令官が、東大陥落後、こんな言葉をつぶやきます。
「私は彼らに憎しみも恨みも感じない、それよりも、学生たちをここまで追い詰めたのはいったい何なのかと思う。このこと(失敗)で、未来の学生たちから気力が失われはしないだろうかと、それが心配だ」
警察官がこんな気のきいたことを言うなど信じられませんが、まさに現代は「学生たちから気力が失われ」ています。
派遣切りや高齢者いじめが政府主導で行なわれているような現代は、それに抵抗する勢力が失われたからに他ならないでしょう。
当時現場を指揮した警視庁の佐々淳行が番組の終盤、「若者は怒らなきゃ。40度は困るが38度くらいの熱は出して欲しい」と言った言葉が印象的です。
当時の彼の対応を考えると、「よく言うよ」という感はありますが。
学生運動が大衆運動として発展しなかった最大の理由は、一言でいえば数の問題。彼らに賛同しともに行動する人々が何万何十万といたならば、違った結果になったことは間違いありません。
なぜそれができなかったか。それは学生たちが、自分たちだけのイデオロギーに固執したことです。もっと広範な大衆に受け入れられる柔軟さがあったら、違ったかたちで闘争は拡大したでしょうが。
連帯する以前に突っ走ってしまったことが失敗ですね。
それより重要なのは、活動家たちはあの失敗から何を学んだのか、という疑問が残ります。さらなる発展につなげる活動家が現れなかったことが、今の状況を生んでいるのではないでしょうか。
また、学生運動に否定的な人が少なくありません。それはいわゆる“新左翼”の末期、よど号事件の「赤軍派」や、浅間山荘事件等の「連合赤軍」の暴挙が印象に残っている場合が多いようです。
しかし、本来の全共闘の闘争方針はアピールと学園ロックアウトであって、暴力的な攻撃にはありませんでした。
火炎瓶や投石は、機動隊の放水や催涙弾攻撃に対する抵抗です。したがって、一人でも怪我人が出れば停戦撤退しました。
全共闘と機動隊の対立は、まさにパレスチナとイスラエル。規模が違いすぎる紛争でした。
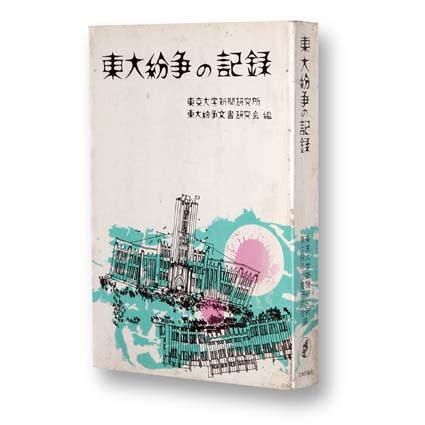
この年、東大紛争を記録した本が2冊出ています。
一冊は安田講堂事件が起きる直前に発行された、東京大学新聞研究所・東大紛争文書研究会編『東大紛争の記録』(日本評論社 1969年1月15日)で、安田講堂事件直前までの記録が掲載されています。

もう一冊は、同年4月10日に発行された東大全学共闘会議編『砦の上にわれらの世界を』(亜紀書房)です。こちらは多くの写真や図版を掲載し、650頁を越える詳細な記録になっています。
この本は当時、日大闘争を記録した『叛逆のバリケード』(三一書房)とともにベストセラーになりました。
ところで、番組の中で「インターナショナル」が何度か学生たちによって歌われます。
「この歌聞くのひさしぶりだなあ」
ぼくが言うと、そばで見ていたカミさんが、
「これ、東大の歌?」
那由と二人でずっこけました。
そういうカミさんですが、「みんな生き生きしてていいなあ、一緒にやりたかった」。
で、「那由(もうすぐ高校生の長女)はどう?」と水を向けると、「たぶんやってる」。
わが家の女性たちは「過激派」です。

「インターナショナル」を久しぶりだと言いましたが、「ソウルフラワー・モノノケサミット」というバンドがロックで演奏していてCDも出ています。
「インターナショナル」は『レヴェラーズ・チンドン』に入っていて、もう1枚の『アジール・チンドン』には「聞け万国の労働者」が入ってます。
【リンク】「昔話ですが…「全共闘」」
◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆
◆出版と原稿作りのお手伝い◆
原稿制作から出版まで、ご相談承ります。
メールでお気軽に galapyio@sepia.ocn.ne.jp まで



















