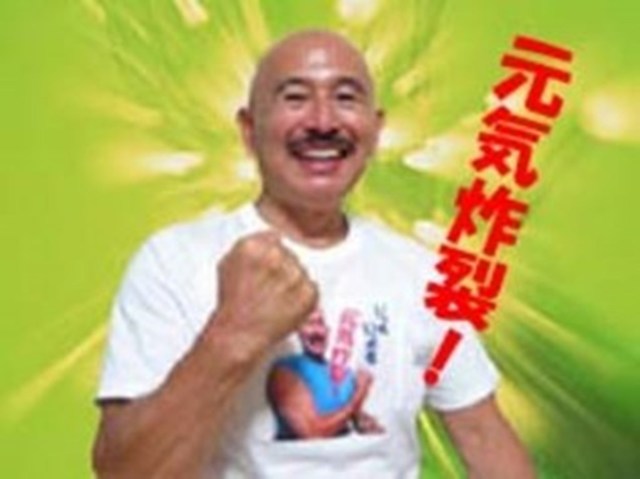今日は二十四節気の「立冬(りっとう)」
昨日までは秋の最後の二十四節季「霜降」の末候「楓蔦黄」だった。
その「楓蔦黄(もみじつたきばむ)」とは・・・
もみじやつたが色づいてくるころ・・・
ブログ友のyamaさんや、kenさんの記事でも各地の素晴らしい
紅葉、黄葉が連日沢山紹介され、私たちは居ながらにしてそれを
楽しませていただいているが、これぞまさしく「山粧う(やまよそおう)」
或いは「山燃ゆる・・」「錦秋の・・」などという言葉で
表される素晴らしい日本の、そして私たちが感じる「深まる秋」を
言い表す、美しい言葉や表現ではないかと思う。
そして今日の「立冬」・・・
その初候の山茶始開(つばきはじめてひらく)は山茶花(さざんか)の
花が咲き始める頃・・・
すでに銀杏の葉が黄色く色づき始め、紅葉(もみじ)が見ごろとなる頃。
さらにはじめて冬の気配があらわれてくる頃。
晩秋から冬にかけて咲くサザンカは、冬枯れが進む中の景色に鮮やかに
色を添える役目があるように思える。
私の住むマンションのフェンスは山茶花(サザンカ)と柊(ヒイラギ)
が交互に植えられた生け垣でできている。
例年、その濃い緑の中に、優しく可愛いピンクや深紅のさざんかが
少しずつ顔を出し、次第にその数を増しながら咲きほこる様子が
私たちを楽しませてくれているが今年はまだ顔を見せていない。
ツバキに先駆けて冬を告げる花サザンカは・・・
七十二項では「山茶」と書いてツバキと呼ぶが実際には山茶花を
指すものらしい、そして昔はサザンカもツバキも混同されていたという。
ちなみに中国では「山茶」と書くとツバキを指すということや
そのわけも今年初めて知った。(ちょっとややこしい)
それは・・・山に生える茶の木としてツバキの葉をお茶として飲んで
いたから・・・そしてサザンカは「茶梅」と書くことも・・・
その由来は椿の枝を火で炙り、お湯に浸して飲む「椿枝茶」からだという。
サザンカは長い間私たちの目を楽しませてくれる。
椿は椿なりにサザンカもその個性(?)をいかんなく発揮し、
その役目(?)を終えるとハラリハラリとひとひらふたひら、地上に落ち、
私たちのいろんな感情を生むきっかけを作ってくれるようでもある。
立冬と言っても今日の天気では寒い冬にはまだほど遠いような気がする。
遠くにあった紅葉も今はすぐ近くでもみられるようになった。
色づいた落ち葉を拾い、その色を楽しむこともいいのではないだろうか、
まだまだ深い秋を静かに楽しむこともできる。