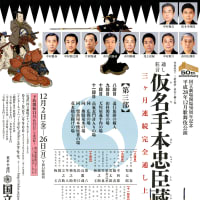19日の夜に中目黒のウディ・シアターで、リチャード・ロジャースとオスカー・ハマースタイン2世のミュージカル「アレグロ」を観る。製作はタチ・ワールドで、勝田安彦の翻訳、訳詞、演出による舞台。ロジャースとハマースタインのミュージカルは、「オクラホマ!」以降「回転木馬」「南太平洋」「王様と私」「サウンド・オブ・ミュージック」など有名な作品が多いが、「アレグロ」は当時としては前衛的過ぎたのか、「偉大なる失敗作」と位置付けられて、近年までほとんど再演されていない作品だ。
僕も、1947年に録音されたオリジナル・キャストの録音を聞いたことがあるが、当時は78回転のSPレコードの時代で、6枚組のアルバムがビクターから出たが、12曲しか収録されていない。「アレグロ」は音楽の比率が高い作品なので、とても12曲では全体像が分からないと評価されていた。そうしたところ、2009年に完全収録を謳った新録音のCD2枚組が発売されたこともあり、再評価が進んだようだ。
長年ブロードウェイでミュージカルの指揮をしていたレーマン・エンゲルは、その著書の中で、1940年の「パル・ジョーイ」以降のヒット作というのは、殆んどが何らかの原作に基づいた作品だと分析している。まあ、その後は「コーラス・ライン」など原作のないオリジナルのヒット作品も出てはいるが、おおむね指摘の通りだと思う。昔は、小説や戯曲が原作だったのに対して、最近は映画を原作とするミュージカルが増えてはいるが、何らかの原作を持っていることが多い。
そうした点で見ると、ロジャースとハマースタインの組んだ作品の中でこの「アレグロ」と「私とジュリエット」は原作を持っておらず、「失敗作品」とされている。だから、あまり、こうした作品には注意を払わないが、実は両作品とも興行的に失敗したというものの記録を見ると300回以上のロングランを記録している。確かにほかの作品のように1000回を超えるようなヒットではないが、300回を超えるならば十分成功作ではないかという気もする。
「アレグロ」の物語は1905年に始まり、1940年頃までが舞台となっている。主人公のジョセフは小さな田舎町の貧乏医師の息子として生まれ、父親の医師が町の人々に尽くす姿を子供の時から見て育ち、自分もその後を継ぎたいと思い、大学では医学を学ぶ。彼は同じ町の裕福な事業家の娘に恋をして結婚する。その娘は美人だが野心家で、1930年代の不況の中で苦労を重ねたこともあり、小さな町ではなく大きな町に出て金持ちを相手にした大病院で稼ぐように彼にすすめる。ジョセフはシカゴの大病院で「アレグロ」のテンポで働き、遂には病院長のオファーを受ける。忙しく働き、社交界とも付き合う中で妻は不倫に走り、金は得られるがやりがいのない生活に嫌気のさしたジョセフは故郷に戻り、父と一緒に街の人々に尽くす決心をする。
一幕が二人の結婚までで、二幕はシカゴ生活の破綻を描くが、全体の構成はなんとなくスティーヴン・ソンドハイムの「ジョージと一緒に日曜日の公園で」に似ている感じがする。この時代にはソンドハイムはハマースタインに面倒を見てもらっていたので、こうした伝統がソンドハイムに引き継がれたのだろうという感じ。
この舞台の特徴は、ギリシャ劇のコロスと呼ばれる「合唱隊」のようなコーラスを舞台上に出演させて、出演者たちの心理を語ったり、補足の物語の展開を助ける歌を歌ったりすることにある。オリジナルの舞台では出演者とコロスは分けられていたが、今回の公演では全部で13人の出演者と一人のピアノ(電子ピアノだが)という編成なので、各役者は主要な役も演じればコロスの役割も果たすという、忙しい舞台となっている。しかし、それが決して違和感なく、見事に演出されていた。
物語を一読すればわかるが、1947年という今から70年も前に作られた作品ではあるが、驚くほど現代的な主題が展開されていて、今見ても全く古びてはいない。有名な役者が出演せず、有名となった曲もないが、よく聞くとどの曲もいかにもロジャースらしい美しさに溢れている。一幕のデュエット「男には女の子が必要」や二幕の看護婦のソロ「紳士連中は食わせ者」は、直前の作品「回転木馬」のムードを彷彿とさせる。
オリジナルの演出・振付は「オクラホマ!」と「回転木馬」で優れたバレエ場面を振り付けたアグネス・デ・ミルで、ダンス・ナンバーも2曲あるが、デ・ミルはどんな振付をしたのだろう。振り付けは映像がないと失われてしまう。今回の舞台では一幕の新入生のダンスが1920年代らしさを出していて工夫の跡が見られた。小さな舞台だが、その後は1930年代の不況の時代となるので、本来ならば衣装は大きく変えたいところだろうが、予算の許す限り精一杯の変化が感じられて、観客にもその心はきちんと伝わったと思う。
一幕終わりの結婚式の場面も「回転木馬」の最後の卒業式を思い起こさせる作り。そうして考えると、「紳士連中は食わせ者」の音楽は「回転木馬」のビリーの独白に似ている。新入生のダンスの音楽も、ロジャースとハートの時代の何かの曲によく似ていると感じたが、なんの曲だったか思い出せない。そのほか、「パル・ジョーイ」の「僕は本を書ける」の曲の一部分のフレーズも使われていた。
田舎の町の何も起こらないごく普通の生活の中に「生きがい」を見出すというテーマは、なんとなくソーントン・ワイルダーの芝居「我等が町」を思い起こさせるものがある。そう思って、wikiの英語版を見たら、オスカー・ハマースタイン2世は「我等が町」を意識していたようだ。
とても良い作品で傑作だと思った。ウディ・シアターは100人程度の客席で、今回は6回公演だから600人ぐらいしか見られない。もったいないので、是非300人ぐらいの劇場で公演してもらえないかなと考えた。
遅くなったので、まっすぐ家に帰り、ムール貝のワイン蒸しと白ワインの食事で済ませた。
僕も、1947年に録音されたオリジナル・キャストの録音を聞いたことがあるが、当時は78回転のSPレコードの時代で、6枚組のアルバムがビクターから出たが、12曲しか収録されていない。「アレグロ」は音楽の比率が高い作品なので、とても12曲では全体像が分からないと評価されていた。そうしたところ、2009年に完全収録を謳った新録音のCD2枚組が発売されたこともあり、再評価が進んだようだ。
長年ブロードウェイでミュージカルの指揮をしていたレーマン・エンゲルは、その著書の中で、1940年の「パル・ジョーイ」以降のヒット作というのは、殆んどが何らかの原作に基づいた作品だと分析している。まあ、その後は「コーラス・ライン」など原作のないオリジナルのヒット作品も出てはいるが、おおむね指摘の通りだと思う。昔は、小説や戯曲が原作だったのに対して、最近は映画を原作とするミュージカルが増えてはいるが、何らかの原作を持っていることが多い。
そうした点で見ると、ロジャースとハマースタインの組んだ作品の中でこの「アレグロ」と「私とジュリエット」は原作を持っておらず、「失敗作品」とされている。だから、あまり、こうした作品には注意を払わないが、実は両作品とも興行的に失敗したというものの記録を見ると300回以上のロングランを記録している。確かにほかの作品のように1000回を超えるようなヒットではないが、300回を超えるならば十分成功作ではないかという気もする。
「アレグロ」の物語は1905年に始まり、1940年頃までが舞台となっている。主人公のジョセフは小さな田舎町の貧乏医師の息子として生まれ、父親の医師が町の人々に尽くす姿を子供の時から見て育ち、自分もその後を継ぎたいと思い、大学では医学を学ぶ。彼は同じ町の裕福な事業家の娘に恋をして結婚する。その娘は美人だが野心家で、1930年代の不況の中で苦労を重ねたこともあり、小さな町ではなく大きな町に出て金持ちを相手にした大病院で稼ぐように彼にすすめる。ジョセフはシカゴの大病院で「アレグロ」のテンポで働き、遂には病院長のオファーを受ける。忙しく働き、社交界とも付き合う中で妻は不倫に走り、金は得られるがやりがいのない生活に嫌気のさしたジョセフは故郷に戻り、父と一緒に街の人々に尽くす決心をする。
一幕が二人の結婚までで、二幕はシカゴ生活の破綻を描くが、全体の構成はなんとなくスティーヴン・ソンドハイムの「ジョージと一緒に日曜日の公園で」に似ている感じがする。この時代にはソンドハイムはハマースタインに面倒を見てもらっていたので、こうした伝統がソンドハイムに引き継がれたのだろうという感じ。
この舞台の特徴は、ギリシャ劇のコロスと呼ばれる「合唱隊」のようなコーラスを舞台上に出演させて、出演者たちの心理を語ったり、補足の物語の展開を助ける歌を歌ったりすることにある。オリジナルの舞台では出演者とコロスは分けられていたが、今回の公演では全部で13人の出演者と一人のピアノ(電子ピアノだが)という編成なので、各役者は主要な役も演じればコロスの役割も果たすという、忙しい舞台となっている。しかし、それが決して違和感なく、見事に演出されていた。
物語を一読すればわかるが、1947年という今から70年も前に作られた作品ではあるが、驚くほど現代的な主題が展開されていて、今見ても全く古びてはいない。有名な役者が出演せず、有名となった曲もないが、よく聞くとどの曲もいかにもロジャースらしい美しさに溢れている。一幕のデュエット「男には女の子が必要」や二幕の看護婦のソロ「紳士連中は食わせ者」は、直前の作品「回転木馬」のムードを彷彿とさせる。
オリジナルの演出・振付は「オクラホマ!」と「回転木馬」で優れたバレエ場面を振り付けたアグネス・デ・ミルで、ダンス・ナンバーも2曲あるが、デ・ミルはどんな振付をしたのだろう。振り付けは映像がないと失われてしまう。今回の舞台では一幕の新入生のダンスが1920年代らしさを出していて工夫の跡が見られた。小さな舞台だが、その後は1930年代の不況の時代となるので、本来ならば衣装は大きく変えたいところだろうが、予算の許す限り精一杯の変化が感じられて、観客にもその心はきちんと伝わったと思う。
一幕終わりの結婚式の場面も「回転木馬」の最後の卒業式を思い起こさせる作り。そうして考えると、「紳士連中は食わせ者」の音楽は「回転木馬」のビリーの独白に似ている。新入生のダンスの音楽も、ロジャースとハートの時代の何かの曲によく似ていると感じたが、なんの曲だったか思い出せない。そのほか、「パル・ジョーイ」の「僕は本を書ける」の曲の一部分のフレーズも使われていた。
田舎の町の何も起こらないごく普通の生活の中に「生きがい」を見出すというテーマは、なんとなくソーントン・ワイルダーの芝居「我等が町」を思い起こさせるものがある。そう思って、wikiの英語版を見たら、オスカー・ハマースタイン2世は「我等が町」を意識していたようだ。
とても良い作品で傑作だと思った。ウディ・シアターは100人程度の客席で、今回は6回公演だから600人ぐらいしか見られない。もったいないので、是非300人ぐらいの劇場で公演してもらえないかなと考えた。
遅くなったので、まっすぐ家に帰り、ムール貝のワイン蒸しと白ワインの食事で済ませた。