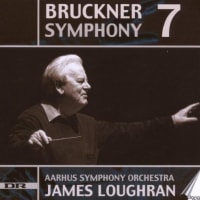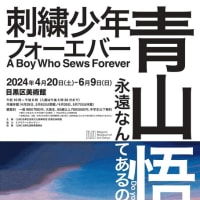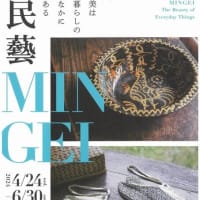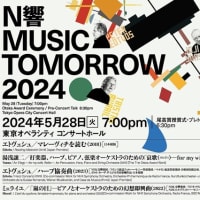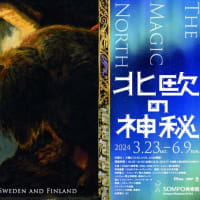宮本輝(1947‐)のデビュー作「泥の河」(初出「文芸展望」1977.7)は、太宰治賞を受賞し、後に映画化された。次作の「螢川」(同「文芸展望」1977.10)は芥川賞を受賞した。続く「道頓堀川」(同「文芸展望」1978.4)は、初出時の版を大幅に加筆して、著者初めての長編小説となった。
それらの3作は「川三部作」と呼ばれている。たぶん華々しい文壇デビューだったろう。だが、当時のわたしは仕事が忙しくて、文学からは遠ざかっていた。その後もこの作家の名前は見聞きしていたが、作品を読むことはなかった。そんなわたしが今頃になって、初めて川三部作を読んだ。抒情的と評されることが多い3作の、みずみずしい感性に触れて、しっとりした余韻に浸った。
「泥の河」は、時は1955年(昭和30年)、所は大阪の安治川(あじかわ)の河畔、主人公は小学2年生(8歳)の板倉信雄。信雄と(ある日突然信雄の前に現れた)同い年の松本喜一との交流が描かれる。続く「螢川」と「道頓堀川」は、時も所も、そして主人公も変わるので、「泥の河」との関連はないが、時と主人公の年齢は「泥の河」からの年月の経過を反映する。
1955年(昭和30年)で8歳という「泥の河」の設定は、宮本輝の年齢と一致する。「螢川」と「道頓堀川」も同様に一致する。3作それぞれに著者がその年齢で見た風景が投影されていると見ていい。そしてその風景は著者より4歳年下のわたしが見た風景とも共通する。3作にはそれぞれの時期の風景が刻印されている。
1955年(昭和30年)当時は、大人には戦争の傷跡が生々しかった。しかし子どもの信雄は(わたしもそうだったが)そんなことは露知らず、明るくのびのび育った。一方、喜一は安治川につながれた小舟で(母と姉とともに)貧しく暮らしている。ガスも電気も水道もない。学校にも行っていない。当時はそんな子どももいただろう。
信雄と喜一が天神祭りに出かける場面がクライマックスだ。信雄の父が二人に小遣いをわたす。喜一は「僕、お金持って遊びに行くのん、初めてや」という。喜一のはしゃぎぶりが痛々しい。ところが喜一はその小遣いを落としてしまう。ズボンのポケットに穴が開いていたのだ。その後の出来事は書かないが、胸がふさぐ。
なにかの象徴のように、川に巨大な鯉が現れる。最初は信雄と喜一が初めて出会ったときに現れる。その晩、高熱を出した信雄は「鯉に乗った少年(引用者注:喜一)が泥の川をのぼっていく」夢を見る。その鯉は信雄と喜一の別れのときにも現れる。川を「悠揚と」泳いでいく。この「悠揚と」という言葉にはネガティブな語感はない。鯉はなにの象徴か。研究者によってさまざまな解釈があるようだが、わたしは喜一の守護神であってくれれば、と思う。
それらの3作は「川三部作」と呼ばれている。たぶん華々しい文壇デビューだったろう。だが、当時のわたしは仕事が忙しくて、文学からは遠ざかっていた。その後もこの作家の名前は見聞きしていたが、作品を読むことはなかった。そんなわたしが今頃になって、初めて川三部作を読んだ。抒情的と評されることが多い3作の、みずみずしい感性に触れて、しっとりした余韻に浸った。
「泥の河」は、時は1955年(昭和30年)、所は大阪の安治川(あじかわ)の河畔、主人公は小学2年生(8歳)の板倉信雄。信雄と(ある日突然信雄の前に現れた)同い年の松本喜一との交流が描かれる。続く「螢川」と「道頓堀川」は、時も所も、そして主人公も変わるので、「泥の河」との関連はないが、時と主人公の年齢は「泥の河」からの年月の経過を反映する。
1955年(昭和30年)で8歳という「泥の河」の設定は、宮本輝の年齢と一致する。「螢川」と「道頓堀川」も同様に一致する。3作それぞれに著者がその年齢で見た風景が投影されていると見ていい。そしてその風景は著者より4歳年下のわたしが見た風景とも共通する。3作にはそれぞれの時期の風景が刻印されている。
1955年(昭和30年)当時は、大人には戦争の傷跡が生々しかった。しかし子どもの信雄は(わたしもそうだったが)そんなことは露知らず、明るくのびのび育った。一方、喜一は安治川につながれた小舟で(母と姉とともに)貧しく暮らしている。ガスも電気も水道もない。学校にも行っていない。当時はそんな子どももいただろう。
信雄と喜一が天神祭りに出かける場面がクライマックスだ。信雄の父が二人に小遣いをわたす。喜一は「僕、お金持って遊びに行くのん、初めてや」という。喜一のはしゃぎぶりが痛々しい。ところが喜一はその小遣いを落としてしまう。ズボンのポケットに穴が開いていたのだ。その後の出来事は書かないが、胸がふさぐ。
なにかの象徴のように、川に巨大な鯉が現れる。最初は信雄と喜一が初めて出会ったときに現れる。その晩、高熱を出した信雄は「鯉に乗った少年(引用者注:喜一)が泥の川をのぼっていく」夢を見る。その鯉は信雄と喜一の別れのときにも現れる。川を「悠揚と」泳いでいく。この「悠揚と」という言葉にはネガティブな語感はない。鯉はなにの象徴か。研究者によってさまざまな解釈があるようだが、わたしは喜一の守護神であってくれれば、と思う。