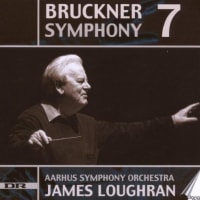友人と続けている読書会の7月のテーマは赤坂真理(1964‐)の「東京プリズン」(2012)だった。わたしは作者も作品も、名前と題名は聞いたことがあるが、それ以上は知らなかった。読むにつれて、「なるほど、こういう小説なのか」と謎解きをする気分だった。そのような未知の作家/作品との出会いが、読書会の楽しみのひとつだ。
驚いたことには、本作のテーマは東京裁判だ。太平洋戦争の敗戦後、連合国によって戦犯が裁かれた東京裁判。あの東京裁判とはなんだったのか。なにが裁かれ、なにが裁かれなかったのか。とりわけ、その裁かれなかったことが、日本の戦後社会にどのような影を落としたのか。それが本作の骨格となるテーマだ。
そのテーマは井上ひさしの戯曲、東京裁判三部作の第三部「夢の痂(かさぶた)」を思い出させた。太平洋戦争の最終責任者(=天皇)の責任を問わないことが(あるいは天皇が責任を取らないことが)、戦後社会にどのようなひずみをもたらしたのか。人々の心の中のなにを封印したのか。そのテーマに思いを巡らした作品が井上ひさしの「夢の痂」であり、赤坂真理の「東京プリズン」だ。
とはいっても、両作品とも理屈っぽい作品ではなく、エンタテインメント性が豊かな作品だ。ストーリーの紹介は省くが、「夢の痂」では思いもよらない展開に驚愕し、浄化された気分になる。一方、「東京プリズン」では(ボロボロになりながらも)なにかを言いきった気分になる。どちらも現実には実現しなかったことだ。実現しなかったことが文学作品の中で実現し、人々のわだかまりが解かれる。
両作品で異なる点は、「東京プリズン」では男性性と女性性というジェンダーの視点が加わることだ。一言でいうと、天皇は戦前~戦中の男性性から、戦後は女性性に移行したという議論が提出される。それは後述する15歳の「私」が、留学先のアメリカの学校で参加するディベートで、相手側から出される議論だ。「私」の意見ではないが、妙に刺激的だ。昨今のジェンダー意識の高まりにかんがみ、この議論はどう捉えるべきか。
本作では2つの時間が並行して進む。前述のように「私」が15歳のときにアメリカの学校に単身留学する1980年10月から翌年4月までの時間と、それから約30年後の「私」が東京で過ごす2009年12月から2011年3月までの時間。それらの2つの時間は、並行して進むだけではなく、互いに浸透し合う。たとえばアメリカにいる15歳の「私」が東京の母にかけた電話を今の「私」が受けたりする。そして今の「私」が、15歳の「私」はなにを求めていたのかと自問する。
そんな「私」の自分探しの物語が、戦後日本の自分探しと重なる点がユニークだ。
驚いたことには、本作のテーマは東京裁判だ。太平洋戦争の敗戦後、連合国によって戦犯が裁かれた東京裁判。あの東京裁判とはなんだったのか。なにが裁かれ、なにが裁かれなかったのか。とりわけ、その裁かれなかったことが、日本の戦後社会にどのような影を落としたのか。それが本作の骨格となるテーマだ。
そのテーマは井上ひさしの戯曲、東京裁判三部作の第三部「夢の痂(かさぶた)」を思い出させた。太平洋戦争の最終責任者(=天皇)の責任を問わないことが(あるいは天皇が責任を取らないことが)、戦後社会にどのようなひずみをもたらしたのか。人々の心の中のなにを封印したのか。そのテーマに思いを巡らした作品が井上ひさしの「夢の痂」であり、赤坂真理の「東京プリズン」だ。
とはいっても、両作品とも理屈っぽい作品ではなく、エンタテインメント性が豊かな作品だ。ストーリーの紹介は省くが、「夢の痂」では思いもよらない展開に驚愕し、浄化された気分になる。一方、「東京プリズン」では(ボロボロになりながらも)なにかを言いきった気分になる。どちらも現実には実現しなかったことだ。実現しなかったことが文学作品の中で実現し、人々のわだかまりが解かれる。
両作品で異なる点は、「東京プリズン」では男性性と女性性というジェンダーの視点が加わることだ。一言でいうと、天皇は戦前~戦中の男性性から、戦後は女性性に移行したという議論が提出される。それは後述する15歳の「私」が、留学先のアメリカの学校で参加するディベートで、相手側から出される議論だ。「私」の意見ではないが、妙に刺激的だ。昨今のジェンダー意識の高まりにかんがみ、この議論はどう捉えるべきか。
本作では2つの時間が並行して進む。前述のように「私」が15歳のときにアメリカの学校に単身留学する1980年10月から翌年4月までの時間と、それから約30年後の「私」が東京で過ごす2009年12月から2011年3月までの時間。それらの2つの時間は、並行して進むだけではなく、互いに浸透し合う。たとえばアメリカにいる15歳の「私」が東京の母にかけた電話を今の「私」が受けたりする。そして今の「私」が、15歳の「私」はなにを求めていたのかと自問する。
そんな「私」の自分探しの物語が、戦後日本の自分探しと重なる点がユニークだ。