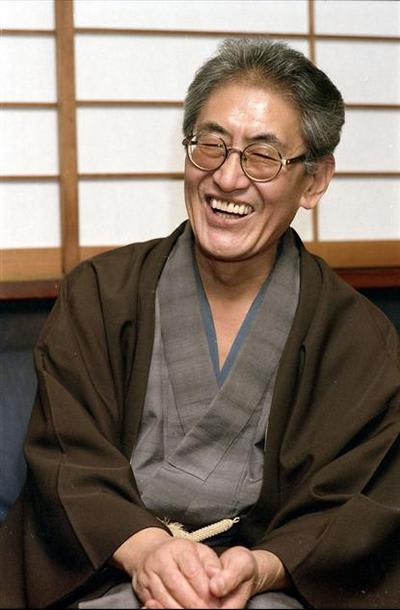関口宏が司会するTBS「サンデーモーニング」に、張本勲がメインのコメンテーターをつとめるスポーツニュースのコーナーがある。「喝っ」「天晴れ!」というやつだ。先週の僅差というか、ほとんど負けていた亀田興毅の防衛戦について、評論家の寺島実郎がこんなことをいっていた。「興業としての評価は別にして、ボクシングとしてはどんなものか。パンチを当てるだけで、切れるようなプロのパンチをまだ見せてもらっていない」と亀田批判である。

不甲斐ない試合に土下座して観客に詫びる亀田興毅
肥えているのにいつもダブルの背広を着ている寺島が、減量がつきものであるボクシングのファンとは意外だった。「21世紀のアジアは大中華圏」を唱えて、「中国のゾルゲ(@オフィス・マツナガ)」と揶揄されるスケールの大きな外交評論に定評ある人だ。肥満体型+着ぶくれファッションという非常識と、「大中華圏構想」という超常識が見合っているように思えるのは困るが、TV局の興業優先を批判したこの発言は、「天晴れ!」に値するものだった。
外交問題といえば、この番組の先週を見のがしてしまったのだが、松井・長嶋のW国民栄誉賞について、張本はどんなコメントをしたのか気になる。松井のおまけに長嶋に与えて、「師弟受賞」とは失礼だし、長嶋に与えるなら、在日韓国人への差別をはね返して、たぶんイチローさえ及ばぬ、3000本安打という前人未踏の大記録を打ち立てた張本が先だろう。
政府内閣の人気とりなら、竹島や慰安婦問題をめぐって、反韓や反在日運動が問題となっているいまこそ、張本に国民栄誉賞を与えるべきだった。在日中国人をルーツとする王貞治に続き張本勲が授賞すれば、どれほど在日社会や国際社会にアピールするか。政治利用の絶好の機会をみずから潰してしまった、前回とあまり変わらぬ安倍政権の政治センスの乏しさには、張本に代わって、「大喝っ」を出したいところだ。
閑話休題、それはさておき、「世界チャンピオンになりながら、まだプロのパンチを見せてもらっていない」という寺島の控えめな亀田批判に、「我が意を得たり」と膝を叩いたのは、北野武の新作「アウトレイジ ビヨンド」を観たからだった。前作「アウトレイジ」に引き続きヒットしたらしいのは慶ばしいのだが、作品としては、捻りすぎた首が戻らず、傾いたまま肩に付いてしまった。いったい、これは映画なのだろうか、とさえ思ったものだ。

寺島のおかげで、亀田興毅と北野武に似ている点が多いことにも気づいた。6度目の防衛を果たした「WBAバンタム級世界チャンピオン」と海外映画祭で数々の受賞歴を誇る「世界の北野」。亀田は大阪西成区、北野は東京足立区の貧困家庭出身。亀田は選手・コーチ未経験である素人の父親の指導でボクシングを学び、北野も漫才のかたわら俳優経験を重ねて独学で監督術を身につけている。二人とも、メディアへの露出は抜群だが、試合や作品に対する安定した評価を得ていない。たんにボクサーや映画監督・お笑い芸人というだけでなく、トリックスター的なキャラクターとして、どちらも人気を博している。
もちろん、ボクサー・亀田興毅、映画監督・北野武、いずれも虚像ではなく、優れた資質を見せたり、よい映画シーンを撮っている。しかし、亀田興毅が海老原博幸や大場政夫と同じ世界チャンピオンか、北野武が今村昌平や深作欣二と同じく映画監督かといえば、どこかなにか違うという気がする。寺島にならい、北野武から、「まだ世界レベルの映画を見せてもらっていない」といえば、すぐさま、カンヌ映画祭をはじめとする輝かしい受賞歴をお前は知らないのかと云われるだろう。だが、それをいえば亀田興毅にしても、31戦30勝(17KO)という圧倒的な戦績を誇り、WBAバンタム級チャンピオンを6度も防衛している。
問題は試合や作品の中味であり、タイトルがすべてではない。観客にとっては、ショットに興奮できるかどうか、それがすべてだろう。私見としては、北野作品のうち、「その男、凶暴につき」以外をさほど優れた作品とは思っていない。この北野武監督デビュー作は、それ以後の作品と異なり、早世した野沢尚が脚本を書いている。これ以外の北野作品は、すべて脚本・北野武となるのだが、実際には脚本はなく、監督北野武の口立てによって俳優にセリフが伝えられている。最新作の「アウトレイジ ビヨンド」も同様である。
深作欣二が監督を降りたおかげで、主演のビートたけしに話題づくりとして監督のお鉢が回ってきた。「その男、凶暴につき」にはそんな経緯があったから、野沢尚脚本だけでなく、カメラや照明、スタッフのほとんどはすでに決まっていて、撮影プランもおおかたできていただろう。少なくとも、いわば中途採用の監督として映画づくりに参加したビートたけしに裁量できる範囲は、きわめて少なかったはずだ。もちろん、ビートたけしにお飾りの監督に甘んじる気はなかった。撮影現場は混乱しただろうが、だからこそ映画としては緊張感に溢れて優れたものになったと思えるのだ。
ほとんどの作品が脚本なしの口立てという映画監督は珍しいはずだが、映画づくりの素人だった北野武が、結局、脚本が書けないがために口立てにしたということはじゅうぶんにあり得る。ならばなぜ、たとえば原案・北野武としてべつに脚本家を立てるとか、あるいは共同脚本にしないのか。「アウトレイジ ビヨンド」では、主演・監督・脚本にくわえ、編集まで自ら手がけている。なぜそこまで、映画のすべてに携わろうとするのか。言い換えるなら、なぜそこまで、すべてが許されるのか。そこらあたりに、映画監督・北野武の「裸の王様」ぶりと、裸と知りつつ気づかないふりを続ける、北野武という空洞がうかがえる気がするのだ。
-この項続く-
(敬称略)

不甲斐ない試合に土下座して観客に詫びる亀田興毅
肥えているのにいつもダブルの背広を着ている寺島が、減量がつきものであるボクシングのファンとは意外だった。「21世紀のアジアは大中華圏」を唱えて、「中国のゾルゲ(@オフィス・マツナガ)」と揶揄されるスケールの大きな外交評論に定評ある人だ。肥満体型+着ぶくれファッションという非常識と、「大中華圏構想」という超常識が見合っているように思えるのは困るが、TV局の興業優先を批判したこの発言は、「天晴れ!」に値するものだった。
外交問題といえば、この番組の先週を見のがしてしまったのだが、松井・長嶋のW国民栄誉賞について、張本はどんなコメントをしたのか気になる。松井のおまけに長嶋に与えて、「師弟受賞」とは失礼だし、長嶋に与えるなら、在日韓国人への差別をはね返して、たぶんイチローさえ及ばぬ、3000本安打という前人未踏の大記録を打ち立てた張本が先だろう。
政府内閣の人気とりなら、竹島や慰安婦問題をめぐって、反韓や反在日運動が問題となっているいまこそ、張本に国民栄誉賞を与えるべきだった。在日中国人をルーツとする王貞治に続き張本勲が授賞すれば、どれほど在日社会や国際社会にアピールするか。政治利用の絶好の機会をみずから潰してしまった、前回とあまり変わらぬ安倍政権の政治センスの乏しさには、張本に代わって、「大喝っ」を出したいところだ。
閑話休題、それはさておき、「世界チャンピオンになりながら、まだプロのパンチを見せてもらっていない」という寺島の控えめな亀田批判に、「我が意を得たり」と膝を叩いたのは、北野武の新作「アウトレイジ ビヨンド」を観たからだった。前作「アウトレイジ」に引き続きヒットしたらしいのは慶ばしいのだが、作品としては、捻りすぎた首が戻らず、傾いたまま肩に付いてしまった。いったい、これは映画なのだろうか、とさえ思ったものだ。

寺島のおかげで、亀田興毅と北野武に似ている点が多いことにも気づいた。6度目の防衛を果たした「WBAバンタム級世界チャンピオン」と海外映画祭で数々の受賞歴を誇る「世界の北野」。亀田は大阪西成区、北野は東京足立区の貧困家庭出身。亀田は選手・コーチ未経験である素人の父親の指導でボクシングを学び、北野も漫才のかたわら俳優経験を重ねて独学で監督術を身につけている。二人とも、メディアへの露出は抜群だが、試合や作品に対する安定した評価を得ていない。たんにボクサーや映画監督・お笑い芸人というだけでなく、トリックスター的なキャラクターとして、どちらも人気を博している。
もちろん、ボクサー・亀田興毅、映画監督・北野武、いずれも虚像ではなく、優れた資質を見せたり、よい映画シーンを撮っている。しかし、亀田興毅が海老原博幸や大場政夫と同じ世界チャンピオンか、北野武が今村昌平や深作欣二と同じく映画監督かといえば、どこかなにか違うという気がする。寺島にならい、北野武から、「まだ世界レベルの映画を見せてもらっていない」といえば、すぐさま、カンヌ映画祭をはじめとする輝かしい受賞歴をお前は知らないのかと云われるだろう。だが、それをいえば亀田興毅にしても、31戦30勝(17KO)という圧倒的な戦績を誇り、WBAバンタム級チャンピオンを6度も防衛している。
問題は試合や作品の中味であり、タイトルがすべてではない。観客にとっては、ショットに興奮できるかどうか、それがすべてだろう。私見としては、北野作品のうち、「その男、凶暴につき」以外をさほど優れた作品とは思っていない。この北野武監督デビュー作は、それ以後の作品と異なり、早世した野沢尚が脚本を書いている。これ以外の北野作品は、すべて脚本・北野武となるのだが、実際には脚本はなく、監督北野武の口立てによって俳優にセリフが伝えられている。最新作の「アウトレイジ ビヨンド」も同様である。
深作欣二が監督を降りたおかげで、主演のビートたけしに話題づくりとして監督のお鉢が回ってきた。「その男、凶暴につき」にはそんな経緯があったから、野沢尚脚本だけでなく、カメラや照明、スタッフのほとんどはすでに決まっていて、撮影プランもおおかたできていただろう。少なくとも、いわば中途採用の監督として映画づくりに参加したビートたけしに裁量できる範囲は、きわめて少なかったはずだ。もちろん、ビートたけしにお飾りの監督に甘んじる気はなかった。撮影現場は混乱しただろうが、だからこそ映画としては緊張感に溢れて優れたものになったと思えるのだ。
ほとんどの作品が脚本なしの口立てという映画監督は珍しいはずだが、映画づくりの素人だった北野武が、結局、脚本が書けないがために口立てにしたということはじゅうぶんにあり得る。ならばなぜ、たとえば原案・北野武としてべつに脚本家を立てるとか、あるいは共同脚本にしないのか。「アウトレイジ ビヨンド」では、主演・監督・脚本にくわえ、編集まで自ら手がけている。なぜそこまで、映画のすべてに携わろうとするのか。言い換えるなら、なぜそこまで、すべてが許されるのか。そこらあたりに、映画監督・北野武の「裸の王様」ぶりと、裸と知りつつ気づかないふりを続ける、北野武という空洞がうかがえる気がするのだ。
-この項続く-
(敬称略)