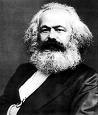日曜日の朝日新聞の「読書」で紹介されていて、読みたくなった。
「それでも、日本人は『戦争』を選んだ」(加藤陽子 朝日出版社)
http://book.asahi.com/news/TKY200908060189.html

「立ち読みページ」というのもあるのか。はじめて知った。
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refISBN=9784255004853
神奈川県鎌倉市に栄光学園という県下屈指の受験エリート校がある。カトリック修道会イエズス会系の中高一貫私立校で、かの養老孟司の出身校である。その歴史研究部の中高生に、気鋭の東大教授が日清日露戦争から太平洋戦争まで、日本の近現代史を講義した。
「歴研」といっても、昔のような唯物史観の学習サークルではないだろうが、生意気盛りの歴史好き中高生たちを瞠目させた講義とはどんなものか。もちろん、岩波歴史講座のような左翼めいたものではなく、いわゆる自由主義史観でもないはずだ。
この本を紹介した小柳学という編集者は、歴史に埋もれた人物に輝きを与えることで現場の空気を伝える、司馬遼太郎の歴史小説を読んだときの感覚に近い、と語っている。
加藤陽子という歴史学者は知らなかったが、最新の近現代史研究の成果を啓いているそうで、中高生向けの語り口ながら、むしろ、これといった歴史観を持てない、あるいはいつまでも歴史観の定まらない大人向きだろう。
講義だから、当然、生徒との間に質疑応答がある。生徒の質問に先生が答えるというより、先生が、「あなたが日本の首相だったらどうする?」「中国の立場だったらどうする?」と問いを投げかけながら講義を進めたようだ。
たぶん、私たち大人の答えは、生徒のそれ以下ではあっても、以上を出せることは少ないだろう、と想像する。
日清戦争が起きた1894年(明治27年)に、松下電器を創業した松下幸之助は生まれ、バブル経済崩壊後の1989年(平成元年)に亡くなっている。つまり、明治生まれの人々が戦前をつくり、戦後をつくった。ついこの間まで、明治人の時代が続いていたともいえる。
「分権化」「民営化」「知識労働者」「非営利企業」など、先駆的なアイディアを提起し続け、企業人の間では、松下幸之助以上に人気が高い経営学者のピーター・ドラッカーも、1909年(明治42年)にウィーンに生まれ、ナチス勃興のドイツから逃れるように出国し、やがてアメリカへ移住、GMの再建などを手がけ、経営マネジメントに大きな影響力を持ち続けて、2005年(平成17年)に没している。
彼ら明治人にとって、近現代史とは同時代史として自明のことであったから、その輝かしい成功にしろ亡国の瀬戸際までいった失敗にしろ、あまり多くを語らなかったように思う。彼らにとっては、自分たちが為すべき仕事ははっきりしていたから、あらためて語る必要はなく、ただ、為すべき仕事に懸命に取り組んだ。私たち後継世代も、積極的に聞く耳を持たなかったと思う。
戦前と戦後を分かたず、近現代史として通史を学ぶには、私たち大人の歴史認識は雑駁かつ手垢にまみれている。団塊の世代はすでに老年期に入ったが、昭和の大人たちは、結局、近現代史の何をも知らないのである。
だから、「属国史観」や「自由主義史観」などに、トリビアリズムの虚仮脅かしに過ぎないものにも、おろおろしてしまう。そのくせ、祖父母や父母に聞こうともしてこなかった。恥ずかしながら、私もそうですがね。
もしかすると「戦前」を経験しているのかもしれない、平成生まれの中高生たちが、司馬遼太郎の歴史小説のように生気あふれる歴史講義を受けているのなら、とても羨ましい気がする。また、本で読むより、講義の熱弁に接するほうが、圧倒的に得るものは大きいはずだ。
彼らの多くは、たぶん、学者にも作家にもならず、自らの教養と見識について多くを語らぬまま、専門職や公務員として、市井に生きていくことだろう。幼い頃から豊かな文化資本を享受した者は、文化を語る必要はなく、ただ味わうことで満足する。
松下電器を起業した松下幸之助は、やがて軍需産業に携わり、戦後は進駐軍からパージを受ける。そして、朝鮮戦争後から高度成長期を迎えた日本は、「三種の神器」の消費ブームを経て、家電業界は飛躍的な発展を遂げ、松下幸之助が唱えた「水道哲学」は実現したかのように思えた。
科学文明を渇仰し、豊かな消費文化を求めた、幸之助のような明治人たちの末裔が私たちである。したがって、もしかすると昭和という時代はなかったのかもしれず、昭和という時代に文化はなかったとも思える。私たちの文化資本とは、せいぜいが消費文化の一分野としてのマンガやアニメくらいに過ぎない。
結局、明治人たちは、私たちは、「戦争」を選んだのだ。先の大戦への悔恨は、明治人たちが亡くなるにつれて、日々薄れていった。それから幾たびも、戦争は起きた。日本以外でだが。しかし、日本でも、「いまや、我々の希望は戦争だけである」と直言する若者も出ている。戦争を待望するほどの彼らの閉塞感を批判することはできない。
戦争を回避する、柔らかな知性と教養は、学ぶというより身につくものだと思う。もちろん、そんな人はごくごく少数だろう。しかし、その人たちの在りかたが、静かに流れる水のように、人々の足下を浸して、わずかずつであってもたしかな影響を及ぼしていくと思う。
豊かな文化資本を享受した平成の中高生たちが、「それでも、日本人は『戦争』を選ばなかった」時代をつくってくれたら、と願う。戦争は全員ではじめるものだが、戦争を止めようとするのは、いつの時代もごく一部の人たちだろう。戦争に反対する戦争(闘争)の以前に、黙って平和の価値を提示できる人たちだ。
戦争に平和を対置するのではなく、戦争に向かう平和を、向かわない平和に変えていく歩みを、日々実践する人たちだ。温かな笑顔で挨拶するように。老人に座席を譲るように。公園のゴミに気づいて拾うように。歴史にはけっして記されることのないこのような人たちは、自分だけが読む自分史を持つ人たちだ。
つまり、私のようにブログなどは持たない人だな。お後がよろしいようで。
(敬称略)
「それでも、日本人は『戦争』を選んだ」(加藤陽子 朝日出版社)
http://book.asahi.com/news/TKY200908060189.html

「立ち読みページ」というのもあるのか。はじめて知った。
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refISBN=9784255004853
神奈川県鎌倉市に栄光学園という県下屈指の受験エリート校がある。カトリック修道会イエズス会系の中高一貫私立校で、かの養老孟司の出身校である。その歴史研究部の中高生に、気鋭の東大教授が日清日露戦争から太平洋戦争まで、日本の近現代史を講義した。
「歴研」といっても、昔のような唯物史観の学習サークルではないだろうが、生意気盛りの歴史好き中高生たちを瞠目させた講義とはどんなものか。もちろん、岩波歴史講座のような左翼めいたものではなく、いわゆる自由主義史観でもないはずだ。
この本を紹介した小柳学という編集者は、歴史に埋もれた人物に輝きを与えることで現場の空気を伝える、司馬遼太郎の歴史小説を読んだときの感覚に近い、と語っている。
加藤陽子という歴史学者は知らなかったが、最新の近現代史研究の成果を啓いているそうで、中高生向けの語り口ながら、むしろ、これといった歴史観を持てない、あるいはいつまでも歴史観の定まらない大人向きだろう。
講義だから、当然、生徒との間に質疑応答がある。生徒の質問に先生が答えるというより、先生が、「あなたが日本の首相だったらどうする?」「中国の立場だったらどうする?」と問いを投げかけながら講義を進めたようだ。
たぶん、私たち大人の答えは、生徒のそれ以下ではあっても、以上を出せることは少ないだろう、と想像する。
日清戦争が起きた1894年(明治27年)に、松下電器を創業した松下幸之助は生まれ、バブル経済崩壊後の1989年(平成元年)に亡くなっている。つまり、明治生まれの人々が戦前をつくり、戦後をつくった。ついこの間まで、明治人の時代が続いていたともいえる。
「分権化」「民営化」「知識労働者」「非営利企業」など、先駆的なアイディアを提起し続け、企業人の間では、松下幸之助以上に人気が高い経営学者のピーター・ドラッカーも、1909年(明治42年)にウィーンに生まれ、ナチス勃興のドイツから逃れるように出国し、やがてアメリカへ移住、GMの再建などを手がけ、経営マネジメントに大きな影響力を持ち続けて、2005年(平成17年)に没している。
彼ら明治人にとって、近現代史とは同時代史として自明のことであったから、その輝かしい成功にしろ亡国の瀬戸際までいった失敗にしろ、あまり多くを語らなかったように思う。彼らにとっては、自分たちが為すべき仕事ははっきりしていたから、あらためて語る必要はなく、ただ、為すべき仕事に懸命に取り組んだ。私たち後継世代も、積極的に聞く耳を持たなかったと思う。
戦前と戦後を分かたず、近現代史として通史を学ぶには、私たち大人の歴史認識は雑駁かつ手垢にまみれている。団塊の世代はすでに老年期に入ったが、昭和の大人たちは、結局、近現代史の何をも知らないのである。
だから、「属国史観」や「自由主義史観」などに、トリビアリズムの虚仮脅かしに過ぎないものにも、おろおろしてしまう。そのくせ、祖父母や父母に聞こうともしてこなかった。恥ずかしながら、私もそうですがね。
もしかすると「戦前」を経験しているのかもしれない、平成生まれの中高生たちが、司馬遼太郎の歴史小説のように生気あふれる歴史講義を受けているのなら、とても羨ましい気がする。また、本で読むより、講義の熱弁に接するほうが、圧倒的に得るものは大きいはずだ。
彼らの多くは、たぶん、学者にも作家にもならず、自らの教養と見識について多くを語らぬまま、専門職や公務員として、市井に生きていくことだろう。幼い頃から豊かな文化資本を享受した者は、文化を語る必要はなく、ただ味わうことで満足する。
松下電器を起業した松下幸之助は、やがて軍需産業に携わり、戦後は進駐軍からパージを受ける。そして、朝鮮戦争後から高度成長期を迎えた日本は、「三種の神器」の消費ブームを経て、家電業界は飛躍的な発展を遂げ、松下幸之助が唱えた「水道哲学」は実現したかのように思えた。
科学文明を渇仰し、豊かな消費文化を求めた、幸之助のような明治人たちの末裔が私たちである。したがって、もしかすると昭和という時代はなかったのかもしれず、昭和という時代に文化はなかったとも思える。私たちの文化資本とは、せいぜいが消費文化の一分野としてのマンガやアニメくらいに過ぎない。
結局、明治人たちは、私たちは、「戦争」を選んだのだ。先の大戦への悔恨は、明治人たちが亡くなるにつれて、日々薄れていった。それから幾たびも、戦争は起きた。日本以外でだが。しかし、日本でも、「いまや、我々の希望は戦争だけである」と直言する若者も出ている。戦争を待望するほどの彼らの閉塞感を批判することはできない。
戦争を回避する、柔らかな知性と教養は、学ぶというより身につくものだと思う。もちろん、そんな人はごくごく少数だろう。しかし、その人たちの在りかたが、静かに流れる水のように、人々の足下を浸して、わずかずつであってもたしかな影響を及ぼしていくと思う。
豊かな文化資本を享受した平成の中高生たちが、「それでも、日本人は『戦争』を選ばなかった」時代をつくってくれたら、と願う。戦争は全員ではじめるものだが、戦争を止めようとするのは、いつの時代もごく一部の人たちだろう。戦争に反対する戦争(闘争)の以前に、黙って平和の価値を提示できる人たちだ。
戦争に平和を対置するのではなく、戦争に向かう平和を、向かわない平和に変えていく歩みを、日々実践する人たちだ。温かな笑顔で挨拶するように。老人に座席を譲るように。公園のゴミに気づいて拾うように。歴史にはけっして記されることのないこのような人たちは、自分だけが読む自分史を持つ人たちだ。
つまり、私のようにブログなどは持たない人だな。お後がよろしいようで。
(敬称略)