
「目白雑録(ひびのあれこれ)」の金井美恵子が、文芸評論家のなかでは唯一といってよいくらい評価していたので、文庫本の新刊コーナーに積んであったのを手にとってみた。
『反=日本語論』(蓮實 重彦 ちくま学芸文庫)
例によって、担当編集者による表紙カバーの紹介文を読んでみる。変な書き方だなと思う。それで読んでみたくなった。どこが変なのか、当ててみてください。
フランス文学者の著者、フランス語を母国語とする
夫人、日仏両国語で育つ令息。そして三人が出会う言
語的摩擦と葛藤のかずかず。著者はそこに、西欧と
日本との比較文明論や、適度な均衡点などを見出そう
するのではない。言葉とともに生きることの息苦しさと
苛立ちに対峙し、言語学理論を援用しつつ、神遠なる
言葉の限界領域に直接的な眼差しを向ける。それは、
「正しく美しい日本語」といった抽象的虚構を追い求める
従来の「日本語論」に対して、根源的な異議申し立てを行う
ことでもある。
解説 シャンタル蓮實
まず、「夫人」「令息」にひっかかるはず。「妻」「息子」と書くのがふつう。編集者が著者に恐縮遠慮している。次に気づくのが、わずか10行の紹介文のほとんどが否定によって埋められている。
西欧と日本との比較文明論や、適度な均衡点などを見出そうする、従来の「日本語論」
が、「根源的」に否定されている。その否定の発端は、日仏語がとびかう蓮實家の「言語的摩擦と葛藤のかずかず」であり、その依拠するところは、「言葉とともに生きることの息苦しさと苛立ち」であり、その根拠は、「言語学理論を援用しつつ」、言葉に「直接的な眼差しを向ける」ことだ。
しかし、「神遠なる言葉の限界領域」とは、持ち上げたものだ。そんな編集者の畏怖が伝わってくるから、「蓮實重彦ってのは、いったい何様なのか」という反発が起きるのはしかたがない。だが、本書を一読すると、たしかにこの紹介文のとおりの内容に間違いない。編集者が真似したか、影響されたか、否定を重ねる書き方も同じ。ぎくしゃくして、とても巧みとはいえない紹介文だが、よく内容を表しているといえる。蓮實重彦が何様扱いされているのを知るおまけ付きだから、じゅうぶん以上かもしれない。
それほど難しい本ではない。フランス人の、それもインテリの嫁さんを持つとどんなに苦労するか、日仏ハーフの息子の教育にどれほど頭を悩ますか、そういう覗き見的な興味もそれなりに満たされる。夫人の解説を読むと、シャンタル夫人とフランス語で対話するとき、蓮實は夫人の顔を見ず、「やや瞳を伏せ、身を傾ける」姿勢をするそうで、夫人はそれを「聞く視線」と呼んでいる。そんな夫や父のほろ苦いエッセイとしても読める。もちろん、そんな読み方は本書中で繰り返し否定されているのだが。
さて、帰納的に否定を重ねながら、演繹的に「言葉に直接的な眼差し」を提出しようとする、蓮實重彦の文芸の力については、次回のお楽しみ。印象としては、マッチョではなくタフネス。執拗なほど繰り返し変奏していくなかで、主題を次第に顕わしていく、その「日本人離れした」タフな文章に、たぶん編集者は圧倒されたのだろう。
たとえば、次回の例文に取りあげようと思っている「シルバーシートの青い鳥」でいうと、40字17行23頁という長文のなかで、「民主主義において、多数決はとるにたりない脇役に過ぎない」という蓮實の考察は、中盤のほんの枝葉に過ぎない。たしかに、西欧と日本の民主主義の比較に止まらない。均衡など測らない。そこから、いくつもの通説や妥当と思える考察が、痛快に否定されていく。
それは同時に、「外人離れした」、一日本人としての思考と葛藤が積み重ねられていく姿でもある。つまり、妻や息子や家庭生活を描いて見せたからエッセイなのではなく、自分という個の思想を語ろうとすることにおいて、エッセイなのだろうと本書を読んで気づかされた。家族と自分の関係性の生々しい叙述を避けたのは、それが下品だということでもなく、家族が読むだろうことを想定して控えたのでもなく、個の思想を語らんがためだと思えた(いやはや、俺もさっそく影響されて否定を重ねているよ)。
つまり、思想エッセイということです。どこかの誰かの借りもの思想ではなく、自分の思想について語っている。その困難さを考えるとき、シャンタル夫人と対話するときの蓮實を思い出す。身をはすにして瞳を伏せ、フランス語に聴き入るその姿を。そんな日本の一知識人の肖像という読後感もある。やっぱり難しげになってしまったが、蓮實がこの本を書いたのは、1970年代の40歳に満たないときだ。けっして若くはなく、若書きではまったくないが、家族との関係性についても、まだ初々しい感性と視線がうかがわれる。
次回の予告として、こんなクイズを。
「ローマ帝国の将軍といえば・・・」
「シーザー!」
「そう、シーザーですが、そのときのエジプトの女王といえば・・・」
「クレオパトラ!」
「はい、ではハリウッドでクレオパトラを演じた女優といえば・・・」
「エリザベス・テーラー!」
「ですが、相手役のアントニーを演じた・・・」
「リチャード・バートン!」
「ですが、なぜリチャード・バートンはシーザー役ではなかったのでしょうか?」
「・・・」
これらの質問がすべて、否定で続けられると思ってください。おもしろそうでしょ。
(敬称略)

読了。期待を裏切らぬ上質のリーダビリティ。『鴨川ホルモー』『鹿男あをによし』『プリンセス・トヨトミ』に続き、この最新作『偉大なるしゅららぼん』も、傑作といってよいおもしろさ。これは尋常なことではない。
なぜ、万城目学はおもしろいのか。いま考え中。これまで読んだどの小説や作家とも似ていない。共通点が見当たらない。上等な映画を観た後に、ストーリーや画面ではなく、俳優が、その役柄が強く印象に残るように、万城目小説ではその登場人物が際立っている。
といっても、登場人物に共感できる、感情移入する、というのではない。「いるいる」「そうそう」「こんな人知ってる」とは逆に、身近にはとてもいそうもない人物ばかり。
ヘタレの王道・日出涼介はともかく、ナチュラルボーン殿様・日出淡十郎、トール&ハンサムリア充・棗広海、グラマーというよりフィジカル絵画女子・速瀬、白馬に跨るグレート清コングこと・日出清子、いつも城内を忙しげなパタパタ走者・パタ子さん、渡し舟からクルーザーまで運転する源爺。
なかでも秀逸なのは、日出家の次の当主にして、誂えの赤い学生服を着て通学するデブの淡十郎であることは誰でも肯くだろう。かつての岩走城に源爺や料理人など大勢の使用人にかしづかれて暮らす「殿様」として、底知れぬ度量を秘めながら、恋をしたパンダのような愛らしい一面を晒らけ出す。
万城目小説はいつも女優陣が魅力的だ。背高く肩幅広い立派な体格なのに、聴きとり難いほど声が小さく、しかしてきぱきとした物言いで、絵の才能もある速瀬。傲岸不遜にして口調辛辣な日本最強のひきこもり清子。いつも呑気な天然師匠の濤子ことパタ子さん。こんな女性がいたら、どれほど世界が笑顔で満たされるかと、あたかも天女や観音様の眼福に与れるかのようだ。
それにひきかえ、涼介のライバルにして、絵に描いたようなモテ男の棗広海の存在感が薄く、物足りない。終盤にさしかかっても、これといった活躍もなくあきらめかけていると、これが南斗聖拳! 颯爽と白馬の騎士となって琵琶湖を駆け抜け、煙のごとく忽然と姿を消したかに見えて実は、という大逆転には、「しゅららぼん」の謎解きとともに、唸らされた。
もう、残頁が5mmくらい、もうすぐ終わりかなと、「サザエさん症候群」みたいな寂寥感が降りてきてから、急展開するのだ。日出涼介は「しゅららぼん」を野球の投球に擬するが、バッターボックス手前から加速して、グンとホップしてくる感じ。たいていはのけぞって見送りだろう。最後の3行の見事さ。
先日、人がくれた週刊文春(6/23号)をめくっていたら、万城目学の連載小説「とっぴんぱらりの風太郎」の第1回が掲載されていた。初の時代小説のせいか、リーダビリティは前4作に比べ、少しもたつく気がする。しかし、また違った万城目小説を読ませてくれるのかもしれない。そのときは、「同時代に巡り会えた幸福」という最大級の賛辞を捧げたい。
(敬称略)

いま、万城目学原作の映画「プリンセストヨトミ」が公開中だが、書店を覗いてみたら新作が出ていた。奥付をみたら、4月30日第一刷、5月30日で3刷りしている。相変わらず、売れているようだ。
『偉大なるしゅららぼん』(集英社 1,700円)
例によって帯文の紹介
この力は、
何なのだ?
「鴨川ホルモー」「プリンセス・トヨトミ」の天才、
最新作にして、
大大大傑作!!!
琵琶湖畔の街・石走(いわばしり)に代々住み続ける日出(ひので)家と棗(なつめ)家。両家には受け継がれてきた特別な「力」があった。石走高校に入学した日出涼介、日出淡十郎、棗広海が偶然同じクラスになったとき、力で力を洗う戦いの幕が上がった---!
おいおい、「鹿男あをによし」を忘れちゃ困る。まだ4作しか小説書いていないんだから。当ブログでも、「プリンセス・トヨトミ」を紹介したことがあるが、ほんとうに、「次作が代表作」といえるほど、一作ごとにより大きな満足感を与えてくれる傑作ぞろい。
意味不明なタイトル「しゅららぼん」、帯文に謎めく「力で力を洗う戦い」、やはり、万城目学らしい結構が楽しめそうだ。今度の舞台は滋賀か。次のお休みまでとっておいて、ゆっくり読も。
(敬称略)

容赦のない文章を書く人は誰かといえば、そりゃ、小谷野敦です。本名かどうかは知らないが、こやの あつし ではなく、こやの とん と読ませるところからして、ただ者ではない
(小谷野敦なら、本名ならどうするんだと突っ込むだろうが)。恋愛至上(市場)主義を批判した『もてない男』など、この人以外に書けそうもない名著である。つまり、他者にはもちろん、自分にも容赦ない人が、脳天気な「日本人論」を許容するわけがなかったという本が、『日本文化論のインチキ』(幻冬舎新書)。裏表紙の紹介文は以下です。
「日本語は曖昧で非論理的」「日本人は無宗教」「罪ではなく恥の文化」……わが民族の独自性を説いたいわゆる日本文化論本は、何年かに一度「名著」が出現し、時としてベストセラーとなる。著者はある時、それらの学問的にデタラメな構造を発見した。
要は①比較対象が西洋だけ、②対象となる日本人は常にエリート、③歴史的変遷を一切無視している、のだ---。国内外の日本論に通じる著者が『武士道』に始まる一〇〇冊余を一挙紹介、かつ真偽を一刀両断。有名なウソの言説のネタ本はこれだ!
表紙カバーの紹介文は、担当編集者が書くのが通例だが、もしかすると、小谷野自身が書いているのかもしれない。小谷野本を読みはじめると、誰でもすぐに、「自意識過剰」という言葉を思い浮かべるはずだが、やがて、その自意識はかなりふてぶてしいことに気づくことになる。帯には、名著の誉れ高い「日本人論」の「ウソの言説」を並べている。
*「甘え」という語は西洋語にはないから日本人特有の感情だ。『「甘え」の構造』土居健郎
*日本人は裸体を気にしない『逝きし世の面影』渡辺京二
*日本は処女の純潔を重んじない『ヨーロッパ文化と日本文化』ルイス・フロイス
*日本の文藝に描かれた恋は、藝者相手迷いのようなものしかない『東の国から』ラフカディオ・ハーン
*日本人の祖先は宝貝を求めて南方から移住してきた『海上の道』柳田國男
*黒船に無理矢理開国させられた日本人は以後トラウマを引きずり、米国に愛憎入り交じった感情を抱くようになった『ものぐさ精神分析』岸田秀
*ユダヤーキリスト教文化は父性的、日本は母性的。『母性社会日本の病理』河井隼雄
このほかにも、李御寧の『「縮み」志向の日本人』やヘーゲルの「歴史哲学」、フロイトやラカン、司馬遼太郎などなど、洋の東西古今を問わず、学問と誤解されているが非学問的なエッセイや世間話に過ぎないと言い放ち、たとえ学問的ではあっても今日では一顧だにされない旧説と切り捨てる、その太刀さばきが痛快この上ない。政治と教育と映画と日本人論は、誰でも何か書けるものだが、小谷野のような人に典拠を示せといわれれば、裸足で逃げ出す他はない。小谷野敦、最強じゃないか。こちらが最弱なのかもしれないが。
(敬称略)
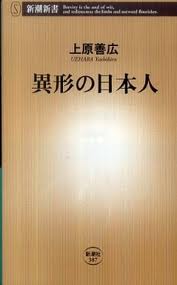
岩波新書から出すには、アカデミックなアプローチに欠け、朝日新書から出すには、ジャーナリスティックな煽情性に足りず、文春新書から出すには、被差別部落出身ライターにしては暴露性に物足りず、ちくま新書から出すには、気楽なサブカルには及ばず、光文社新書や幻冬舎新書は売れないだろうと踏み、たまたま、新潮新書の編集者に物好きな知り合いがいた。かどうかはわからないが、上原善広の新潮新書2冊目。
『異形の日本人』(上原 善広 新潮新書)
当ブログでは、2008/11/13に、『被差別の食卓』(上原 善広 新潮新書)を紹介している。
表紙カバーの紹介文は以下。
虐げられても、貧しくとも、偏見に屈せず、たくましく生きた人たちがいた。哀しい宿命のターザン姉妹、解放同盟に徹底的に糾弾された漫画家、パチプロで生活しながら唯我独尊を貫く元日本代表アスリート、難病を患いながらもワイセツ裁判を戦った女性、媚態と過激な技で勝負する孤独なストリッパー……。社会はなぜ彼らを排除したがるのか? マスメディアが伝えようとしない日本人の生涯を、大宅賞作家が鮮烈に描く。
新潮新書の物好き編集者は、あまり文章が上手くないし、文章を書くのが好きではないようだ。「虐げられても、貧しくとも、偏見に屈せず、たくましく生きた人たちがいた」とは、そのとおりなのだが、そのとおり過ぎるだろう。また、困ったことに要約が、少しあるいはかなり内容とずれている。「社会はなぜ彼らを排除したがるのか?」というが、社会の側の視点には、ほとんど触れられていない。当事者に取材したルポだからあたりまえなのだが、「社会人」の贖罪意識を刺激しようという惹句はいただけない。たぶん、『被差別の食卓』は売れなかっただろうから、大宅ノンフィクション賞受賞後第一作で売りたかった気持ちはわかるのだが。
目次
はじめに
各分野におけるマイノリティ、「異端」とされてきた人たちを取り上げてきた。そうした人々の物語や、一種タブーとされてきた出来事の中にこそ、日本人の本質的な何かが隠されているのではないかと思ったからだ。
彼らの本当の声が、テレビなどの大手メディアで報道されることは決してない。(帯に抜粋された文)
37歳(1973年生まれ)と若いわりには、1970年代に若いライターが書いたように生硬。「隠された本質的な何か」「彼らの本当の声」など、「本質」や「本当」が直感的に認識できるかのような純朴さも似かよっている。
「テレビなどの大手メディアで報道されることは決してない」という、いまさらなマスコミ批判も、かつてなら、大手メディアに登壇したいという上昇指向か、その補完物に過ぎないのではという苦さを隠したものであったがために、少なくとも書き手のリアリティには裏づけられていた。
ところが、この著者が採用するのは、「彼らの本当の声に隠された本質的な何か」を問うなかで、「忘れられた日本人」のよすがを辿る、民俗学的なフィールドワークらしい。路地(被差別部落)をテーマに大宅ノンフィクション賞を受賞したが、もう少し広い野原(フィールド)に出るために、これまでの主題と方法論を突破したいと悩んでいるらしい。
本書の登場人物たちを「忘れられた日本人」にまとめるには、かなり無理がある。それぞれの雑誌に寄稿した文章を集めただけなのに、なんとか作家性を貫いたように見せたい苦しまぎれとしか読めない。この著者のルポには、時代錯誤な味わいがあるのに、編集者が沢木耕太郎のように売り出したいという時代錯誤を犯しては、贔屓の引き倒しになるだろう。
「はじめに」はなくてよかった。それぞれのルポは、じゅうぶんに読みがいのあるものばかりだったので、惜しい気がする。
第一章 異形の系譜-禁忌のターザン姉妹
半裸の姉妹 鹿児島の村 東大の研究と皇室
生家を見に行く 侏儒どんと姉妹の墓 姉妹との邂逅
昭和27年の新聞記事に発見した、ほとんど言葉を解さず、野生の猿のように生きた「障碍者」姉妹を追ったルポ。「人権に配慮して」、中途で取材を止めたことに疑問は残るが、取材に振り回されない姿勢には、好感が持てた。
第二章 封印された漫画-平田弘史『血だるま剣法』事件
封印された漫画 被差別を描く 解放同盟の糾弾と改作
休筆の果てに 差別は悪くない
平田弘史ファンなら知る有名な事件だが、平田弘史の苦悩がかいま見え、解放同盟側をここまで書いたのははじめてだろうと、新鮮に読めた。もっと、その後の「自主規制」や「自粛」につながる差別的な「言論弾圧」構造に迫ってほしかった。
第三章 溝口のやり-最後の無頼派アスリート
アジア記録をもつ男 奇抜な思考と奇異な投擲術
精神と肉体 原動力は悔しさ アスリートの過去
溝口伝説 決定的な敗北 再び世界へ 世界新記録
壊れた肩 パチプロへの転身 室伏広治への指南
アスリート無頼 燃えつきた男
「やりの溝口」はまったく知らなかった。優に一冊にできる素材だ。パチプロへの転落ではなく、転身というのが凄い。豪放かつ繊細な溝口に魅了され、ハードボイルドの日本語訳は、無頼であるべきだなと思った。
第四章 クリオネの記-筋萎縮症女性の性とわいせつ裁判
脊髄性進行性筋萎縮症 淡い恋 癒し系の障害者
恋愛から求婚へ 医師の淫行 自殺未遂とわいせつ行為
わいせつ裁判の行方 判決への道のり 流氷の天使
これもまったく知らない事件だった。読み進むうちに、『AV女優』(永沢 光雄 文春文庫)という優れたインタビュー集を思い起こさせた。インタビューは上手下手ではなく、結局人格なのだろう。
第五章 「花電車は走る」-ストリッパー・ヨーコの半生
花電車への喝采 八つの出し物 お股からの炎
波潤の半生 ストリップデビュー 病床の父との再会
年の瀬のファイヤー
花電車を稼業とする中年ストリッパーを、言葉の正しい意味で、キャリアウーマンとしてとらえ、「キャリア(職歴)」を問うなかで、彼女の仕事への真摯な姿勢を浮かび上がらせている。男出入りには眼を向けない、そんなプライバシーはどうだっていい、という著者の潔い視線が好ましい。
第六章 皮田藤吉伝-初代桂春團治
落語との出会い 「王将」阪田三吉と春團治
人間の業の肯定 春團治の落語 噺の特徴
皮田家に生まれて 修行時代 後家殺し
人気者になれ 皮田姓から岩井姓へ 火宅の人
漫才の台頭 晩年 春團治の下げ
桂春團治も名前は知っていたが、ほとんど知らなかったことを知ることになった。これも一冊にできる内容だ。その場合、被差別と春團治の芸や個性との距離の置きかたは、それこそもっと遠く迂回しなければならないだろう。被差別もまた、「伝統」であるようだから。
あとがき
興味深い登場人物たちとの交流や後日談。「はじめに」の気負いがとれている。列車を見送った帰り道、見送った人について、ちょっと語り合うような、和やかだけど少し寂しい気分になる。売れないだろうが、よい本でした。なぜか、新大手町ビル1Fの小さな書店で買い求めました。
(敬称略)









