「ベルリン国立美術館展 学べるヨーロッパ美術の400年」に行って来ました。

9月17日までの開催なので、慌てて行きました。いつも、こうなっちゃんですよね。
最終日が近づくと、混雑はピークが見込まれるので、会館時間の1時間前に上野につきましたが、なんと美術館前には2人しか人がいません。
あれ~っ。人気ないのかな。これで並ぶのも馬鹿馬鹿しいので、東京都美術館でやっている「マウリッツハイス美術館展」の様子を見に行きました。

こちらの目玉は、フェルメールの真珠の耳飾の少女です。人はこちらも表には並んでいませんでしたが、続々と人が中庭に入っていっています。こちらを見に行くなら1時間前到着は絶対必要だなと言う感じです。

そろそろかなと、国立西洋美術館の方にもどってみると、開館20分前だと言うのに10人くらいしか並んでいません。

予想を裏切られたので、涼しい木影に腰掛けて、開館を待つことにしました。流石に開館5分前には100人ぐらい並びましたが、それでも前回の「ルーヴル美術館展」から比べたら意外でした。
さて、この美術展の目玉は、もちろん日本初公開フェルメールの「真珠の首飾りの少女」です。「真珠の耳飾の少女」と間違えて、こちらに並ぶ人もいるみたいで、美術館の人が盛んに違いを連呼して案内していました。
入館していつものとおり、フェルメールの絵の前に急行します。
ところが、いつもなら絵の前に1~2人しか見物客がいなくて、じっくりと見られるはずなのに、今回は15人ぐらいの人がたまっているのです。これも意外でした。
更に、この連中がルール無視の団塊世代と、いかにも「僕は友達が少ない」感じの男女(もちろん連れのいない)で、絵の前からいっこうに動こうとせず、他人に場所を譲るなんて、いっさい考慮しない非常識な連中でした。5分ぐらい待ったのですが状況は一向に改善しません。あんまり腹が立ったので、あとで見ようともう一度入り口付近にもどりました。こんなことも初めてです。
戻っては見たものの、今回の 「ベルリン国立美術館展 学べるヨーロッパ美術の400年」はひどいです。フェルメールの絵以外、見るものありません。ベルリン国立美術館に騙されてくずみたいなものを押し付けられた感じです。それとも、ヒトラーが収集した美術品などとともに、あらかた美術品はソ連が略奪したみたいですから、ドイツ国内には、あまりいいものが残っていないのかもしれません。
一応、15世紀から18世紀までのヨーロッパ美術を、イタリアと北方の美術を比較しながら観ることのできる展覧会と銘打っていますが、展示作品の多くが、どこからかはがしてきたようなレリーフや宗教的な塑像などです。古典のヨーロッパ美術はキリスト教と切り離しては存在しませんが、日本人、とくに私にとってまったく、知識も興味もありませんから退屈そのものです。


もうひとつの目玉、ボッティチェッリの素描などは、鳥獣戯画みたいな体裁のなぐり書きでした。

あんまり、つまらないので、途中でもう一度フェルメールのところに行って見ます。
やりました、先ほどの非常識な連中は流石にいなくなり、みんな、少しずつ流れながら観賞しています。それも10人ぐらいしか絵の前にいません。
とうとう、初対面です。

なんだ、この他の作品と別次元を成す静謐な雰囲気は!! フェルメールの作品を見ると、いつも思うのですが、天才というものはこういうものなのだなと実感させられます。
とくにこの絵には、「真珠の耳飾の少女」の真珠のイアリングや「手紙を書く女」の机の上に置かれているリボン付きのネックレス、黄色いアーミン(白テンの毛皮)の服、青い陶器などフェルメールの好きな題材がふんだんに使われています。最後までフェルメールも手放さなかったようで思い入れのある絵なのではないでしょうか。
修復はなされているようですが、適度なもので、私のフェルメールのイメージにある雰囲気が伝わるいい感じのものです。
結局4回ほど、時間を置いてじっくり観賞させてもらいました。
これで実際に観賞できたフェルメールの絵は13点になりました。
フェルメールには満足しましたが、なんだか1,500円も払ったのに物足りません。
特別展の入場券で、国立西洋美術館の常設展示も観賞できるとのことなので、初めて常設展示をみてみました。
有名な松方コレクションです。
これがすばらしい、ベルリン国立美術館なんて問題にならない充実ぶりです。


ジョルジョ・ヴァザーリ ゲッセマネの祈り。 ヤン・ブリューゲル(父) アブラハムとイサクのいる森林風景


ロイスダール 砂丘と小さな滝のある風景 マリー=ガブリエル・カペ 自画像


コロー ナポリの浜の思い出 クロード・モネ 睡蓮
有名な品質の高い作品がめじろ押しです。結局1時間以上観賞しました。
これで、満足して帰れます。
あとは、東京都美術館のフェルメールをどうするかですが、実は今回来ている「ディアナとニンフたち」と「真珠の耳飾の少女」は1984年、28年前に既に本物を見ているのです。その後、修復がされているようですが、当時と違ってフェルメールの人気もうなぎのぼりですから、なんと、「真珠の耳飾の少女」を見るだけでも館内で30分まちとかの情報もあります。まあ、この有名作品なら、生きてる間にまたくることは予想されますので、今回はパスすることにしました。
ここで、忘れないうちに、いままでのフェルメール観賞記録を残しておきたいと思います。
1984 マウリッツハイス王立美術館展 国立西洋美術館
1 「青いターバンの少女」(真珠の耳飾の少女) 当時はこういう題名とされていました。

2 ディアナとニンフたち

1987 西洋の美術 その空間表現の流れ 国立西洋美術館
3 手紙を書く女

2008 フェルメール展~光の天才画家とデルフトの巨匠たち~ 東京都美術館
4 マルタとマリアの家のキリスト

2 ディアナとニンフたち
5 小路

6 ワイングラスを持つ娘

7 リュートを調弦する女

8 手紙を書く婦人と召使い

9 ヴァージナルの前に座る若い女

2009 ルーヴル美術館展―17世紀ヨーロッパ絵画 国立西洋美術館
10 レースを編む女

2011 シュテーデル美術館所蔵 フェルメール《地理学者》とオランダ・フランドル絵画展 Bunkamuraザ・ミュージアム
11 地理学者

2011 フェルメールからのラブレター展 Bunkamuraザ・ミュージアム
12 手紙を読む青衣の女[修復直後の初来日]

3 手紙を書く女
8 手紙を書く女と召使
2012 ベルリン国立美術館展 国立西洋美術館
13 真珠の首飾りの少女


帰りには流石に次々と人がやってきていました。























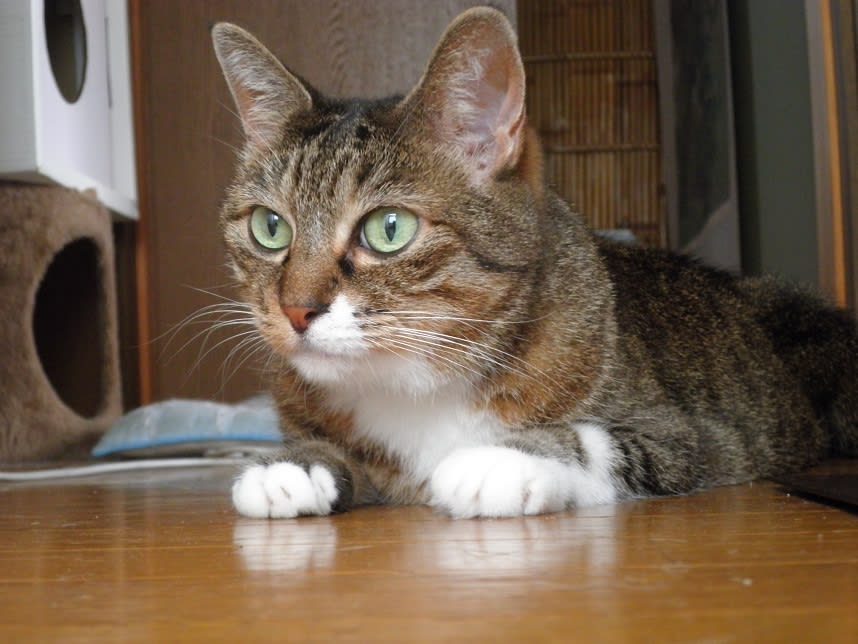






























![【送料無料】リアリズム絵画入門 [ 野田弘志 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f8758%2f87586190.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f8758%2f87586190.jpg%3f_ex%3d80x80)
![【送料無料】青木敏郎画集(2) [ 青木敏郎 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f7630%2f76309843.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f7630%2f76309843.jpg%3f_ex%3d80x80)









































![【新品・送料無料!延長保証受付中】カシオ HIGH SPEED EXILIM EX-ZR100BK [ブラック]HIGH SPEE...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fshop-ex-a%2fcabinet%2fitem%2f5%2fvvvvggmlgv-586.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fshop-ex-a%2fcabinet%2fitem%2f5%2fvvvvggmlgv-586.jpg%3f_ex%3d80x80)