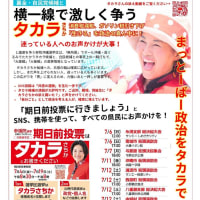12月19日(土)、那覇で開催された「高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する対話型全国説明会」に参加した。
多くの人たちが来ると思っていたが、参加者はわずか14人。ビデオ上映と担当者らの説明の後、「質問は全てグループ討議で受付ます」ということで3つのグループに分けられた。
私は、グループ討議の冒頭、「今日の説明は地層処分の技術的な問題に終始している。現行の原発推進政策を止めない限り、核のゴミは増え続ける。まず、脱原発の方向性を示すことが必要ではないか?」と質問した。
NUMO(原子力発電環境整備機構)の担当者は、「今のような質問はいつもいただくが、私どもは国から最終処分の技術的な問題を委託されている立場なのでお答えできません」と言うだけ。他の2つのグループには資源エネルギー庁の職員もいたようだが、私のグループには国の職員がいないので議論はまるで深まらない。
後で聞くと、隣のグループには福島から避難してきた方がおられ、「何故、まず、原発を減らそうとしないのか?」と追及されていたという。少人数のグループに分け、それ以外の場での質問を受け付けないのも、参加者から出されるこうした批判・疑問を共通のものにさせないための姑息な手段ではないかと思われる。
2017年に発表された科学的特性マップでは、沖縄のほぼ全域が地層処分の「適地」とされている。沖縄の特に中南部には活断層が集中しており、「適地」とは言えないことは明らかである。そもそも沖縄には原発はなく、他県から原発の電力供給も受けてていない。担当者らは、必死に「沖縄での地層処分をお願いするものではありません」と繰り返していたが、それならこのような説明会など必要はない。
米軍基地だけではなく、核のゴミまで沖縄に押し付けようというのか?