
<目次>
序章 ウィーン・デビュー
第1章 小沢征爾の「実験」
第2章 「世界のオザワ」と日本
第3章 一人一人の心に音楽を届けたい
第4章 ほんものの音楽へ
第5章 美しい音楽は悲しい味がする
第6章 みんなの音楽へ
「音楽を聞いて、その美しさにひたれる人は幸福だ、(中略)音楽をする苦しみは何も知らず、ただ音楽の恩恵だけを受けていられるのだから、ぼくなんかよりずっと幸福だと思う」(小澤征爾著『ボクの音楽武者修行』新潮文庫)
音楽の受け手にとっては、かなり挑戦的なコメントです。でも、これに異を唱えることができる人は多くはないでしょう。演奏者である音楽家の場合、その演奏によって聴き手の人生を揺さぶろうとしているわけですから、命がけの演奏に対して、その気迫を受け止められるほどのキャパシティを持った聴き手になるために訓練しているという人は、そうそういません。
<今も続く小澤征爾の壮大なる実験>
1973年9月24日、38歳の小澤征爾さんが、アメリカ5大オーケストラの一つであるボストン交響楽団の常任指揮者に就任して初コンサートを開きました。
「日本のクラシックファンにとっては、日本人指揮者の演奏をアメリカから逆輸入する形で聴くこととなり、また日本人指揮者の演奏が国際的に有名なレーベルから発売されるのは初めてであった。・・・ボストン交響楽団の音楽監督は2002年まで務めたが、一人の指揮者が30年近くにわたり同じオーケストラの音楽監督を務めたのは極めて珍しいことであった」。(ウィキペディア)
しかし小澤征爾さんはこのとき既に「世界のオザワ」になっていました。そしてその初志は、1959年2月1日、貨物船「淡路山丸」でスクーターとともに一路、欧州を目指した23歳の気持ちから始まっていました。その初志は、次の言葉に集約されます。
「クラシック音楽は世界共通だと思っているんですよ。その実証の実験なんですよ」
小池真一さんの2003年の著書「小澤征爾 音楽ひとりひとりの夕陽」(講談社+α新書)にはこの実験について次のように述べられています。
「小澤征爾の『実験』の出発点は、『東洋人として西洋音楽をどこまでやれるか』だった。それが音楽家と聴者を『個』として裸にし、さまざまな人々と文化が共存する世界の『特殊性』『多様性』へとつなげ、人類としての『普遍性』に導く、実験のこうした全体地図を一望しただけで、いかに壮大な試みであるかがわかる」。
この壮大な実験を胸に秘めた小澤さんは、欧州に渡った七ヵ月後の1959年9月10日。日本人として、あるいは東洋人として西洋音楽の扉を開きました。フランスのプザンソンで行われた国際若手指揮者コンクールで24歳の小澤征爾がドイツ、フランス、米国などの俊英たちを抑え、優勝したのです。そのときの模様を新聞では次のように伝えています。
「各国政府は数人ずつ代表を派遣、なかにはすでにオペラ座とか交響楽団の常任指揮者など30才を超えた人も加わっている、(中略)曲目はフランス音楽が主だったので、それになれていない私にはとても見込みがないと思っていたしまた日本人が一人もいないこの町に乗込んだときは、なかなか悲壮な気分だった。ところが、予選の結果、発表のことから『お前は一等になる』『すばらしい』なとという声がきかれるようになり、本選会にはバイオリンの前田郁子さんはじめ応援もかけつけてくれて気楽になることができた」(1959年9月28日「毎日新聞」夕刊)
本書を読んで、まず音楽家にとっての「いい音楽」と「わるい音楽」について学びました。小澤さんは、音楽は個人的なものだと繰り返して述べていることが書かれています。さらに、その中で「いい音楽」と「わるい音楽」について次のように述べています。
<いい音楽>
「いい音楽は、音楽会でお客さんが千人座ってても、音楽やっている人と一人ひとりの線ですから。ぼくはいつもそう思う。たとえ客席でぼくといっしょに家族が座っていても、ぼくはぼくで聴くわけ。一人ひとりが音楽を聴いている。たくさん聴いていても、音楽は個人的なもんじゃん」
「人間が生きていく時の根本的なものの中に音楽もあるんだろうと。音楽はもっと直接的に何か、食ったり飲んだりする以外で、人間の活気が出てくる、音楽はその中の大事な一つだと思いますね。もちろん、具体的に哲学とか文学とかあるだろうけれど、それよりも直感的に、直接的に一人ひとりの心に入っていくのが音楽です」
そして、「いい音楽」がもたらす世界について著者は、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスター、ライナー・キュッヒル(オーストリア、1950年8月25日-)が、最高の音楽の時空では、「たった一人の私」という感覚と「もはや私ではない」という感覚がいっしょにあるとした次のコメントを引用しています。

「演奏する上での理想的な音楽体験は、舞台の上で何か一つの作品を演奏していても、自分が何を弾いているのか、作為のようなものが一切なくなってしまって、音と響きの流れに引っぱられていくような感じになるんです。次々と音が流れていく、けれど、何をやっているのか自分でもわからなくなる、自分の意志のようなものを感じられなくなる。そういう時は同じように聴き手も、自分が座っていることすら忘れてしまう。まるで宙に浮いたような状態になり、響きの流れに身を任せる、そういう状態になれば、誰が弾いていようが、何がそこで行われていようが、そういうことは一切気にならなくなるはず。まるで夢のような、憑依した状態というのでしょうか」(P155)
<わるい音楽>
「街を歩いていても、まわりになんとなく音楽が流れているでしょ。特に日本は洪水のようじゃない。聞きたくても逃げることもできないで、否応なく聞かされてしまう。個人の自由な意思を無視した音楽なんて、やり方はテロと似ていますよね」
「今はだんだん世の中変わってきて、レコードもよくなって、テレビもよくなって、ラジオもよくなって、なんにもしないで、音楽が向う側ぁらやって来るもんだと思っているのとちがうかな。ホテルびエレベーターに乗ればひどい話、音楽が向うからやって来る」「ロマンチックな音や部厚い音なんかぜんぜん出てこない。そういうミューザックもあるわけ。しかしそういう受け身の音楽は音楽とは言えないのであって、自分から手をくだすものが音楽じゃないか」(小澤征爾・武満徹著『音楽』新潮文庫)
ミューザック(MUZAK)とは「歌もなく、また激しく編曲されているため、最初は何の曲かわからないが、意識を集中させて聞くと、原曲がわかるようなBGMのこと。BGMがあると作業効率が上がるといった科学的管理法の成果などをもとに1930年代にMuzak社が様々なBGMを工場や商店などに提供し始めたのがそもそもの起源」。(http://www.kanshin.com/keyword/331926)
このミューザック的なるものについては作家の故・城山三郎さんもエッセーで厳しく批判していました。
<音楽する>
「ムジツィーレン(musizieren)」、と言う言葉があるそうです。日本語に訳せば「音楽する」。著者は、日本人作曲家の埋もれた傑作を演奏するために2002年に結成されたアマチュア楽団「オーケストラ・ニッポニカ」の設立実行委員長、吉川久さんの次の解説を紹介しています。
「仲間同士で楽器を持ち寄りアンサンブル、合奏を気軽に楽しむ、それがムジツィーレンです。その際、楽譜通りに音を間違わないように、合わせることに汲々とするのではなく、楽器と音楽を通じて感情を交換することを優先する。親密なコミュニケーションをする場が、ムジツィーレンです」
<夕陽の悲しさと美しさ>
「聴く人を感動させる美しい音楽は、さんさんと昇る太陽ではなくて、沈んでいく夕陽を見た時のような悲しい味がするんです。自分が年をとってきたからかもしれないけれど、大事なものとか美しいもの、美しいと言ってもただ見て美しいのではなくて、心に染みわたる美しさとか、心を打たれる美しさというのは、少し悲しみの味がするのよ。どういうわけか、不思議なことに。楽しい曲でも、いい音楽の時はそれがあるみたいなんですよね。不思議なことに」。(P148)

小澤 征爾(おざわ せいじ、1935年9月1日 - )
1961年 - 1962年 ニューヨーク・フィルハーモニック副指揮者
1965年 - 1969年 トロント交響楽団音楽監督
1970年 サンフランシスコ交響楽団音楽監督
1973年 - 2002年 ボストン交響楽団音楽監督
2002年 - 2010年(予定) ウィーン国立歌劇場音楽監督
小池真一;1964年、東京都生まれ。慶応義塾大学経済学部卒業。1989年、共同通信社入社。現在は文化部で主に消費者問題を取材している。「アラーキーの幸福写真」も担当。
<備忘録>
「音楽する苦しみ」「クラシック音楽は世界共通か?」(P26)、「人生を賭けて実験を敢行する魅力」(P27)、「バイロイト音楽祭、ニーベルングの指輪、藤村実穂子」(P27)、「桐朋学院」(P30)、「齋藤メトーデ」(P30-32)、「小澤のストラビンスキー、『春の祭典』」(P34)、「中心音を持たない『無調音楽』」(P34)、「シェーンベルク『月に抱かれたピエロ』、内田光子」(P35)、「PMF」(P39)、「クラシック音楽、宗教から現代社会へ」(P42)、「ダブルスタンダードはダメ」(P46、64)、「サトウ・キネン・オーケストラ」(P46、64)、「大友直人、飯森秦次郎、宮本文昭、磯絵理子」(P48)、「高橋大海」(P56)、「梁塵秘抄」(P58)、「伊福部昭」(P63)、「個でありながらエゴイズムでない」(P82)、「合奏と気」(P82)、「疑問の対話」(P92)、「アナログな欲望」(P116)、「間の文化」(P125)、「炎のコバケン」(P41)、「秘すれば花」(P144)、「夕陽のかなしさ」(Pp148-9)、「芸術家とは」(P176)
序章 ウィーン・デビュー
第1章 小沢征爾の「実験」
第2章 「世界のオザワ」と日本
第3章 一人一人の心に音楽を届けたい
第4章 ほんものの音楽へ
第5章 美しい音楽は悲しい味がする
第6章 みんなの音楽へ
「音楽を聞いて、その美しさにひたれる人は幸福だ、(中略)音楽をする苦しみは何も知らず、ただ音楽の恩恵だけを受けていられるのだから、ぼくなんかよりずっと幸福だと思う」(小澤征爾著『ボクの音楽武者修行』新潮文庫)
音楽の受け手にとっては、かなり挑戦的なコメントです。でも、これに異を唱えることができる人は多くはないでしょう。演奏者である音楽家の場合、その演奏によって聴き手の人生を揺さぶろうとしているわけですから、命がけの演奏に対して、その気迫を受け止められるほどのキャパシティを持った聴き手になるために訓練しているという人は、そうそういません。
<今も続く小澤征爾の壮大なる実験>
1973年9月24日、38歳の小澤征爾さんが、アメリカ5大オーケストラの一つであるボストン交響楽団の常任指揮者に就任して初コンサートを開きました。
「日本のクラシックファンにとっては、日本人指揮者の演奏をアメリカから逆輸入する形で聴くこととなり、また日本人指揮者の演奏が国際的に有名なレーベルから発売されるのは初めてであった。・・・ボストン交響楽団の音楽監督は2002年まで務めたが、一人の指揮者が30年近くにわたり同じオーケストラの音楽監督を務めたのは極めて珍しいことであった」。(ウィキペディア)
しかし小澤征爾さんはこのとき既に「世界のオザワ」になっていました。そしてその初志は、1959年2月1日、貨物船「淡路山丸」でスクーターとともに一路、欧州を目指した23歳の気持ちから始まっていました。その初志は、次の言葉に集約されます。
「クラシック音楽は世界共通だと思っているんですよ。その実証の実験なんですよ」
小池真一さんの2003年の著書「小澤征爾 音楽ひとりひとりの夕陽」(講談社+α新書)にはこの実験について次のように述べられています。
「小澤征爾の『実験』の出発点は、『東洋人として西洋音楽をどこまでやれるか』だった。それが音楽家と聴者を『個』として裸にし、さまざまな人々と文化が共存する世界の『特殊性』『多様性』へとつなげ、人類としての『普遍性』に導く、実験のこうした全体地図を一望しただけで、いかに壮大な試みであるかがわかる」。
この壮大な実験を胸に秘めた小澤さんは、欧州に渡った七ヵ月後の1959年9月10日。日本人として、あるいは東洋人として西洋音楽の扉を開きました。フランスのプザンソンで行われた国際若手指揮者コンクールで24歳の小澤征爾がドイツ、フランス、米国などの俊英たちを抑え、優勝したのです。そのときの模様を新聞では次のように伝えています。
「各国政府は数人ずつ代表を派遣、なかにはすでにオペラ座とか交響楽団の常任指揮者など30才を超えた人も加わっている、(中略)曲目はフランス音楽が主だったので、それになれていない私にはとても見込みがないと思っていたしまた日本人が一人もいないこの町に乗込んだときは、なかなか悲壮な気分だった。ところが、予選の結果、発表のことから『お前は一等になる』『すばらしい』なとという声がきかれるようになり、本選会にはバイオリンの前田郁子さんはじめ応援もかけつけてくれて気楽になることができた」(1959年9月28日「毎日新聞」夕刊)
本書を読んで、まず音楽家にとっての「いい音楽」と「わるい音楽」について学びました。小澤さんは、音楽は個人的なものだと繰り返して述べていることが書かれています。さらに、その中で「いい音楽」と「わるい音楽」について次のように述べています。
<いい音楽>
「いい音楽は、音楽会でお客さんが千人座ってても、音楽やっている人と一人ひとりの線ですから。ぼくはいつもそう思う。たとえ客席でぼくといっしょに家族が座っていても、ぼくはぼくで聴くわけ。一人ひとりが音楽を聴いている。たくさん聴いていても、音楽は個人的なもんじゃん」
「人間が生きていく時の根本的なものの中に音楽もあるんだろうと。音楽はもっと直接的に何か、食ったり飲んだりする以外で、人間の活気が出てくる、音楽はその中の大事な一つだと思いますね。もちろん、具体的に哲学とか文学とかあるだろうけれど、それよりも直感的に、直接的に一人ひとりの心に入っていくのが音楽です」
そして、「いい音楽」がもたらす世界について著者は、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスター、ライナー・キュッヒル(オーストリア、1950年8月25日-)が、最高の音楽の時空では、「たった一人の私」という感覚と「もはや私ではない」という感覚がいっしょにあるとした次のコメントを引用しています。

「演奏する上での理想的な音楽体験は、舞台の上で何か一つの作品を演奏していても、自分が何を弾いているのか、作為のようなものが一切なくなってしまって、音と響きの流れに引っぱられていくような感じになるんです。次々と音が流れていく、けれど、何をやっているのか自分でもわからなくなる、自分の意志のようなものを感じられなくなる。そういう時は同じように聴き手も、自分が座っていることすら忘れてしまう。まるで宙に浮いたような状態になり、響きの流れに身を任せる、そういう状態になれば、誰が弾いていようが、何がそこで行われていようが、そういうことは一切気にならなくなるはず。まるで夢のような、憑依した状態というのでしょうか」(P155)
<わるい音楽>
「街を歩いていても、まわりになんとなく音楽が流れているでしょ。特に日本は洪水のようじゃない。聞きたくても逃げることもできないで、否応なく聞かされてしまう。個人の自由な意思を無視した音楽なんて、やり方はテロと似ていますよね」
「今はだんだん世の中変わってきて、レコードもよくなって、テレビもよくなって、ラジオもよくなって、なんにもしないで、音楽が向う側ぁらやって来るもんだと思っているのとちがうかな。ホテルびエレベーターに乗ればひどい話、音楽が向うからやって来る」「ロマンチックな音や部厚い音なんかぜんぜん出てこない。そういうミューザックもあるわけ。しかしそういう受け身の音楽は音楽とは言えないのであって、自分から手をくだすものが音楽じゃないか」(小澤征爾・武満徹著『音楽』新潮文庫)
ミューザック(MUZAK)とは「歌もなく、また激しく編曲されているため、最初は何の曲かわからないが、意識を集中させて聞くと、原曲がわかるようなBGMのこと。BGMがあると作業効率が上がるといった科学的管理法の成果などをもとに1930年代にMuzak社が様々なBGMを工場や商店などに提供し始めたのがそもそもの起源」。(http://www.kanshin.com/keyword/331926)
このミューザック的なるものについては作家の故・城山三郎さんもエッセーで厳しく批判していました。
<音楽する>
「ムジツィーレン(musizieren)」、と言う言葉があるそうです。日本語に訳せば「音楽する」。著者は、日本人作曲家の埋もれた傑作を演奏するために2002年に結成されたアマチュア楽団「オーケストラ・ニッポニカ」の設立実行委員長、吉川久さんの次の解説を紹介しています。
「仲間同士で楽器を持ち寄りアンサンブル、合奏を気軽に楽しむ、それがムジツィーレンです。その際、楽譜通りに音を間違わないように、合わせることに汲々とするのではなく、楽器と音楽を通じて感情を交換することを優先する。親密なコミュニケーションをする場が、ムジツィーレンです」
<夕陽の悲しさと美しさ>
「聴く人を感動させる美しい音楽は、さんさんと昇る太陽ではなくて、沈んでいく夕陽を見た時のような悲しい味がするんです。自分が年をとってきたからかもしれないけれど、大事なものとか美しいもの、美しいと言ってもただ見て美しいのではなくて、心に染みわたる美しさとか、心を打たれる美しさというのは、少し悲しみの味がするのよ。どういうわけか、不思議なことに。楽しい曲でも、いい音楽の時はそれがあるみたいなんですよね。不思議なことに」。(P148)

小澤 征爾(おざわ せいじ、1935年9月1日 - )
1961年 - 1962年 ニューヨーク・フィルハーモニック副指揮者
1965年 - 1969年 トロント交響楽団音楽監督
1970年 サンフランシスコ交響楽団音楽監督
1973年 - 2002年 ボストン交響楽団音楽監督
2002年 - 2010年(予定) ウィーン国立歌劇場音楽監督
小池真一;1964年、東京都生まれ。慶応義塾大学経済学部卒業。1989年、共同通信社入社。現在は文化部で主に消費者問題を取材している。「アラーキーの幸福写真」も担当。
<備忘録>
「音楽する苦しみ」「クラシック音楽は世界共通か?」(P26)、「人生を賭けて実験を敢行する魅力」(P27)、「バイロイト音楽祭、ニーベルングの指輪、藤村実穂子」(P27)、「桐朋学院」(P30)、「齋藤メトーデ」(P30-32)、「小澤のストラビンスキー、『春の祭典』」(P34)、「中心音を持たない『無調音楽』」(P34)、「シェーンベルク『月に抱かれたピエロ』、内田光子」(P35)、「PMF」(P39)、「クラシック音楽、宗教から現代社会へ」(P42)、「ダブルスタンダードはダメ」(P46、64)、「サトウ・キネン・オーケストラ」(P46、64)、「大友直人、飯森秦次郎、宮本文昭、磯絵理子」(P48)、「高橋大海」(P56)、「梁塵秘抄」(P58)、「伊福部昭」(P63)、「個でありながらエゴイズムでない」(P82)、「合奏と気」(P82)、「疑問の対話」(P92)、「アナログな欲望」(P116)、「間の文化」(P125)、「炎のコバケン」(P41)、「秘すれば花」(P144)、「夕陽のかなしさ」(Pp148-9)、「芸術家とは」(P176)










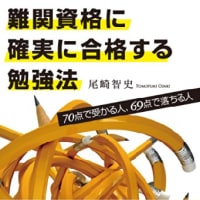
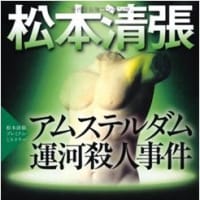
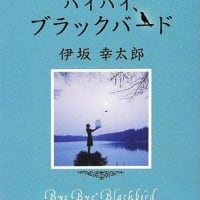

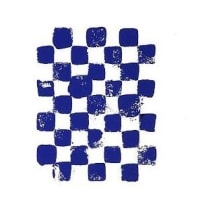
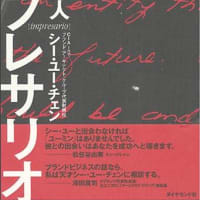



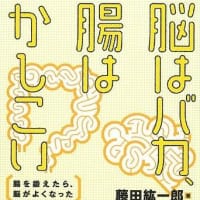
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます