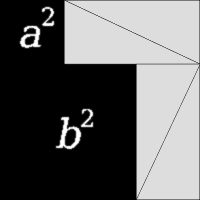ピタゴラスの定理のアニメ証明
幾何と代数のつなぎ目、ピタゴラスの定理の果たした役割と証明法の歴史 第1回
序(その1)
ピタゴラスの定理は実用幾何学の中で最もポピュラーな定理で、応用範囲が広く重宝しています。ピタゴラスの定理と相似三角形の辺の比例則(タレスの定理)の二つで大概の問題は間に合うほどです。幾何学は直感的にわかることが基本となり、代数計算はしないのが美しい解法と言われています。幾何学には形から離れた演算は邪道という人もいます。補助線と円を引きまくって形で分かることだということです。ですからタレスの定理は直感で分かるが、ピタゴラスの定理は直感的には出て来ません。直感的に分からないから証明が必要になります。直感から出てこない定理がどうして発見されたのでしょうか。だれがいつごろこの法則に気が付いたのか全く分かっていません。ピタゴラスという紀元前6世紀のギリシャ人にその栄誉が与えられていますが、そのまえからバビロニアやエジプトでは知っていたようです。そのため古くからいろいろの証明法が考察されてきました。その歴史は本書に書かれているが、近世まで日本にはピタゴラスの定理の本は全く存在しなかった。本来日本では厳密な論理による証明という科学的な方法論がなかったので、セクト集団で伝授される和算という職人芸に過ぎなかった。著者大矢真一氏(1907年 - 1991年、日本の数学史学者、富士短期大学名誉教授)が本書を書いたのは昭和21年(1946年)のことであるが、版が紛失したこともあって1975年に新版ができたという。2001年に東海大学秋山教授の労によって東海大学出版部から発刊されたという経緯を持つ本である。ピタゴラスの定理とは平面幾何学において直角三角形の斜辺の長さを c、他の2辺の長さを a, b とすると、ピタゴラスの定理式が成り立つという定理です。ピタゴラスの定理によって、直角三角形をなす3辺の内、2辺の長さを知ることができれば、残りの1辺の長さを知ることができる。例えば、直交座標系において原点と任意の点を結ぶ線分の長さは、ピタゴラスの定理に従って、その点の座標成分を2乗したものの総和として表すことができる。このことは2次元の座標系に限らず、3次元の系やより大きな次元の系についても成り立ちます。この事実から、ピタゴラスの定理を用いて任意の2点の間の距離を測ることができ、ユークリッド距離と呼ばれる。「ピタゴラスが直角二等辺三角形のタイルが敷き詰められた床を見ていて、この定理を思いついた」など幾つかの逸話が知られているものの、この定理はピタゴラスが発見したかどうかは分からない。バビロニア数学のプリンプトンや古代エジプトなどでもピタゴラス数については知られていたが、彼らが定理を発見していたかどうかは定かではない。中国古代の数学書『九章算術』や『周髀算経』でもこの定理が取り上げられている。中国ではこの定理を勾股定理と呼び、日本では三平方の定理という。このピタゴラスの定理は3)ピタゴラス数(整数)で明らかになるが直角三角形の斜辺cと底辺bとの差が1または2という僅差ばかりで、三角形としては面白くない形です。三角関数ではsinθ=θ(斜辺と底辺のなす角度)というくらいの小さな角度しかありません。微分の創始者ニュートンはこの小さな角度での直角三角形を使って力学を幾何学から導きました。しかしピタゴラスの定理はそんな薄い直角三角形ばかりを扱うのではなく、実数という範囲では一般化されて応用の広い形になります。
(つづく)