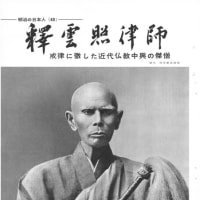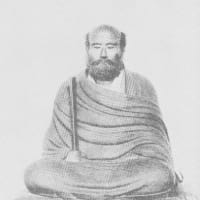『ブッダという男』を読んで
2023年12月10日刊『ブッダという男-初期仏典を読みとく』という本を読んだ。佛教大学総合研究所特別研究員の清水俊史という新進気鋭の先生が著した筑摩新書の一冊である。これまでブッダは、差別を否定し、万人の平等を唱えた平和主義者であり、階級差別や男女の差別を批判し、業や輪廻を否定した先駆的開明的な人物とされてきたことを真っ向から否定している。
その著作からここでは特にブッダの殺生や戦争に対する見解を学んでみよう。清水氏は、長い歴史の中で、仏教は殺生や戦争を何らかの形で許容してきたのだと述べている。
はじめに、スリランカの歴史書『大王統史』二五章を引いて、タミル人を駆逐してスリランカを初めて統一するために戦争で多くの殺戮を繰り返したアバヤ王は、自分に多くの悪業があるのではと心配していた。その王に対して、僧団の長老は、「貴方のその業によって天への道に障害となるものはありません。これについて、ただ一人半だけが殺戮されました。一人は帰依に住する者、他の一人は五戒にも住する者です。残りの者たちは邪見を抱き悪戒を持ち獣にも等しいと考えられます」と説かれたという。
アバヤ王の殺めた一人とは仏教に帰依し五戒を守る信者のことであり、帰依はしているが五戒を守っていない者は半人と数えている。つまり、戒を守っていない者は命の価値は一人として数えることなく、さらには、邪教の徒で悪しき行動をとる者は獣に等しく命の価値が低いと理解されていたのである。この後、「善を最上として福徳をなし、多くの決定的でない悪を覆い隠す者は、自宅に帰るように、天上へ趣く」と続き、アバヤ王は死後間違いなく天界に逝くであろうとある。
その場合の決定的な悪とは、仏道から外れるような極端な見解と無間罪(父・母・悟った人を殺す・僧団を分裂させる・ブッダの身体から出血させる)の二つであり、それ以外の悪は、たとえ百万人殺めても善業さえ積めば地獄落ちを回避できる可能性があると考えるのが上座部の解釈であるという。
また、初期仏典に残されるブッダの言行を考察しても、戦争の無益さを説く教えはあっても王に対して戦争そのものを止めようとした教えはないという。コーサラ国のヴィドゥーダバ王が釈迦族の首都カピラバストゥを攻め滅ぼそうとしたとき、弟子から「鉄籠をカピラバストゥ城の上に被せましょう」と提案されているが、ブッダはそれを斥け「過去の業縁が熟し、その報いを受けて釈迦族は滅びるだろう」と言われ放任された、と記している。
さらに、マガダ国のアジャータサットゥ王からヴァッジ族を攻め滅ぼすつもりだと奏上されたとき、ブッダは、攻め滅ぼされるヴァッジ族への憐れみから離間計の策略を助言して、征服を先延ばしさせたが、戦争そのものを非難したり止めることなかったのだと指摘する。
ブッダが生きた時代には、起こるべき定めの戦争は避けられないものとして理解されていた。が、そこには武士階級が戦争を起こすことは彼らに課せられた神聖な生き方であるとされ、業報輪廻の世界において戦争の惨禍は避けられないものと信じられていたことが背景にあるとしている。
また、アングリマーラが大量殺人を犯した人間にもかかわらず出家を許され、世俗での刑罰も受けることなく解脱していることにも言及している。大量殺人の悪業は、本来ならば地獄で何千年も煮られる報いを受けるべきところではあるが、アングリマーラの出家後の精進努力により悟りを得たがために、現世で大けがをする程度で済んだと経典にある。そして、ブッダは、アングリマーラによって殺害された被害者への憐憫の情を一切起こしていないとも指摘している。
清水氏が述べているように、初期経典において、ブッダは戦争の無益さを説き、殺生や戦争を積極的に是認したわけではないが、ときに戦争を容認し、人にも差別があり、多くの人を殺しても地獄にいくとは限らないとされており、決して現代的な意味での平和主義者ではなかったのであると結論している。
このほか、ブッダは、業と輪廻を否定したのか、階級差別を否定したのか、男女平等を主張したのか、などについても探求され、私たちが陥ってきた理想的現代的ブッダ像はそうあって欲しいという願望に過ぎないという。ブッダの歴史性を明らかにする際の障害は、神話的装飾や後代の加筆などではなく、ブッダは現代の私たちの願いに叶う有意義なものであって欲しいという衝動だとする。
万人の平等を唱えた平和主義者ブッダは人々の期待が生んだ神話に外ならない。誤謬と偏見を排しその実像に迫ると本書の帯にあるが、今一度大本から仏教の本質を捉え直す必要がありそうだ。
(↓よろしければ、一日一回クリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
2023年12月10日刊『ブッダという男-初期仏典を読みとく』という本を読んだ。佛教大学総合研究所特別研究員の清水俊史という新進気鋭の先生が著した筑摩新書の一冊である。これまでブッダは、差別を否定し、万人の平等を唱えた平和主義者であり、階級差別や男女の差別を批判し、業や輪廻を否定した先駆的開明的な人物とされてきたことを真っ向から否定している。
その著作からここでは特にブッダの殺生や戦争に対する見解を学んでみよう。清水氏は、長い歴史の中で、仏教は殺生や戦争を何らかの形で許容してきたのだと述べている。
はじめに、スリランカの歴史書『大王統史』二五章を引いて、タミル人を駆逐してスリランカを初めて統一するために戦争で多くの殺戮を繰り返したアバヤ王は、自分に多くの悪業があるのではと心配していた。その王に対して、僧団の長老は、「貴方のその業によって天への道に障害となるものはありません。これについて、ただ一人半だけが殺戮されました。一人は帰依に住する者、他の一人は五戒にも住する者です。残りの者たちは邪見を抱き悪戒を持ち獣にも等しいと考えられます」と説かれたという。
アバヤ王の殺めた一人とは仏教に帰依し五戒を守る信者のことであり、帰依はしているが五戒を守っていない者は半人と数えている。つまり、戒を守っていない者は命の価値は一人として数えることなく、さらには、邪教の徒で悪しき行動をとる者は獣に等しく命の価値が低いと理解されていたのである。この後、「善を最上として福徳をなし、多くの決定的でない悪を覆い隠す者は、自宅に帰るように、天上へ趣く」と続き、アバヤ王は死後間違いなく天界に逝くであろうとある。
その場合の決定的な悪とは、仏道から外れるような極端な見解と無間罪(父・母・悟った人を殺す・僧団を分裂させる・ブッダの身体から出血させる)の二つであり、それ以外の悪は、たとえ百万人殺めても善業さえ積めば地獄落ちを回避できる可能性があると考えるのが上座部の解釈であるという。
また、初期仏典に残されるブッダの言行を考察しても、戦争の無益さを説く教えはあっても王に対して戦争そのものを止めようとした教えはないという。コーサラ国のヴィドゥーダバ王が釈迦族の首都カピラバストゥを攻め滅ぼそうとしたとき、弟子から「鉄籠をカピラバストゥ城の上に被せましょう」と提案されているが、ブッダはそれを斥け「過去の業縁が熟し、その報いを受けて釈迦族は滅びるだろう」と言われ放任された、と記している。
さらに、マガダ国のアジャータサットゥ王からヴァッジ族を攻め滅ぼすつもりだと奏上されたとき、ブッダは、攻め滅ぼされるヴァッジ族への憐れみから離間計の策略を助言して、征服を先延ばしさせたが、戦争そのものを非難したり止めることなかったのだと指摘する。
ブッダが生きた時代には、起こるべき定めの戦争は避けられないものとして理解されていた。が、そこには武士階級が戦争を起こすことは彼らに課せられた神聖な生き方であるとされ、業報輪廻の世界において戦争の惨禍は避けられないものと信じられていたことが背景にあるとしている。
また、アングリマーラが大量殺人を犯した人間にもかかわらず出家を許され、世俗での刑罰も受けることなく解脱していることにも言及している。大量殺人の悪業は、本来ならば地獄で何千年も煮られる報いを受けるべきところではあるが、アングリマーラの出家後の精進努力により悟りを得たがために、現世で大けがをする程度で済んだと経典にある。そして、ブッダは、アングリマーラによって殺害された被害者への憐憫の情を一切起こしていないとも指摘している。
清水氏が述べているように、初期経典において、ブッダは戦争の無益さを説き、殺生や戦争を積極的に是認したわけではないが、ときに戦争を容認し、人にも差別があり、多くの人を殺しても地獄にいくとは限らないとされており、決して現代的な意味での平和主義者ではなかったのであると結論している。
このほか、ブッダは、業と輪廻を否定したのか、階級差別を否定したのか、男女平等を主張したのか、などについても探求され、私たちが陥ってきた理想的現代的ブッダ像はそうあって欲しいという願望に過ぎないという。ブッダの歴史性を明らかにする際の障害は、神話的装飾や後代の加筆などではなく、ブッダは現代の私たちの願いに叶う有意義なものであって欲しいという衝動だとする。
万人の平等を唱えた平和主義者ブッダは人々の期待が生んだ神話に外ならない。誤謬と偏見を排しその実像に迫ると本書の帯にあるが、今一度大本から仏教の本質を捉え直す必要がありそうだ。
(↓よろしければ、一日一回クリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)