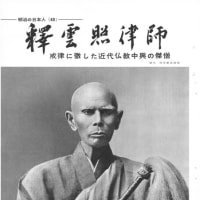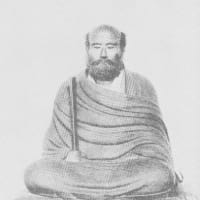江戸時代の仏教
江戸時代は仏教が巧みに政治に利用され封建機構の中に組み込まれる時代である。禁制にもかかわらず浸透していくキリスト教を統制すべく寺請制度ができ、改宗した者はその身元を引き受ける檀那寺から寺請証文をもらう必要があった。そして、1664年には幕令によって、キリシタンにかかわらず誰もが寺請を強制されることとなり、家単位で宗旨年齢を記載させ、村の名主と組頭連署のもと檀那寺住職が証明する「宗旨人別帳」が全国画一的に法制化された。
こうして婚姻、旅行、移住、奉公の際にも檀徒であることを証明する寺請証文の携行が、さらに死亡時には住職検分の上キリシタンでないことを請け合いの上引導を渡すことが義務づけられた。つまりこれにより全国民が強制的に仏教徒となり、葬式、年忌法要、墓碑の建立が義務となる。この所謂寺檀制度が全国に普及定着するのは、四代将軍家綱の頃といわれ、後になると、さらに一家一宗旨、檀那寺の変更も禁止された。
各寺院は宗旨宗派本山を決められ、本末制度によって寺格が固定された。本山の地位を保証した上で全国の末寺を組織統制させ、末寺住職の最終任命権を本山が握ることになった。江戸には各宗に触頭寺院を置き、幕府の通知はそこから地方の中本寺に届けられ、順次末寺へ下ろされ周知させた。これにより、すべての寺院が中央集権的な組織に組み入れられることになった。こうした規定を定めた「寺院法度」が各宗別々に1608年頃より制定されていく。
また法談の制限、勧進募財の取り締まり、新寺建立、新規の教義、異説の提唱などが禁じられるが、その一方、寛永寺や増上寺など幕藩政治を讃美する寺院には厚い保護がなされた。そうした時代にあって唯一の例外として、明の高僧隠元隆琦が来日すると、浄禅一致を説く念仏禅を伝え、黄檗宗が立宗。宇治に黄檗山萬福寺を開創した。
また、各宗僧侶の僧階も細かく規定され、住職資格には一定の修行年限や学問が規定された。学問が奨励され各宗に、檀林、学寮、談義所など学問所が整備され、宗祖研究、経典解釈など教学が促進された。
そうして、いわゆる檀家制度が世の中に定着していくと、僧侶は官僚化し安逸をむさぼり、腐敗堕落を招いた。そして社会から反感の声があがると、僧風の粛正と戒律の復興運動が各宗に起こってくる。諸宗の中で、特に真言宗は戒を持せずば霊験なしとして戒を重んじたので、この時代の戒律復興にも、いち早く先鞭をつけた。
鎌倉時代に奈良西大寺を中興した叡尊の戒律を受法した明忍(みょうにん)らは、慶長7年(1602)、京都栂尾(とがのお)にて自誓受戒。戒律の復興を誓い、多くの学徒を養成した。自誓受戒とは仏の好相を見て滅罪したとして自戒し、戒を授ける主体を仏として直接具足戒を授かったとするものである。
江戸時代中期には淨厳(じょうごん)が出て、戒律を仏道修行の根本に据えた「如法真言律」を唱導。高野山で密教を修め、梵語を研鑽、江戸に出て講座を開くと常に聴衆は千人を超え、綱吉の帰依を受けて湯島に霊雲寺を建立。百五十万人を超える人々に三帰五戒を授けたという。
そしてこの真言宗内での戒律運動は、やがて他宗へも伝播されていく。寛文から元禄の頃、天台宗では妙立、霊空が大乗小乗律兼学の護持を主張し「安楽律」を唱え、浄土宗では慈空、霊潭が「浄土律」を、日蓮宗の元政らは「法華律」を提唱して、律を広め僧風の刷新をはかった。
そして宝暦から寛政の頃、釈尊在世時の戒律復興を目指した慈雲尊者飲光(おんこう)(1710-1804)が登場する。慈雲は、奈良の南都仏教や真言宗を修学し、律を研究。曹洞宗に参禅。そして、河内高貴寺にて釈尊当時の僧団に回帰するための戒律として、「正法律(しょうぼうりつ)」を創唱。僧侶の生活規律、禁止条項などについて、私意を交えず、時代や場所の不相応を論ずることなく仏説のままに行じることを旨とした。
僧団の組織や袈裟の縫い方かけ方、日々の誦経坐禅まで釈尊在世時の如くに行う「正法律」に従う限り、その出身宗派にとらわれることがないため、宗派を越えた沢山の僧尼が慈雲を師と仰ぎ雲集したのであった。正法を仏説の経文律蔵にもとめ、受戒僧坊による自派他派の別を立てず、宗派宗旨の深浅を論ずることを禁じた。
そして、十善戒をすべての戒の根本であるとして、身を治め家を治め国を治める大本の教え、人の人たる道であると平易に説いて、数多の道俗を教化。特に多くの皇室関係者が帰依するなど、その徳風は一世を風靡したといわれる。『梵学津梁』(ぼんがくしんりょう)一千巻、『十善法語』十二巻など多くの著作をなし、特に十善戒に関する著作は近代の仏教者に多大な影響を与えることになる。
(↓よろしければ、一日一回クリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
江戸時代は仏教が巧みに政治に利用され封建機構の中に組み込まれる時代である。禁制にもかかわらず浸透していくキリスト教を統制すべく寺請制度ができ、改宗した者はその身元を引き受ける檀那寺から寺請証文をもらう必要があった。そして、1664年には幕令によって、キリシタンにかかわらず誰もが寺請を強制されることとなり、家単位で宗旨年齢を記載させ、村の名主と組頭連署のもと檀那寺住職が証明する「宗旨人別帳」が全国画一的に法制化された。
こうして婚姻、旅行、移住、奉公の際にも檀徒であることを証明する寺請証文の携行が、さらに死亡時には住職検分の上キリシタンでないことを請け合いの上引導を渡すことが義務づけられた。つまりこれにより全国民が強制的に仏教徒となり、葬式、年忌法要、墓碑の建立が義務となる。この所謂寺檀制度が全国に普及定着するのは、四代将軍家綱の頃といわれ、後になると、さらに一家一宗旨、檀那寺の変更も禁止された。
各寺院は宗旨宗派本山を決められ、本末制度によって寺格が固定された。本山の地位を保証した上で全国の末寺を組織統制させ、末寺住職の最終任命権を本山が握ることになった。江戸には各宗に触頭寺院を置き、幕府の通知はそこから地方の中本寺に届けられ、順次末寺へ下ろされ周知させた。これにより、すべての寺院が中央集権的な組織に組み入れられることになった。こうした規定を定めた「寺院法度」が各宗別々に1608年頃より制定されていく。
また法談の制限、勧進募財の取り締まり、新寺建立、新規の教義、異説の提唱などが禁じられるが、その一方、寛永寺や増上寺など幕藩政治を讃美する寺院には厚い保護がなされた。そうした時代にあって唯一の例外として、明の高僧隠元隆琦が来日すると、浄禅一致を説く念仏禅を伝え、黄檗宗が立宗。宇治に黄檗山萬福寺を開創した。
また、各宗僧侶の僧階も細かく規定され、住職資格には一定の修行年限や学問が規定された。学問が奨励され各宗に、檀林、学寮、談義所など学問所が整備され、宗祖研究、経典解釈など教学が促進された。
そうして、いわゆる檀家制度が世の中に定着していくと、僧侶は官僚化し安逸をむさぼり、腐敗堕落を招いた。そして社会から反感の声があがると、僧風の粛正と戒律の復興運動が各宗に起こってくる。諸宗の中で、特に真言宗は戒を持せずば霊験なしとして戒を重んじたので、この時代の戒律復興にも、いち早く先鞭をつけた。
鎌倉時代に奈良西大寺を中興した叡尊の戒律を受法した明忍(みょうにん)らは、慶長7年(1602)、京都栂尾(とがのお)にて自誓受戒。戒律の復興を誓い、多くの学徒を養成した。自誓受戒とは仏の好相を見て滅罪したとして自戒し、戒を授ける主体を仏として直接具足戒を授かったとするものである。
江戸時代中期には淨厳(じょうごん)が出て、戒律を仏道修行の根本に据えた「如法真言律」を唱導。高野山で密教を修め、梵語を研鑽、江戸に出て講座を開くと常に聴衆は千人を超え、綱吉の帰依を受けて湯島に霊雲寺を建立。百五十万人を超える人々に三帰五戒を授けたという。
そしてこの真言宗内での戒律運動は、やがて他宗へも伝播されていく。寛文から元禄の頃、天台宗では妙立、霊空が大乗小乗律兼学の護持を主張し「安楽律」を唱え、浄土宗では慈空、霊潭が「浄土律」を、日蓮宗の元政らは「法華律」を提唱して、律を広め僧風の刷新をはかった。
そして宝暦から寛政の頃、釈尊在世時の戒律復興を目指した慈雲尊者飲光(おんこう)(1710-1804)が登場する。慈雲は、奈良の南都仏教や真言宗を修学し、律を研究。曹洞宗に参禅。そして、河内高貴寺にて釈尊当時の僧団に回帰するための戒律として、「正法律(しょうぼうりつ)」を創唱。僧侶の生活規律、禁止条項などについて、私意を交えず、時代や場所の不相応を論ずることなく仏説のままに行じることを旨とした。
僧団の組織や袈裟の縫い方かけ方、日々の誦経坐禅まで釈尊在世時の如くに行う「正法律」に従う限り、その出身宗派にとらわれることがないため、宗派を越えた沢山の僧尼が慈雲を師と仰ぎ雲集したのであった。正法を仏説の経文律蔵にもとめ、受戒僧坊による自派他派の別を立てず、宗派宗旨の深浅を論ずることを禁じた。
そして、十善戒をすべての戒の根本であるとして、身を治め家を治め国を治める大本の教え、人の人たる道であると平易に説いて、数多の道俗を教化。特に多くの皇室関係者が帰依するなど、その徳風は一世を風靡したといわれる。『梵学津梁』(ぼんがくしんりょう)一千巻、『十善法語』十二巻など多くの著作をなし、特に十善戒に関する著作は近代の仏教者に多大な影響を与えることになる。
(↓よろしければ、一日一回クリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)