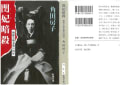先の戦争が昭和二十年に終結し、その後昭和は六十四年まで続いた。平成が三十年、そして令和も七年となる。今の時代を思えば、戦後十五年にして生まれた私には、今と比べて、いい時代を生きてきたという感慨がある。昭和40年代頃まで上野や浅草には腕や膝から下にギブスをはめた傷痍軍人が2、3人で駅前に座り込み小型のオルガンを弾いて哀愁をそそり募金していた。そういう時代であった。しかし戦後復興の息吹のようなものが残り、高度経済成長期のまっただ中でもあり、これから良くなるばかりという気分があった。
昔は良かったという者は馬鹿だという人もある。常に産業技術が発展進化をもたらす時代にあって、昔がいいなどと言うのは戯言に過ぎないという。だが、何もかにもが進歩発展したからいいというものでもない。都内の電車に乗れば老若男女殆どの人がスマホ片手にスリスリしている様を見ていると、その弊害を説く人の声がかき消されている現実をそら恐ろしく思うのは私だけではあるまい。原発もその一つだし、薬害もそうだろう。一部の人たちの利益のために多くの人の命や健康が疎かにされている。
同様に、戦後八十年と言われるが、人類の精神的発展進化を疑う人も多いのではないか。多くの人類の命を葬り去った大戦から私たちは何を学んだのであろうか。未だに世界中から戦争はなくなっていない。そればかりか、東西の冷戦によって両陣営ともに恐ろしいほどの数の原爆が配備された。その後ベルリンの壁が崩壊し、東西ドイツの統一がなされたはずなのに、未だにウクライナを盾に東西の衝突が進展している。中東の安定もほど遠い。
されたことだけでなく私たちがなした残虐な行為も含め悲惨な戦争を語り継ぎ、世界平和を祈り、世界の宗教者との連帯の元に平和構築を懇談するのは大切なことに違いない。だがその上で、私たちに課せられているのは、今この時代だからこそ先の戦争が何故引き起こされたのか。どうしたら防げたのか。原爆は必要だったのか、なぜ広島、長崎だったのか。そうしたことを誰もが素人ながらも自ら歴史を掘り起こし考え続けることが大切なのではないか。いざというときに必要なのは、時代に流されず一方的な報道に呑み込まれないで一人一人が事の是非を判断できることではないか。狂気に飲み込まれそうになったとき冷めた目でその状況を見れるかどうか。大衆が冷静にその判断ができなければ、同じ過ちを繰り返すことになるだろう。
そもそも私たちは何故戦争をしなくてはいけなかったのか。鎖国によって諸外国との交渉を制限して自国の平安を享受してきたのに、四隻の蒸気船によってその泰平が壊され、諸外国の干渉により体制が変わり、富国強兵に舵を取り、近隣地域の植民地化に危機感を催して、欧米諸国の帝国主義さながらに日清日露の戦争の末、いつの間にか列強の仲間入りをはたし、その後先の戦争への道を突き進んだ。それは諸外国に翻弄され続けた時代ではなかったか。
はたして戦争とは何だろう。戦争とは国と国の利害の対立によって引き起こされるものだという思い込みがある。だが、戦争によって利益を得るのは誰なのか。経済的には、膨大な資金を調達融資する国際金融財閥であり、その資金が注がれる武器兵器を製造する軍需産業、それを支える諸の基幹産業であろうか。さらには世界の覇権国が大きな戦争によって入れ替わることを考えれば、戦後の世界支配まで視野に入れた利益権益が想定されているものと言えるのではないだろうか。
ところで、当時の仏教界の姿勢はいかがなものであったのか。昭和14年に宗教団体法が成立してすべての宗教が戦争協力を強制された。伝統仏教は天台、真言、浄土、臨済、日蓮の五宗に宗派合同されられ、全宗教団体が大日本宗教報国会へ結集させられて翼賛体制が敷かれた。有無を言わせぬ間に戦争に加担させられ、政府の方針に則り、聖戦の基礎理念を仏教思想によって解説し戦争遂行を肯定し戦時下における仏教の有用性を論じた戦時教学なるものも作られた。
末寺では地元檀家の出征兵士の名前を毎朝読み上げて無事を祈った。拙寺の大檀前机には今もその出征兵士の名簿が大事に保管されている。本山からは、右に日の丸左に羯磨が描かれ、祈願として「今上陛下玉體安穏 皇軍将兵武運長久 同心協力国威発揚 天下泰平萬民豊楽 乃至法界平等利益」と印刷されたチラシが用意され、檀信徒に配布されたのであろう。そうした印刷物も保存されている。そして、大阪市福島区から学童疎開児童を受け入れ、共同生活の場となった。
これから戦争が起こった時、各本山ないし全日仏はいかなる対応をするのか。従順に素直な対応に徹するのか、より積極的に協力体制を取るのか。それとも、お釈迦様は平和主義者であったからと拒否するのか。拒否できるのか。私たち仏教者はいかにあるべきかを今からでも早急に慎重審議すべきであろう。全体の合意がなければ結局は同じ過ちを繰り返すことになるだろう。
ところで、アジアにも飛び火するのではと心配されるウクライナ戦争は、ロシア軍による領土拡張のための突然の軍事行動ではないという米国の国際政治学者の分析がある。それによれば、主に西側の政治家たちによって、三十年にもわたって戦争に至る道筋が作られていたという。1990年東西ドイツ統一後に東西両陣営が交わした同盟不拡大の合意を一方的に反故にしたのは西側であるのだという。元々東側の軍事同盟であったポーランド、チェコ、ハンガリーが1999年に、ルーマニア、バルト三国が2004年にNATOに加盟している。
ウクライナでは2014年アメリカの支援を受けたクーデターにより親ロシア派の政権から親米派の政権となるが、ロシアはそれを容認せず違法な政権転覆と非難してクリミア半島侵攻につながった。こうした観点からの解説を聞くこともないほど、すべて東側が悪いという一方的な報道体制が西側諸国には徹底されている。戦争になればそうした偏向報道、プロパガンダがまかり通ることを誰より知っているはずなのは私たち日本人ではなかったか。昔を忘れてはならない。
(↓よろしければ、一日一回クリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)