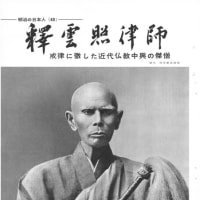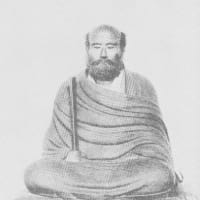大教院の設立と信教の自由
西本願寺の島地黙雷は、キリスト教に対抗するためには民衆教化に実績ある仏教が中心的役割を担うべきであるとして神道唯一主義を批判する建言を提出。国家神道を国民に布教するべき大教宣布運動がその後実効が上がらなかったこともあり、一八七二年(明治五)教部省が設立され、神官僧侶双方による教導職が定められます。
そして、教導職が宣揚すべきものとして「敬神愛国の上旨を体すべき事、天理人道を明らかにすべき事、皇上を奉戴し朝旨を遵守せしむべき事」を内容とする三条の教則を布告。天皇崇拝神社信仰を主軸とする宗教的政治的思想を国民に浸透させることを提議。仏教各宗の代表者は早速政府に大教院という教導職養成機関の創設を訴え、諸般諸学科を教授することを許されます。
しかしその大教院開院式が行われた東京芝の増上寺では、山門に白木の大鳥居が建てられ、本堂の本尊は別に移され神鏡をおいて注連縄を張り、そこで神官とともに烏帽子直垂の各宗管長が神式の祭儀を行うものでした。こうして、大教院も神道様式に仏教側が迎合し、復古神道の思想啓蒙の場となり、また単なる神仏混淆の新しい国教を作る運動と化し、神仏分離の当初の原則とも矛盾するものとなりました。
一方、一八七一年(明治四)末から欧米を訪問していた岩倉使節団は、訪問国でキリスト教迫害を抗議され、信教の自由を承認せざるを得ない状況に追い込まれます。時同じく欧州に宗教事情を視察した島地黙雷らは三条の教則は政教を混同するものであり、政教分離と信教の自由を主張して建白書を提出。仏教の自律性を要望します。
そして、一八七三年(明治六)にはキリスト教禁制を撤廃。氏子調べも同年中止となり、一八七五年(明治八)には大教院は解散。神道を非宗教として天皇と神社崇拝を承認させた上で信教の自由を保障。仏教諸宗派の宗政については各管長に委ねることとなり、一八七七年(明治十)教部省も廃止されました。
肉食妻帯の解禁
三条の教則布告に先立つ、一八七二年(明治五)四月、「僧侶の肉食妻帯蓄髪は勝手たるべき事、但し、法要の他は人民一般の服を着用して苦しからず」という、それまで僧尼令によって定められていた肉食妻帯の禁を解く布告がなされます。
さらに同年九月には僧侶にも一般人民同様に苗字を称させる太政官布告がありました。
これらは国家として出家者を特別扱いしないという意思表示であり、神道を国の教えとする上で当然のことではありました。
戒律は、本来国家とは何の関わりもなく自発的に遵守されるべきものです。しかし、古来国法によって厳重に管理されてきたために、仏教の世俗化に拍車をかけるものとして志ある僧侶たちは反対し、一方では喜んで肉食妻帯する僧侶もあったということです。
その後、この肉食妻帯問題は明治後期に各宗の宗議会で戒律問題として公認すべきか否かで紛糾し、結局自然の成り行きに順じることとされ、今日に至っています。
護法運動の旗手 行誡と雲照
こうした仏教排撃の機運に抗して仏教擁護のため僧風の粛正と通仏教の立場から様々な護法活動が展開されます。
浄土宗の福田行誡(一八〇九ー八八)は、この混迷期に政府に対し数々の意見を建白したことで知られています。仏僧本来の面目に帰るには、まずは戒を守り、自戒内省し、広く他宗の学問も修める兼学を提唱します。
伝通院、増上寺貫主として、縮刷大蔵経刊行にも着手。「仏法を以て宗旨を説くべし、宗旨を以て仏法を説くなかれ」と言われ、仏教の真理に基づいた説法をすべきであると戒めています。
また、肉食妻帯は法律上のことであって、僧侶のあるべき姿を真摯に守るべき事を要求して自らもそれを実践し、他宗の僧侶からも尊敬されたと言われています。
真言宗の釈雲照(一八二七ー一九〇九)は、古今未曾有の排仏の事態に至ったのは、みな僧侶自らの破戒濫行世間の名利に執着した罰であるとして、如来正法の戒定慧の三学に耐える者のみを留めて他を還俗せしめ仏教界の刷新を主張。しかし一方で、太政官に出頭して「仏法は歴代天子の崇信する所にして皇国の神道及び儒教の忠孝と相助け国家を擁護するものである」という趣旨の建白は数度に及び、また宗内でも護法に奔走。
一八八五年(明治十八)東京に出て、政府の大書記青木貞三、山岡鉄舟らの支援のもと目白僧園を建立します。戒律学校として平素四十名ほどの持戒堅固な僧侶がその薫陶を受け、その学徳と戒律を厳格に守る崇高なる人格に山県有朋、伊藤博文、大隈重信はじめ、将軍や財界人、学者に及ぶ蒼々たる人々が訪問し帰依しています。
雲照は、西洋哲学の方法論から仏教哲学を体系化した井上円了が創設した哲学館(後の東洋大学)で「仏教大意」を講じるなど、慈雲尊者の唱えた人間の原理としての「十善戒」を広く紹介。在家者のために十善会や夫人正法会を発足して社会の道徳的宗教的な教会として通仏教の立場から国民道徳の復興に貢献します。
北海道を含む全国に巡錫して法を説き、日露戦争時には満州にも布教。また晩年には西洋化する世間に対抗し神儒仏を一貫した精神をもって教育する徳教学校設立運動を起こしました。つづく
西本願寺の島地黙雷は、キリスト教に対抗するためには民衆教化に実績ある仏教が中心的役割を担うべきであるとして神道唯一主義を批判する建言を提出。国家神道を国民に布教するべき大教宣布運動がその後実効が上がらなかったこともあり、一八七二年(明治五)教部省が設立され、神官僧侶双方による教導職が定められます。
そして、教導職が宣揚すべきものとして「敬神愛国の上旨を体すべき事、天理人道を明らかにすべき事、皇上を奉戴し朝旨を遵守せしむべき事」を内容とする三条の教則を布告。天皇崇拝神社信仰を主軸とする宗教的政治的思想を国民に浸透させることを提議。仏教各宗の代表者は早速政府に大教院という教導職養成機関の創設を訴え、諸般諸学科を教授することを許されます。
しかしその大教院開院式が行われた東京芝の増上寺では、山門に白木の大鳥居が建てられ、本堂の本尊は別に移され神鏡をおいて注連縄を張り、そこで神官とともに烏帽子直垂の各宗管長が神式の祭儀を行うものでした。こうして、大教院も神道様式に仏教側が迎合し、復古神道の思想啓蒙の場となり、また単なる神仏混淆の新しい国教を作る運動と化し、神仏分離の当初の原則とも矛盾するものとなりました。
一方、一八七一年(明治四)末から欧米を訪問していた岩倉使節団は、訪問国でキリスト教迫害を抗議され、信教の自由を承認せざるを得ない状況に追い込まれます。時同じく欧州に宗教事情を視察した島地黙雷らは三条の教則は政教を混同するものであり、政教分離と信教の自由を主張して建白書を提出。仏教の自律性を要望します。
そして、一八七三年(明治六)にはキリスト教禁制を撤廃。氏子調べも同年中止となり、一八七五年(明治八)には大教院は解散。神道を非宗教として天皇と神社崇拝を承認させた上で信教の自由を保障。仏教諸宗派の宗政については各管長に委ねることとなり、一八七七年(明治十)教部省も廃止されました。
肉食妻帯の解禁
三条の教則布告に先立つ、一八七二年(明治五)四月、「僧侶の肉食妻帯蓄髪は勝手たるべき事、但し、法要の他は人民一般の服を着用して苦しからず」という、それまで僧尼令によって定められていた肉食妻帯の禁を解く布告がなされます。
さらに同年九月には僧侶にも一般人民同様に苗字を称させる太政官布告がありました。
これらは国家として出家者を特別扱いしないという意思表示であり、神道を国の教えとする上で当然のことではありました。
戒律は、本来国家とは何の関わりもなく自発的に遵守されるべきものです。しかし、古来国法によって厳重に管理されてきたために、仏教の世俗化に拍車をかけるものとして志ある僧侶たちは反対し、一方では喜んで肉食妻帯する僧侶もあったということです。
その後、この肉食妻帯問題は明治後期に各宗の宗議会で戒律問題として公認すべきか否かで紛糾し、結局自然の成り行きに順じることとされ、今日に至っています。
護法運動の旗手 行誡と雲照
こうした仏教排撃の機運に抗して仏教擁護のため僧風の粛正と通仏教の立場から様々な護法活動が展開されます。
浄土宗の福田行誡(一八〇九ー八八)は、この混迷期に政府に対し数々の意見を建白したことで知られています。仏僧本来の面目に帰るには、まずは戒を守り、自戒内省し、広く他宗の学問も修める兼学を提唱します。
伝通院、増上寺貫主として、縮刷大蔵経刊行にも着手。「仏法を以て宗旨を説くべし、宗旨を以て仏法を説くなかれ」と言われ、仏教の真理に基づいた説法をすべきであると戒めています。
また、肉食妻帯は法律上のことであって、僧侶のあるべき姿を真摯に守るべき事を要求して自らもそれを実践し、他宗の僧侶からも尊敬されたと言われています。
真言宗の釈雲照(一八二七ー一九〇九)は、古今未曾有の排仏の事態に至ったのは、みな僧侶自らの破戒濫行世間の名利に執着した罰であるとして、如来正法の戒定慧の三学に耐える者のみを留めて他を還俗せしめ仏教界の刷新を主張。しかし一方で、太政官に出頭して「仏法は歴代天子の崇信する所にして皇国の神道及び儒教の忠孝と相助け国家を擁護するものである」という趣旨の建白は数度に及び、また宗内でも護法に奔走。
一八八五年(明治十八)東京に出て、政府の大書記青木貞三、山岡鉄舟らの支援のもと目白僧園を建立します。戒律学校として平素四十名ほどの持戒堅固な僧侶がその薫陶を受け、その学徳と戒律を厳格に守る崇高なる人格に山県有朋、伊藤博文、大隈重信はじめ、将軍や財界人、学者に及ぶ蒼々たる人々が訪問し帰依しています。
雲照は、西洋哲学の方法論から仏教哲学を体系化した井上円了が創設した哲学館(後の東洋大学)で「仏教大意」を講じるなど、慈雲尊者の唱えた人間の原理としての「十善戒」を広く紹介。在家者のために十善会や夫人正法会を発足して社会の道徳的宗教的な教会として通仏教の立場から国民道徳の復興に貢献します。
北海道を含む全国に巡錫して法を説き、日露戦争時には満州にも布教。また晩年には西洋化する世間に対抗し神儒仏を一貫した精神をもって教育する徳教学校設立運動を起こしました。つづく