
はたして、私たちはこの般若心経をどのように受け取るべきなのであろうか。毎日お唱えしてきた心経が、まったくもって、価値のない経典であったとも言い難い。これからも唱える機会がある。また写経もなされるであろう。
そこで、私がかつて解釈した「般若心経私見」に述べたように、心経は、観音菩薩がサーリプッタ尊者に話された内容であって、私たち凡夫にとっては、空を悟るために、無とされたお釈迦様の根本教説をとても大事な教えとして受け入れるべきではないか。
自らの心を観察し、いかに生きるべきかと教えてくれる大事な教えをそこから展開し学ばせてくれるものと受け取ったらいかがであろうかと思う。「般若心経私見」の最後に私は、以下のように書いた。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~zen9you/pada/singyo.htm
「直観によって覚る、ということは簡単ではないのです。般若経典が成立した時代のインドのように戦乱に生きる民衆の荒廃した心にこそ、それは必要でありました。平和な、いまに生きる私たちにとって、それはとても難しい。
だからこそ、お釈迦様は、様々な手法によって、弟子たちに世の中のことを説き聞かせ諄々と説法を続けられたのではないでしょうか。私とは何か。なぜまわりに流され、落ち着かないのか。人生とはいかなるものか。いまをどう受けとめ、いかに生きるべきか。
このように身近で、なおかつ切実な問題について教えられたのがお釈迦様であり、それが心経で否定された、五蘊、十二処十八界、十二縁起、四諦八正道の教えでありました。
我が国で広く民衆に受け入れられた心経において、仏教の根本的教説が否定されたことにより、私たちはそれらを深く顧みることをしてこなかったのではないでしょうか。そのことによって、仏教とは神秘的直観によって獲得するものと受け取られてきたのではないかと思います。これによって仏教本来の教えを封印してしまった、と言っても言い過ぎではありません。
心経を生んだインドでは、どのようにこのお経が民衆に受け入れられていったのか。おそらく彼らは既にもっていた仏教の素養、自らの心を探究するという姿勢の上に、心経を吸収していったのではないか、と私は思います。
般若心経をいかに読むべきか。私たち凡夫にとって、否定された教説に冠された無の字は、南無の無と受け取っては如何なものかと私は思っています。心経を読誦して満足することなく、それら(南)無と唱える仏教本来の根本教説と向き合い、自ら心の内なるものにたずねいたるために示された教えであると受け取って欲しいのです。
そうして、がんばっている、つっぱっている自分、我を無くしていく、無我を実現していく、つまり自分の心の中に空を実現するための経典として心経を位置づけていきたいと思うのであります。」
最後に、スマナサーラ師が日本の私たち仏教徒にエールを送って下さっているように思える言葉を紹介し、この小論を締めくくりたい。
「それで大乗の世界で何をするかというと、般若心経のように呪文を唱えたり、南無妙法蓮華経と唱えたりするだけで終わってしまうのです。これは、世界宗教として仏教を見ると恥ずかしいことです。世界で太陽のごとく、一切の哲学思想宗教の上に立って、皆に打ち勝って勝利者になるべき仏教が、すごくだらしなくて、コソコソと隠れていなければならない状況に陥っているのです。」
「私たちテーラワーダ仏教徒は、仏教徒であることをすごく自慢して言うのです。その裏にどんなニュアンスが隠れているかとというと、私たちはバカではない。科学的な人間であって、迷信のかけらもない。怖いものはないという誇りなのです。」
「仏教は真理に基づき、どのようにすれば生命が幸せに至るのか、論理的、具体的に説くのです。真理に基づくので、仏教には普遍性があるのです」
「仏道は、自分の心を高める実践です。仏教徒は道徳を守り、慈悲の心で、最高の幸福にチャレンジするのです。本人が精進せずに幸福になるなどという甘い話ではありませんが、苦行の類は一切なく、誰にでも実践が可能です。」
いかがであろう。仏教を信奉する者として日本仏教徒にもその誇りと気概を持てるような教えの説き方をしなければいけないのだろうと思える。「私には仏教がある。そして日々実践している」と思えるだけでしあわせを感じられる日本仏教徒が一人でも多く増えていかなければいけないのであろう。
本書「般若心経は間違い?」は、般若心経を題材に、大乗仏教、日本仏教の問題点を鋭く指摘する指南書であり、同時に、本来の仏教とはいかなるものか、経典とは何か、仏教徒とはいかにあるべきかをやさしく教えてくれている。
他の仏教国に共通する仏教の常識、仏教徒として知らねばならない事々に、私たち日本人は誠に疎いことを知らない。本書は、身近な般若心経を通して、世界基準の仏教とはいかなるものかを学ぶ好著であると言えよう。是非、多くの人にじっくりと読んでいただきたい。
(↓よろしければ、一日一回クリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)

日記@BlogRanking
そこで、私がかつて解釈した「般若心経私見」に述べたように、心経は、観音菩薩がサーリプッタ尊者に話された内容であって、私たち凡夫にとっては、空を悟るために、無とされたお釈迦様の根本教説をとても大事な教えとして受け入れるべきではないか。
自らの心を観察し、いかに生きるべきかと教えてくれる大事な教えをそこから展開し学ばせてくれるものと受け取ったらいかがであろうかと思う。「般若心経私見」の最後に私は、以下のように書いた。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~zen9you/pada/singyo.htm
「直観によって覚る、ということは簡単ではないのです。般若経典が成立した時代のインドのように戦乱に生きる民衆の荒廃した心にこそ、それは必要でありました。平和な、いまに生きる私たちにとって、それはとても難しい。
だからこそ、お釈迦様は、様々な手法によって、弟子たちに世の中のことを説き聞かせ諄々と説法を続けられたのではないでしょうか。私とは何か。なぜまわりに流され、落ち着かないのか。人生とはいかなるものか。いまをどう受けとめ、いかに生きるべきか。
このように身近で、なおかつ切実な問題について教えられたのがお釈迦様であり、それが心経で否定された、五蘊、十二処十八界、十二縁起、四諦八正道の教えでありました。
我が国で広く民衆に受け入れられた心経において、仏教の根本的教説が否定されたことにより、私たちはそれらを深く顧みることをしてこなかったのではないでしょうか。そのことによって、仏教とは神秘的直観によって獲得するものと受け取られてきたのではないかと思います。これによって仏教本来の教えを封印してしまった、と言っても言い過ぎではありません。
心経を生んだインドでは、どのようにこのお経が民衆に受け入れられていったのか。おそらく彼らは既にもっていた仏教の素養、自らの心を探究するという姿勢の上に、心経を吸収していったのではないか、と私は思います。
般若心経をいかに読むべきか。私たち凡夫にとって、否定された教説に冠された無の字は、南無の無と受け取っては如何なものかと私は思っています。心経を読誦して満足することなく、それら(南)無と唱える仏教本来の根本教説と向き合い、自ら心の内なるものにたずねいたるために示された教えであると受け取って欲しいのです。
そうして、がんばっている、つっぱっている自分、我を無くしていく、無我を実現していく、つまり自分の心の中に空を実現するための経典として心経を位置づけていきたいと思うのであります。」
最後に、スマナサーラ師が日本の私たち仏教徒にエールを送って下さっているように思える言葉を紹介し、この小論を締めくくりたい。
「それで大乗の世界で何をするかというと、般若心経のように呪文を唱えたり、南無妙法蓮華経と唱えたりするだけで終わってしまうのです。これは、世界宗教として仏教を見ると恥ずかしいことです。世界で太陽のごとく、一切の哲学思想宗教の上に立って、皆に打ち勝って勝利者になるべき仏教が、すごくだらしなくて、コソコソと隠れていなければならない状況に陥っているのです。」
「私たちテーラワーダ仏教徒は、仏教徒であることをすごく自慢して言うのです。その裏にどんなニュアンスが隠れているかとというと、私たちはバカではない。科学的な人間であって、迷信のかけらもない。怖いものはないという誇りなのです。」
「仏教は真理に基づき、どのようにすれば生命が幸せに至るのか、論理的、具体的に説くのです。真理に基づくので、仏教には普遍性があるのです」
「仏道は、自分の心を高める実践です。仏教徒は道徳を守り、慈悲の心で、最高の幸福にチャレンジするのです。本人が精進せずに幸福になるなどという甘い話ではありませんが、苦行の類は一切なく、誰にでも実践が可能です。」
いかがであろう。仏教を信奉する者として日本仏教徒にもその誇りと気概を持てるような教えの説き方をしなければいけないのだろうと思える。「私には仏教がある。そして日々実践している」と思えるだけでしあわせを感じられる日本仏教徒が一人でも多く増えていかなければいけないのであろう。
本書「般若心経は間違い?」は、般若心経を題材に、大乗仏教、日本仏教の問題点を鋭く指摘する指南書であり、同時に、本来の仏教とはいかなるものか、経典とは何か、仏教徒とはいかにあるべきかをやさしく教えてくれている。
他の仏教国に共通する仏教の常識、仏教徒として知らねばならない事々に、私たち日本人は誠に疎いことを知らない。本書は、身近な般若心経を通して、世界基準の仏教とはいかなるものかを学ぶ好著であると言えよう。是非、多くの人にじっくりと読んでいただきたい。
(↓よろしければ、一日一回クリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)
日記@BlogRanking











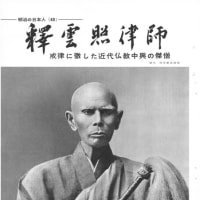
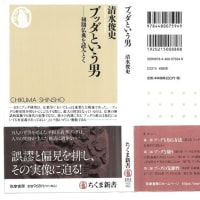














YAHOO!Blogでブログを書いています。
僕は仏教、神道等、宗教に触れずに育ちました25歳です。
数ヶ月前に、上座部仏教を知り、スマナサーラ長老の本を読んでいて、『般若心経は間違い?』も読みました。
僕が学校に通っていた頃は、エホバの証人が数名、創価学会が数名居た程度で、仏教徒(仏教を実践している)の方は居ない様に感じます。
78歳の祖父母は真言宗の様ですが、51歳の母は特に無い様です。
宗教は、親から子へと『教え』が受け継がれるものだと思いますが、今の社会は、それが無いのではないでしょうか?
仏教に触れる機会が無い上に、新興宗教の変な事件で『宗教=あやしい』があるのだと思います。
僕は仏教の知識が全くないので、お経に意味がある事さえ知りませんでした。
数年前に知人のお葬式に出席したのですが、お坊さんはお経を唱えるだけで帰りました。
お葬式では『法話』はしないのでしょうか?
ちなみに、僕は、こころを育てる様に、仏教を少しですが実践しています。
無知なコメントですが、失礼しました。勉強させて頂きます。
「痛み」など最初から生じてなく、消えてもいない。行中に痛みの思考から解放されるだけです。見聞きする「光や音」は情報として目と耳から伝わる電気信号みたいなもの・・・頭の中だけで生起しています。お釈迦様は「一切は幻だ」と様々な喩えで語られましたが、皆、思考が邪魔をしてその確信の部分に至らない。
般若心経に書かれているのは「道」です。地図のようなものです。観自在菩薩は道を歩んでいる行者のことです。食べたことのないものの味は語ることが出来ないのと同じように、行ったことのない世界を語ることは出来ません。
しかし、多くの人が究極の道(般若心経)を訳している。訳す行為は、その道に逆行しているようなもので、挙句の果てには「心経は嘘だ」と書かれる。訳すことは分別によって粉々にした真理を復元しているようなものです。英語から日本語に訳すのとは訳が違う。
般若心経が語りかける道は原点に向かう道です。秘密は「時(三摩耶)」の中にあります。一切を知識として捉えるのであれば、道に逆行してしまう。知識は壊れた真理を再構築したもので空の雲のようなものです。(諸行無常)
一般の人にこんなことを言ったって忙しい喧騒の中、分かりそうにないので書かせていただきました。
お葬式ではあまりお話しする時間がないのです。ですから、私の場合はお通夜の時とか、初七日の法要の後とか、または七日参りの際にお話しするようにしています。
飾りを見てものを話すのは僧侶ではありません。あなたもその類いですか?僧侶は職業ではない・・・。
顕現するものに問題はありません。執着や怒り(煩悩)の問題なのですよ。知識では分かっていても、執着や怒りから心を支配されるのが早いのです。私のコメントを読んで、何か恐れが生じたのですか?あり得ないことを考えて心に怪我をしてませんか?
話が出来る人かと思っていました。残念です。コメントしておきました。
http://blogs.yahoo.co.jp/moment_of_setuna/MYBLOG/guest.html
これについてブログに書きました。
No.1
http://blogs.yahoo.co.jp/prajunya777/4444016.html
No.2
http://blogs.yahoo.co.jp/prajunya777/4453086.html
テーラヴァーダ仏教諸国も日本と似たような事情があるような気がします。つまり、一般人(世俗の人)は、呪文で得られるご利益のようなものを求め、テーラヴァーダ仏教はそれに答えているというか、上手く利用しているような気がするのです。
前田恵学先生の本「現代スリランカの上座仏教」でも、庶民の仏教と出家(僧)の仏教が違うということについて同様の説明があります。
般若心経は、そういう庶民の仏教の経典なのではないかと思います。したがって、ご住職のおっしゃるように、無理に般若心経を仏教聖典として崇める必要はないのではないでしょうか。読んですっきりしない般若心経の(無理な)読み方を勧めるよりも、アーガマのいずれかの経を選んで示したほうがずっと善いような気がします。しかし、いずれにしろ、スマナサーラ師も言い、ご住職もおっしゃるように(十不浄と死随念の説明や般若心経についてのここの説明)、お釈迦様の仏教とは、本来、出家に可能なものであり、ほとんどの在家にとっては、功徳を積むこと、天など在家の希望する来世を目指すことが限界であったと思います。これは、現代でも変わらないのではないでしょうか。こういう限界に不満な在家の期待に応えたのが大乗のような気がします。だから、最初から無理があったような気がします。ご住職は、出家と在家が、全く異なる生活をしているのもかかわらず、共に、涅槃にいたれると本気でお考えでしょうか。抜け道を通る以外、在家が涅槃に到るのは不可能だと思います。般若心経のような呪文を使う以外は。ところで、ご住職は涅槃に到っていらっしゃるのでしょうか。
順に私なりのお答えをさせていただきます。
>テーラヴァーダ仏教は、本当に日本の仏教に比べ、お釈迦様当時の仏教に近いでしょうか?私は疑問を持っています。
今日仏教の歴史はほぼ解明されてきていると思っています。その歴史、特に経典の起こり、そして大乗運動が生じ大乗経典が作成されたということは疑いえないことと存じます。
>つまり、一般人(世俗の人)は、呪文で得られるご利益のようなものを求め、テーラヴァーダ仏教はそれに答えているというか、上手く利用しているような気がするのです。
前田恵学先生の本「現代スリランカの上座仏教」でも、庶民の仏教と出家(僧)の仏教が違うということについて同様の説明があります。
確かに、庶民の求めるものを与えるような形で出家の仏教と違うものが提示されることもあるでしょう。しかし、仏教としての教えを提示する場合には、きちんとお釈迦様の教えの根幹を説いていると思うのですが。
>般若心経は、そういう庶民の仏教の経典なのではないかと思います。
庶民の仏教の教えとして受け入れるのはよいのですが、それを経典として、あたかも、お釈迦様が説いたような、形式を取るので困ったことになるのだと思います。きちんと、これは在家の為ですよ、仏教ではないと但し書きがあれば何も問題はないと思います。そうではなくて、別のありがたい仏教があるのだというようなことで、大乗のお坊さんができ、お釈迦様の教えを否定するような書き方をするので問題なのだと思います。
>お釈迦様の仏教とは、本来、出家に可能なものであり、ほとんどの在家にとっては、功徳を積むこと、天など在家の希望する来世を目指すことが限界であったと思います。これは、現代でも変わらないのではないでしょうか。こういう限界に不満な在家の期待に応えたのが大乗のような気がします。だから、最初から無理があったような気がします。
そうでしょうか。お釈迦様の教えは十分に在家の人たちにも身近に役に立つものばかりだと思いますが。実際に、アメリカやヨーロッパでは、鬱をはじめとする精神療法に仏教のヴィパッサナーの瞑想が取り入れられ、マインドフルネス認知療法として効果を上げていて、医学的な研究がかなり前から始まっています。日本でもやっとそれらの研究書が翻訳され始めています。
>ご住職は、出家と在家が、全く異なる生活をしているのもかかわらず、共に、涅槃にいたれると本気でお考えでしょうか。抜け道を通る以外、在家が涅槃に到るのは不可能だと思います。般若心経のような呪文を使う以外は。ところで、ご住職は涅槃に到っていらっしゃるのでしょうか。
私はまだまだ初歩の修行の身です。ですが、何が正しく何が間違っているかということをある程度分かっていて、正しい教えに基づいて道を歩んでいきたいと思っています。在家で修行を重ね、ある程度まで行けば、出家しなくてはいけない段階があるようです。ですが、その段階まで行くのは、現代にあっては、テーラワーダの出家の方々でも大変難しい時代であることは間違いないと思われます。ところで、般若心経のような呪文を唱えて涅槃に行かれたという方をご存じですか。それは本当に簡単な道なのでしょうか。