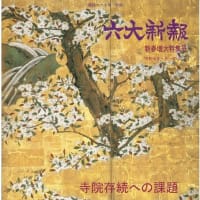四国遍路とは何だろう
先週18日東京のお寺の御開帳法会に参加させてもらいました。一時間ほどの法会のあと恒例の四国霊場のお砂踏みをしました。きれいにお寺の名前が書かれた一尺四方ほどの布団に御砂を入れられ、一番札所から八八番へ、そして最後に高野山の御砂を踏んで結願となる御砂踏み霊場が本堂内陣に特設されていて、参詣の皆様と共に御宝号をお唱えしつつ歩きました。
実は、こちら國分寺でも十年ほど前までは4月の21日にお砂踏みをしていました。本堂内外陣にぐるっと八十八箇所のお砂を置いて掛け軸をその前に取り付けて、護摩供の後皆さんで御宝号を唱え巡っていました。
また、30年も前になりますが、実際に四国を歩いて遍路したのも4月でした。4月の後半から、一度目は36日、二度目は39日かけて歩きました。その間車の御接待なども受けたりしましたから、それがなければ余計に三、四日は要していたでしょう。そんなこともあり、4月になると四国霊場を思い出し、またゆっくり歩きたいと思います。
二度目に歩いて遍路したとき、妙絹尼を愛媛の番外札所・鎌大師に訪ねたことがありました。お四国病で尼にまでなってしまいました、そう言われてました。関東から毎年、春になると四国にきて、公共のバスや電車で近くまで行き、あとは歩いて遍路するという方法で歩かれた方でした。気がつけば尼になり、縁あって鎌大師の庵住さんになられていたとか。
団体参拝のバスや車での巡拝は点を結ぶ巡拝ですが、歩いて巡ると、線となり面や立体として四国のお参りを体感することができます。お大師さんが歩かれた道であり、その前には行基さんや沢山の修験者、数数え切れないお遍路さんたちが修行した道です。そうした古の遍路行者たちの霊気をいまも感じられる遍路道を踏み歩くと、ふとタイムスリップして、現実世界から抜け出したように感じられるものです。
今もお遍路さんは菅笠をかぶり白装束に金剛杖をもって歩きます。バスで巡拝する方々も同様に皆さん白装束で参るのが慣習となっています。これはご存じのとおり、死装束で、杖は途中で息絶えたら墓標にしました。そうした昔からのお遍路さんのスタイルが今に伝わっているのですが、それはどういうことかと言えば、四国遍路とは、つまり生き直す、生まれ変わるための旅だったということです。お大師様への信仰心ばかりか、生きるのに疲れ、人生に絶望し、救いを求めて訪れる人も多かったことでしょう。
だから四国巡拝はいまも絶大な人気があり、人々の関心を失わないのではないかとも思われます。海外からも精神世界に関心のある方たちが歩きに来る場所でもあります。私も以前インドのリシケシで出会った外国の人とばったり遍路道で出会ったこともありました。
遍路道を歩くと、四国の人たちは何かしら御接待として、果物や菓子、飲み物を下さったり、時には小銭をそれらにのせて下さったりします。それは自分ができない遍路を外から来てして下さっているお遍路さんへの、供養であり、賛同する気持ちを添えられています。日常を離れ、四国に来て信仰をもって修行する、遍路する人に対する励ましであり、同じ気持ちをもって生きていることを表すものなのかもしれません。
私たちも時に日常を離れ、自分ひとりになり、ものを考える、人生を振り返る、日頃の我のあり方に思いをはせる、そんな時間が必要ではないかと思います。毎日の生活に埋没して、あっという間に年をとっています。気がつけば還暦をすぎて、年金までもらう年になってしまいます。生きるとはなにか、どういうことなのか、静かに人生を振り返ることも必要であろうかと思います。
旅は誰かと何人かで行きたいと思い勝ちですが、四国の遍路は、特に歩き遍路は一人で参ることをお勧めします。一人になり考える、考えて考えて何も考えられなくなり、ただ足下だけを見て歩く、そうした体験もよいものです。
私ももう一度ゆっくり四国を歩いて遍路したいと思います。
(↓よろしければ、一日一回クリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
先週18日東京のお寺の御開帳法会に参加させてもらいました。一時間ほどの法会のあと恒例の四国霊場のお砂踏みをしました。きれいにお寺の名前が書かれた一尺四方ほどの布団に御砂を入れられ、一番札所から八八番へ、そして最後に高野山の御砂を踏んで結願となる御砂踏み霊場が本堂内陣に特設されていて、参詣の皆様と共に御宝号をお唱えしつつ歩きました。
実は、こちら國分寺でも十年ほど前までは4月の21日にお砂踏みをしていました。本堂内外陣にぐるっと八十八箇所のお砂を置いて掛け軸をその前に取り付けて、護摩供の後皆さんで御宝号を唱え巡っていました。
また、30年も前になりますが、実際に四国を歩いて遍路したのも4月でした。4月の後半から、一度目は36日、二度目は39日かけて歩きました。その間車の御接待なども受けたりしましたから、それがなければ余計に三、四日は要していたでしょう。そんなこともあり、4月になると四国霊場を思い出し、またゆっくり歩きたいと思います。
二度目に歩いて遍路したとき、妙絹尼を愛媛の番外札所・鎌大師に訪ねたことがありました。お四国病で尼にまでなってしまいました、そう言われてました。関東から毎年、春になると四国にきて、公共のバスや電車で近くまで行き、あとは歩いて遍路するという方法で歩かれた方でした。気がつけば尼になり、縁あって鎌大師の庵住さんになられていたとか。
団体参拝のバスや車での巡拝は点を結ぶ巡拝ですが、歩いて巡ると、線となり面や立体として四国のお参りを体感することができます。お大師さんが歩かれた道であり、その前には行基さんや沢山の修験者、数数え切れないお遍路さんたちが修行した道です。そうした古の遍路行者たちの霊気をいまも感じられる遍路道を踏み歩くと、ふとタイムスリップして、現実世界から抜け出したように感じられるものです。
今もお遍路さんは菅笠をかぶり白装束に金剛杖をもって歩きます。バスで巡拝する方々も同様に皆さん白装束で参るのが慣習となっています。これはご存じのとおり、死装束で、杖は途中で息絶えたら墓標にしました。そうした昔からのお遍路さんのスタイルが今に伝わっているのですが、それはどういうことかと言えば、四国遍路とは、つまり生き直す、生まれ変わるための旅だったということです。お大師様への信仰心ばかりか、生きるのに疲れ、人生に絶望し、救いを求めて訪れる人も多かったことでしょう。
だから四国巡拝はいまも絶大な人気があり、人々の関心を失わないのではないかとも思われます。海外からも精神世界に関心のある方たちが歩きに来る場所でもあります。私も以前インドのリシケシで出会った外国の人とばったり遍路道で出会ったこともありました。
遍路道を歩くと、四国の人たちは何かしら御接待として、果物や菓子、飲み物を下さったり、時には小銭をそれらにのせて下さったりします。それは自分ができない遍路を外から来てして下さっているお遍路さんへの、供養であり、賛同する気持ちを添えられています。日常を離れ、四国に来て信仰をもって修行する、遍路する人に対する励ましであり、同じ気持ちをもって生きていることを表すものなのかもしれません。
私たちも時に日常を離れ、自分ひとりになり、ものを考える、人生を振り返る、日頃の我のあり方に思いをはせる、そんな時間が必要ではないかと思います。毎日の生活に埋没して、あっという間に年をとっています。気がつけば還暦をすぎて、年金までもらう年になってしまいます。生きるとはなにか、どういうことなのか、静かに人生を振り返ることも必要であろうかと思います。
旅は誰かと何人かで行きたいと思い勝ちですが、四国の遍路は、特に歩き遍路は一人で参ることをお勧めします。一人になり考える、考えて考えて何も考えられなくなり、ただ足下だけを見て歩く、そうした体験もよいものです。
私ももう一度ゆっくり四国を歩いて遍路したいと思います。
(↓よろしければ、一日一回クリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)