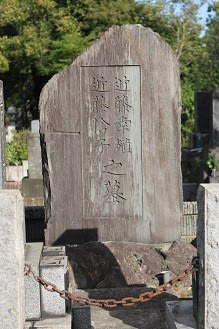世の中に歴史家という人種は数多存在しているが、その中にあって個人的にもっとも波長が合っている気がしているのが、本書の著者家近良樹先生(大阪経済大学特別招聘教授)である。
第一章では「歴史学者のしごと」と題して、小説と歴史学の違いを説く。「時代小説家の書いたものを全面的に真実だと受けとめている人が多い」と嘆くが、この背景には「「創作」話を、あたかも、この世で実際に起こった出来事であったかのように読者に思わせる、時代小説家の筆力(力量)が大いに関係している」のである。史料的裏付けに基づいて記述するのが歴史家であり、史料にない空白部分を豊かな想像力で補うのが小説家の仕事である。
実在の人物を題材にした小説では、読者は「これが本当にあったこと」だと思うことで、ことさら感動を催すものであり、作家はその作用を利用するために、まるで「本当にあったこと」のように描くのである。
話は少し逸れてしまうが、先日最終回が放映された大河ドラマ「西郷どん」は、ほぼ八割・九割が創作であった。それでも私が最後までこの番組を視聴し続けたのは、出演俳優の熱演に心を打たれたからに他ならない。
脚本において、安政の大獄、寺田屋事件、長州征伐、王政復古のクーデター、戊辰戦争、岩倉使節団、明治六年政変、西南戦争、大久保暗殺という「点」は史実であるが、点と点を結ぶ線はほぼ全てが創作と断言してよい。私は心の中で「そりゃないだろ」と呆れながらも、熱演に引きずられて結局最終回まで視ることになった。それにしても、どれほどの視聴者がこれを創作と思ってみているのだろうか。せめて「これは歴史を題材としたフィクションです」と断りを入れるのが、公共放送としての良心ではないか。
西郷菊次郎の子供時代を演じて一躍人気者となった城桧吏君はインタビューに答えて「歴史って面白いなと思いました」と語っているが、正確にいえば「歴史が面白い」のではなく、「歴史の名を借りた物語」が面白いのであって、これを混同してはいけない。NHKの影響力が大きいだけに、大河ドラマをみてこれが真実だと思いこむ日本人が大量発生することを危惧している。
第二章「なぜ西郷隆盛は人気者なのか」では、筆者は若者の歴史離れを嘆く。「日露戦争のことをまったく知らない学生が現れた」「織田信長が幕末維新期に活躍したと信じている学生」が存在していることもわかり、ショックを受けたと告白している。さらに株式会社ドワンゴの夏野剛氏が「日本人のプログラミング力を上げるうえで、別に日本史なんか教えなくてもいい」といった発言をしたことを取り上げている。筆者は「そのあまりのあっけらかんとした無邪気な発言に、ある種の哀しみ、淋しさを覚え」たと嘆く。
夏野氏の発言がどのような文脈で発せられたのか、本書では詳しく述べられていないが、いずれにせよ、世の中、歴史離れが進み、それが行き過ぎて一部では歴史蔑視の風潮すら生まれているのかもしれない。夏野氏の発言は、氷山の一角であろう。
筆者は「プログラマーにも日本史は必要だ」「過去を知らなければ現在は分からない」「先人の生き方から学べ」と掻き口説くように主張する。筆者の叫びは悲痛ですらある。私などはその国の歴史は民族の背骨のようなものであり、歴史を軽視する民族に将来はないと信じている(なかなかそれを論理的に説明せよといわれると難しいが…)。歴史を学ばなくてはいけないのは何もプログラマーに限ったことではなく、全ての国民にとって必須科目であろう。
筆者によれば、江戸期から明治期にかけて生きた日本のリーダーたちは「名を後世に残すとともに後世の歴史家からどのように自分のとった行動が評価されるかとひどく気にしていて生きた」という。
たとえば、文久二年(1862)の寺田屋騒動で壮絶な斬り合いの結果、落命した薩摩藩士、文久三年(1863)の生野挙兵で散った秋月藩の戸原夘橘や長州藩士、慶応四年(1868)の神戸事件で切腹を命じられた瀧善三郎、堺事件の土佐藩士ら、いずれも鮮烈な印象を後世に残しているが、彼らはいずれも名を惜しみ、潔い最期を演出して、そのとおり死んでいった。自らの美意識に従って死ぬことを非常に意識していた。「時代の空気」といってしまえば身もフタもないが、少しは現代に生きる我々も見習いたいものである。さすれば、意地の汚い詐欺事件だとか、身勝手極まりない殺人事件とか、自己中心的なあおり運転といったみっともない事件も少しは減るであろう。
第三章「「支配者の歴史」から「民衆の歴史」へ」では、一世を風靡したマルクス主義史観について解説する。マルクス主義史観とは、「階級闘争の末に人類の歴史が進歩発展し、最終的には労働者階級が資本家階級に勝利し、社会主義体制が誕生する」というものである。しかし、現実の歴史が物語るように、資本家階級を打倒して社会主義が実現した例はないし、資本主義は今も健在である。さらにいえば、社会主義を国是としている国であっても資本主義的体制をとらないと現代社会で生き残れないのは自明である。
筆者は、「勝者中心の歴史観に違和感がある」「歴史の多様性がなかなか認められない」と、マルクス主義史観を批評する。私も人間(個人)不在の史観には興味も持てないし、納得もできない。しかし、ロシア革命(1917)以来、マルクス主義史観は多くの若者に支持され、あたかも「絶対的真理」となった観があった。筆者はここで佐々木寛司という研究者を紹介する。マルクス主義史観に対する批判を許さないような時代風潮の中にあって、彼は健全な批判精神を発揮したというのである。流れに竿をさす勇気も称賛に価するが、それを許す空気というのも大事だと思う。
第四章「学校では教えてくれない日本史」では、「なぜ各地の戦国大名の墓が高野山にあるのか」「なぜ一揆で鉄砲が使われなかったのか」「なぜペリー来航は特別視されるのか」といった問いを通じて、歴史を勉強する楽しみを説く。
第五章「過去と未来をつなぐ」では歴史離れが進む我が国と比べ、中国も韓国も多くの授業時間を歴史教育に割いている事実を指摘する。先方の教育内容の是非はともかく、日々せっせと反日教育をやっているというのに、あまりに我が国は無防備であろう。
歴史マニアを自認する私でも、日露戦争から後の歴史になると途端に知識がしぼんでしまう。昭和史に至ってはさっぱりスットコドッコイである。本当に「歴史に学ぶ」のであれば、通常の日本史の授業以外に、現代史という授業があっても良いのではないか。
筆者は、司馬作品には「創作」以外にも明らかな事実誤認が多く含まれていると批判する一方で、司馬遼太郎の修辞能力を絶賛する。例にあげたのは「街道をゆく」である。司馬遼太郎はとても無口な人を「樋から、雨上がりのあとポツリポツリと落ちる水滴のような話し方をする人」と表現した。司馬作品を読んでいると、この手の見事な修辞に随所で出会う。これも司馬作品の魅力の一つとなっている。歴史家であれば、単に「寡黙な人」で済ませてしまうところだろう。歴史家にも多少の文学性が必要というのが、筆者の結論である。確かにもう少し読者に面白く読ませる工夫が必要かもしれないが、あまり無用な修辞が目につく歴史書も「信用性」に欠けるかもしれない。
筆者は、歴史を学ぶこと、さらに読書の効用を熱心に説く。これが、家近先生が本書で一番いいたかったことかもしれない。歴史を学ぶと「原因と結果で物事を合理的に考える習慣が身につく」「論理的に自分たちの考え(方針)を相手側に伝え」「雑談力がつく」、「現在を自分が生きている時代の特色がよく理解できるようになる」「先人の生き方を大いに参考にできる」「歴史を学ぶことで「人物」を育てる」という。
読書の効用としては「自分の視点や思考の幅が広がる」とか「人を見る目を養ってくれる」「先人が長いあいだかかって営々と培ってきた知識を借用することで、時間を無駄にしないで済みます」「退屈がまぎれる」「人生を歩むうえでの重要なヒントを得られる」といった点を挙げる。
ほかにもあるかもしれないが、歴史を学ぶこと、本を読むことで得られる効用は、筆者のいうとおりであろう。しかし、そのような効用を得ようとして最初から歴史を学ぼうという人もそう多くはあるまい。私も単純に歴史が楽しいから、興味があるから、知りたいからのめり込んだのであって、それ以上でも以下でもない。その結果、特別な知識や教養が得られたとしてもそれは結果でしかない。そういう意味では、ほかの趣味と大差はない。知れば知るほど面白いのが歴史であり、もっと多くの人に興味を持ってほしいと思う次第である。
読書も同じ。本を読めばそれだけ知識が広がり、人生にもプラスになることは間違いないが、多くの読書家は別に効用ばかりを求めて本を読んでいるわけではなかろう(だったらノウハウ本ばかりが売れることになってしまう)。
ただ一つ言えるのは、同じ時間を過ごすのであれば、テレビ・ゲームなどで無為に浪費するより、読書した方が余程良いということである。人生には限りがあるのだから。
第一章では「歴史学者のしごと」と題して、小説と歴史学の違いを説く。「時代小説家の書いたものを全面的に真実だと受けとめている人が多い」と嘆くが、この背景には「「創作」話を、あたかも、この世で実際に起こった出来事であったかのように読者に思わせる、時代小説家の筆力(力量)が大いに関係している」のである。史料的裏付けに基づいて記述するのが歴史家であり、史料にない空白部分を豊かな想像力で補うのが小説家の仕事である。
実在の人物を題材にした小説では、読者は「これが本当にあったこと」だと思うことで、ことさら感動を催すものであり、作家はその作用を利用するために、まるで「本当にあったこと」のように描くのである。
話は少し逸れてしまうが、先日最終回が放映された大河ドラマ「西郷どん」は、ほぼ八割・九割が創作であった。それでも私が最後までこの番組を視聴し続けたのは、出演俳優の熱演に心を打たれたからに他ならない。
脚本において、安政の大獄、寺田屋事件、長州征伐、王政復古のクーデター、戊辰戦争、岩倉使節団、明治六年政変、西南戦争、大久保暗殺という「点」は史実であるが、点と点を結ぶ線はほぼ全てが創作と断言してよい。私は心の中で「そりゃないだろ」と呆れながらも、熱演に引きずられて結局最終回まで視ることになった。それにしても、どれほどの視聴者がこれを創作と思ってみているのだろうか。せめて「これは歴史を題材としたフィクションです」と断りを入れるのが、公共放送としての良心ではないか。
西郷菊次郎の子供時代を演じて一躍人気者となった城桧吏君はインタビューに答えて「歴史って面白いなと思いました」と語っているが、正確にいえば「歴史が面白い」のではなく、「歴史の名を借りた物語」が面白いのであって、これを混同してはいけない。NHKの影響力が大きいだけに、大河ドラマをみてこれが真実だと思いこむ日本人が大量発生することを危惧している。
第二章「なぜ西郷隆盛は人気者なのか」では、筆者は若者の歴史離れを嘆く。「日露戦争のことをまったく知らない学生が現れた」「織田信長が幕末維新期に活躍したと信じている学生」が存在していることもわかり、ショックを受けたと告白している。さらに株式会社ドワンゴの夏野剛氏が「日本人のプログラミング力を上げるうえで、別に日本史なんか教えなくてもいい」といった発言をしたことを取り上げている。筆者は「そのあまりのあっけらかんとした無邪気な発言に、ある種の哀しみ、淋しさを覚え」たと嘆く。
夏野氏の発言がどのような文脈で発せられたのか、本書では詳しく述べられていないが、いずれにせよ、世の中、歴史離れが進み、それが行き過ぎて一部では歴史蔑視の風潮すら生まれているのかもしれない。夏野氏の発言は、氷山の一角であろう。
筆者は「プログラマーにも日本史は必要だ」「過去を知らなければ現在は分からない」「先人の生き方から学べ」と掻き口説くように主張する。筆者の叫びは悲痛ですらある。私などはその国の歴史は民族の背骨のようなものであり、歴史を軽視する民族に将来はないと信じている(なかなかそれを論理的に説明せよといわれると難しいが…)。歴史を学ばなくてはいけないのは何もプログラマーに限ったことではなく、全ての国民にとって必須科目であろう。
筆者によれば、江戸期から明治期にかけて生きた日本のリーダーたちは「名を後世に残すとともに後世の歴史家からどのように自分のとった行動が評価されるかとひどく気にしていて生きた」という。
たとえば、文久二年(1862)の寺田屋騒動で壮絶な斬り合いの結果、落命した薩摩藩士、文久三年(1863)の生野挙兵で散った秋月藩の戸原夘橘や長州藩士、慶応四年(1868)の神戸事件で切腹を命じられた瀧善三郎、堺事件の土佐藩士ら、いずれも鮮烈な印象を後世に残しているが、彼らはいずれも名を惜しみ、潔い最期を演出して、そのとおり死んでいった。自らの美意識に従って死ぬことを非常に意識していた。「時代の空気」といってしまえば身もフタもないが、少しは現代に生きる我々も見習いたいものである。さすれば、意地の汚い詐欺事件だとか、身勝手極まりない殺人事件とか、自己中心的なあおり運転といったみっともない事件も少しは減るであろう。
第三章「「支配者の歴史」から「民衆の歴史」へ」では、一世を風靡したマルクス主義史観について解説する。マルクス主義史観とは、「階級闘争の末に人類の歴史が進歩発展し、最終的には労働者階級が資本家階級に勝利し、社会主義体制が誕生する」というものである。しかし、現実の歴史が物語るように、資本家階級を打倒して社会主義が実現した例はないし、資本主義は今も健在である。さらにいえば、社会主義を国是としている国であっても資本主義的体制をとらないと現代社会で生き残れないのは自明である。
筆者は、「勝者中心の歴史観に違和感がある」「歴史の多様性がなかなか認められない」と、マルクス主義史観を批評する。私も人間(個人)不在の史観には興味も持てないし、納得もできない。しかし、ロシア革命(1917)以来、マルクス主義史観は多くの若者に支持され、あたかも「絶対的真理」となった観があった。筆者はここで佐々木寛司という研究者を紹介する。マルクス主義史観に対する批判を許さないような時代風潮の中にあって、彼は健全な批判精神を発揮したというのである。流れに竿をさす勇気も称賛に価するが、それを許す空気というのも大事だと思う。
第四章「学校では教えてくれない日本史」では、「なぜ各地の戦国大名の墓が高野山にあるのか」「なぜ一揆で鉄砲が使われなかったのか」「なぜペリー来航は特別視されるのか」といった問いを通じて、歴史を勉強する楽しみを説く。
第五章「過去と未来をつなぐ」では歴史離れが進む我が国と比べ、中国も韓国も多くの授業時間を歴史教育に割いている事実を指摘する。先方の教育内容の是非はともかく、日々せっせと反日教育をやっているというのに、あまりに我が国は無防備であろう。
歴史マニアを自認する私でも、日露戦争から後の歴史になると途端に知識がしぼんでしまう。昭和史に至ってはさっぱりスットコドッコイである。本当に「歴史に学ぶ」のであれば、通常の日本史の授業以外に、現代史という授業があっても良いのではないか。
筆者は、司馬作品には「創作」以外にも明らかな事実誤認が多く含まれていると批判する一方で、司馬遼太郎の修辞能力を絶賛する。例にあげたのは「街道をゆく」である。司馬遼太郎はとても無口な人を「樋から、雨上がりのあとポツリポツリと落ちる水滴のような話し方をする人」と表現した。司馬作品を読んでいると、この手の見事な修辞に随所で出会う。これも司馬作品の魅力の一つとなっている。歴史家であれば、単に「寡黙な人」で済ませてしまうところだろう。歴史家にも多少の文学性が必要というのが、筆者の結論である。確かにもう少し読者に面白く読ませる工夫が必要かもしれないが、あまり無用な修辞が目につく歴史書も「信用性」に欠けるかもしれない。
筆者は、歴史を学ぶこと、さらに読書の効用を熱心に説く。これが、家近先生が本書で一番いいたかったことかもしれない。歴史を学ぶと「原因と結果で物事を合理的に考える習慣が身につく」「論理的に自分たちの考え(方針)を相手側に伝え」「雑談力がつく」、「現在を自分が生きている時代の特色がよく理解できるようになる」「先人の生き方を大いに参考にできる」「歴史を学ぶことで「人物」を育てる」という。
読書の効用としては「自分の視点や思考の幅が広がる」とか「人を見る目を養ってくれる」「先人が長いあいだかかって営々と培ってきた知識を借用することで、時間を無駄にしないで済みます」「退屈がまぎれる」「人生を歩むうえでの重要なヒントを得られる」といった点を挙げる。
ほかにもあるかもしれないが、歴史を学ぶこと、本を読むことで得られる効用は、筆者のいうとおりであろう。しかし、そのような効用を得ようとして最初から歴史を学ぼうという人もそう多くはあるまい。私も単純に歴史が楽しいから、興味があるから、知りたいからのめり込んだのであって、それ以上でも以下でもない。その結果、特別な知識や教養が得られたとしてもそれは結果でしかない。そういう意味では、ほかの趣味と大差はない。知れば知るほど面白いのが歴史であり、もっと多くの人に興味を持ってほしいと思う次第である。
読書も同じ。本を読めばそれだけ知識が広がり、人生にもプラスになることは間違いないが、多くの読書家は別に効用ばかりを求めて本を読んでいるわけではなかろう(だったらノウハウ本ばかりが売れることになってしまう)。
ただ一つ言えるのは、同じ時間を過ごすのであれば、テレビ・ゲームなどで無為に浪費するより、読書した方が余程良いということである。人生には限りがあるのだから。