中国、パキスタン、アフガン経済圏の出現は、日本にとって、セカンドチャイナマーケットに変貌する可能性が極めて高い、豪州レベルの資源領域が誕生する可能性も存在する、
この論考は「パキスタンの恐怖」のタイトルで終わっているが、9.11以降の、米国による対テロアフガン戦争の開始よって、局面は大きな変化の過程にある、パキスタンの対米従属的な、対テロ.アフガン戦争への協力、参加によって、パキスタン国内は、親米派と反米派の2極へ分化され、民衆の動向は反米へ向かって加速的に収斂されつつある、NATO、14万人と米、9万人(民間の傭兵を含めれば、10万人を越える?)大軍がその1/5といわれる無人兵器を駆使して、アフガン、パキスタン領域の地域せん滅的戦略を拡大し続けている、以上、民衆は反米,反NATOに向かう、憎悪と怨恨は執念化しつつ地下茎のネットを肥大、強化することになり、イラク同様の、その領域にはアメリカはいられない、という異国化をパキスタンにもたらしている、パキスタン民衆に親米化、協米化をもたたらすことは絶望に近い、米もNATOもアフガン撤退は不可欠で、不可避的である、NATOの母国であるEUそのものが瓦解に向けて進行している、強硬派の仏のサルコジの再選も困難視される現状である、アフガン、パキスタン、中国3国の鉄の結合が生まれる可能性が高い、アフガン、パキスタンが中国の経済圏と言うことになれば、両国の経済成長は一挙に加速化するであろうし、それはまた日本にとての、セカンドチャイナマーケットになる可能性が高い、
中国とパキスタン:「全天候方の友好関係」
一方、三次にわたる印パ戦争で、いずれにも敗北を喫したパキスタンにとっての仮想敵は、一貫してインドである。パキスタンの国家安全保障戦略は、いかにして隣の大国・インドの脅威に対抗して国家としての「生存」を図るかにある。インドの脅威に対抗するために、パキスタンは核兵器開発、通常戦力の充実による自己防衛力を強化する一方で、米国をはじめ西側諸国との友好協力関係を維持、特に中国(インドの仮想敵)との友好協力関係は40年ほど安定的に継続している。両国ともがそれぞれ国境に接しているインドを「共通の脅威」とみなし、「敵の敵は味方」の関係にあることがその背景にある。
その見返りにパキスタンは、イラン、サウジアラビアなど中東イスラム諸国と中国との関係作りの橋渡し役を果たし、88年の中国製ミサイルのサウジ輸出に道を開いた。パキスタンは中国にとって、「中東イスラム世界に開かれた窓」の役割も果たしたのだ。89年の天安門事件で中国が国際的非難を浴びでいる中にあっても、パキスタンは外務次官を訪中させて「中国支持」を表明した。中国はこれに感謝し、89年11月に李鵬首相がパキスタンを訪問、300メガワッドの原子力発電所のパキスタンへの売却を発表した。こうした中国とパキスタンとの40年ほどにわたる極めて安定した緊密な戦略的関係は、「全天候型友好関係」と呼ばれ、隣の大国・インドに対抗する上で、欠くことのできない柱として、パキスタンの安全保障・外交政策の中に位置づけられている。
・インドにとって中国脅威なのか
1998年5月、インドとパキスタンが相次いで地下核実験を実施した。冷戦が終結し、膨大な核兵器を保有した米ソの軍事対決が終焉を迎え、いよいよ「経済重視」の平和な国際社会が実現されるという期待か日増しに高まりつつある中だっただけに、世界中が驚愕し、大きなショックをうけた。とくに、核兵器のこれ以上の拡散に歯止めをかけることをめざした「核拡散防止条約」(NPT)の無期限延長が1995年5月に決定され、翌96年9月にはすべての核実験を禁止した「包括的核実験禁止条約」(CTBT)が国連総会に圧倒的多数で採択されて、国際社会の核不拡散体制作りが順調に進展していたと皆が考えていただけに、インドとパキスタンの核実験は、こうした世界の流れに真っ向から挑戦する行動として国際社会の激しい非難を浴びた。
98年5月、インドは24年ぶりに核実験を行った。その直後にインドのバジパイ首相は、クリントン大統領や橋本竜太郎首相など主要国の指導者にあてて書簡を送った。この中でバジパイ首相は、インドは核実験に踏み切らざるを得なかった理由として、次の三点を挙げた。
1、 インドは公然たる核保有国(中国を指す)に国境を接しており、その国は1962年にインドに軍事侵攻した。
2、 この国(すなわち中国)とインドの関係はここ10年間、改善が進んでいるが、国境線問題のために不信感が続いているうえに、わが国のもう一つの隣国(パキスタンと指す)による秘密裏の核兵器開発を物理的に支援したことで、この不信感は増幅された
3、 インドはこの隣国(すなわちパキスタン)との間では、過去50年間に三度も侵略をこうむっており、この10年間でもパンジャーブとカシミールなど数ヶ所でこの隣国に支援されたテロと軍事行動の被害を受けている。
以上、インドが今回の核実験を合理化する理由としてあげている三点のうち、二点までもが「中国の核の脅威」に言及しているのだ。では、その保有している核兵器が果たして、インドが主張しているように「インド向け」に配備されているのだろうか。
中国の安全保障戦略は「冷戦期」と「ポスト冷戦期」で大きく異なっている。冷戦期においては、中国にとっての「主敵」はソ連と位置づけ、次いで米国を「潜在敵国」と位置づけてきた。なぜ、「主敵」は米国ではなくソ連なのかの理由は、60年代の文化大革命期に、ソ連が米国に対し「中国の核戦力が強大になる前に、今のうちに中国の核基地を叩いておこう」と提案したことにあった。米国はこれを通報した結果、中国のICBM(長距離の大陸間弾道ミサイル)の大部分がモスクワなどソ連の大都市に照準をあてた配備に変更された。こうして、冷戦期の中国の核戦略は以下の三本柱で構成されてきた。
1、米ソからの「核による威嚇」を抑止する。
2、ソ連による核攻撃に対する報復能力を維持する。
3、大国の威信として核兵器を維持する。
この後、89年12月の米ソ首脳マルタ会談で東西冷戦の終結が正式に宣言され、91年にはソ連が崩壊したことで中国にとっての長年の「北の脅威」は大幅に減少した。この結果、現在では中国の核ミサイルの多くは米国に指向していると見られている。
以上が、中国の核戦略の概観だが、インドは中国の核ミサイルが中射程ミサイル(すなわちインド全土を射程内に入れることができる)に重点が置かれ続けていることを挙げ、あくまで「中国の核はインドに向けられている」と主張しているのだ。それに加えてインドが挙げていたのが、中国が近年、IRBM(中距離弾道ミサイル)の射程のさらなる延伸と、弾頭の個別誘導多弾頭化および小型化、推進ロケットの燃料を従来の液体から固形燃料への切り替えなどを進めている点で、これらの近代化努力はインドに対する核攻撃能力の向上を目指したものだ、と主張している。
もうひとつ、インドが「中国脅威」の理由として挙げているのが、中国が冷戦終結を受けて新しく採用した軍事戦略だ。中国はそれまで、米ソ対決下で一度戦争が起きれば、それは核兵器の使用を含む世界戦争となるのは必至であるから、中国はこれに備えねばならないとする、「世界戦争戦略」をとってきた。だが、冷戦終結によって米ソ対決状態は終焉した。そこで中国は、こうした情勢変化を受けて新しい軍事戦略を採用した。それが「国内の地域戦争(台湾を指す)および、国外の地域戦争(地区性戦争)を勝つ戦略」はインドへの進攻が含意されているというのだ。
しかし、ポスト冷戦期の中国にとって最大の脅威はあくまでも米国であることはいうまでもない。他方、かつては「主敵」だった旧ソ連(ロシア)は、順位5番目に落ち、日本、ベトナムに対する警戒心を高めてきた。インドについては順位4番目にランクされ、インドが「中国脅威」を強調しているわりには、当の相手の中国には、インドをそれほどの脅威とは見ていないはずだ。
その理由は中国軍の総兵力は290万人で、インドの115万人に対し圧倒的な優位にあることが第一だ。また、62年の中印国境紛争では終始中国側が主導権をとり、現在も「中国優位」の状態のまま一応の安定を見せていることが第二の理由だった。中国としては、チベット独立運動への外国からの直接支援ルートは断たれた状態となっており、これ以上、中印国境であえて事を構える必要に迫られていない状態にあるといえる。
想定されるインドによる中国攻撃は、チベット問題を利用してチベット自治区を分裂させることであろう。中印紛争再発の可能性を完全には否定しない中国は、中印国境紛争が再発したとしても、インド軍を十分に撃退できるとの自信をもっている。「中印国境には高い山脈が連なっており、中国は山岳部隊だけで十分守れる。したがって、中印国境を進攻してくるインド軍に対して中国が核兵器を使う場面はまったく想定していないし、ありえない」と中国側が断言した。
パキスタンの恐怖心
インドが核実験をした後、パキスタンが国際社会から懸命な自制働きかけを振り切って、なぜ核実験を踏み切った。その原因の究明するには背後にあるインドとの宿命的な敵対関係は必要がある。両国間の衝突の「発火点」として常にカシミール紛争がマスコミにとりあげられてきたが、現地の実情は、カシミール紛争は実は二義的要素でしかなく、イギリス植民地からの分離・独立時の熾烈な内部闘争に起因した「インドは必ずパキスタンを吸収・併合する拳に出る」というパキスタン側の強烈な恐怖心が根底にある。今回のパキスタンによるインド追随の核実験もまた、パキスタン国民の心の奥深くに刻み込まれている恐怖心が駆り立てたものだったのだ。
パキスタンの核実験の成功は「自主開発」によるものといっていたが、米国側はパキスタンの核開発は中国からの輸出を受けるはずだと疑惑をもっていていた。95年7月3日日付米紙「ワシントン・ポスト」は、「偵察衛星写真やその他の情報に基づいて米情報機関はこのほど、パキスタンの大都市、ラホールの西にあるサルゴダ空軍基地に30基以上の中国製ミサイルが存在している結論に達した」と報じた。中国の外務省スポークスマンはロイター通信に対し、「ポスト紙の報道は、事実無根だ」と否定した。パキスタンのシェイク外務次官は「パキスタンはMTCRに違反するような取引は、一切していない」と、ややニュアンスを残したコメントをした。ワシントンからの情報により、ミサイルの本体を格納しているとみられる「運搬用ケース」が、中国国内のミサイル製造工場から運び出され、海路ではなく陸路でパキスタンに運びこまれたことを示す偵察衛星情報を米国は握っている、とのことだった。
最新の画像[もっと見る]
-
 綜合商社、非鉄大手18/3期、利益上振れ期待、中国景気追い風
7年前
綜合商社、非鉄大手18/3期、利益上振れ期待、中国景気追い風
7年前
-
 綜合商社、非鉄大手18/3期、利益上振れ期待、中国景気追い風
7年前
綜合商社、非鉄大手18/3期、利益上振れ期待、中国景気追い風
7年前
-
 中国新車市場、10月販売台数、前年比比2%、乗用車の伸びは鈍化、成長は維持されている、
7年前
中国新車市場、10月販売台数、前年比比2%、乗用車の伸びは鈍化、成長は維持されている、
7年前
-
 ポーラのシワ取り化粧品、1本1万5400円が売れている!シワがミニマ浅くなる?感じ!
7年前
ポーラのシワ取り化粧品、1本1万5400円が売れている!シワがミニマ浅くなる?感じ!
7年前
-
 93才の介護ダイアリー、ママ、今年は90才になるんだよ、ウソツ、私はならないわよ!
7年前
93才の介護ダイアリー、ママ、今年は90才になるんだよ、ウソツ、私はならないわよ!
7年前
-
 ドンキ、ユニファミマ提携報道はユミファミマのドンキ化による業績の改革、向上.ドンキ、出資も4割
7年前
ドンキ、ユニファミマ提携報道はユミファミマのドンキ化による業績の改革、向上.ドンキ、出資も4割
7年前
-
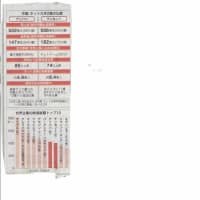 アリババ、テンセント中国IT2強の比較,世界企業の時価総額、トップ10位リスト、
7年前
アリババ、テンセント中国IT2強の比較,世界企業の時価総額、トップ10位リスト、
7年前
-
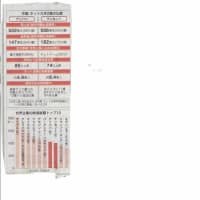 世界の時価総額リスト、中国アリババとテンセントの比較
7年前
世界の時価総額リスト、中国アリババとテンセントの比較
7年前
-
 ドラッグ市場、上位4社の寡占的競合、5位のココカラは再編、あるいはM&Aが戦略的課題?
7年前
ドラッグ市場、上位4社の寡占的競合、5位のココカラは再編、あるいはM&Aが戦略的課題?
7年前
-
 93 才の介護ダイアリー、不思議な縁で、カラオケでユー・レイズ・ミー・アップを歌う!
7年前
93 才の介護ダイアリー、不思議な縁で、カラオケでユー・レイズ・ミー・アップを歌う!
7年前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます