計量器大手のイシダ(京都市)は計量した食品を袋詰めする機器でアジアの新興国に攻め込む。2020年までにインドに生産拠点を設け、現地の食品工場に供給する方針を決めた。東南アジアや中国の販売体制も拡充する。日本で競争環境が厳しさを増す中、人口増や人件費上昇で機器の需要が伸びている新興国で生産・販売体制を整える。
食品工場向けの組み合わせ計量器では世界シェア7割に達する(滋賀県栗東市)
食品を正確に計量して袋詰めする「組み合わせ計量器」は食品工場に不可欠の機器だ。柿の種やポテトチップス、チーズなど、形や大きさがバラバラの食品を大型の機械に投入する。機械をぐるりと取り囲む小型のカップに食品が少量ずつ入れられ、合計すると規定の重量に最も近くなるよう幾つかのカップから食品がプラスチックの袋に滑り落ち袋詰めする。イシダの主力製品で、アジアや欧米、アフリカなど世界約120カ国に販売し、世界シェアは約7割を占める。
インドで生産するのは計量器と組み合わせて使う袋詰め機。17年3月期の海外売上高は約400億円と全体の3分の1強。23年3月期までに750億円に増やし、海外売上高比率を5割に高める計画だ。
石田隆英社長は「インドでは大手食品メーカーの工場新設が相次ぐ。現地の規格に合った商品の需要増に対応する」と話す。海外工場は英国、ブラジル、韓国、中国に続き5カ国目となる。投資額は数十億円とみられる。
インドには現在、営業拠点があるが、滋賀県や中国・上海の工場から供給している。包装機メーカーとの提携やM&A(合併・買収)を視野に新工場を建設し、日本や欧米の進出企業のほか、現地資本の食品メーカーにも販売する。価格は日本で販売している製品より抑える考えだ。
インドなど新興国の食品工場では多くの従業員を採用し、手作業で計量や袋詰め、検品をしてきた。だが現地の人件費が上昇し、機械への切り替えが広がりつつある。さらにアジアで積極出店する外資系の小売り大手などが食品の安全基準を厳格化。より正確で衛生的に袋詰めなどができる省力機器の需要が伸びている。
イシダは1988年に韓国で、00年に中国で生産子会社を設立した。中国では大手包装機メーカーとの提携などで知名度が高まったという。アジアの販売体制も強化する。01年に販売子会社を設けたタイでは今年4月から従業員向けに、自社の生産ラインに沿った機器を提案するための教育を始めた。現地で生産ラインに適した機器を提案販売することで納品までの期間が半分になった。
現地の販売拠点では袋詰め機や計量器を工場の生産ラインとどう組み合わせるべきかについて、習熟した人材がおらず、顧客の要望に対し複数の機器を組み合わせて提案することが難しかった。日本の本社の技術者が設計に対応する必要があり、納品までの期間も長くなりがちだった。今後、中国やインドでも提案販売を教育する。
■計量器や検査装置、幅広く
イシダ 1893年(明治26年)創業。はかりメーカーとしてスタートし、1972年に開発した組み合わせ計量器がヒットした。現在は計量器のほか、袋詰め済みの食品を計量して欠品がないか調べる検査装置や、コンビニの総菜をプラスチックの入れ物に盛りつける機器など、食品工場向けの装置を幅広く手掛ける。
2017年夏には水産加工場などで寄生虫「アニサキス」を光らせて検出する装置を工場向けに発売した。17年3月期の連結業績は売上高が1091億円、営業利益が120億円。













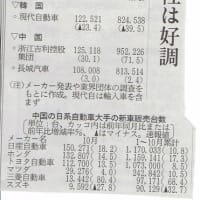


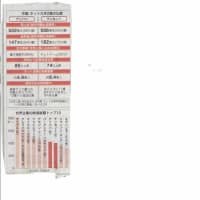
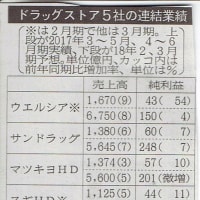

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます