ジャスティン・マッカリー(Justin McCurry)氏は、英国ガーディアン紙の東京特派員として、日本や朝鮮半島報道に10年以上携わっている。4月19日にも、財務次官セクハラ疑惑をめ ぐって東京発で Japan's #MeToo: senior bureaucrat resigns over sexual misconduct allegations という記事を書いている。
昨年は、イギリスの政界でも#MeToo運動が大きなムーブメントとなり、女性ジャーナリストに対するセクハラが原因で国防大臣が辞任する事態にまでなった。
一連のセクハラ疑惑についてどう考えるのか、寄稿してもらった。
日本の番がやってくるのも時間の問題だった
今月、財務省の福田淳一事務次官が、女性記者に対して性的に不適切な言葉遣いをしたという疑惑を指摘されて辞任を表明したとき、私を含む多くのジャーナリストは、「この一件は日本における#MeToo運動の起点になるかもしれない」と予想しました。
オンラインのハッシュタグに端を発して世界中で報道されるようになった数ヶ月間の#MeToo運動を追ってきた私たちにとって、日本の職場環境で もセクハラが起きているという事実は驚きではありません。#MeTooはすでにイギリスやアメリカなど、各国で大きなうねりとなっているのです。いずれ日 本の番がやってくるのも、時間の問題でした。
日本社会は未だにセクハラと戦うことに消極的
ただし、昨年ハリウッドの大物映画プロデューサーであるハーヴェイ・ワインスタインのセクハラ騒動によって社会的な議論が沸き起こったことはフェ ミニストたちから賞賛されましたが、福田氏の一件は日本社会が未だにセクハラ(場合によっては、より深刻な性的暴行も含む)と戦うことに消極的であること を示しました。
福田氏の辞任表明の2日後、アメリカ国務省が「日本の職場でセクハラが依然として横行している」と最新の人権報告書に明記したことに意外性はあり ませんでした。報告書は、日本の厚労省による2016年の調査結果を引用しており、それによるとフルタイムもしくはパートタイムで働く日本人女性の30% が職場においてセクハラを受けていると回答しているとのことです。
イギリスでも雪崩のようなセクハラ報告が
ただ、ハッキリ言っておく必要があるでしょう。職場でのセクハラは、全世界共通の現象です。私の母国・イギリスでワインスタインのケースの後に起 きたのは、大きな組織の要職に就いている人間が、女性に対して不適切な、そしてときには犯罪的な態度を取っているという雪崩のような報告でした。
いくつかのケースは、日本とも類似しています。昨年のある時期、イギリスの政界に激震が走りました。複数の国会議員に、議会職員や女性ジャーナリ ストへのセクハラ疑惑が浮上したのです。その後、人道支援の分野でも同じようなレポートが出されました。国際NGO「オックスファム」は、「過去12ヶ月 間に性的虐待の疑いがあった」としてスタッフ22人を解雇したことを認めました。
福田氏の辞任は、必然的に日本におけるジャーナリズムのあり方、そして大半を男性が占める高級官僚と新聞やテレビ局の女性記者の力関係に注目を集めさせることになりました。
麻生財務相は無知をさらけ出した
同じようにセクハラと戦っている人は少なくないようです。英字紙ジャパン・タイムズは、複数の日本人女性ジャーナリストから「取材の過程でセクハ ラを受けたことがある」とメールがあったことを明らかにしています。セクハラを受けた女性(そして男性)記者のうち、上司に報告した人はほとんどいなかっ たそうです。
その理由は想像に難くありません。テレビ朝日による抗議文を受けて、「もう少し大きな字で書いてもらった方が、見やすいなと思った程度に見まし た」と漏らした麻生太郎財務相のことを思い出してください。彼がセクハラの事実認定をめぐって「(告発者)本人が出てこなければどうしようもない」と述べ たことは、戦うことを決意した日本の女性が直面するリスクについて、信じられないような無知をさらけ出したと言うしかありません。
女性記者の所属していたテレビ朝日の当初の対応を見れば、セクハラに関する訴えが深刻に受け止められると確信できる日本人女性があまりに少ない理 由がよくわかります。実際、彼女たちの多くは、セクハラ被害を訴え出ることによって自分たちのキャリアに傷がつくと恐れています。
報道によると、テレビ朝日が当初、福田氏の問題行動についての報道を拒否したことで、被害女性は週刊誌に証拠を持ち込んだそうです。また、彼女の 上司は、彼女の名前が公になることによって新たなハラスメントが発生することを憂慮していたといいます。テレビ朝日が福田氏の言動をきちんと報じたいと望 んだ女性記者の意思を尊重しなかったことは誤りですが、一方では事件が公になることによる結果についてはあながち予想が間違っていたとはいえません。
SNSで「ハニートラップ」と非難の標的に
ジャーナリスト・伊藤詩織さんのケースを思い出してみましょう。昨年、彼女はかなり異例の、そして彼女自身にとってリスクの高い方法で、ある年長 のジャーナリストによって2015年にホテルの一室でレイプされたと公表しました。伊藤さんの主張は一部で報道されましたが、それは主として外国の報道機 関によるもので、日本国内ではおおむね黙殺されました。一方、伊藤さんのことを「売春婦」だとレッテルを貼るソーシャルメディアのユーザーたちによって、 敵対勢力を誘惑した「ハニートラップ」であると非難の標的にされたのです。
セクハラ疑惑を否定した福田氏をめぐる論争は、公的機関におけるセクハラ対応が根源的に変わることの難しさを物語っています。
一部では、記者たちと取材対象である官僚たちの関係は大きく変わるだろうとの声もあります。彼らは「本当に両者が適切な関係であると言えるのだろ うか」と問うているのです。「女性記者と男性官僚が、仕事が終わってから、ときには一対一になってバーで一緒に飲む? そんなのはトラブルを起こしてくれ と自分から言っているようなものだろう」と。
ただ、私に言わせれば、これは的外れな意見です。一人の職業人としては“ヨウチアサガケ”の取材手法には疑問を感じないわけではありませんが、だ からといって男性記者でも、女性記者でも、通常のオフィスアワーの後に官僚と話せる機会は必要です。省庁の記者会見室であろうが、やや薄暗いバーであろう が、性的に不適切な言動に怯えることなく取材できる。それが動かぬ大前提のはずです。
韓国の#MeTooデモには文在寅大統領の姿も
東アジアにおいて、ようやくセクハラ撲滅に向けて重い腰をあげたのは日本だけではありません。男性社会であるとされる韓国でも、現役の女性検事 ソ・ジヒョン氏が「2010年に葬儀場で元法務省幹部からセクハラを受けた」と告発した際には、何百人もの女性が抗議活動を行いました。
中国でさえ、当局による検閲や社会的圧力ではセクハラをめぐる議論の勃興を抑えることができず、主として大学生たちが一番槍となってネット上で広がりをみせています。
緩慢ではありますが、日本でも物事は変化しています。総務相・女性活躍担当相である野田聖子氏が、メディア業界で働く女性たちとセクハラについて積極的な意見交換の場を設けたいと表明したことは好意的に受け止めたいと思います。
ただ、財務省のスキャンダル自体がセクハラ被害に悩む女性たちを勇気づけるわけではなく、また問題は政治やメディアの世界に限った話ではありません。より不安定な職に就いている何百万人もの女性たちは、補償を求めることによって失うものが大きいのです。
つい最近、韓国の女性たちが#MeTooデモをソウルで行った際には、演説者の一人は文在寅大統領でした。彼はこう主張していました。
「法だけで解決することはできない。私たちの文化と態度を変える必要がある」
あるいは、次は「女性活躍社会」を掲げる安倍晋三首相が、同じようにセクハラを根絶すべく立ち上がる番なのかもしれません。時代遅れの財務大臣がいくら怒ったとしても。
(ジャスティン・マッカリー)















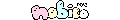

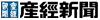




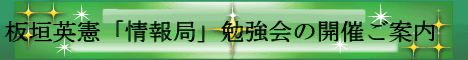













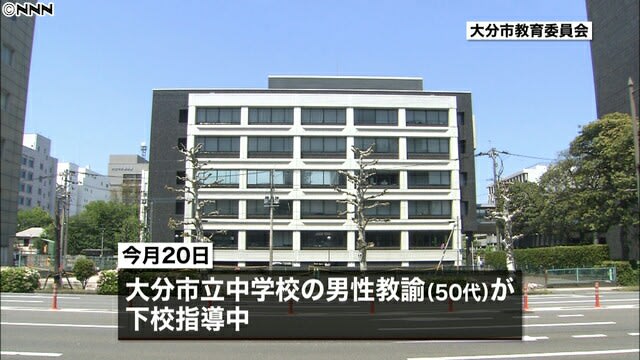 中学校教諭、生徒の首絞め失神させる 大分
中学校教諭、生徒の首絞め失神させる 大分



