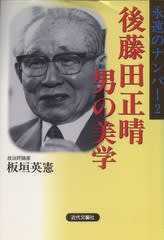日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。
条文
第九十九条[1] 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
沿革
- 大日本帝国憲法
- (上諭)…朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ爲ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及將來ノ臣民ハ此ノ憲法ニ對シ永遠ニ從順ノ義務ヲ負フヘシ
- 憲法改正要綱[2]
- なし
- GHQ草案[3]
- 第九十一条 皇帝皇位ニ即キタルトキ並ニ摂政、国務大臣、国会議員、司法府員及其ノ他ノ一切ノ公務員其ノ官職ニ就キタルトキハ、此ノ憲法ヲ尊重擁護スル義務ヲ負フ
- 此ノ憲法ノ効力発生スル時ニ於テ官職ニ在ル一切ノ公務員ハ右ト同様ノ義務ヲ負フヘク其ノ後任者ノ選挙又ハ任命セラルルマテ官職ニ止マルヘシ
- Article XCI. The Emperor, upon succeeding to the Throne, and the Regent, Ministers of State, Members of the Diet, Members of the Judiciary and all other public officers upon assuming office, shall be bound to uphold and protect this Constitution.
- All public officials duly holding office when this Constitution takes effect shall likewise be so bound and shall remain in office until their successors are elected or appointed.
- 憲法改正草案要綱[4]
- 第九十四 此ノ憲法ノ日本国民ニ保障スル基本的人権ハ人類ノ多年ニ亙ル自由獲得ノ努力ノ成果ニシテ、此等ノ権利ハ過去幾多ノ試錬ニ堪へ現在及将来ノ国民ニ対シ永劫不磨ノモノトシテ賦与セラレタルモノトスルコト
- 天皇又ハ摂政及国務大臣、両議院ノ議員、裁判官其ノ他ノ公務員ハ此ノ憲法ヲ尊重擁護スルノ義務ヲ負フコト
- 憲法改正草案[5]
- 第九十五条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
- 日本国憲法
- 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
解説
天皇また一般職か特別職か・政府機関勤務か地方公共団体勤務かを問わずあらゆる立場の公務員全てが、日本国憲法を遵守し擁護しなければならないと定めている。政治に携わる者達に、憲法を守り、さらに「憲法違反行為を予防し、これに抵抗」[6]する義務を課したものとしている。この規定は「内閣が、憲法を批判し、憲法を検討して、そして憲法を変えるような提案をすることを禁止している」とする見解がある[7][8][9]。一方で、公務員は職務を遂行するにあたり、憲法に問題点があるを認識した場合にその問題点を広く国民に問いかけることを禁止していないとする見解もある[10]。
法律[11]では裁判官及び一部の公務員[12]について、「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」を欠格条項とする規定が存在し、また公務員は就任の際に憲法を守る宣誓を行うことが法令等[13]で規定されているが、これは本条文が根拠となっている。その一方で、国務大臣、国会議員、その他一部の特別職公務員[14]のように「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」を欠格条項とする規定や就任の際に憲法を守る宣誓を行うことが法令等が明記されていない例もある[15]。
なお、ドイツの憲法である基本法では国民に憲法擁護義務を課している(戦う民主主義)が、日本国憲法第99条の憲法尊重擁護義務に一般の国民は含まれていない。
関連条文
脚注
- ^ 「日本国憲法」、法令データ提供システム。
- ^ 「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- ^ 「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- ^ 「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- ^ 「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- ^ 佐藤幸治他共著『注釈 日本国憲法』下巻、青林書院
- ^ 拝啓 安倍晋三様 あなたが「改憲」に前のめりになるのは筋が違いませんか? 法学館憲法研究所(伊藤真・浦部法穂・水島朝穂・村井敏邦・森英樹連名)
- ^ 憲法擁護尊重義務 浦部法穂の憲法時評 2013年2月21日(法学館憲法研究所)
- ^
憲法の改正は、ご承知のとおり内閣の提案すべき事項ではございません。内閣は憲法の忠実な執行者であり、また憲法のもとにおいて法規をまじめに実行するところの行政機関であります。したがって、内閣が各種の法律を審査いたしまして、憲法に違反するかどうかを調査することは十分できます。しかし憲法を批判し、憲法を検討して、そして憲法を変えるような提案をすることは、内閣にはなんらの権限がないのであります。この点は、内閣法の第5条におきましても、明確に認めているところでございます。(中略)内閣法のこの条文は、事の自然の結果でありまして、内閣には、憲法の批判権がないということを明らかに意味しているものだと思います。(中略)内閣に憲法改正案の提出権がないということは、内閣が憲法を忠実に実行すべき機関である、憲法を否定したり、あるいはまた批判したりすべき機関ではないという趣旨をあらわしているのだと思うのであります。憲法の改正を論議するのは、本来国民であります。内閣が国民を指導して憲法改正を企図するということは、むしろ憲法が禁じているところであるというふうに私は感じております。(中略)元来内閣に憲法の批判権がないということは、憲法そのものの立場から申しまして当然でございます。内閣は、けっして国権の最高機関ではございません。したがって国権の最高機関でないものが、自分のよって立っておるところの憲法を批判したり否定したりするということは、矛盾でございます。こうした憲法擁護の義務を負っているものが憲法













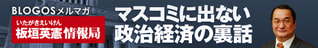
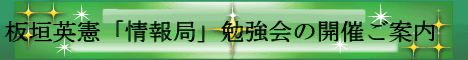
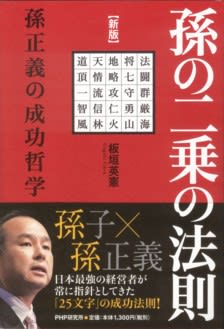
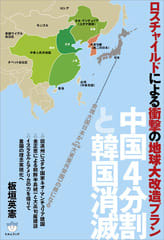
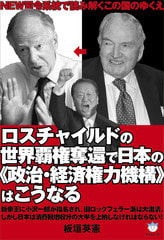
 6月開催の勉強会がDVDになりました。
6月開催の勉強会がDVDになりました。