
奈良女子大の校門で鹿に遭遇
奈良女子大学校臨床心理学の2回目。大学の校門に到着したら、2頭の鹿が中から出てきました。
一瞬だったので画像は撮れなかったのですが、警備員さんに訊くと5頭ほど校門の前で待っていたらしいです。
というのは何ヶ月かまえに、こんなニュースがテレビで流れたからです。
「奈良女子大の草は美味しいらしい」
https://www.youtube.com/watch?v=240-U9OCW9I
今日は、イメージを共有するということに気づくワークショップです。
星野 欣生先生が開発された「流れ星」というワークショップを参考にして作成した「南国の島」です。
絵は、わたしが現職だったころの若手の先生に描いてもらいました。
絵にもいろいろしかけを施しているのですが、イメージを共有するにはどうすればいいのか・・ということに気づくことができます。
http://aiainet-hrs.jp/…/…/1-3%20nangokunoshima-kaisetsu.html
***
 |
いじめ・不登校を防止する人間関係プログラム |
| 深美隆司 価格:¥ 2,000(+税) | |
| 学事出版 |
 |
子どもと先生がともに育つ人間力向上の授業 |
| 深美隆司 価格:¥ 1,800(+税) | |
| 図書文化社 |
あいあいネットワーク of HRS
ホームページURL:http://aiainet-hrs.jp/


















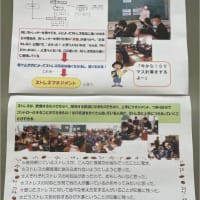







今日の「南国の島」というワークは,以前にワークの練習として取り組んだ覚えがあるのですが,1回目と2回目の違いがあまり出ず,うまくいかなかったという印象が残っていました。今回はとても楽しく,また気づきも多いワークだったので,前回はなぜうまくいかなかったのだろうと不思議に感じて,授業が終わってからずっと気になっていたのですが,つい先ほどその理由に思い至りました。
それは,グループごとにワークを選び,授業で他のメンバーにやってみるというときのことでした。深美先生のご本を始めいくつかのワークの本からみんなでこの「南国の島」を選び,試しにグループ内でやってみた結果,うまくいかなかったのです。なぜなのかわからず,なんとなくもやもやした気持ちでした。結局他のワークを選び直したと思います。
なぜ1回目と2回目の違いが出なかったのか。それは,ワークを選んだ際に,全員がお題の絵を(しっかりではないにせよ)見ていたからではないかと思いました。だから,なんとなくそのイメージが残っていて,質問をしてもしなくても違いを感じなかったのではないか。しかも,その時点で私はそのことに全く気付きませんでした。自分が,自分の意識していないところで何かを前提としてしまっているかもしれない。少し恐ろしくなりましたが,よく考えてみれば,本当に真っ白の状態でいることなど,できないことだとも思います。今回のワークをきっかけにもうひとつの気付きがありました。ありがとうございました。
「自分が,自分の意識していないところで何かを前提としてしまっているかもしれない。」、いいところにお気づきになられたと思います。昨日のことで言いましたら、グループの話し合いのプレゼンのなかで「質問したからといって、とくに変わりは有りませんでした。むしろ質問をしなかったほうが似た絵が描けました。」というようなふりかえりがあったのを覚えておられますか。その時のわたしからのフィードバックは、軽く受けとめただけで、スルーに近い状態だったことに気づかれましたか。「こんな結果に導かなければならない」「答えはちゃんとある」という固定観念で受けとめますと、さきほどのようなふりかえりは、どうしても否定的に対応してしまいますね。なので、その場でわたしがしゃべりますと、そんなふうにとられては困りますので、あえてスルーに近い反応になったわけです。「そういう方もおられて当然」というあるがままの状態を肯定的に受け止めることが肝心なのですね。場で起こっていることを大切にするということです。決して操作、誘導をしないのがファシリテータの仕事です。
「南国の島」では、自由に質問ができないことによるイメージの齟齬と、自由に質問ができることによるイメージの先走り・解釈の違いを体感できました。
自由に質問できないことでイメージの共有がうまくできなかったのですが、自由に質問できてイメージ共有の精度は上がっても、一つの要素についての質問の流れが終わらないと先走って解釈してしまう時がありました。
コミュニケーションを取らなければ相手に伝えたいことが伝わらず、取ったとしても相手への伝わり方は様々で、思い違いが発生してしまうこともあります。
心理学に携わる上で共感的理解が求められますが、今回のワークショップを通して、状態・イメージの共有は永遠の課題であると改めて感じました。
次回のワークショップも楽しみにしております。
もし今回のワークで、生徒さん同士に伝えて描くという作業をしてもらったら、「◯◯の伝え方が悪いから分からない!」という言い合いなどに発展してしまうのかもしれないと思いました。その点、ファシリテーターが2回とも説明することで、「質問することの意義」という要因が明確になるのだなと感じました。
子どもどうしで伝え合う、というワークショップは一般的に「伝達ゲーム」などと呼ばれているものにあります。この手のワークショップは、いかに情報がちゃんと伝わらずに、事実やお題と異なってどのように変化していくのか・・に気づくワークショップですので、ちゃんと伝わらないほうがおもしろく、気づきも多いのものになります。特に大阪の子どもたちは、ほんとにおもしろく間違ってくれます。
第2回目のワークを教えて頂いてありがとうございました。
今回は、「南国の島」のワークを通じて、人によって違う物の捉え方や、考え方について深く考えることが出来ました。
また前回のなんでもキャッチの時と同じように、自分勝手に先走ってしまわないように注意するということについても振り返ることが出来ました。
自分が当たり前と思っていることを疑ってみる、これが身につけば、様々な物の捉え方や、異なる意見を持つ人の考え方にも共感できるようになると思いました。
行動はイメージングし、自己対話し、評価する。
評価はシェアリングして認知する。
まず自らについてやってみようと思います。
そしてアドバイスを必要としている人に対し、その人が自信を持てるような、ポジティブな支えになっていきたいと思います。
ありがとうございました。
南国の島を通して、私自身がいかにせっかちでテキトーなのかが身に染みてわかりました。
だいたい合っていればこんなもんでいいだろうと思う私に対して、他の院生たちはすごく質問していて自分の性格が浮き彫りになりました。
それから、それぞれの絵を見ると、それぞれの特徴が出ていて面白かったです
ありがとうございました。