
奈良女子大学大学院学校臨床心理学第一回目でした。
今日から三回連続講座です。
伊藤美奈子先生から、模擬授業を中心に、というご依頼を受けていますので、スタートプログラムからの三本をチョイスした授業になります。
今日はそのなかから ”なんでもキャッチ’ です。
相手の名前を呼び、相手の返事を聞いてからボールを投げます。
相手が無事キャッチできればOK、それを全員にまわすと、終了です。
投げるものはボールに限らず、マラカスやたわしも投げます。
相手の返事を待てずに投げてしまうケースが頻発するのですが、進むにしたがって、うまくできるようになりましたね。
ふりかえりのなかに、ボールを何かに例えると というのがあるのですが、よく言葉とか気持ちとかが出ます。
今日は視線、と感じた方もおられたようです。
いろんな気づきがありますねぇ。
***
 |
いじめ・不登校を防止する人間関係プログラム |
| 深美隆司 価格:¥ 2,000(+税) | |
| 学事出版 |
 |
子どもと先生がともに育つ人間力向上の授業 |
| 深美隆司 価格:¥ 1,800(+税) | |
| 図書文化社 |
あいあいネットワーク of HRS
ホームページURL:http://aiainet-hrs.jp/


















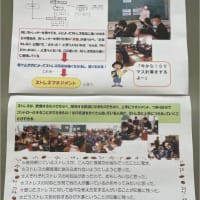








「なんでもキャッチ」「だまってキャッチ」はどちらも、相手を思いやる気持ちが求められます。
ボールを投げるという簡単な行動ですが、自分が日常生活でどれほど相手を思いやる行動ができているかを考えるきっかけとなりました。
親子関係などで過度な侵入や、過度な期待が不登校原因の殆どを閉めるというのは考えさせられました。
ミラーリングやフィードバックを通して、過度な侵入にならない人間関係は、どの人間関係にも通じると感じました。
大変貴重な経験となりました。どうもありがとうございました。
なんでもキャッチで、簡単なルールを守ることの難しさや同じルールの中で個人の振る舞いが違ったりする面白さを感じました。
理論だけでなく、ゲームの中で体験できるところが魅力的でした。
ボールなどを投げる・受け取るという単純な動きから、人間関係や不登校について考えることができるなんて思いもしませんでした。また、特に「だまってキャッチ」では、アイコンタクトや体の向きなど、非言語表現がいかに重要な情報であるか、改めて考えさせられました。臨床現場だけでなく、普段の行動を振り返るいい機会となりました。ありがとうございました。
次回も楽しみになりました。よろしくお願いします。
「なんでもキャッチ」ではいかに相手のことを考えられるか。いかに名前を呼ばれて返事をするという当たり前のことを忘れがちなのか。
「だまってキャッチ」ではいかに普段言語に頼っているのか。非言語表現がいかに重要なものなのか。
たくさんのことを考えさせられる機会となりました。
そのまま"返す"フィードバックが簡単なようで難しく、それができないことで親子関係に困難を抱えることになるということは今後、臨床現場においてポイントになってくると思いました。
残り2回もとても楽しみです。ありがとうございました。
「なんでもキャッチ」は昨年も教えて頂きましたが,メンバーの人数や関係性が違っていたので,少しリラックスした状態で取り組むことができたように感じました。
また,今回初めて体験した「黙ってキャッチ」は,「なんでもキャッチ」と似ているのに全く異なるコミュニケーションが必要で,大変興味深かったです。
ひとつ質問させていただきたいのですが,「黙ってキャッチ」のようにアイコンタクトなど非言語コミュニケーションが必要なワークを実施する際に,たとえば発達障害傾向の特性などで,非言語コミュニケーションが苦手な生徒が参加している(参加している可能性がある)場合,どのような配慮や工夫をすればワークをスムーズに進めることができるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
ウォーミングアップの声出し123で身体が徐々に温まり、なんでもキャッチもボールからキャッチするのが難しいマラカスまで、ルールを忘れてしまうほど楽しく参加させて頂きました。(なにがなんでもキャッチだなとも思いました。)
自分が何気なく、相手のペースを考えずに話したり、受け答えしてるのかも知れないと、自分を省みることのできるいい機会でした。
自分がファシリテーターとしてこのワークを行う際は、深美先生が上で書かれているように、段階をつけてレベルアップできるよう、またジャッジとして冷静に、かつユーモラスに場を取り仕切れたらいいと思いました。
また来週のワークを楽しみにしています。
以前、ボールだけを用いて「なんでもキャッチ」と似たようなワークを行ったことはあるのですが、今回はボール以外のものもあり、なおかつ大きさ・重さなどがバラエティに富んでいたので、投げる時の力の強さや距離感、感触に注意を向ける必要がある、とより強く感じました。
ボールなどを投げる・受け取る行為を通して、相手の反応を見たり発信する人に注目したりするだけでなく、受け取った相手の反応・気持ちを予想するのも大切であると改めて気付かされました。
また、適切にフィードバックを行うことは、過小・過大評価をせずにちょうど良い塩梅でその人の変化・気付きを認めることにもつながるのかな、と思いました。
次回のワークも楽しみです。ありがとうございました。
「なんでもキャッチ」、「黙ってキャッチ」などのゲームから学んだことは、人とのやりとりやカウンセリング場面においても通用できると考えられます。有効なコミュニケーションでは、単なる一方通行ではなく、お互いに相手のことへの思いやりを持って、言語や非言語の形で交流する過程だと思います。自分の気持ちを相手に伝える際に、相手が受けやすいように工夫する必要があることを改めて気付されました。また、聞き手側として、相手の期待を答えるように、ちゃんと「はい」を言うこと、つまり話をうまく進めるために、相手の話を聞いていることを示すのもとっても大事だと思います。
次回も楽しみにしています。よろしくお願い致します。