劇作家そして劇団主催の山崎哲は「自分がサリンで殺されたって仕様がない。10人や20人の死よりも、ここには大事なことがある・・・・。」という。
では、命よりももっと大事なこととは、なんなのかと、ぼくは山崎の語りを検討しはじめたのだが、たちまち、その難解な、抽象的な言い回しに、つかみようのない特殊な言い回しにひっかかって動きがとれない感じになった。そこには、どうしようもない粘液質などろどろの情念のようなものがあり、明晰な理由も根拠も辿りようもないようなものを感じたのである。
だが、楠木かつのりは、その韜晦な語りをくぐりぬけながら、次第に山崎を論理的に回答せざるをえない領域に立たせていった。そのプロセスも、インタービューの読みどころである。楠木は、後に詩のボクシングの企画主催者として知られるようになった。
江川さんと遣り合って彼女の何処が違和感があるのかと聞かれて山崎は、「いやあ、あの正義感ですよ。社会正義を絶えず背負う。自分の意見の背後に市民社会をもってくる。そうやって自分を一切無罪の立場に置く。そこが僕とは決定的に違う。僕には芸能をやっているからかもしれないけど、市民社会からどうやって出るか、というテーマがある。」と、江川の市民社会的正義感を痛烈に批判する。
「正義ってのが何かって言ったら、単純なことで、八十%、あるいは九十%の中流意識です。」とつづける。さらに「それは(オーム批判)せいぜい市民社会の倫理意識のレベルなわけじゃないですか。それは1972年以降、消費する人間が主体になった社会ができあがって、わずか二十年くらいでつくられた倫理なわけでしょう、そんなものは屁でもないんだって僕は考えてますけどね。」ととうとうと、論が展開する。しかし、中流意識の正義も、1972年以降に作られた倫理も、感性的なかれの心情のイメージにすぎず、具体性も正確性もない、それは論争タームでしかないとぼくには思えてならない。
このようなポレミストの語りがつづくなかで楠木は、「そこまで言ってしまうと、当然、オウムに殺された側の立場に立ったらそんなことが言えるのか、と言う批判が出てくると思うんですが」と突っ込みを入れてくる。「もし自分がサリンで殺される側になったとしたら、どうなんですか」と切り込む。「それはし様がないですね。もう事故みたいなものだから、仕方がないよ。そのときは潔よく受けますよ。」「たとえば家族が殺されても、同じですか。」「やっぱり仕方がないって思うでしょうね。そこはその人間が、どのようにこの事件に対して立ち向かうかっていう、ひとつの思想的な決定をするしかないんじゃないでしょうか。」と彼は答える。
さらに、かれは、親鸞を引用して「たとえ人間がどんな悪を為そうと、たとえばサリンを使って殺傷をしようと、そんなことは関係ないんだ、みんな救われちゃうんだよ。悪人なんてもっと救われちゃうんだよっていう、言い方をするわけですよ。」といいつづけるのだ。
楠木は、オームの宗教体験で身体、命の露出という面を山崎が語るのを聞いた後「オウムがサリンを撒いてくれたおかげで、われわれもその生命体験を共有できたと、いうことですか。」とたたみかけると「結果的にですけどね、彼らの唱える人間救済ってのは命をどうやって露出させるか、というテーマに繋がってくるだろうと思うんですよ。・・・そこはたぶん、自分たちの生命体験を分かち合わねばならないというボランティア精神があった。」といい、「つまりこの事件の本質とは、戦後社会が五十年かけてやってきた、自分の生命が直接自分に触れることをどんどん隠していくという営為を一挙に崩してしまったということです。そのことの意味はいくら強調してもしすぎることはないと思う。」と言って終るのである。
しかし、それにしても山崎哲が、ここまではっきり言えるのはなぜなのか、その強靭さも、たしかに否定できぬ存在感がある。それはなんなのか、それはある、確かに。そこに実際のサリン被害者を知る必要があるのだ。彼にとって、山崎はなんなのであろうかと。
ではかれの言葉と、明石達夫、志津子兄、妹、その家族とのいのちをどうふれあっているのか、かれらを納得させられるものがあるのかどうか、山崎のことばをその命の場で検討してみよう。
では、命よりももっと大事なこととは、なんなのかと、ぼくは山崎の語りを検討しはじめたのだが、たちまち、その難解な、抽象的な言い回しに、つかみようのない特殊な言い回しにひっかかって動きがとれない感じになった。そこには、どうしようもない粘液質などろどろの情念のようなものがあり、明晰な理由も根拠も辿りようもないようなものを感じたのである。
だが、楠木かつのりは、その韜晦な語りをくぐりぬけながら、次第に山崎を論理的に回答せざるをえない領域に立たせていった。そのプロセスも、インタービューの読みどころである。楠木は、後に詩のボクシングの企画主催者として知られるようになった。
江川さんと遣り合って彼女の何処が違和感があるのかと聞かれて山崎は、「いやあ、あの正義感ですよ。社会正義を絶えず背負う。自分の意見の背後に市民社会をもってくる。そうやって自分を一切無罪の立場に置く。そこが僕とは決定的に違う。僕には芸能をやっているからかもしれないけど、市民社会からどうやって出るか、というテーマがある。」と、江川の市民社会的正義感を痛烈に批判する。
「正義ってのが何かって言ったら、単純なことで、八十%、あるいは九十%の中流意識です。」とつづける。さらに「それは(オーム批判)せいぜい市民社会の倫理意識のレベルなわけじゃないですか。それは1972年以降、消費する人間が主体になった社会ができあがって、わずか二十年くらいでつくられた倫理なわけでしょう、そんなものは屁でもないんだって僕は考えてますけどね。」ととうとうと、論が展開する。しかし、中流意識の正義も、1972年以降に作られた倫理も、感性的なかれの心情のイメージにすぎず、具体性も正確性もない、それは論争タームでしかないとぼくには思えてならない。
このようなポレミストの語りがつづくなかで楠木は、「そこまで言ってしまうと、当然、オウムに殺された側の立場に立ったらそんなことが言えるのか、と言う批判が出てくると思うんですが」と突っ込みを入れてくる。「もし自分がサリンで殺される側になったとしたら、どうなんですか」と切り込む。「それはし様がないですね。もう事故みたいなものだから、仕方がないよ。そのときは潔よく受けますよ。」「たとえば家族が殺されても、同じですか。」「やっぱり仕方がないって思うでしょうね。そこはその人間が、どのようにこの事件に対して立ち向かうかっていう、ひとつの思想的な決定をするしかないんじゃないでしょうか。」と彼は答える。
さらに、かれは、親鸞を引用して「たとえ人間がどんな悪を為そうと、たとえばサリンを使って殺傷をしようと、そんなことは関係ないんだ、みんな救われちゃうんだよ。悪人なんてもっと救われちゃうんだよっていう、言い方をするわけですよ。」といいつづけるのだ。
楠木は、オームの宗教体験で身体、命の露出という面を山崎が語るのを聞いた後「オウムがサリンを撒いてくれたおかげで、われわれもその生命体験を共有できたと、いうことですか。」とたたみかけると「結果的にですけどね、彼らの唱える人間救済ってのは命をどうやって露出させるか、というテーマに繋がってくるだろうと思うんですよ。・・・そこはたぶん、自分たちの生命体験を分かち合わねばならないというボランティア精神があった。」といい、「つまりこの事件の本質とは、戦後社会が五十年かけてやってきた、自分の生命が直接自分に触れることをどんどん隠していくという営為を一挙に崩してしまったということです。そのことの意味はいくら強調してもしすぎることはないと思う。」と言って終るのである。
しかし、それにしても山崎哲が、ここまではっきり言えるのはなぜなのか、その強靭さも、たしかに否定できぬ存在感がある。それはなんなのか、それはある、確かに。そこに実際のサリン被害者を知る必要があるのだ。彼にとって、山崎はなんなのであろうかと。
ではかれの言葉と、明石達夫、志津子兄、妹、その家族とのいのちをどうふれあっているのか、かれらを納得させられるものがあるのかどうか、山崎のことばをその命の場で検討してみよう。











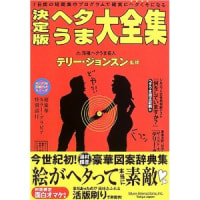












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます