さて、前回の山崎哲の語りを、実際のサリン被災者の現実に合わせてみよう。だれにするかで、明石達夫さん37歳(自動車パーツ会社営業)を躊躇なく選んだ。丸の内御茶ノ水駅で、サリンにあったのは、実は達夫さんのただひとりの妹で、植物人間状態になる重症を受け、ようやく意識は回復したが車椅子生活を送っている彼女と、彼女をとりまく自分たちの運命について、語っているのである。直接の被害者は志津子さんではあるが、まわりの家族もまた語りつくせぬ被害者となっているのを、この証言は伝えている。
その日まで彼女は年老いた両親とともに暮らし、バスでスーパーのレジ係りとして働いていた。達夫さんも共稼ぎの家庭でこどもは、小学生になったばかりの子供二人、民間の小さな会社の社員である。父は、不況で会社が破産して今は働いていない。母はひざの故障で杖なしでは歩けず、無職、それゆえに志津子さんは両親の面倒をみるために結婚をしてない。
明石さんの親族模様をこのように要約すれば、三浦展(あつし)が下流社会と名づけてしまう階層だろうが、いまさらながらその呼称が侮蔑でしかないのを感じざるを得ない。そんな下層とか下流の言葉ではない家族があるのだ。明石さんの証言は、家族の生きている暮らしの模様、その豊かさ、切実さ、愛や苦悩を伝えている。ぼくは読んで、ふと50年ほどまえに読んだことのあるシャルル・ルイ・フィリップの短編集「小さな町で」や「朝のコント」、その他のなもなき人々を主題にした小説を思い出したのだ。かれの小説はなによりも、ひとの暮らしのリアリティに打たれる。明石さんの話もまたその実感であふれている。」
「事件の前日の夜、家族みんなで食事をしながら話していたんです。{ほんとうに、こういうのが幸福というものなんだよな}って。みんなで一緒に集まってごはんを食べて、わいわいとつまらない話をして・。たったちょっとの幸せですよ。」
このことばにかれらの小さな幸せの暮らしぶりがみごとに集約されているのではないか。そして、それはぼくらも感じることの出来る庶民の現実である。かれの証言は、実はこの暮らしの実感が、すみずみにまであふれていることだ。この感じはもう原文をよんでもらうしか、つたえないようがないのだ。
これが斧でたたき切られるように破壊される。これまでの生活は激変する。まもなく父も癌で倒れる。それから父の病院,妹の病院,歩けなくなった母の面倒と日々がくりかえされる。「また病院に行くの。どこか遊びに行こうよ。」という子供たち。そういわれるとどうしようもなく私は辛いと、かれは言う。病院のほうは、もう一生ひとりで自活は無理だと言う。母はたまりかねて「志津子はあのまま死んでくれたらよかったのに」と口にし「お前たちにこれ以上の迷惑をかけるのは忍びないい。」というのだ。
しかし、やがて、なんとか意識がもどり、半年後からリハビリがつづけられるようになり、現在が語られるわけだが、それは決して悲惨には語られていない。これが凄い。ひとの深さ、不可思議な生のエネルギーを感じさせるのだ。
「でもこの二年近く、妹の会社の皆さんや、私の会社の同僚や上司や、お医者さん、看護婦さんたちには、ほんとうに良くしていただきました。それが私にとっての大きな救いとなりました。」と証言は結ばれている。
ぼくはこの証言を読んだとき、人の強靭さ、豊かさ、深さ、そして個性ある存在としても重みを感じて言葉を失ったほどである。「10人や20人は殺されたって仕様がない、この社会には人の命よりももっと大切なものがある」という言説などは
まさに安全地帯にいるやつの虚妄でしかないことを、確信させられたのだ。
その日まで彼女は年老いた両親とともに暮らし、バスでスーパーのレジ係りとして働いていた。達夫さんも共稼ぎの家庭でこどもは、小学生になったばかりの子供二人、民間の小さな会社の社員である。父は、不況で会社が破産して今は働いていない。母はひざの故障で杖なしでは歩けず、無職、それゆえに志津子さんは両親の面倒をみるために結婚をしてない。
明石さんの親族模様をこのように要約すれば、三浦展(あつし)が下流社会と名づけてしまう階層だろうが、いまさらながらその呼称が侮蔑でしかないのを感じざるを得ない。そんな下層とか下流の言葉ではない家族があるのだ。明石さんの証言は、家族の生きている暮らしの模様、その豊かさ、切実さ、愛や苦悩を伝えている。ぼくは読んで、ふと50年ほどまえに読んだことのあるシャルル・ルイ・フィリップの短編集「小さな町で」や「朝のコント」、その他のなもなき人々を主題にした小説を思い出したのだ。かれの小説はなによりも、ひとの暮らしのリアリティに打たれる。明石さんの話もまたその実感であふれている。」
「事件の前日の夜、家族みんなで食事をしながら話していたんです。{ほんとうに、こういうのが幸福というものなんだよな}って。みんなで一緒に集まってごはんを食べて、わいわいとつまらない話をして・。たったちょっとの幸せですよ。」
このことばにかれらの小さな幸せの暮らしぶりがみごとに集約されているのではないか。そして、それはぼくらも感じることの出来る庶民の現実である。かれの証言は、実はこの暮らしの実感が、すみずみにまであふれていることだ。この感じはもう原文をよんでもらうしか、つたえないようがないのだ。
これが斧でたたき切られるように破壊される。これまでの生活は激変する。まもなく父も癌で倒れる。それから父の病院,妹の病院,歩けなくなった母の面倒と日々がくりかえされる。「また病院に行くの。どこか遊びに行こうよ。」という子供たち。そういわれるとどうしようもなく私は辛いと、かれは言う。病院のほうは、もう一生ひとりで自活は無理だと言う。母はたまりかねて「志津子はあのまま死んでくれたらよかったのに」と口にし「お前たちにこれ以上の迷惑をかけるのは忍びないい。」というのだ。
しかし、やがて、なんとか意識がもどり、半年後からリハビリがつづけられるようになり、現在が語られるわけだが、それは決して悲惨には語られていない。これが凄い。ひとの深さ、不可思議な生のエネルギーを感じさせるのだ。
「でもこの二年近く、妹の会社の皆さんや、私の会社の同僚や上司や、お医者さん、看護婦さんたちには、ほんとうに良くしていただきました。それが私にとっての大きな救いとなりました。」と証言は結ばれている。
ぼくはこの証言を読んだとき、人の強靭さ、豊かさ、深さ、そして個性ある存在としても重みを感じて言葉を失ったほどである。「10人や20人は殺されたって仕様がない、この社会には人の命よりももっと大切なものがある」という言説などは
まさに安全地帯にいるやつの虚妄でしかないことを、確信させられたのだ。











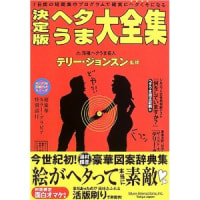












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます