(北海道新聞夕刊<魚眼図>2011年10月14日掲載)
カシューナッツの実がどのようになるかご存じだろうか。
アフリカ・タンザニアの海岸部は、乾期でも蒸し暑い。この気候を利用して、ココナッツ、マンゴー、カシューナッツなどが栽培されている。南東部ではカシューナッツが特産品となっており、最南端の都市ムトワラはその積み出し港として有名だ。
この地方を9月に車で旅していて、現地のドライバーに「これがカシューナッツの木ですよ」と教えられた。車を止めて道路沿いに立つ、見上げるほどの巨木の下に入った。オレンジ色の実がたくさんなっている。小型の柿のようだ。この実は食べられる。やや渋い柿のような味がする。面白いのはその種が果物の外側にできる点。枝から果物がなり、さらにその先に、薄緑色の勾玉(まがたま)状のものがついている。これが殻で、この中にある種がいわゆるカシューナッツだ。
この殻は固く、種が取り出しにくい。ある村でやり方を教えてもらった。まず果実と、種入りの殻とを分離する。殻をおき火に入れて熱する。これを石やこん棒でたたくとカシューナッツが出てくる。日本で一般的に売られているのは、この段階の白っぽいナッツだが、現地では茶色にローストされたものもある。これが香ばしくておいしい。
道端に立って、車を呼び止める少年たちがいた。止まると袋入りのカシューナッツを持って売りに来る。小屋を架け、ござを敷いて、少年5人と成人男性1人とで、種の取り出しと袋詰めの手作業をしている。つましくも、確かななりわいだ。向こうにはカシューナッツ畑が広がっている。日本のスーパーでこれからカシューナッツを買うとき、僕はこの風景を思い出すだろう。
(小田博志・北大大学院准教授=文化人類学)
カシューナッツの実
ムトワラで買ったカシューナッツ(左がローストしたもの)
道路沿いのカシューナッツ作業小屋と販売所















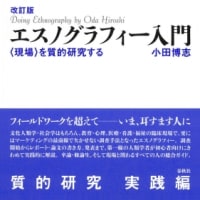








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます