なんといっても執筆に集中した年でした。
年の初めは『エスノグラフィー入門』を仕上げて、4月に刊行。さっそく北海道大学での授業で使いはじめました。またメールなどでも読者の方々から、感想をありがたくいただいています。読んでいただいてとてもうれしく思っています。
7月には、波平恵美子先生との対談『質的研究の方法』を出版しました。正確にいうと、僕が聴き手になって、波平先生のご経験から研究の方法とコツを語っていただいたものです。まえがきにも書きましたが、この企画に加われたこと自体「特別な幸運」でした。いかに研究をするかについて、多くのことを学べる本です。
それから今取り組んでいるのが、『質的研究入門』の新版の作成。本来ならこの年末には出ているはずですが、遅れてしまってご迷惑をかけています。でももうゲラになっていますから、近日刊行間違いなしです。この本、2002年に翻訳を刊行してはや8年が経ちました。その間に英語版は第4版になり、単純に比較して1.6倍に加筆されています。また従来の訳書の文章も改めて読んでみると、わかりにくい箇所が目につきます。そこで現在、原書の最新版を底本に、全面改訂の新しい訳書を作成中です。しかしまー翻訳というのは時間がかかる仕事でして、8月からほぼ毎日のように原書(英語版とドイツ語版)とにらめっこして、やっとここまでこぎつけた次第です。
これらの他に分担執筆の仕事もしました。ある文化人類学の教科書の、質的研究の章を担当。これは7月ごろには出版予定です。それから現代のドイツに関する論集に、ドイツの歴史和解について寄稿します。まさに今研究していることですから、手ごたえのある仕事です。
このようにパソコンの前に座る時間が増えると、その反面、調査に出かける時間を減らさざるを得なくなります。半年間海外で調査をした昨年とはそこが大違い。今年はヨーロッパに行く時間が取れませんでした。しかしアジアには出かけることができました。中国には2度訪ね、主に東北地区(瀋陽、撫順、ハルビンなど)を回りました。それから沖縄にも滞在することができました。道東(北見、留辺蘂、網走など)では民衆史掘りおこし運動を実践してきた方々とお会いして、そのお話を伺いました。道北の猿払村で行なわれた戦時強制動員の犠牲者の遺骨発掘にも参加。これは民衆史掘りおこし運動の流れの中にあるものです。
沖縄と関わりのあるのが、国立民族学博物館での共同研究「平和・紛争・暴力に関する人類学的研究の可能性」です。今年は民博を会場に5回の研究会を開催、平和構築、平和展示、平和資源などについて討論を重ねました。来年の2月には沖縄での研究会を予定しています。〈平和の現場〉を担う方々との交流が実に楽しみです。
来年は海外調査に再び時間を取りながら、「平和の人類学」の研究成果を形にしていきたいと思っています。
お世話になった方々には心よりありがとうを申し上げます。
新年がみなさまにとって幸い多い年となりますようお祈りいたします。












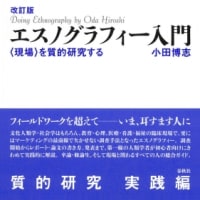







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます