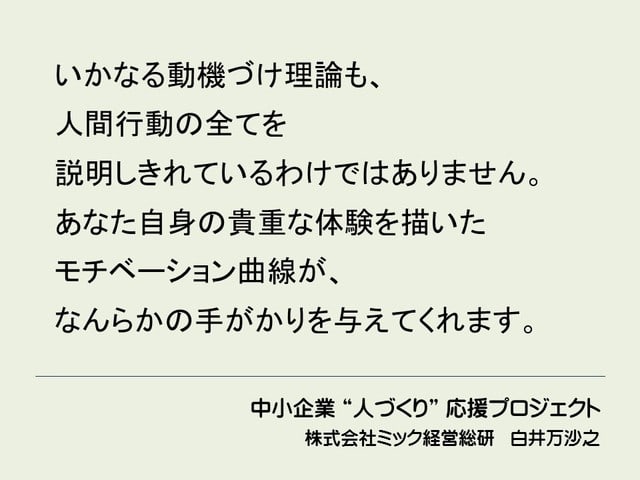
人間にある行動を起こさせることを一般に「動機づけ」といいますが、
動機づけについては、内容理論や過程理論、内発的動機づけ理論などが提唱されています。
しかし、いかなる理論も人間行動のすべてを説明しきれているわけではありません。
理論を研究し現実に対応することはとても大切ですが、
相手との関係や、お互いの置かれた状況により、動機づけの方法は当然に変わってきます。
なかなか理屈通りにはいかないものです。
では、現実の状況に対応するにはどうしたらいいのでしょうか。
そこで一つの手がかりとなるのが、モチベーション曲線です。
あなたのいままでの職場経験を振り返り、
ヤル気になった時、やる気をなくしたときを想い起こし、
思い切って山あり、谷あり、一本の曲線を時系列に描いてみます。
そして、その曲線をよく眺めてみて、
モチベーションがアップしたとき、ダウンした時の出来事や状況、
その出来事や状況の背景にある要因やプロセス、心理的な状態などを探り出してみます。

この自分自身の貴重な体験から得た、
要因やプロセス、状態などが、動機づけ方法の手がかりとなります。
この手がかりを、動機づけの理論と照らし合わせてみてください。
貴重な経験から得た手がかりは、
理論の裏づけを伴った確かな動機付け方法として、
その置かれた状況に対応した確かな確信をあなたに示唆してくれる筈です。












